■化学療法で治療した硬膜外リンパ腫の猫14頭の神経学的回復
Neurological Recovery in 14 Cats With Epidural Lymphoma Treated With Chemotherapy
Vet Comp Oncol. 2025 Sep;23(3):366-376. doi: 10.1111/vco.13061. Epub 2025 Apr 23.
Julya Nathalya Felix Chaves , Mathias Reginatto Wrzesinski , Julia da Silva Rauber , Denis Antonio Ferrarin , Marcelo Luis Schwab , Glaucia Denise Kommers , Mariana Martins Flores , Ana Paula da Silva , Angel Ripplinger , Diego Vilibado Beckmann , Alexandre Mazzanti
この研究の目的は、化学療法で治療した硬膜外リンパ腫の猫の神経学的回復の確率およびタイミングを評価することだった。
研究には、リンパ腫と脊髄の関与の診断が確認され、様々な程度の神経学的欠損のある猫を含めた。
リンパ腫と診断された14頭の猫の治療開始時、14,3%(n=2)は歩行可能な対麻痺不全麻痺、14.3%(n=2)は歩行不可能な対麻痺不全麻痺、7.1%(n=1)は深部痛覚のある対麻痺、50%(n=7)は深部痛覚のない対麻痺、14.3%(n=2)は歩行不可能な四肢不全麻痺だった。
実施された化学療法治療は、10頭の猫でCOP、2頭の猫でCOPおよびCHOP、2頭の猫でCHOPだった。神経学的回復にたいして必要とされた化学療法セッションの回数は1-4回、1頭あたり合計1-13セッションと変化があった。神経学的回復の比率は、83.3%(10/12)で満足の行くものだった。
この研究は、化学療法で治療した硬膜外リンパ腫の猫は、神経学的欠損のレベルに関係なく、7-28日の期間内で、神経学的部分的回復の確率83.3%、神経学的完全回復の50%のチャンスがある。(Sato訳)
■犬の上皮向性リンパ腫のオクラシチニブと併用薬の短期投与:8頭の犬の回顧的研究
Short-term administration of oclacitinib with concomitant medications in canine epitheliotropic lymphoma: A retrospective study of eight dogs
Vet Dermatol. 2025 Jun 17. doi: 10.1111/vde.13366. Online ahead of print.
Yuta Baba , Tomo Asakura , Saki Obayashi , Miyuki Yamada , Motoki Otsuka , Shinya Morikawa , Angeline Teh , Ikki Mitsui , Takafumi Osumi
背景:犬の皮膚上皮向性リンパ腫(CEL)は、珍しい腫瘍性疾患で予後は悪い。ヤヌスキナーゼ阻害剤のオクラシチニブは、犬のアレルギーおよびアトピー性皮膚炎の治療に使用され、他の皮膚疾患も引き起こすかもしれない。
目的:この研究の目的は、犬の皮膚型リンパ腫の治療において、オクラシチニブの効果を評価することだった。
動物:研究にCELの8頭の飼い犬を含めた。
素材と方法:犬にオクラシチニブを投与した。この研究は免疫学的特徴、治療開始前の期間、用量、皮膚病変及び痒み、有害事象、生存期間とオクラシチニブ使用前を調べた。
結果:8頭のうち1頭(12.5%)のみが、オクラシチニブ治療後の症状改善を示したが、他の症例には臨床的改善が観察されなかった。掻痒の改善は1頭の犬のみに認められた。有害事象は、1頭の犬の軽度の白血球減少が含まれ、予後に有意に影響することはなかった。診断後の生存期間中央値は、228.5日だった。
結論と臨床的関連:それらの結果は、経口オクラシチニブは、犬のCELの治療において効果は限られていたことを示唆する。オクラシチニブの最適な用量、治療期間、併用療法の可能性をさらに調査する大規模前向き研究が薦められる。(Sato訳)
■CHOPあるいはCEOPベースのプロトコールで治療した多中心型リンパ腫の消化管有害事象の発症に関係する因子:多施設回顧的研究
Factors associated with the development of gastrointestinal adverse events in dogs with multicentric lymphoma treated with CHOP or CEOP-based protocols: a multi-institutional, retrospective study
J Small Anim Pract. 2025 May 4.
doi: 10.1111/jsap.13880. Online ahead of print.
E Treggiari , E Catania , P Valenti , K Boyd , R Finotello
目的:犬の多中心型リンパ腫は、アントラサイクリンすなわちドキソルビシン、エピルビシンあるいはミトキサントロンを含む多剤プロトコールで治療される。エピルビシンとドキソルビシンは、消化管有害事象を引き起こすことがしられている;しかし、その2剤の有害事象の比較に焦点を当てた報告は非常に少ない。この研究の目的は、リンパ腫と診断され、ドキソルビシンまたはエピルビシンを含む多剤プロトコールで治療した犬における消化管有害事象の頻度と重症度を分析することだった。
素材と方法:4か所の施設の医療データベースから、CHOPあるいはCEOPで治療されているリンパ腫と確定診断された犬を検索した。分析した変数は、犬種、性別、年齢、体重、臨床ステージ、サブステージ、免疫表現型、プレドニゾロンの使用、アントラサイクリンの初回投与量、アントラサイクリンの最初の投与後の寛解状況を含めた。消化管関与の検出された犬、消化管リンパ腫の疑いがある、あるいは受診時に腹部画像検査を行っていない犬は除外した。
結果:合計178頭の犬を含め、114頭(64.1%)はエピルビシン、64頭(35.9%)はドキソルビシンを投与されていた。エピルビシン群の46頭(40.3%)、ドキソルビシンの36頭(56.2%)が消化管有害事象を発症した。去勢したオス犬、10-15歳より若い犬、1mg/kgの用量でエピルビシンを投与、ステージVの疾患は、消化管有害事象発症リスクがより高かった。
臨床的意義:それらの結果は有害事象を防ぐのに役立つ可能性があるが、今後の前向き研究で、消化管有害事象のより少ない比率に関連したアントラサイクリンの選択を判定する必要があるだろう。(Sato訳)
■リンパ腫に対する化学療法を完了した犬における腎臓生化学パラメーターの短期評価
Short-term evaluation of renal biochemical parameters in dogs completing chemotherapy for lymphoma
Aust Vet J. 2025 Jan 26.
doi: 10.1111/avj.13419. Online ahead of print.
L Venman , T Sparks , A Swallow
目的:リンパ腫を治療中の犬において、CHOPプロトコールの化学療法薬が腎臓パラメーターを上昇させるかどうかを確認し、プレドニゾロンの使用あるいは年齢のような因子がこの結果に影響するかどうかを調査することだった。
方法:2015年から2019年の間に、個人二次診療施設でCHOP化学療法プロトコールを受けたリンパ腫と診断された犬の記録から回顧的にデータを入手した。最初の治療でCHOPプロトコールを受け、4サイクルを完了し、プロトコールの終わりに寛解している犬を含めた。基礎と最後の化学療法投与時に入手した血液サンプルで、クレアチニン、尿素、リン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、アルブミン、総タンパク、ヘマトクリット、好中球、血小板数を含む血清生化学および血球に対して分析を行った。データはペアt-検定で解析した。同じ測定における変化は、ピアソンの相関を用い、年齢の可能性に対し調査した。それらの測定の変化は、プレドニゾロンを投与された犬と、投与されなかった犬で、等分散の想定をせず、2-サンプルt-検定で比較した。変化は一般線形モデルを用い、年齢とプレドニゾロン使用を共同で比較した。有意はP<0.05とした。
結果:30頭が組み入れ基準に合致した。血清クレアチニン濃度における有意な変化は観察されなかった。プレドニゾロンを投与された若い犬において、治療の終了時に血清アルブミン濃度の上昇が観察された。
影響/臨床的意義:犬において、CHOP化学療法プロトコール後の腎臓パラメーターの短期変化は観察されなかった。今後の前向き研究が正当化される。
利害関係の宣言:資金は受け取っておらず、公表する利害の抵触はなかった。(Sato訳)
■リンパ腫の猫の血小板数に対するビンクリスチン反復投与の影響
Effect of repeated vincristine administration on platelet count in cats with lymphoma
Vet Rec. 2025 Jan 31:e5124.
doi: 10.1002/vetr.5124. Online ahead of print.
Giulia Marceglia , Andrea Zoia , Matteo Petini
背景:ビンクリスチンはリンパ腫のような造血性の腫瘍の治療に使用される化学療法剤である。健康な犬や、免疫介在性血小板減少症の犬において、ビンクリスチン投与は血小板数を増加させる。逆に、骨髄抑制が副作用の1つと報告されている。しかし、猫におけるビンクリスチンの血液学的影響に関する情報は不足している。そこで、リンパ腫の猫において、ビンクリスチン投与後の血小板数変動を調べるのがこの研究の目的だった。
方法:2010年から2023年の間にリンパ腫の細胞学的、あるいは組織学的診断を受けた猫の回顧的コホート研究を行った。ビンクリスチンを投与し、投与前後でCBCを実施した猫を研究に含めた。各ビンクリスチン投与は、連続したイベントとして記録した。その後、ビンクリスチン投与後の血小板数の変化を算出した。
結果:研究に含めた52頭の猫に対し、4回の連続した治療イベントで、94回のビンクリスチンが投与されていた。猫の治療後の血小板数は、常に治療前の数値より高かった;しかし、2度目のビンクリスチン投与後からのみ、その差が統計学的に有意となった(平均差53.2±124.4
x 10(3)μL;p=0.019)。
制限:この研究の回顧的特性により、血液のサンプリングプロトコールは標準化されておらず、CBC分析のタイミングは個々の症例間で異なり、結果に影響しているかもしれない。
結論:ビンクリスチンの反復投与は、リンパ腫の猫で血小板減少の原因とはならず、血小板減少の猫において禁忌ではない。(Sato訳)
■脾摘後にリン酸トセラニブで治療した犬の肝脾T細胞性リンパ腫の長期生存:非定型リンパ腫の1症例
Long-Term Survival in Canine Hepatosplenic T-Cell Lymphoma Treated with Toceranib Phosphate Following Splenectomy: A Case of Atypical Lymphoma
Vet Sci. 2024 Oct 1;11(10):458.
doi: 10.3390/vetsci11100458.
Makoto Akiyoshi , Masaharu Hisasue , Midori Goto Asakawa , Sakurako Neo
リン酸トセラニブ(トセラニブ)は、犬の肥満細胞腫の治療に認可されている。しかし、犬の肝脾T細胞性リンパ腫(HSTCL)においてトセラニブの長期反応は報告されていない。
ここで、3か月前からの体重減少、多渇、多尿を呈する10歳の去勢済み雑種犬の症例を述べる。
臨床病理および画像検査異常は、黄疸、胆管閉塞、複数の広範性低エコー性結節を伴う脾腫が含まれた。21病日、閉塞を解除するために胆嚢切除を実施し、続いて肝生検と脾摘を行った。脾臓と肝臓の細胞診は、細胞質ない顆粒を伴う多くの小リンパ球(sGLs)を示した。腫瘍性CD3/グランザイムB陽性小細胞の脾臓と肝臓浸潤およびグランザイムB陰性小細胞を伴う胆嚢炎を認めた。T細胞レセプター遺伝子クローン再拝列が肝臓組織内に観察された。
その犬は、リンパ急性胆嚢炎を併発したsGLsのHSTCLと診断された。黄疸は術後解消したが、肝酵素濃度の進行性の上昇があった。39秒実にトセラニブを投与し、肝酵素濃度が減少し、その犬は良好な状態を維持した。その犬はトセラニブ投与後寛解を保ち、460日生存した。
トセラニブは、犬HSTCLに対する効果的な治療オプションと考えるべきである。(Sato訳)
■小型犬種のシクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン(CHOP)で治療した多中心型リンパ腫の臨床結果
Clinical Outcome of Multicentric Lymphoma Treated with Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisolone (CHOP) in Small Breed Dogs
Animals (Basel). 2024 Oct 17;14(20):2994.
doi: 10.3390/ani14202994.
Tae-Hee Kim , Woo-Jin Song , Min-Ok Ryu , Hyun-Tae Kim , Aryung Nam , Hwa-Young Youn
リンパ腫は犬の一般的な悪性腫瘍の1つである。ビンクリスチン、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、プレドニゾロンの併用化学療法(CHOP)は、多中心型リンパ腫に対する最も効果的な治療である。過去の研究は、CHOP治療に対する大型犬の反応を評価し、予後因子を確認している;しかし、小型犬に対する研究は欠如している。
この研究では、CHOPで治療した多中心型リンパ腫の小型犬に対する結果と予後因子を調査した。
CHOP治療に対する反応を評価し、54.3%が完全寛解(CP)、31.4%が部分寛解(PR)、14.3%が緩解せず(NR)と評価した。総反応率は85.7%だった。CR、PR、NR患犬の生存期間中央値は、それぞれ683日(85-1496日)、241日(15-777日)、119日(61-308日)だった。CP患犬の中で、以下の状況下で生存期間は延長した:10歳以下(p=0.011)、心血管心疾患がない(p=0.046)、化学療法による副作用での入院病歴がない(p=0.002)。
それらの結果は、小型犬種の犬の多中心型リンパ腫に対する治療プランの構築に役立つかもしれない。(Sato訳)
■犬の末梢結節性B-細胞性リンパ腫の治療におけるCHOP-19とCHOP-25の比較:ヨーロッパの多施設回顧的コホート研究
Comparison of CHOP-19 and CHOP-25 for treatment of peripheral nodal B-cell lymphoma in dogs: A European multicenter retrospective cohort study
J Vet Intern Med. 2024 Oct 18.
doi: 10.1111/jvim.17222. Online ahead of print.
Charles Hawkes , Joanna Morris , Spela Bavcar , Craig Wilkie , Surajit Ray , Charlotte Auquier , Sarah Benjamin , Juan Borrego Massó , Sébastien Bottin , Owen Davies , Isabelle Desmas-Bazelle , Anat Einhorn , Celia Figueroa-Gonzalez , Katerina Holenova , Elisavet Kritsotalaki , Kerry Peak , Katherine Smallwood , Elisabetta Treggiari , Paola Valenti , Miguel Garcia de la Virgen , Quentin Fournier
Free article
背景:末梢結節性B-細胞性リンパ腫(PNBCL)は、犬のリンパ腫の一般的なタイプである。多剤CHOP(C=シクロフォスファミド、H=ヒドロキシダウノルビシン(ドキソルビシン)、O=オンコビン、P=プレドニゾロン)-ベースの化学療法プロトコールはゴールドスタンダードの第一選択治療として広く受け入れられている。CHOP-25とCHOP-19は最も一般的に述べられているが、直接比較されていない。
目的:主な目的は、PNBCLと診断された犬で、治療に第一選択CHOP-19あるいはCHOP-25プロトコールを用いた結果を比較することだった。2つ目の目的は、結果に対するプロトコールが関連した変数の影響を調べることだった。
動物:16か所のヨーロッパの腫瘍紹介センターからの502頭の犬。155頭はCHOP-19で治療し、347頭はCHOP-25で治療した。
方法:2014年から2021年の間にPNBCLと診断された犬の回顧的多施設コホート研究。
結果:6か月、1年、無増悪生存期間(PFS)中央値は、CHOP-19で56.5%(95%CI、49.2-65.0)、14.1%(95%CI、9.4-21.0)、196日(95%CI、176-233);CHOP-25で56.4%(95%CI、51.4-61.9)、17%(95%CI、13.4-21.6)、209日(95%CI、187-224)だった。
1年、2年および総生存期間(OS)中央値は、CHOP-19で36.9%(95%CI、29.7-46.0)、13.5%(95%CI、8.6-21.1)、302日(95%CI、249-338);CHOP-25で42.8%(95%CI、37.7-48.7)、15.4%(95%CI、11.7-20.4)、321日(95%CI、293-357)だった。両プロトコールのPFSおよびOSに有意差は見つからなかった。
結論と臨床的重要性:我々の研究は、第一選択CHOP-19あるいはCHOP-25で治療したPNBCLの犬で同様の結果を確認した。ゆえに、両プロトコールは今後の試みで標準治療として使用可能だった。(Sato訳)
■verdinexorで治療した1頭の犬の皮膚型リンパ腫の臨床的寛解
Clinical Remission of Cutaneous Lymphoma in a Dog Treated with Verdinexor
J Am Anim Hosp Assoc. 2024 Sep 1;60(5):223-226.
doi: 10.5326/JAAHA-MS-7443.
Jennifer Lynn Grady , Jaymee Gencher , Sarah Adrianowycz , Gisela Martinez-Romero
5歳のメスの避妊済みピットブルテリアの雑種犬の、体重減少と元気消失を伴う2週間以上前からの多発性皮膚結節の発症を評価した。
病理組織検査と免疫組織化学検査で、皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫の確定診断が得られた。
治療は経口verdinexorの能書に従い、週2回の32.9mg/m2(1.2mg/kg)で開始した。治療開始から1週間で、臨床的寛解は、皮膚結節の完全な消失を認めた。
その犬は中断せずに週2回の投与を継続し、最初の投与から17か月、完全寛解を維持している。
この症例は犬皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫の治療において、verdinexorの有用性のエビデンスを提供する。(Sato訳)
■リンパ腫の犬の診断時の蛋白尿と生存期間の関係
Association of proteinuria at time of diagnosis with survival times in dogs with lymphoma
J Vet Intern Med. 2024 Jul 13.
doi: 10.1111/jvim.17144. Online ahead of print.
Stephanie M Skinner , Andrew J Specht , Victoria Cicchirillo , Stacey Fox-Alvarez , Autumn N Harris
Free article
背景:犬の蛋白尿の潜在的原因としてリンパ腫が関係している。しかし、リンパ腫の犬の蛋白尿の潜在的重要性についての情報は限られている。
仮説:リンパ腫の犬の診断時の蛋白尿の有無が生存期間中央値と関係しているかどうか、リンパ腫のステージ(I-V)、あるいはタイプ(B vs T)が蛋白尿の有無に関係したかどうかを判定する
動物:2008年から2020年の間にリンパ腫と新しく診断された飼い犬86頭
方法:これは、ディップスティック尿蛋白(蛋白≧30mg/dLを蛋白尿と分類)、あるいはディップスティック尿蛋白と尿比重の比(比≧1.5を蛋白尿と分類)を基に尿蛋白群と非尿蛋白群に振り分けた犬の回顧的横断研究だった。除外した犬は(1)2か月以内にグルココルチコイド、抗腫瘍、あるいは抗蛋白尿の治療を受けた犬、(2)副腎皮質機能亢進症あるいは腎臓リンパ腫と診断された犬、(3)活動的尿沈渣の犬、(4)尿pH>8の犬だった。生存解析は、カプラン-マイヤー推定値およびログランク検定を使用した。
結果:尿ディップスティック(245日(91、399)vs335日(214、456);P=.03)あるいはUP:USG(237日(158、306)vs304日(173、434);P=.03)で分類した蛋白尿と非蛋白尿の犬の生存期間中央値に有意差があった。ステージ(I-V)あるいはタイプ(BとT)の間に蛋白尿の有病率の違いは確認されなかった。
結論と臨床的重要性:リンパ腫と新しく診断された犬において、蛋白尿は生存期間にネガティブに関係すると思われる。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の犬においてシクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン化学療法中および後の早期進行はレスキュープロトコールの悪い結果を示す
Early progression during or after cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone chemotherapy indicates poor outcome with rescue protocols in dogs with multicentric lymphoma
J Vet Intern Med. 2024 Jul 3.
doi: 10.1111/jvim.17139. Online ahead of print.
Ashley S Parker , Jenna H Burton , Caitlin M Curran , Amber Wolf-Ringwall , Douglas H Thamm
Free article
背景:シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン化学療法(CHOP)が失敗したリンパ腫の犬は、一般的に長期結果が悪いと思われるが、レスキュー化学療法を行う犬の無増悪期間(PFI)あるいは総生存期間(OST)に対する早期再燃の影響を評価している研究はない。
目的:多中心型リンパ腫の犬における第一選択治療のCHOP化学療法後の結果と、レスキュー治療の結果との関連
方法:第一選択治療のCHOP化学療法を受け、その後、ロムスチン(CCNU)、L-アスパラギナーゼとプレドニゾン(LAP)、ラバクフォサジン(RAB、Tanovea)、±プレドニゾロンあるいはL-アスパラギナーゼの治療を受けた多中心型リンパ腫の犬187頭における、6つの過去の回顧的あるいは前向き研究からデータを集めた。
結果:CHOP化学療法の開始後のPFIは、両レスキュープロトコールに対する進行後反応率、PFI、レスキュー後生存期間(ST)と有意に関係した。免疫表現型(B-
vs T-細胞性)は、LAPに対する反応、PFI、OSTと有意に関係しなかったが、RABに対する反応およびPFIと有意に関係した。
結論:第一選択治療のCHOP化学療法中あるいは後にPFIが短かった犬は、レスキュー治療に対する反応率が低く、PFIおよびSTが短かった。免疫表現型は、LAPの結果に有意に影響しなかったが、RABに対するPFIに関係した。(Sato訳)
■犬の多中心型リンパ腫の第一選択治療としてロムスチンとプレドニゾロンの使用
Use of Lomustine and Prednisolone as First-Line Treatment in Canine Multicentric Lymphoma
Vet Comp Oncol. 2024 Jun 18.
doi: 10.1111/vco.12990. Online ahead of print.
Catalucci Chiara , Bianchi Marco Luigi , Treggiari Elisabetta , Pieri Marta , Ruess Katja , Valenti Paola
犬の高グレードリンパ腫に対し、多剤併用化学療法が最も効果的な治療と考えられている;しかし、費用と時間がかかるため、単剤プロトコールも述べられている。
この研究の目的は、多中心型リンパ腫に罹患した犬で、第一選択治療としてロムスチンとプレドニゾロンで治療した時の結果と予後因子を評価することだった。
中-大型細胞性多中心型リンパ腫で、ロムスチンとプレドニゾロンで治療した症例を研究に含めた。治療への反応、無増悪期間(TTP)、無病期間中央値(MDFI)、生存期間中央値(MST)を回顧的に述べた。
30症例を含めた。11頭(36.67%)はT細胞、11頭(36.67%)はB細胞、8頭(26.66%)は不明な免疫表現型だった。総奏効率(RR)は87%で、15頭はCR(50%)、11頭はPR(37%)を達成した。TPP中央値、MDFI、MSTはそれぞれ42、63、90日だった。MDFIおよびMSTに有意に関連した唯一の因子はステージだった。
ロムスチンとプレドニゾロンで治療した多中心型リンパ腫の犬は、多剤併用プロトコールで治療した犬と比べて、RR、TTP、MDFI、MSTがより低い。短期間持続反応を基に、この研究は、このプロトコールが緩和を超えて最小の有用性があるかもしれないことを確認する。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の小型から中型サイズの犬におけるドキソルビシンベースの化学療法中の心臓の連続評価の結果
Outcome of serial cardiac evaluations during doxorubicin-based chemotherapy in small- to medium-sized dogs with multicentric lymphoma
Vet J. 2024 May 13:106134.
doi: 10.1016/j.tvjl.2024.106134. Online ahead of print.
Y S Tang , S L Wang
ドキソルビシンは、用量依存性および累積性心毒性をもつアントラサイクリン抗腫瘍抗生物質である。しかし、拡張性心筋症(DCM)に対するリスク因子のない犬で、連続した心臓評価に対する必要性は不明である。
この研究の目的は、小型から中型の犬において、4回のドキソルビシン投与後、心エコーおよび心電図測定において連続変化を調査することだった。
体重20kg未満の多中心型リンパ腫の犬17頭を含めた。多剤化学療法プロトコールの一部として、全ての犬に30分以上かけて4週間ごとにドキソルビシンを投与した。平均ドキソルビシン投与は、犬あたり3.8回だった。モニタリング期間中に臨床的心毒性は観察されなかった。不整脈に発展する発生率は、ドキソルビシン投与回数と有意に関係することはなかった(P=0.600)。それらの犬において、弁の逆流および僧帽弁逆流への発展は、ドキソルビシン投与回数と有意に関係しなかった(それぞれ、P=0.363、P=0.779)。他の心エコー検査結果は、各評価間で有意差はなかった。
結論として、我々の結果は、DCMに対するリスク因子のない小型から中型サイズの犬において、30分注入法で4回のドキソルビシン投与後、心エコーおよび心電図検査下で有意な心毒性がないことを示した。(Sato訳)
■最初のレスキュー療法で治療した犬多中心型リンパ腫における臨床反応と予後因子の評価
Evaluation of clinical response and prognostic factors in canine multicentric lymphoma treated with first rescue therapy
Vet Comp Oncol. 2024 Apr 22.
doi: 10.1111/vco.12974. Online ahead of print.
John E Blaxill , Peter F Bennett
化学療法で治療した多中心型リンパ腫の犬の多くは、最初の強い反応にもかかわらず、いまだ再発が良く起こる。難治性あるいは再発性の犬の多中心型リンパ腫に対し述べられた、明らかに優れた最初のレスキュープロトコールはない。
この研究の目的は、最初のレスキュープロトコールで治療した犬の多中心型リンパ腫に対し、臨床反応と結果を評価することだった。2つ目の目的は、それらのプロトコールを行う犬に対し、予後的変数を評価することだった。
これは2施設の回顧的コホート研究だった。265頭の犬を最初のレスキュー化学療法(アントラサイクリンベースの併用化学療法(CHOP様、n=50)、ニトロソウレアアルキル化剤強化化学療法(n=45)。アントラサイクリンベースあるいは関係した合成化学療法(n=34)、ニトロソウレア単剤化学療法(n=136))で治療した。
最初のトレスキュープロトコールの全体の無増悪期間中央値は、56.0日(0-455日)だった。最初のレスキュープロトコールに対して確認された重要な予後因子は、最初のレスキュー化学療法に対する完全奏功の達成(p<.001)、CHOP様最初のレスキュープロトコールの使用(p=.009)、最初の寛解の持続期間(HR
0.997、p=.028)、最初のレスキュープロトコールにプレドニゾロンが含まれた場合(HR 0.41、p=.003)が含まれた。
有害事象(AE)は一般的で、81.1%の犬が最初のレスキュー化学療法中に1つ以上のAEを経験した。
この研究は、犬の難治性あるいは再発性リンパ腫において、長期寛解を提供する最初のレスキュー療法を改善する必要性を強調する。(Sato訳)
■COPおよびL-COPプロトコールで治療している犬多中心型リンパ腫における生存性の予後的指標として血液学および血液生化学パラメーター
Hematological and blood biochemistry parameters as prognostic indicators of survival in canine multicentric lymphoma treated with COP and L-COP protocols
Vet World. 2024 Feb;17(2):344-355.
doi: 10.14202/vetworld.2024.344-355. Epub 2024 Feb 8.
Somchin Sutthigran , Phasamon Saisawart , Patharakrit Teewasutrakul , Sirintra Sirivisoot , Chutimon Thanaboonnipat , Anudep Rungsipipat , Nan Choisunirachon
背景と目的:化学療法中の犬多中心型リンパ腫の評価とモニタリングに対し、血液学および血液化学パラメーターは重要である。この疾患に対し、治療前の血液学および血液化学パラメーターは、予後的生存結果として使われることができる。ゆえに、この研究の目的は、シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロンの組み合わせ(COP)、あるいはCOPとL-アスパラギナーゼの組み合わせ(L-COP)のプロトコールで治療した犬の生存結果に対し、治療前と治療から4週目の血液学および血液化学パラメーターの影響を調査することだった。
素材と方法:我々は回顧的研究を行った。L-COP(n=26)、COPプロトコール(n=15)で治療した多中心型リンパ腫の犬41頭の医療記録、血液学および血液化学パラメーターを、病院情報システムから入手した。ほとんどの症例は、Kiel細胞分類を基に高グレードリンパ腫に分類された。生存結果に対する血液学および血液化学パラメーターの影響は、Cox比例ハザード回帰モデルで調査した。生存結果に影響する各血液学および血液化学パラメーターに対する生存期間中央値(MST)を確立し、Kaplan-Meier product limit method と log-rank testで比較した。
結果:COPプロトコールで治療し、治療前に単球増加症の高グレード多中心型リンパ腫の犬は、正常な単球数の犬よりもMSTが有意に短かった(p=0.033)。また、治療前および治療から4週目、両方で高窒素血症だった犬は、正常な血清クレアチニン濃度の犬よりも有意にMSTが短かった(p=0.012)。L-COPプロトコールで治療した高グレード多中心型リンパ腫の犬で、治療前および治療から4種目の両方で低アルブミン血症(血清アルブミン濃度<2.5mg/dL)だった犬は、正常な血清アルブミン濃度の犬よりも有意にMSTが短かった(p<0.001)。さらに、治療から4週目に白血球増加の犬は、正常な総白血球数の犬よりも有意にMSTが短かった(p=0.024)。
結論:L-COPプロトコールで治療した高グレード多中心型リンパ腫の犬において、血清アルブミン濃度は、生存結果の単純な負の予後指標として役立てることができる。治療前と治療から4週目に低アルブミン血症の犬は、正常な血清アルブミン濃度の犬よりもMSTが短い傾向があった。(Sato訳)
■リンパ腫の治療をしている犬の体重に関連するビンクリスチン誘発性の有害事象
Vincristine-induced adverse events related to body weight in dogs treated for lymphoma
J Vet Intern Med. 2024 Apr 2.
doi: 10.1111/jvim.17063. Online ahead of print.
Keira E Sztukowski , Zachary Yaufman , Matthew R Cook , Turi K Aarnes , Brian D Husbands
Free article
背景:体表面積を基にした従来の化学療法薬の用量は、小型犬でオーバードーズとなり、有害事象(AEs)の頻度が増すことにつながるかもしれない。
仮説/目的:体重>15kgの犬と比較して、新規にリンパ腫と診断され、ビンクリスチンで治療した体重≦15kg以下の犬の血液および消化管AEsの頻度を評価する。体重≦15kgの犬はより高い頻度でAEsを経験するだろうと仮説を立てた。
動物:新規にリンパ腫と診断され、ビンクリスチンで治療した138頭の犬
方法:血液学的データと医療記録の情報を再検討する多施設回顧的研究。CBCはビンクリスチン投与前の24時間以内に実施し、それから、投与後4日目、8日目に行った。データはロジスティック回帰あるいはオリジナルロジスティック回帰で評価した。
結果:体重≦15kgの犬38頭と体重>15kgの犬100頭が含まれた。両群のビンクリスチン用量中央値は0.6mg/m2だった。好中球減少症の17例(12.3%)は、両群で全体の頻度あるいはグレードに有意差なく発生した。当初、無症候性のサブグレードAの30例(29.4%)は消化管AEsを経験した。消化管の支持療法の薬剤は幅広く使用されたため、群間の統計学的比較は実施できなかった。入院は7例(5.0%)で、入院のリスクは群間で有意に違わなかった。
結論と臨床的重要性:≦0.6mg/m2でのビンクリスチンの投与量は、体重≦15kgの犬の血液学的AEsのリスクは増加しない。(Sato訳)
■大顆粒リンパ球性リンパ腫の犬65頭(2005-2023)
Large granular lymphocyte lymphoma in 65 dogs (2005-2023)
Vet Comp Oncol. 2023 Dec 29.
doi: 10.1111/vco.12959. Online ahead of print.
Andrew D Yale , Asia L Crawford , Irina Gramer , Alexandra Guillén , Isabelle Desmas , Emma J Holmes
大顆粒リンパ球性リンパ腫(LGLL)は、犬の珍しい型のリンパ腫である。症状、治療反応、結果に関する情報は限られている。
この一施設回顧的研究の目的は、LGLLの犬の臨床症状、生物学的挙動、結果、予後因子の特徴の述べることだった。細胞学的レビューも実施した。
65頭の犬を含めた。一般的な犬種は、ラブラドールレトリバー(29.2%)で、一般的に呈する症状は、元気消失(60%)、食欲低下(55.4%)だった。一般的な原発の解剖学的型は、肝脾臓型(32.8%)と消化管型(20.7%)だった。20頭(30.8%)の犬は末梢血あるいは骨髄が侵されていた。
32頭は最大許容量の化学療法(MTDC)で治療し、反応は74.1%の犬で認められた。7歳以上の犬、診断時に好中球減少あるいは血小板減少のある犬は、治療反応の見込みが低下していた。
MTDCで治療した犬において、無増悪期間(PFI)中央値は17日(範囲、0-481)で、総生存期間(OST)中央値は28日(範囲、3-421)、6-か月および1-年生存率は9.4%と3.1%だった。
多変量解析において、単球増加と末梢血関与は、有意にPFIおよびOST短縮と関係した。長期生存(100日以上)は、細胞診において中間のリンパ球サイズと有意に関係した。
LGLLの犬は、化学療法に対して中程度の反応率だが、総生存性は悪い。更なる予後因子の評価、最適な治療推奨法のガイドのため、追加研究が必要である。(Sato訳)
■リンパ腫の犬の悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症と高窒素血症併発の臨床的結果の評価
Evaluation of the clinical outcome of hypercalcemia of malignancy and concurrent azotemia in dogs with lymphoma
J Vet Intern Med. 2023 Dec 22.
doi: 10.1111/jvim.16974. Online ahead of print.
Alyssa A Strumpf , Laura Selmic , Brian Husbands
Free article
背景:犬のリンパ腫による二次的な悪性腫瘍の伴う高カルシウム血症(HM)は、腎傷害を引き起こす可能性を持つ
仮説/目的:HMによる二次的な急性腎障害(AKI)に関連する結果の特徴を述べる。リンパ腫の診断、あるいは再燃時のHMの重症度に関係なく、犬はAKIを経験すると仮説を立てた。
動物:回顧的研究。化学療法を行ったHMおよび高窒素血症(IRISグレード2あるいはより高いAKI)のリンパ腫の犬29頭を2か所の獣医施設で確認した。
方法:ロジスティック回帰および記述統計解析で、潜在的予後因子に対してデータを評価した。
結果:治療開始後、高カルシウム血症と高窒素血症の解消は、それぞれ100%(29/29)、79.3%(23/29)の犬で起こった。高窒素血症の解消は、診断時の血清クレアチニン濃度(オッズ比、0.148;信頼区間、0.03-0.734;P=.02)と総高カルシウム血症(OR、0.36;CI、0.14-0.93;P=.04)により影響を受けたが、血中尿素窒素濃度、IRISグレード、性別、犬が入院したかどうかは有意な因子ではなかった。データ解析時、13.8%(4/29)の犬は生存あるいはフォローアップができなかった。それらの死亡のうち、4頭(15%)は死亡時に腎疾患があり、2/4頭は同時にリンパ腫が進行していた。
結論と臨床的重要性:診断時にリンパ腫による二次的なHMのある犬でAKIは臨床的懸念であるかもしれないが、腎臓の障害による死亡はまれだと思われる。(Sato訳)
■再燃した犬のリンパ腫の治療に対しメルファラン、ビンクリスチン、シタラビン化学療法の回顧的評価
Retrospective Evaluation of Melphalan, Vincristine, and Cytarabine Chemotherapy for the Treatment of Relapsed Canine Lymphoma
J Am Anim Hosp Assoc. 2024 Jan 1;60(1):7-14.
doi: 10.5326/JAAHA-MS-7372.
Margaret E Duckett , Katie M Curran , Shay Bracha , Haley J Leeper
多中心型リンパ腫と診断された犬は、治療開始から1年以内の導入治療後に再燃することも多い。
この研究の主な目的は、再燃したリンパ腫の治療に対し、メルファラン、ビンクリスチン、シタラビン(MOC)を使用した新規薬剤併用の許容性を評価することだった。
1日目、犬にビンクリスチン(0.5-0.6mg/m2 IV)とシタラビン(4-6時間かけて300mg/m2 IVを投与、あるいは2日かけて皮下投与)した。7日目、メルファラン(20mg/m2経口)を投与した。この2週間のプロトコールを少なくとも3サイクル、あるいは治療が失敗するまで繰り返した。
26頭の犬をMOCで治療し、組み入れ基準に合致した。23頭の犬に毒性データがあり、ほとんどが軽度のグレードの全頭が有害事象を経験した。全体の反応率は38%で、完全寛解を達成した19%の犬が含まれた。無増悪期間中央値は29日(範囲1-280日)だった。全体の臨床的有効率は、65%で、中央値37日(範囲33-280日)だった。
MOCは犬の再燃性リンパ腫に対し、安全な治療オプションである。(Sato訳)
■リンパ腫の犬77頭の生存期間に影響する因子の評価
Evaluation of factors influencing survival time in 77 dogs with lymphoma
Open Vet J. 2023 Sep;13(9):1124-1134.
doi: 10.5455/OVJ.2023.v13.i9.8. Epub 2023 Sep 30.
Soo-Yeon Jeong
背景:犬のリンパ腫は、最も一般的に報告される血液生成腫瘍の1つである。
目的:診断的特徴や治療プロトコールを含む複合の評価に関与している回顧的研究はいくつかあるが、それらの研究は、生存期間に影響する不定の因子を証明している数は少なく、化学療法プロトコール間の比較は限られている。この研究の目的は、リンパ腫の犬で、生理的および血液学的所見の異常や治療プロトコールのような簡単に検出できる予後因子を判定することだった。
方法:リンパ腫と診断された77頭の犬の臨床記録を回顧的に再評価した。
結果:著者は新規に、負の予後因子として白血球と血小板異常を確認した。さらに、この研究は正の予後因子として、消化管毒性の低下と、化学療法作用中の末梢血における貧血、血小板減少およびリンパ球あるいはリンパ芽球増加症のような血液異常の改善を示唆している。最後に、治療プロトコールの厳格な遵守とレスキュープロトコールの複数薬剤の選択は、生存期間を延ばすために重要である。
結論:この研究は、生存解析を通し予後因子として役立つ指標を確認した。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の犬の個別の化学療法薬用量増量
Individualized chemotherapy drug dose escalation in dogs with multicentric lymphoma
J Vet Intern Med. 2023 Oct 3.
doi: 10.1111/jvim.16875. Online ahead of print.
Jacob M Siewert , Daniel L Gustafson , Kristen M Weishaar , Annie M Galloway , Douglas H Thamm
Free article
背景:この研究は、多中心型リンパ腫の犬の15週CHOPにおいて、薬用量を増量可能か判定するために実施した。
仮説:少なくとも半数の犬が、最低1薬剤の増量に成功すると仮説を立てた。2つ目の目的は、奏効率(ORR)、無増悪期間(PFI)、総生存期間(OST)を確証することだった。
動物:新規に多中心型リンパ腫と診断された30頭の犬を前向きに15週CHOPプロトコールで治療した。
方法:これは前向きコホート研究である。用量を制限する副作用(AEs)を引き起こさなかった薬用量は、標準化した増量プロトコールを用いて増加させた。AEsと反応はVCOG基準を用いて評価した。薬物動態解析のため、各薬剤の最初の投薬後に連続して血液サンプルを採取した。
結果:薬剤増量の期会があった23頭中、18頭(78%)で少なくとも1薬剤は増量に成功した。11頭の犬でビンクリスチンの0.8mg/m2以上、16頭のシクロフォスファミドは300mg/m2以上、9頭のドキソルビシンは35mg/m2あるいは1.4mg/kg以上の増量に成功した。23頭中3頭(13%)は、薬剤誘発のAEsのため1回以上入院した。全ての薬剤で、好中球減少はもっとも多い用量を制限する毒性だった。ドキソルビシンのピーク濃度は、ドキソルビシンの増量に成功した犬において有意に低かった。奏効率は100%だった、無増悪期間中央値は171日だった。総生存期間中央値は254日だった。
結論:CHOPプロトコールにおける薬剤は、管理可能なAEsで、安全に増量できることが多い。(Sato訳)
■抵抗性多中心型リンパ腫の治療においてメクロレタミン、ビンブラスチン、プロカルバジン、プレドニゾンの評価
Evaluation of mechlorethamine, vinblastine, procarbazine, and prednisone for the treatment of resistant multicentric canine lymphoma
Vet Comp Oncol. 2023 May 24.
doi: 10.1111/vco.12913. Online ahead of print.
Kelley Zimmerman , Koranda A Walsh , Jonathan T Ferrari , Nicholas S Keuler , Matthew J Atherton , Jennifer A Lenz
多剤併用化学療法は、ほとんどのまだ処置をしていない高グレード犬リンパ腫の寛解に導くことができるが、疾患の再発は一般的である。MOPP(メクロレタミン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン)は、再度寛解に導くために使用される有効なレスキュープロトコールであるが、消化器毒性に関係し、過去にビンクリスチンを含むプロトコールで失敗している犬に対し、あまり望ましいオプションではない可能性がある。
ゆえに、ビンカアルカロイド属の種類変更(ビンブラスチンのような)が、消化管毒性や化学療法抵抗性を減らすためにビンクリスチンの代用品として有利な可能性があった。
この研究の目的は、ビンクリスチンをビンブラスチンに置き換える修正MOPPプロトコール(MVPP)で治療した再発したあるいは難治性多中心型リンパ腫の犬36頭の臨床結果および毒性を報告することだった。
MVPPの総反応率は25%で、無進行生存期間中央値は15日、総生存期間中央値は45日だった。規定された用量でのMVPPは中程度の一時的な臨床的利点を得られただけだが、副作用による治療延期あるいは入院はなく、許容性は良かった。最小限の毒性ならば、臨床的反応の改善のために用量強化が考慮できた。(Sato訳)
■犬のリンパ系腫瘍の癌の播種のバイオマーカーとして血清C-反応性蛋白濃度の影響
Impact of serum C-reactive protein level as a biomarker of cancer dissemination in canine lymphoid neoplasia
Vet World. 2022 Dec;15(12):2810-2815.
doi: 10.14202/vetworld.2022.2810-2815. Epub 2022 Dec 10.
Nawin Manachai , Duangchanok Umnuayyonvaree , Panitnan Punyathi , Anudep Rungsipipat , Kasem Rattanapinyopituk
Free PMC article
背景と目的:C-反応性蛋白(CRP)は、感受性は高いが、非特異的な急性期蛋白で、癌の患者の生物学的挙動の予測に広く使用されている。この研究の目的は、リンパ腫の犬の予後の予測において血清CRPバイオマーカーの意義を調査することだった。
素材と方法:34頭のリンパ腫の犬と健康なコントロール犬から血液サンプル(5ml)を採取した。犬のリンパ腫臨床的ステージングは、WHO基準を用いて分類した。全てのリンパ腫の犬は、疾患ステージを基に2群に再分類した。ステージIVとVは進行ステージとし、ステージI-IIIは他のステージとした。血清CRP濃度は、市販の犬CRPフルオレセントイムノアッセイkitと通常の血液および生化学検査で判定した。CRP濃度、好中球/リンパ球比、リンパ球/単球比、血小板/リンパ球比のような循環炎症パラメーターを、進行ステージ(IVとV)とステージI-IIIでマン-ホイットニーU検定を用いて比較した。受信者操作特性(ROC)曲線も作成して、CRP濃度のカットオフ値、診断感受性、特異性を判定した。
結果:前向き研究で、最近犬リンパ腫と診断された34頭の犬を確認した。CRPは、ステージI-IIIのリンパ腫の犬よりも、進行ステージ(IVとV)のリンパ腫の犬で有意に高かった。ROC曲線解析に従い、CRPカットオフ値54.1mg/Lは、犬リンパ腫の進行ステージを示し、癌の播種を予測するバイオマーカーとして使用できる。
結論:血清CRP濃度は、臨床応用においてリンパ腫の犬のWHOステージに対し、臨床的意思決定をアシストする。この研究の制限は、リンパ腫の犬が少数なことと生存解析がないことが含まれる。(Sato訳)
■犬の皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫の予後的臨床および病理組織的特徴
Prognostic clinical and histopathological features of canine cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma
Vet Pathol. 2022 Dec 21;3009858221140818.
doi: 10.1177/03009858221140818. Online ahead of print.
Martina Dettwiler , Elizabeth A Mauldin , Sara Jastrebski , Deborah Gillette , Darko Stefanovski , Amy C Durham
犬の皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫は、不均一な臨床および病理組織学的症状を持つ腫瘍の1つである。生存期間や治療に対する反応は変動し、結果を予測する指標は欠如している。
ペンシルバニア及びベルン大学(2012-2018)から、176頭のアーカイブ症例のパラメーターを用い、臨床結果に関係するものを調査した。病理組織学的評価は、デジタル化した全スライド画像とQuPathソフトを用いた。
48犬種の107頭のメス犬と69頭のオス犬を症例に含め、平均年齢は10.4歳だった。最も一般的な臨床症状は、紅斑(n=131)、痂皮(n=108)、鱗屑(n=102)だった。罹患部位は毛の生えた皮膚(n=159)、口唇(n=74)、鼻鏡(n=49)、肢のパッド(n=48)だった。生存期間中央値(MST)は95日(1-850)だった。支持療法と比較し、化学療法およびプレドニゾンで治療した時のMSTはそれぞれ4.26倍、2.82倍延長した。毛の生えた皮膚の関与(ハザード比(HR):2.039、95%CI:1.180-3.523)糜爛/潰瘍(HR:1.871、95%CI:1.373-2.548)、結節(HR:1.496、95%CI:1.056-2.118)、痂皮形成(HR:1.454、95%CI:1.061-1.994)は予後不良を予測する臨床パラメーターだったが、治療後の完全寛解(HR:0.469、95%CI:0.324-0.680)及び安定疾患(HR:0.323、95%CI:0.229-0.456)は、長期生存性と関係した。
死亡リスク増加と関係する病理組織学的特徴は、組織層の広範な浸潤(HR:20865、95%CI:1.565-4.809)、有糸分裂数≧7/強拡大(HR:3.027、95%CI:2.065-4.439)、細胞径≧10.0μm(HR:2.078、95%CI:1.281-3.372)、核径≧8.3μm(HR:3.787、95%CI:1.647-8.707)だった。(Sato訳)
■原発性結節性瀰漫性大細胞型B細胞リンパ腫に対しシクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンで治療している犬におけるより高い基礎血清C-反応性蛋白濃度は生存期間の短縮に関係する
Greater baseline serum C-reactive protein concentrations are associated with reduced survival in dogs receiving cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone chemotherapy for primary nodal diffuse large B-cell lymphoma
Vet J. 2022 Oct 3;105911.
doi: 10.1016/j.tvjl.2022.105911. Online ahead of print.
Michael O Childress , John A Christian , José A Ramos-Vara , Nicole K Rosen , Audrey Ruple
瀰漫性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の犬に対する予後因子は、あまり特徴づけられていない。以前の報告は、リンパ腫の診断時に全身性炎症性反応のある犬は、生存期間が短くなると示唆している。しかし、DLBCLの犬の予後因子として、特定の炎症のバイオマーカーは確認されていない。
化学療法で治療したDLBCLの犬91頭の保管していた血清で、市販の検査測定法を用い、基礎C-反応性蛋白(CRP)濃度を測定した。基礎血清CRP濃度および潜在的予後の意義の他の変数と、無増悪生存期間(PFS)の関係を、Cox比例ハザードモデルで調べた。
最終的な多変量モデルで、化学療法による完全(部分よりも)寛解(ハザード比(HR)0.02;95%CI:0.01-0.07;P<0.001)と血清CRP濃度>1.0mg/dL(HR、1.73;95%CI:1.02-2.92;P=0.042)のみが有意にPFSと関係した。CRP濃度≦1.0mg/dL(検査参照範囲内)の犬に対するPFS中央値は315日だったが、CRP濃度>1.0mg/dLの犬では232日(P=0.06)だった。
基礎血清CRP濃度は、DLBCLの犬の無増悪生存期間に独立して関係し、この顔の犬に対する潜在的に有効な予後バイオマーカーであるとこれらの結果は示唆する。(Sato訳)
■高グレード多中心型リンパ腫の犬のシクロフォスファミド薬物動態に対する分割経口投与とその影響
Fractionated oral dosing and its effect on cyclophosphamide pharmacokinetics in dogs with high-grade multicentric lymphoma
Vet Comp Oncol. 2022 Sep 3.
doi: 10.1111/vco.12856. Online ahead of print.
Sridhar Veluvolu , Jennifer L Willcox , Katherine A Skorupski , Sami Al-Nadaf , Robert Rebhun , Luke Wittenburg
シクロフォスファミド(CP)は、犬の癌に対する多剤治療プロトコールに一般に含まれるアルキル化剤である。プロドラックのため、CPは中間合成物4-ヒドロキシシクロフォスファミド(4-OHCP)(その後自然にアルカリ化フォスフォラミドマスタードを形成する)を活性化するため、肝臓代謝が必要である。CPは数日に分けて総量を投与する分割法で投与されることが多い。CPはヒトで代謝の自動誘導を引き起こすと報告されており、ボーラス投与に対し、分割投与後はより速いCPクリアランスと4-OHCP形成の相対的増加を伴うが、犬のCP投与分割の薬物動態研究は欠けている。
この研究の目的は、担癌犬の前向きに確認した集団において、3-4日間かけて200-250mg/m2の用量でCPの分割経口投与の薬物動態を評価することだった。CP代謝の自動誘導を評価するため、8頭の犬の最初と最後の投与後、CPと4-OHCPの血漿濃度を超高速液体クロマトグラフィータンデム-マス質量分析で測定した。
最初と最後の投与間でCP排出速度に有意差はないことが分かった(0.73±0.46/hr vs 1.22±0.5/hr;p=0.125)。また、最初と最後の投与間で、用量を標準化した4-OHCP暴露に有意差は認めなかった(5.9±2.1hr*ng/mL
vs 7.9±6.4hr*ng/mL;p=0.936)。
それらの結果は、ヒトと同じように犬において分割投与はCPの活性代謝物の暴露を増加させないかもしれないと示唆される。これを踏まえ、200-250mg/m2の用量を投与した犬において、CPのバイオ活性に関し、標準的ボーラス投与と分割投与は同等かもしれない。(Sato訳)
■上皮向性リンパ腫の犬12頭のイソトレチノインによる治療
Isotretinoin treatment of 12 dogs with epitheliotropic lymphoma
Vet Dermatol. 2022 May 30.
doi: 10.1111/vde.13079. Online ahead of print.
Sofia Chichorro Ramos , Michael John Macfarlane , Gerry Polton
背景:上皮向性リンパ腫は、Tリンパ球のあまり一般的ではない皮膚の悪性腫瘍である。この疾患の犬の治療と結果に関して、入手できる情報は限られている。
目的:上皮向性リンパ腫の犬のイソトレチノインによる治療結果および毒性プロフィールを評価する
動物:上皮向性リンパ腫と診断された12頭の犬を含めた。
素材と方法:医療データベースで、2010年から2021年の間に上皮向性リンパ腫と診断され、イソトレチノインで治療した犬を検索した。12頭の診断、治療の詳細、腫瘍の反応を記録した。
結果:治療した12頭中4頭(33%)の全ての病変は解消した。さらに、3頭の病変は目に見えて改善し、奏効率は58%だった。2頭の犬の病変は変化なしのまま、3頭は治療にかかわらず進行した。副作用は3頭(25%)の犬で発生し、全てはすぐに解消、あるいはQOLに影響しなかった。
結論:犬の上皮向性リンパ腫に対するイソトレチノインによる治療は、許容性が良く、効果的な治療だった。(Sato訳)
■ロキベトマブは皮膚上皮向性リンパ腫の1頭の犬の痒みを改善した
Lokivetmab improved pruritus in a dog with cutaneous epitheliotropic lymphoma
J Vet Med Sci. 2021 Dec 6.
doi: 10.1292/jvms.21-0346. Online ahead of print.
Kiyohiko Inai , Keita Kitagawa , Mami Murakami , Toshiroh Iwasaki
13歳メスの避妊済みのキャバリアキングチャールズスパニエルが、左前脚の接地面と尾の慢性腫脹と掻痒を呈した。病理組織検査と免疫細胞化学検査により皮膚上皮向性リンパ腫(CEL)と診断された。
当初、CELに対する代替法としてプレドニゾロンを単独で使用した。長期コルチコステロイド療法にもかかわらず、その犬の生理学的(掻痒)および皮膚症状(脱毛、紅斑、糜爛、痂皮を伴う潰瘍)は進行し、改善のエビデンスを示さなかった。
掻痒の悪化状況のため、プレドニゾロンに加えロキベトマブを開始した。ロキベトマブ使用により、掻痒は着実に改善し、解消と緩解維持に効果的だった。CELの犬の掻痒の経路において、IL-31の重要な役割に対する追加調査が求められる。(Sato訳)
■ミニチュアダックスフンドのリンパ腫:日本の108症例の回顧的多施設研究(2006-2018)
Lymphoma in Miniature Dachshunds: A retrospective multicenter study of 108 cases (2006-2018) in Japan
J Vet Intern Med. 2022 May 27.
doi: 10.1111/jvim.16455. Online ahead of print.
Kenji Rimpo , Miyuki Hirabayashi , Aki Tanaka
Free article
背景:ミニチュアダックスフンド(MD)は若い年齢でのリンパ腫発生と長期に生存する傾向がある。
目的:MDと非MDの犬のリンパ腫の臨床的特徴と生存期間を比較する
動物:リンパ腫の108頭のMDsとリンパ腫のMDではない犬種の犬149頭を研究に含めた。
方法:これは回顧的多施設観察研究である。リンパ腫はシグナルメント、組織病理/細胞学、疾患の解剖学的部位を基に分類した。リンパ腫の各タイプに対し、生存期間中央値をカプラン-マイヤー推定値とライフテーブル解析で分析した。大細胞性消化管リンパ腫(LGIL)に対する予後因子を、Cox回帰で分析した。
結果:非MDs(41/149)に比べ、MDs(53/108)に消化管リンパ腫は多く見られた。MDs(33/108)に比べ、非MD犬(74/149)で多中心型リンパ腫が一番多く見られた。MDおよび非MDでリンパ腫を発症した犬の年齢中央値は、両方とも10歳だったが、非MDs(9/149)に比べ、MDs(20/108)においてリンパ腫は、より若い犬(4歳未満)で多く観察された(P=.002)。70%の犬はB-細胞と診断され、診断の年齢中央値は3(1-14)歳だった。Mott細胞分化は6頭の犬で観察された。LGILのMDにおいて、4歳未満とB-細胞性表現型は、より長い生存期間に対する有意な因子だった。
結論と臨床的重要性:他の研究した犬種より、MDsのリンパ腫は、消化管病変の頻度が高かった。MDにおける早期発現のLGILでB-細胞性リンパ腫はより一般的で、Mott細胞分化に関与する症例が観察された。犬のリンパ腫のこの特定の提示の認識は、LGILのMDの飼い主に対し、治療決断プロセスに影響する可能性があるだろう。(Sato訳)
■症例報告:クロラムブシル、プレドニゾロン、イマチニブで治療した慢性リンパ球性白血病の犬の一例
Case Report: Long-Term Survival of a Dog With Chronic Lymphocytic Leukemia Treated With Chlorambucil, Prednisolone, and Imatinib
Front Vet Sci. 2022 Jan 17;8:625527.
doi: 10.3389/fvets.2021.625527. eCollection 2021.
Ga-Won Lee , Min-Hee Kang , Jin-Ha Jeon , Doo-Won Song , Woong-Bin Ro , Heyong-Seok Kim , Hee-Myung Park
Free PMC article
7歳、去勢済みオスのプードルが慢性の進行性リンパ球増多を呈した。血液検査及び末梢血スメア所見は、高分化小型リンパ球を伴う顕著なリンパ球増加だった。骨髄吸引の細胞診は、小型成熟リンパ球の浸潤を伴う過形成の完全な状態を示し、全有核細胞の45%を占めた。血液および骨髄サンプルのフローサイトメトリーは、CD21分子を主に発現する腫瘍性のリンパ球が明らかになった。
B細胞性慢性リンパ球性白血病(CLL)が免疫表現型解析で診断された。プレドニゾロンとクロラムブシルの投与を開始し、その反応は顕著ではなかった。ゆえに、イマチニブを追加投与し、CLLに関係する血液学的異常は解消した。
治療から1年以上たったフローサイトメトリーは、CD21に陽性のリンパ球数の正常化を示し、血液学的リンパ球増多は解消した。その犬を2年間フォローアップし、重度副作用はなかった。
この症例は、プレドニゾロンとクロラムブシルで治療反応のないCLLの犬への補助療法として、イマチニブは良いオプションかもしれないと示す。(Sato訳)
■犬のリンパ腫に対するプロカルバジン、プレドニゾロン、シクロフォスファミド(PPC)経口併用化学療法
Procarbazine, prednisolone and cyclophosphamide (PPC) oral combination chemotherapy protocol for canine lymphoma
Vet Comp Oncol. 2022 Mar 25.
doi: 10.1111/vco.12814. Online ahead of print.
Kathleen O'Connell , Maurine Thomson , Elizabeth Morgan , Joerg Henning
最大耐用量化学療法に失敗あるいは許容できない犬の集団において、毎日の化学療法の経口投与は犬のリンパ腫に対する新しい治療アプローチを提供する。
多剤経口化学療法プロトコールを計画し、多中心型リンパ腫の50頭の犬の治療に対し、最小副作用で行われた。プロトコールは、プロカルバジン、プレドニゾロン、シクロフォスファミド(PPC)を毎日経口投与した。効果と毒性は、臨床および血液検査で評価した。
PPCプロトコールの治療で総奏功率は70%に達し、24%は部分奏功、46%は完全寛解だった。PPC化学療法の開始から死亡までの期間に対する予測因子として、PPCプロトコールの反応(完全あるいは部分)と年齢が唯一確認された。グレード4の血小板減少によりプロトコールの中止を余儀なくされた1頭を除き、全体的にプロトコールは非常のよく許容した。8頭は消化管毒性を記録し、7頭はグレードI、1頭はグレードIIの毒性だった。
これらの所見は、持続的併用化学療法の経口投与は、最小副作用で多中心型リンパ腫の犬のレスキューに匹敵する生存期間を提供できる。(Sato訳)
■リンパ腫の犬におけるラバクフォサディンの多施設無作為化二重盲検プラセボ対照試験
Multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled study of rabacfosadine in dogs with lymphoma
J Vet Intern Med. 2021 Dec 24.
doi: 10.1111/jvim.16341. Online ahead of print.
Kristen M Weishaar , Zachary M Wright , Mona P Rosenberg , Gerald S Post , Jennifer A McDaniel , Craig A Clifford , Brenda S Phillips , Philip J Bergman , Elissa K Randall , Anne C Avery , Douglas H Thamm , Abigail A Christman Hull , Cathy M Gust , Ann R Donoghue
背景:ラバクフォサディン(RAB、Tanovea-CA1)は、犬のリンパ腫に条件付きで認可された新しい化学療法剤である。
仮説/目的:リンパ腫の犬におけるRABの効果と安全性を判定する
動物:2019年の1月から10月の間に、158頭の新規あるいは再燃した多中心型リンパ腫の飼育犬を登録した。
方法:犬は3:1の割合で、RABあるいはプラセボを無作為に投与した。治療は21日毎に5回まで行った。研究のエンドポイントは、与えられた日時での無増悪期間(PFS)、総反応率(ORR)、一番良い総反応率(BORR)、治療完了後1か月無増悪のパーセントを含めた。安全性のデータも集めた。
結果:RAB群のPFS中央値は、プラセボよりも有意に長かった(82vs21日;p<.0001、HR6.265(95%CI、3.947-9.945))。RAB投与犬に対するBORRは73.2%(完全奏功(CR)50.9%、部分奏功(PR)22.3%)で、プラセボのそれは5.6%(CR0% 、PR5.6%)(P<.0001)だった。最後の投与から1か月後、37頭のRAB投与犬(33%)は、0頭のプラセボ犬に比べて無増悪だった(P<.0001)。RAB群で見られた一般的な有害事象は、下痢(87.5%)、食欲低下(68.3%)、嘔吐(68.3%)で、一般的にグレードは低く、可逆的だった。一連の有害事象は24頭のRAB投与犬(20%)と5頭のプラセボ犬(13%)で報告された。
結論と臨床的重要性:リンパ腫の犬においてラバクフォサディンは、プラセボと比較した時、21日毎の5回投与まで使用し、統計学的に有意な抗腫瘍効果を証明した。(Sato訳)
■まだ治療していないB細胞性多中心型リンパ腫の犬に対するシクロフォスファミドとプレドニゾロン:32症例(2017-2021)
Cyclophosphamide and prednisolone for chemotherapy naïve B cell multicentric lymphoma in dogs: 32 cases (2017-2021)
J Small Anim Pract. 2021 Oct 14.
doi: 10.1111/jsap.13428. Online ahead of print.
J Todd , P Thomas , S Nguyen
目的:この研究の目的は、新規に診断され、化学療法をまだ受けていないB細胞性多中心型リンパ腫の犬に対し、シクロフォスファミドとプレドニゾロンを投与した時の反応率と毒性プロフィールの特徴を述べることだった。
素材と方法:著者の施設で化学療法の治療をまだ行っていないB細胞性リンパ腫と診断された犬を前向きに確認し(2017-2021)、飼い主の了解を得て最初の化学療法剤としてプレドニゾロンと併用し、シクロフォスファミドを投与した。シグナルメント、検査所見、ステージ、治療反応、毒性を記録した。
結果:32頭の犬を研究に含めた。この集団の総反応率は84%だった。20頭(62%)の犬は部分奏功、3頭(9%)は完全寛解、4頭(12%)は安定疾患、5頭(15%)は進行性疾患だった。47%に副作用が見られ、好中球減少が最も多く報告された。
臨床的意義:シクロフォスファミドとプレドニゾロンは限られた副作用で、許容性は良かった。化学療法を受けていないB細胞性多中心型リンパ腫の犬のこの集団で観察された反応率は有望である。この治療の安全性と有効性を確認する追加比較研究が必要である。(Sato訳)
■犬の体表リンパ節の吸引あるいは非吸引細針標本の細胞学的クオリティーの比較
A comparison of cytologic quality in fine-needle specimens obtained with and without aspiration from superficial lymph nodes in the dog
J Small Anim Pract. 2021 Sep 30.
doi: 10.1111/jsap.13429. Online ahead of print.
V Karakitsou , M M Christopher , E Meletis , P Kostoulas , D Pardali , C K Koutinas , M E Mylonakis
目的:犬のリンパ節から得た細針標本の細胞学的クオリティーに対する吸引の影響を評価し、2つのサンプリング方法間の細胞学的診断の一致レベルを比較する
素材と方法:53頭の飼育犬を前向きに登録した。リンパ節の細胞学的検査が、臨床的診断作業の流れで指示された場合、この研究に前向きに登録した。各犬において、明らかにアクセス可能な2か所の体表リンパ節からサンプル採取した:1か所は21Gの針を用い5mLシリンジで細針吸引、もう1つは21Gの針で非吸引。細胞質、血液コンタミネーション、厚さ、細胞保存、細胞質破砕をあらかじめ定義したスコアシステムを用いて評価する2人の観察者により、細胞学的クオリティーを複製したスメアで評価した。
結果:53頭の飼育犬をこの研究に含めた。評価した全ての細胞学的クオリティーパラメーターに対し、2つのサンプリング方法の間のスコアに有意差は見つからなかった。Cohen's kappa係数は0.84(95%CI、0.68-1.00)で、サンプリング方法の間の診断的一致が示された。
臨床的意義:この研究で、細針吸引および細針非吸引法ともに、細胞学的診断で許容できる一致性があり、同等の細胞学的クオリティーのリンパ節標本が得られた。(Sato訳)
■ロムスチン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LOPP)併用化学療法で治療した犬の非緩慢性T細胞性リンパ腫に対する予後指標
Prognostic indicators for naïve canine non-indolent T-cell lymphoma treated with combination lomustine, vincristine, procarbazine and prednisolone (LOPP) chemotherapy
Vet Comp Oncol. 2021 Aug 31.
doi: 10.1111/vco.12768. Online ahead of print.
John Blaxill , Peter Buzzacott , Jessica Finlay
背景:無処置の非緩慢性T細胞性リンパ腫(TCL)の犬に対し、ロムスチン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LOPP)化学療法は効果的な治療と提唱されている。LOPP化学療法で治療したTCLの犬に対する予後因子を評価した研究はない。
目的:この回顧的研究の目的は、犬の無処置の非緩慢性TCLをLOPP化学療法で治療した時の潜在的予後因子を評価することだった。
素材と方法:1か所の獣医腫瘍専門病院において、LOPP化学療法プロトコールで治療した無処置の非緩慢性TCLの回顧的コホート研究
結果:67頭の犬が組み込み基準に合致した。無進行生存期間(PFS)、総生存期間(OST)、完全寛解の持続期間(DCR)を含む結果を評価した。全体のPFS中央値は118日(範囲7-2302日)だった。OST中央値は202日(範囲8-2302日)だった。全体のDCR中央値は316日(範囲38-2261日)だった。投与した治療回数(p<0.0001)、多中心型疾患(p=0.044)、高カルシウム血症の存在(p=0.006)はPFSの予後的指標だった。治療回数の増加(p<0.0001)と年齢(p=0.0088)はOSTの予後的指標だった。
結論:我々の知るところでは、これはLOPP化学療法で治療したTCLに対するPFSの正の予後指標として高カルシウム血症を述べた最初の研究である。LOPP化学療法は、無処置の高カルシウム血症性非緩慢性TCLに対する第一選択治療プロトコールと考えることができる。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の犬に対する第一選択治療としてL-アスパラギナーゼ、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン(LHOP)化学療法
L-Asparaginase, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisolone (LHOP) Chemotherapy as a First-Line Treatment for Dogs with Multicentric Lymphoma
Animals (Basel). 2021 Jul 26;11(8):2199.
doi: 10.3390/ani11082199.
Jih-Jong Lee , Albert Taiching Liao , Shang-Lin Wang
Free PMC article
犬のリンパ腫の治療に対するCHOP(C、シクロフォスファミド;H、ドキソルビシン;O、ビンクリスチン;P、プレドニゾロン)化学療法プロトコールのうち、ビンクリスチンやドキソルビシンに比べ、シクロフォスファミドは最も弱い治療効果である。
20頭の多中心型リンパ腫の犬をLHOPプロトコール(シクロフォスファミドの代わりにL-アスパラギナーゼを使用)で治療し、その結果を同施設で過去にCHOP化学療法で治療した犬の結果と比較した。
年齢(p=0.107)、体重(p=0.051)、性別(p=0.453)、臨床ステージV(p=1)、サブステージb(p=0.573)、T細胞表現型(p=0.340)、全体の反応(p=1)、高カルシウム血症の状態(p=1)に関し、LHOPとCHOP群に有意差を認めなかった。L-アスパラギナーゼの副作用は、許容性が良く自己限定的だった。
LHOP群の無病期間(PFS)中央値は344日(範囲:28-940日)で、生存期間(ST)中央値は344日(範囲:70-940日)だった。
CHOP群のPFS中央値は234日(範囲:49-1822日)で、ST中央値は314日(範囲:50-1822日)だった。
LHOP化学療法を受けた犬のPFSは、CHOP化学療法を受けた犬よりも有意に長かった(p=0.001)。LHOP群とCHOP群のSTに有意差は観察されなかった(p=0.131)。
ゆえに、我々の研究所見は、LHOPプロトコールは、犬の多中心型リンパ腫の第一選択化学療法プロトコールとして使用できることを示す。(Sato訳)
■シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンをベースにした化学療法プロトコールで治療した多中心型リンパ腫の犬の予後因子として好中球増多の評価
Evaluation of neutrophilia as a prognostic factor in dogs with multicentric lymphoma treated with a cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone-based chemotherapy protocol
J Am Vet Med Assoc. 2021 Sep 1;259(5):494-502.
doi: 10.2460/javma.259.5.494.
Sridhar Veluvolu, MacKenzie Pellin, Nathaniel Vos
目的:まだ何もしていない多中心型リンパ腫の犬において、最初の診断時の好中球増多は無増悪生存期間(PFST)あるいは総反応率(すなわち、完全寛解あるいは部分寛解の犬の比率)に関係したかどうか、最初の好中球-リンパ球比がPFSTに関係するかどうかを調べる
動物:多中心型リンパ腫と好中球増多の犬30頭(シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン(CHOP)ベースプロトコールで治療した16頭を含む)と、CHOPベースで治療した好中球増多のない過去のコントロール犬37頭
方法:医療記録を再調査し、PFSTsと反応を記録した
結果:好中球増多でCHOPベースプロトコールで治療した16頭(70日;範囲0-296日)の犬のPFST中央値は、好中球増多のないコントロール犬37頭(184.5日;範囲23-503日)のそれより有意に短かく、好中球増多の犬(12/16(75%))の総反応率は、好中球増多のない犬(36/37(97%))の率より有意に低かった。しかし、この研究の全ての犬とコントロール集団を共に考えた時、診断時の好中球-リンパ球比は、PFSTと有意に関係しなかった。
結論と臨床関連:最初の診断時の好中球増多は、多中心型リンパ腫の犬の予後がより悪いことを示唆するかもしれないと結果は示唆した。担癌犬の末梢循環及び腫瘍の微環境において好中球の役割に対する前向き調査が正当化される。(Sato訳)
■犬の多中心型リンパ腫の病理組織学的診断においてコアニードルバイオプシーの有効性
Core-Needle Biopsy efficacy in histopathology diagnosis of canine multicentric lymphoma
Top Companion Anim Med. 2021 Jul 11;100561.
doi: 10.1016/j.tcam.2021.100561. Online ahead of print.
Juliana Silva do Nascimento , Tábata Maués , Juliana da Silva Leite , Ana Maria Reis Ferreira , Maria de Lourdes Gonçalves Ferreira
コアニードルバイオプシー(CNB)は現在、ヒトのリンパ腫の診断や分類に広く使用されている。しかし、リンパ腫が疑われる犬に対し、獣医療でCNBの使用を報告している研究はあまりない。
この研究は、犬の多中心型リンパ腫の診断に対するCNBサンプル収集物の有効性を評価することだった。
全身性末梢リンパ節腫大と、リンパ腫を示唆する細胞病理学的特徴を持つ種々の犬種の16頭の犬を研究に登録した。
左側膝窩リンパ節のCNBの後、リンパ節切除を実施した。両サンプルで病理組織評価を実施した。16頭中14頭はリンパ腫だった。リンパ腫に対し陽性だったCNBは14頭中12頭(85.7%)だった。多中心型リンパ腫の犬の診断に対しCNB解析の感受性は86%で、特異性は100%だった。
CNBは犬の多中心型リンパ腫の確定診断や、顕微鏡的評価の達成に向け全身性リンパ節腫脹において効果的で、細胞のサイズ、病理組織学的タイプ、グレードのような形態学的分類に対し重要な特徴を明らかにする。(Sato訳)
■犬の上皮向性および非上皮向性皮膚型T細胞性リンパ腫における結果と予後因子
Outcomes and prognostic factors in canine epitheliotropic and nonepitheliotropic cutaneous T-cell lymphomas
Vet Comp Oncol. 2021 Jul 11.
doi: 10.1111/vco.12752. Online ahead of print.
Kazushi Azuma , Aki Ohmi , Yuko Goto-Koshino , Hirotaka Tomiyasu , Koichi Ohno , James K Chambers , Kazuyuki Uchida , Hiroyuki Namba , Masahiko Nagata , Eiji Nagamine , Kazumi Nibe , Mitsuhiro Irie , Hajime Tsujimoto
犬の皮膚型リンパ腫は、犬の珍しいリンパ腫の1つである。ほとんどの犬の皮膚型リンパ腫症例は、T細胞由来である。犬の皮膚型T細胞性リンパ腫(CTCL)は、上皮向性と非上皮向性皮膚型リンパ腫に分類され、リンパ腫の各タイプでいくつかの組織学的サブタイプに細分類される。CTCLの犬の臨床的変数および病理組織学的サブタイプの予後的意義に関する情報は限られている。
この回顧的研究の目的は、CTCLの犬の予後に対する臨床的変数および病理組織学的サブタイプの影響を調査することだった。
病理組織検査でCTCLと診断された46頭の犬を含めた。病理組織学的標本を再検査し、CTCLサブタイプに分類した。全体の生存期間(OS)に対する皮膚病変のタイプ、病理組織学的サブタイプ、血液学的検査結果、治療に対する反応の影響を調べた。
31頭は上皮向性CTCL(28頭は菌状息肉腫;3頭はパジュエット様細網症)と診断され、15頭は非上皮向性CTCL(6頭は未分化大T細胞性リンパ腫;9頭は末梢T細胞性リンパ腫でそれ以外特定できなかった)と診断された。
上皮向性CTCLと診断された犬(141日)のOSは、非上皮向性CTCLと診断された犬(374日)のそれよりも有意に短かった。臨床的変数として、末梢血の腫瘍性リンパ球の存在、血小板減少、最初の化学療法への反応は予後と関係した。
我々の結果は、病理組織学的サブタイプといくつかの臨床的変数は、CTCLの犬の予後に影響することが分かったことを示した。
■今まで治療せず、末梢結節があり、中-大細胞性リンパ腫をプレドニゾンのみで治療した犬の生存期間
Survival time for dogs with previously untreated, peripheral nodal, intermediate- or large-cell lymphoma treated with prednisone alone: the Canine Lymphoma Steroid Only trial
J Am Vet Med Assoc. 2021 Jul 1;259(1):62-71.
doi: 10.2460/javma.259.1.62.
Kenneth M Rassnick, Dennis B Bailey, Debra A Kamstock, Casey J LeBlanc, Erika P Berger, Andrea B Flory, Michael A Kiselow, Joanne L Intile, Erin K Malone, Rebecca C Regan, Margaret L Musser, Nathan Yanda, Chad M Johannes
目的:過去に治療しておらず、末梢結節があり、中-大細胞性リンパ腫をプレドニゾン単独で治療した犬に対する生存期間を評価する
動物:アメリカの15施設から募集した109頭の飼育犬
方法:犬にプレドニゾンを40mg/m2、PO、1日1回7日間投与し、その後20mg/m2、PO、1日1回で投与した。治療開始時(0日)、治療開始後1、2週目、その後4週間ごとにビジュアルアナログスケールで、オーナーによりQOLを評価してもらった。関心の主要結果は、カプラン-マイヤー法で判定した生存期間だった。生存期間に関係するかもしれないファクターは調査した。
結果:全体の生存期間中央値は50日(95%CI、41-59日)だった。生存期間に関係するファクターは、サブステージ(a vs b)と免疫表現型(B細胞vsT細胞)だった。0日目と14日目のオーナーが評価したQOLスコアは、生存期間と有意にポジティブに相関した。QOLを二分した時、0日あるいは14日目のQOLスコアが50以上の犬は、50未満の犬よりも有意に生存期間が長かった。長期生存(>120日)を予測する変数はなかった。
結論と臨床関連:今まで治療していないで、末梢に結節があり、中あるいは大細胞性リンパ腫をプレドニゾンのみで治療した犬に対する生存期間は短かったと示唆された。オーナーが認めたQOLと臨床医が評価したサブステージは、両方とも生存期間に関係した。所見は、臨床医にとって治療方針決定時に、オーナーと話し合うための潜在的に重要な情報を提供する。(Sato訳)
■B細胞型慢性リンパ球性白血病の犬における臨床結果と予後因子:回顧的研究
Clinical outcome and prognostic factors in dogs with B-cell chronic lymphocytic leukemia: A retrospective study
J Vet Intern Med. 2021 May 17.
doi: 10.1111/jvim.16160. Online ahead of print.
Emily D Rout , Julia D Labadie , Janna A Yoshimoto , Paul R Avery , Kaitlin M Curran , Anne C Avery
Free article
背景:犬のB細胞型慢性リンパ球性白血病(BCLL)は、一般に進行が遅いと考えられるが、過去の研究は幅広い生存期間を示している。
目的:著者らはBCLLはヒトの慢性リンパ急性白血病に似て、不均一な臨床経過を取ると仮説を立てた。目的は、BCLLの犬の症状と結果を査定し、臨床とフローサイトメトリーのファクターの予後的関連を評価することだった。
動物:フローサイトメトリーにより診断されたBCLLの犬121頭。3つの犬種群を示した:BCLLのリスク増加のため小型犬種の犬(n=55);未変異免疫グロブリン遺伝子の優先使用のためボクサー(n=33);他の犬種(n=33)。
方法:回顧的研究で、BCLLの犬のシグナルメント、臨床病理データ、身体検査所見、治療、生存性を再検討した。細胞増殖(フローサイトメトリーによるKi67-発現CD21+B-細胞の比率により判定)は、121頭中39頭で測定した。臨床および検査の変数は、生存性との関係を評価した。
結果:全症例の生存期間中央値(MST)は、300日(範囲、1-1644日)だった。ボクサー(MST、178日)は、ボクサー以外の犬(MST、423日;P<.0001)よりも生存期間が有意に短く、小型犬種の犬とボクサー以外の犬の生存期間に有意差はなかった。犬種に関係なくKi67の高い(>40%
Ki67-発現B-細胞)症例(MST、173日)は、<40% Ki67の症例(MST判定できず;P=.03)よりも有意に生存期間が短かった。リンパ球が高い(>60000リンパ球/μL)、あるいは来院時の臨床症状がある症例は有意に生存期間が短かった。
結論と臨床的重要性:B細胞型慢性リンパ球性白血病は、変動しやすい臨床経過を持ち、ボクサー犬やKi67の高い症例は、より攻撃的な疾患である。
■CHOPで治療した犬の瀰漫性大細胞型B細胞性リンパ腫における予後因子として末梢血球比
Peripheral blood cell ratios as prognostic factors in canine diffuse large B-cell lymphoma treated with CHOP protocol
Vet Comp Oncol. 2020 Nov 28.
doi: 10.1111/vco.12668. Online ahead of print.
J Henriques , R Felisberto , F Constantino-Casas , J Cabeçadas , J Dobson
瀰漫性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)は犬の最も一般的な造血腫瘍で、ヒトのそれの臨床モデルとして認識されている。近年、CHOP化学療法で治療したDLBCLの犬において、好中球リンパ球比(NLR)およびリンパ球単球比(LMR)が、無増悪期間(TTP)およびリンパ腫特定生存期間(LSS)を予測することが示されている。
DLBCLと診断された59頭の犬において、血液学的パラメーターと導き出した比率(NLR、LMR、血小板リンパ球比(PLR)、血小板好中球比(PNR)、180日と365日目の比率として関連する副次的評価項目(TTPRとLSSR))の予後的価値を回顧的に評価した。
PNRはTTPR/180および365日に対し独立した予後マーカーで(P≦0.001)、0.032以上のPNRの犬は、180日前に進行する確率が高かった(感受性46.5%、特異性87.5%、p=0.004)。一変量解析でNLRはLSSR/180(p=0.006)とLSSR/365(p=0.009)に対し、予後的意義を示した。NLRの基礎値が7.45以下は、180日目の生存性に正の関係を示した(感受性52%、特異性85.3%、p=0.025)。サブステージbの存在は、早期進行に関係し、180日目の生存性を低下させた(p=0.031)。貧血は有意に365日目のLSSRを低下させた(p=0.028)。
これは犬のDLBCLにおけるPLRおよびPNRを評価した最初の研究で、PNRはリンパ腫の早期進行の指標となる可能性があることを証明する。末梢血球組成は、重度の非腫瘍性の原因でも影響を受ける可能性があるため、均一の組み込み基準を設けた大規模多施設研究の開発は、CHOP化学療法で治療したDLBCLの犬における血球比の確実な予後的価値をよりよく判定する助けとなるだろう。(Sato訳)
■猫のリンパ腫のレスキュー治療としてロムスチン、メトトレキサート、シタラビン化学療法
Lomustine, methotrexate and cytarabine chemotherapy as a rescue treatment for feline lymphoma
J Feline Med Surg. 2020 Nov 12;1098612X20972066.
doi: 10.1177/1098612X20972066. Online ahead of print.
Katherine Smallwood , Aaron Harper , Laura Blackwood
目的:この研究の目的は、猫のリンパ腫のレスキュー治療として、ロムスチン、メトトレキサート、シタラビン化学療法の効果と許容性を評価することだった。
方法:2013年から2018年の間に1施設において、再燃性高グレード猫リンパ腫に対し、ロムスチン、メトトレキサート、シタラビンで治療した13頭の猫の医療記録を調査した。全ての解剖学的タイプを含めた。データは記述統計で分析した。
結果:9頭の猫は全3種の薬剤が投与され、4頭は進行性疾患のため2種類のみ投与された。全て3種類を投与された(あるいはその治療の意向があった)猫において、6/13(46%)は化学療法による完全あるいは部分奏功を示した。治療は一般的によく許容されたが、2頭の猫はVeterinary
Comparative Oncology Group(VCOG)グレード3の好中球減少、1頭の猫はVCOGグレード3の血小板減少を起こした。無増悪生存期間中央値は61日(範囲16-721日)だった。
結論と関連性:猫のリンパ腫に対し、CHOP-(シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)およびCOP-ベースのプロトコールが第一選択化学療法として確立されているが、標準レスキュープロトコールはない。ロムスチンはポピュラーな単剤オプションとなっているが、長期あるいは累積骨髄抑制で治療遅延となる可能性があり、再燃のリスクがある。ゆえに、多剤ロムスチン-ベースのプロトコールが有利かもしれず(第一原理から)、また、抵抗性をより克服するはずである。
この研究は、猫のリンパ腫レスキューとしてロムスチン、メトトレキサート、シタラビンが有効で許容性の良いプロトコールかもしれないと示唆する。(Sato訳)
■多剤併用化学療法においてシクロフォスファミドの1回あるいは分割投与後の犬多中心リンパ腫の結果
Outcome of Canine Multicentric Lymphoma after Single or Divided Treatment with Cyclophosphamide in Multidrug Chemotherapy
Top Companion Anim Med. 2020 Jun 29;41:100461.
doi: 10.1016/j.tcam.2020.100461. Online ahead of print.
Jih-Jong Lee , Albert Taiching Liao , Shang-Lin Wang
リンパ腫の犬を治療するため、シクロフォスファミドは併用化学療法でよく使用される。シクロフォスファミド、アクロレインの代謝産物は、膀胱を刺激し、無菌性出血性膀胱炎を起こす可能性がある。複数の日にわたるシクロフォスファミドの分割投与は、膀胱におけるこの代謝物の濃度を低くし、膀胱炎の可能性を減ずるかもしれない。しかし、この方法の治療効果への影響は評価されず、従来の1回の最大耐容量法と比較されていない。
シクロフォスファミドのボーラス投与あるいは分割投与を行った多中心型リンパ腫の犬72頭を、この研究に含めた。2つのシクロフォスファミド投与群に出血性膀胱炎の発生の有意差はなかった(P=0.357)。2群の無増悪期間および生存期間に統計学的差はなかった(P=0.267およびP=0.346)。
リンパ腫の犬において、シクロフォスファミド投与のこの変更は、膀胱炎の副作用を減らすことなく、寛解および生存期間に影響することもなかった。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の犬の最初の化学療法中の体重変化と臨床結果との関係
Association between weight change during initial chemotherapy and clinical outcome in dogs with multicentric lymphoma
Vet Comp Oncol. 2020 Jul 12.
doi: 10.1111/vco.12637. Online ahead of print.
Wei-Shan Lee , Jih-Jong Lee , Albert Taiching Liao , Chia-Lien Kao , Shang-Lin Wang
リンパ腫の犬のわかっている予後因子のほとんどは、治療開始前、あるいは診断時に評価されている。治療の初期の段階で評価した予後因子はあまり述べられてないが、重要な臨床的情報を提供してくれるかもしれない。
この回顧的研究において、診断から化学療法の5週後までの体重変化により、82頭のリンパ腫の犬を分類した。最初の体重から>5%増加あるいは>5%減少した犬を、体重増加群と体重減少群に分類した。5%以下の体重変化の犬は、体重維持群と分類した。
体重増加群、体重維持群、体重減少群の無増悪期間(PFS)中央値は、それぞれ226日、256日、129日だった。体重減少群は増加群および維持群よりも有意にPFSが短かった(それぞれP=0.023、P=0.003)。体重増加、維持、減少群の生存期間(ST)中央値は、それぞれ320日、339日、222日だった。3群でSTに有意差はなかった(P=0.128)。Cox回帰の結果で、体重変化群と最初の体重は、PFSに関係する有意なリスクファクター(それぞれP=0.007、P=0.001)だが、STに対する有意なリスクファクターは最初の体重だけだった(P=0.013)。
結論として、最初の体重および経過中の体重変化の評価は、多中心型リンパ腫の犬のPFSおよびSTに関する有益な情報を提供できる。(Sato訳)
■64頭のイングリッシュスプリンガースパニエルにおける特発性化膿性肉芽腫性リンパ節炎の特徴と結果
Characterisation and outcome of idiopathic pyogranulomatous lymphadenitis in 64 English springer spaniel dogs.
J Small Anim Pract. 2019 Jul 17. doi: 10.1111/jsap.13052. [Epub ahead of print]
Dor C, Gajanayake I, Kortum A, Day MJ, Tappin S, Harris B, Battersby I, Walker D, Glanemann B, Myatt P, Dunning M, Bexfield N.
目的:特発性化膿性肉芽腫性リンパ節炎と診断されたイングリッシュスプリンガースパニエルの病歴、臨床病理異常、診断画像所見、リンパ節細胞診/組織検査所見、治療、結果を述べる
素材と方法:この回顧的UKベースの多施設研究において、2010年から2016年の間に、委託センター10施設、一時診療32施設、病理組織/細胞検査3施設から64頭の犬を採用した。
結果:来院時の年齢中央値は6歳(範囲:0.17-11.75歳)だった。避妊したメスが多く罹患していた。発熱(83.8%)、末梢リンパ節腫大(78.4%)、皮膚病変(72.9%)、元気消失(67.6%)、食欲低下(54%)、下痢(29.7%)、発咳(24.3%)、鼻出血、くしゃみ、鼻汁(21.6%)、眼症状(21.6%)、嘔吐(16.2%)が、病歴および身体検査記録が得られた犬で報告された。膝窩(45.3%)、浅頸(35.9%)、顎下(37.5%)リンパ節腫大が多く報告された。血液および血性生化学検査に特異的変化はなかった。診察時、全ての症例で感染疾患の検査は陰性だった。リンパ節細胞診、病理組織検査あるいはその両方で混合炎症(27%)、化膿性肉芽腫(24%)、好中球(20%)、肉芽腫(11%)性リンパ節炎が示された。治療の詳細は38頭の犬で入手でき、そのうち34頭はプレドニゾロンを投与期間中央値15週(範囲:1-28週)で投与されていた。両から優良な臨床反応は1症例以外の全ての犬で報告された。10頭はプレドニゾロン中止後に再発した。
臨床意義:イングリッシュスプリンガースパニエルにおける特発性化膿性肉芽腫性リンパ節炎は、リンパ節腫大と発熱の鑑別診断に入れるべきである。その疾患の特徴は、確認できる感染源がないこと、グルココルチコイドに反応することは免疫介在性の病因を示唆する。(Sato訳)
■尿の細胞診およびフローサイトメトリーによる犬の腎臓リンパ腫の診断
Diagnosis of canine renal lymphoma by cytology and flow cytometry of the urine.
Vet Clin Pathol. 2020 Mar 3. doi: 10.1111/vcp.12825. [Epub ahead of print]
Witschen PM, Sharkey LC, Seelig DM, Granick JL, Dykstra JA, Carlson TW, Motschenbacher LO.
リンパ腫は犬の一般的な造血性腫瘍である。確定診断には一般に針吸引あるいはバイオプシーによるサンプルの収集が必要である。尿沈渣顕微鏡検査とフローサイトメトリーおよびT細胞受容体再構築に対するPCR(PARR)を用いて診断した犬の腎臓T細胞性リンパ腫の独特な症例を紹介する。
新鮮な尿サンプルは尿カテーテルで採取し、すぐに細胞診、フローサイトメトリー、PARRに対する準備をした。
フローサイトメトリー検査は、臍傍の83%が大型CD3+CD8+T細胞と示し、一方PARRはクローナリー再編成T細胞受容体遺伝子を確認し、フローサイトメトリー所見を支持した。
支持療法にもかかわらず、その犬は無尿性腎不全に進行し、人道的に安楽死された。検死を行い、上部および下部尿道から組織を採取した。組織学的に右および左腎に皮質と髄質がなくなった腫瘍性円形細胞集団に浸潤されていた。TおよびB細胞抗原CD3およびCD20に対する免疫組織化学染色で、腎臓内の腫瘍集団は、瀰漫性、強い、膜様の細胞質内CD3発現を示したが、CD20発現は欠如していた。それらの結果、腎臓T細胞リンパ腫の診断を確認した。
これは尿フローサイトメトリーあるいはクローナリティ検査で診断した犬リンパ腫の最初の報告である。ゆえに、選ばれた症例で、尿フローサイトメトリーおよび/あるいはPARRは、尿路リンパ腫の診断で役立つ迅速で費用対効果の高い方法として尿中細胞に対し実行可能である。(Sato訳)
■犬の無菌性ステロイド反応性リンパ節炎の犬49頭
Canine sterile steroid-responsive lymphadenitis in 49 dogs.
J Small Anim Pract. May 2019;60(5):280-290.
DOI: 10.1111/jsap.12980
A Ribas Latre , A McPartland , D Cain , D Walker , V Black , N Van Den Steen , S Warman , I Battersby , K Murtagh , P Silvestrini , D Batchelor , S W Tappin
目的:イギリスで無菌性ステロイド反応性リンパ節炎と診断された犬の臨床および検査の特徴、治療反応、結果を報告する
材料と方法:6か所の専門二次センターで2009年から2016年の間に無菌性ステロイド反応性リンパ節炎と診断された犬の医療記録を回顧的に評価した。
結果:研究に49頭の犬を含めた。スプリンガースパニエルが多く見られた(16頭)。若い犬(中央値:3歳9か月)とメス犬(31頭)が多く罹患していた。臨床症状は不定で、発熱(39頭)、元気消失(35頭)、食欲不振(21頭)が多く報告された臨床症状だった。リンパ節細胞診あるいは病理検査は、全ての症例で基礎に検出可能な原因がない、好中球性、化膿肉芽腫性、肉芽腫性あるいは壊死性リンパ節炎を示した。無菌性免疫介在性の病因が疑われたため、全ての犬にプレドニゾロンを投与し、続いてほとんどの症例で臨床症状とリンパ節腫脹の急速な解消が見られた。
臨床意義:無菌性ステロイド反応性リンパ節炎は、炎症性リンパ節腫脹と原因不明の発熱を伴う犬で、基礎の原因が見つからない場合考慮すべきで、免疫抑制のコルチコステロイド治療によく反応することが多い。(Sato訳)
■再燃性あるいは難治性多中心型リンパ腫の犬に対するラバクホサジンとL-アスパラギナーゼの併用
Concurrent use of rabacfosadine and L-asparaginase for relapsed or refractory multicentric lymphoma in dogs.
J Vet Intern Med. 2020 Feb 16. doi: 10.1111/jvim.15723. [Epub ahead of print]
Cawley JR, Wright ZM, Meleo K, Post GS, Clifford CA, Vickery KR, Vail DM, Bergman PJ, Thamm DH.
背景:犬のリンパ腫の治療に条件付きで認可された新しい抗腫瘍薬のラバクホサジン(RAB)は、無治療あるいは過去に治療された犬に対して効果的である。その薬剤とL-アスパラギナーゼ(L-ASP)との併用はまだ研究されていない。
仮説と目的:再燃性多中心型リンパ腫の犬に対し、L-ASPとRABの併用の安全性と効果を評価する
動物:最低1回のドキソルビシンベースの化学療法プロトコールを受けた後に、リンパ腫が再燃した犬52頭
方法:非盲検多施設前向き単一群臨床試験。合計5回まで、RABを1.0mg/kgで21日毎に静脈注射した。RABの最初の2回に、L-ASPを400IU/kg
SQを同時投与した。
結果:全ての犬に対する総奏功率(ORR)は67%で、19頭の犬(41%)は完全寛解(CR)に達した。無増悪生存期間中央値(MPFS)は63日(範囲5-428日)だった。一番良い反応でCRを経験した犬のMPFSは144日(範囲44-428日)だった。有害事象は過去に単剤RABで評価した研究と同じだった。CRに達しなかった犬や過去にL-ASPを投与されていた犬は、多変量解析の負の予後因子だった。
結論と臨床的重要性:RABとL-ASPの併用は、犬の再燃性多中心型リンパ腫の治療に対し、効果的で安全と思われる。有害事象はほとんどが軽度で、予期されない毒性は観察されなかった。(Sato訳)
■犬のB細胞型リンパ腫細胞株においてドキソルビシンの抗腫瘍効果をイマチニブは強化する
Imatinib enhances the anti-tumour effect of doxorubicin in canine B-cell lymphoma cell line.
Vet J. 2019 Dec;254:105398. doi: 10.1016/j.tvjl.2019.105398. Epub 2019 Nov 2.
Chen W, Liu I, Tomiyasu H, Lee J, Cheng C, Liao AT, Liu B, Liu C, Lin C.
犬のリンパ腫は犬で発生する最も一般的な悪性腫瘍の一つで、世界中で高い発生率を示す。がん予防の進歩にかかわらず、腫瘍疾患の治療は未だ改善が必要である。いくらかのがん細胞は、薬剤流出の増加に導く薬物輸送体の上方制御により化学療法剤の効果に抵抗を示すかもしれず、内因性あるいは獲得性薬剤抵抗を起こし、それは一般的にドキソルビシン-抵抗性腫瘍細胞に見られるメカニズムの一つである。
この研究では、培養中にドキソルビシン濃度を増すことでCLBL-1に由来するドキソルビシン-抵抗性B細胞型リンパ腫細胞株、犬B細胞型リンパ腫細胞株CLBL1-8.0はP-糖蛋白(P-gp、ATP-結合カセット サブファミリーBメンバー1(ABCB1))の高い発現を示す。
それらの蛋白は一般にドキソルビシンに抵抗性のがん細胞に関与する。チロシンキナーゼ阻害剤のイマチニブは、P-gp過剰発現したドキソルビシン-抵抗性細胞において、ドキソルビシンの感受性を有意に強化した。さらに、それら2薬剤の組み合わせは、P-gp蛋白過剰発現に影響することなく、ドキソルビシンの流出を低下させることでドキソルビシンの保持を増加させるかもしれない。
結論として、P-gp過剰発現ドキソルビシン抵抗性犬リンパ腫細胞において、イマチニブは薬剤流出を低下させることで、ドキソルビシン抵抗性を逆転させた。
それらの結果は、犬のリンパ腫の治療に最も広く使用されている化学療法剤の一つであるドキソルビシンと、イマチニブの併用は、臨床でドキソルビシン抵抗性に打ち勝つ可能性を秘めているのかもしれない。(Sato訳)
■リンパ腫の犬の血小板数に対するビンクリスチンの影響の評価
Evaluation of the effect of vincristine on platelet count in dogs with lymphoma.
J Small Anim Pract. 2019 Nov 18. doi: 10.1111/jsap.13080. [Epub ahead of print]
Campbell O, MacDonald VS, Dickinson RM, Gagnon J.
目的:リンパ腫と診断された犬の血小板数、血小板の形態、血小板減少症の発生率に対するビンクリスチン投与の影響を調べる
素材と方法:硫酸ビンクリスチンを投与したリンパ腫の犬59頭の医療記録を回顧的に再検討した。
結果:ビンクリスチン投与後、血小板数はより高く、血小板減少症の犬の頭数は少なかった。ビンクリスチン投与後の拡大した血小板及び楕円形の血小板の犬の頭数に違いは見られなかった。
臨床医意義:リンパ腫の犬で、ビンクリスチン投与は血小板数を増加させる。血小板減少のリンパ腫の犬に対するビンクリスチンの投与は禁忌ではない。(Sato訳)
■チロシンキナーゼインヒビターによるリンパ管肉腫の治療に成功した子犬の1症例
Successful management of lymphangiosarcoma in a puppy using a tyrosine kinase inhibitor.
Can Vet J. April 2018;59(4):367-372.
Ji-Hyun Kim , Hakyoung Yoon , Hun Young Yoon , Kidong Eom , Hyun-Jeong Sung , Jung-Hyun Kim
1頭の子犬がリンパ管造影と病理検査を基にリンパ水腫に関係するリンパ管肉腫と診断された。病変はトセラニブによる治療で解消し、その犬は1年後も寛解を維持している。これは1頭の犬のリンパ管肉腫の第一選択治療として、経口トセラニブ投与後に良好な結果を得られた最初の報告である。(Sato訳)
■CCR4阻害は膀胱癌のイヌモデルで制御性T細胞を大幅に減少させ、生存期間を延長する
CCR4 Blockade Depletes Regulatory T Cells and Prolongs Survival in a Canine Model of Bladder Cancer.
Cancer Immunol Res. 2019 Jul;7(7):1175-1187.
Maeda S, Murakami K, Inoue A, Yonezawa T, Matsuki N.
制御性T細胞(Treg)浸潤は、がん免疫療法として標的とすることが出来る可能性がある。
ここでは、膀胱癌の犬モデルにおけるこの戦略の治療効果について記述する。
自然発生する膀胱癌の犬を使用して、膀胱癌組織へのTreg浸潤の分子メカニズムと抗Treg治療の効果を研究した。腫瘍浸潤性Tregを免疫組織化学により評価し、膀胱癌の犬で予後との関連を調べた。Treg浸潤の分子メカニズムは、RNAシーケンスとタンパク質分析によって調査した。マウス異種移植実験およびイヌ研究を使用して、膀胱癌に対する抗Treg治療の治療的可能性を調査した。
腫瘍浸潤Tregは、自然発症膀胱癌を発症した犬の予後不良と関連があった。 Treg浸潤は、腫瘍の成長を促すケモカインCCL17と、Tregに発現する受容体CCR4との相互作用によって引き起こされた。 CCR4阻害は、異種移植マウスモデルの腫瘍成長と組織へのTreg浸潤を抑制した。自発性膀胱癌の犬は、抗CCR4治療に反応し、生存率が向上し、臨床的に関連する毒性の発生率が低くなった。膀胱癌のヒト患者では、免疫組織化学により、腫瘍浸潤性TregがCCR4を発現していることを示した。
よって、抗CCR4治療は、膀胱癌のヒト患者を対象とした臨床試験の合理的なアプローチかもしれない。(Dr.Masa訳)
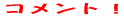 基礎から臨床研究まで繋がっている報告。日本からこういった報告が発信されるのは嬉しいですね。非ランダム化比較試験ですが、OS中央値でピロキシカム単独群は241日、ピロキシカム・ヒト化抗CCR4抗体併用群で474日(p
= 0.000568)。
基礎から臨床研究まで繋がっている報告。日本からこういった報告が発信されるのは嬉しいですね。非ランダム化比較試験ですが、OS中央値でピロキシカム単独群は241日、ピロキシカム・ヒト化抗CCR4抗体併用群で474日(p
= 0.000568)。
■犬びまん性大細胞型B細胞リンパ腫のPD-L1陽性の定量と予後
Quantification and prognostic value of programmed cell death ligand-1 expression in dogs with diffuse large B-cell lymphoma
Lisbeth A. Ambrosius, Deepika Dhawan, José A. Ramos-Vara, Audrey Ruple, Deborah W. Knapp, Michael O. Childress
Am J Vet Res 2018;79:643-649.
目的:犬びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の原発病変のPD-L1mRNA発現を測定し無腫瘍生存期間と関連があるか調べる。
サンプル:罹患42頭の標本と10頭の正常リンパ節(コントロール)。
方法:両群を多重qPCR分析(中略)PD-L1mRNAを測定した。(中略)Kaplan-MeierとCox比例ハザード分析を行い無腫瘍生存期間とさまざまな腫瘍および臨床因子を評価した。
結果:PD-L1mRNAは正常群と比べて0.21-7.44倍であった。42頭中21頭(50%)は1より多く過剰発現であった。リンパ腫の無腫瘍生存期間中央値は249日でPD-L1mRNAとは関連がないが診断時の血小板減少とは関連があった(ハザード比2.56、95%信頼区間1.28-5.15)。
結論と臨床意義:PD-L1mRNA発現は様々であるが半数例で過剰に発現していた。そのためPD-L1抗体は特定の犬では有効かもしれない。(Dr.Maru訳)
■ゴールデンレトリーバーにおけるCD45陰性T細胞(Tゾーン細胞)の増加
Increased frequency of CD45 negative T cells (T zone cells) in older Golden retriever dogs
K. L. Hughes, J. D. Labadie, J. A. Yoshimoto, J. J. Dossey, R. C. Burnett, A. C. Avery
Vet Comp Oncol. 2018;16:E109-E116.
Tゾーンリンパ腫(TZL)はCD45抗原を欠くT細胞(TZ細胞)のクローン増殖によって特徴付けられ、ゴールデンレトリーバーで認められる。本研究は異常なCD45mRNAを確認し、臨床的にリンパ腫を発症していないゴールデンレトリーバーに循環しているTZ細胞の増加があるかを見る。TZLと確認された遺伝子分析では遺伝子発現は正常犬と比べてCD45の有意な減少が認められた。高齢犬の末梢血サンプルとして242頭のゴールデンと42頭のゴールデン以外でリンパ増殖疾患ではないものについてTZ細胞の存在をフローサイトメトリーで評価した。
31%のゴールデンはTZ細胞があり、非ゴールデンでは14%であった。TZ細胞をもつゴールデンの24%はクローン性T細胞レセプターガンマ遺伝子の再編成を持っていた。
ゴールデンはTZ細胞数の増加によりTZLになるリスクが高いのかもしれない。(Dr.Maru訳)
■多中心リンパ腫に侵され化学療法を行っている犬の腸管寄生虫感染
Intestinal parasite infections in dogs affected by multicentric lymphoma and undergoing chemotherapy.
Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2019 Apr;63:81-86. doi: 10.1016/j.cimid.2019.01.006. Epub 2019 Jan 19.
Cervone M, Gavazza A, Zbriger A, Mancianti F, Perrucci S.
高グレード多中心リンパ腫に罹患し、化学療法の治療を受けている犬とコントロールの健康犬において、腸管寄生虫の有病率と種類構成を評価した。
入手したデータは統計学的に解析した。
全体の腸管寄生虫感染の有病率は33.3%だった。リンパ腫の犬において、プロトゾア感染の有病率(46.7%)は蠕虫感染(6.7%)よりも有意に高く(P<0.05)、ジアルジアduodenalis、クリプトスポリジウム属、ネオスポーラcaninum、シストイソスポーラohioensis-複合体、アメーバ種、スピロセルカlupiが確認された。コントロールの犬において、15頭中3頭(20%)にだけ陽性が見つかり、蠕虫(鉤虫と犬回虫)やプロトゾア(ジアルジアduodenalis)感染に関して統計学的有意差は見られなかった。
この研究の結果は、高グレード多中心リンパ腫に罹患している犬において、数種の潜在的な人獣共通種を含む日和見的な腸管プロトゾアのより高い有病率を示す可能性が示唆され、このことは、リンパ腫にかかった犬の特に化学療法で治療している犬で、それらのプロトゾアに対するモニターの必要性を強調するものである。(Sato訳)
■環境、健康歴、Tゾーンリンパ腫、および意義が未確定のTゾーン様細胞の関連性:高齢のゴールデンレトリーバーの症例対照研究
Associations of environment, health history, T-zone lymphoma, and T-zone-like cells of undetermined significance: A case-control study of aged Golden Retrievers.
J Vet Intern Med. 2019 Jan 21. doi: 10.1111/jvim.15405.
Labadie JD, Magzamen S, Morley PS, Anderson GB, Yoshimoto J, Avery AC.
【背景】T領域リンパ腫(TZL)は、高齢犬において緩徐に進行する疾患であり、犬のリンパ腫の約12%を占めている。
TAL細胞は活性化された表現型を示し、これは疾患が抗原惹起型であることを示している。
以前の研究では、無徴候性の老齢ゴールデンレトリーバー(GLDRs)で意義が不明のT領域様細胞(表現型的にはTZLと同じ)(T-zone-like
cells of undetermined significance TZUS)の集団を一般に存在することを見出した。
【目的】GLDRsのケース-コントロールを用いることで炎症が認められること, TZLとTZUSの関連性を明らかにする。
【動物】フローサイトメトリーで診断されたTZL症例(n = 140)は、コロラド州立大学のClinical Immunology Laboratoryによって同定された。 研究参加に関心のある所有者のデータベースまたはTZL症例の提出クリニックのいずれかを介して募集された非TZL犬は、その後フローサイトメトリーでTZUS(n = 221)または対照(n = 147)に分類された。
【方法】健康歴、特徴、環境、および生活習慣の要因は、所有者が記入した質問表から得た。
オッズ比(OR)および95%信頼区間(95%CI)は、多変量ロジスティック回帰を使用して推定し、TZLおよびTZUSについて(対照に対して)別々の推定値を得た。
【結果】甲状腺機能低下症(OR, 0.3, 95%CI, 0.1-0.7)、オメガ3補給(OR,
0.3, 95%CI, 0.1-0.6)、および疥癬(OR, 5.5, 95%CI, 1.4-21.1)は有意にTZLに関連していた。
胃腸疾患(OR, 2.4; 95%CI, 0.98-5.8)では、TZLオッズは有意には増加しなかった。
TZLとTZUSの2つの共通の関連性が同定された: 膀胱感染または結石(TZL OR, 3.5;
95%CI, 0.96-12.7; TZUS OR, 5.1; 95%CI, 1.9-13.7)および眼疾患(TZL OR,
2.3; TZL OR 95%CI, 0.97-5.2; TZUS OR, 0.97-5.2; TZUS OR, 1.9; 9.5%CI,
0.99-3.8)
【結論と臨床的重要性】これらの知見は、TZUSのリスクおよびTZUSからTZLへの進行に関与する経路を解明する可能性があるかもしれない。 オメガ3サプリメントの保護的な関連についてのさらなる調査が必要である。(Dr.Masa訳)
コメント:日本ではGLDRsによりはシー・ズーでよく遭遇する気がします。基礎疾患の治療を施すことで、腫瘍への影響を軽減する可能性があることは予防医学的な観点で非常に有用な報告だと思います。
■リンパ腫の犬に対しミトキサントロンとダカルバジンの多剤化学療法の許容性の評価
Evaluation of the Tolerability of Combination Chemotherapy with Mitoxantrone and Dacarbazine in Dogs with Lymphoma.
J Am Anim Hosp Assoc. 2019 Jan 17. doi: 10.5326/JAAHA-MS-6878. [Epub ahead of print]
Intile JL, Rassnick KM, Al-Sarraf R, Chretin JD.
犬の抵抗性リンパ腫の治療に対し、併用化学療法は効果的なオプションである。
この回顧的研究は、ドキソルビシンを含む化学療法プロトコールに抵抗性のあるリンパ腫の犬の集団において、5-(3,3-dimethyl-1-triazeno)-imidazole-4-carboxamide(ダカルバジン)(DTIC)の組み合わせの許容性と効果について検査した。
3週間ごとにミトキサントロンを5mg/m2で10分以上かけてIV投与し、その後DTICを600mg/m2で5時間以上かけてIV投与した。全ての犬に予防的にトリメトプリム-スルファジアジンとメトクロプラミドを投与した。
グレード4の好中球減少の頻度は18%で、敗血症で入院した犬は5%だった。消化管毒性は珍しかった。全体の反応率は34%(44頭中15頭;95%信頼区間20-48%)で、持続期間の中央値は97日(範囲24-636日、95%信頼区間44-150日)だった。最初のレスキューとしてミトキサントロンとDTICを投与された15頭中14頭は治療に反応した。最初にL-アスパラギナーゼ、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン化学療法プロトコールで完全寛解に至った犬は、ミトキサントロンとDTICに反応する確率がより高かった(23vs11%、P=0.035)。
ミトキサントロンとDTICの組み合わせは、抵抗性リンパ腫の犬の安全な治療オプションである。(Sato訳)
■多中心型中-大細胞性リンパ腫の犬の多剤併用化学療法に対する第一選択治療においてドキソルビシンに代わりミトキサントロンの使用
Substitution of mitoxantrone for doxorubicin in a multidrug chemotherapeutic protocol for first-line treatment of dogs with multicentric intermediate- to large-cell lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. 2019 Jan 15;254(2):236-242. doi: 10.2460/javma.254.2.236.
Marquardt TM, Lindley SES, Smith AN, Cannon CM, Rodriguez CO Jr, Thamm DH, Childress MO, Northrup NC.
目的:多中心性中-大細胞性リンパ腫の犬の第一選択治療として、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン(CHOP)化学療法プロトコールにおいて、ドキソルビシンの代わりにミトキサントロンの使用効果を評価する
デザイン:回顧的コホート研究
動物:12カ所の二次診療施設において、シクロフォスファミド、ミトキサントロン、ビンクリスチン、プレドニゾロン(CMOP)で治療した犬44頭と、CHOPで治療した犬51頭
方法:治療に対する反応、無増悪生存期間、全生存期間を調べるために医療記録を見直した。CMOPで治療した犬に対し、有害事象も記録した。
結果:CMOPで治療した全44頭(100%)とCHOPで治療した38頭中37頭(97.4%)は完全あるいは部分奏功だった。CMOPで治療した犬の無増悪生存期間中央値は165日(95%信頼区間(CI)、143-187日)で、全生存期間中央値は234日(95%CI、165-303日)だった。CHOPで治療した犬の無増悪生存期間中央値は208日(95%CI、122-294日)、全生存期間中央値は348日(95%CI、287-409日)だった。無増悪および全生存期間にグループ間で有意差はなかった。全体で、CMOPで治療した44頭中9頭(20%)は、おそらくたぶんミトキサントロンに関連する有害事象があったが、それらすべて軽度であった。
結論と臨床関連:多中心型中-大細胞性リンパ腫の犬の治療で、ドキソルビシンが禁忌の場合、ミトキサントロンはCHOPプロトコールの適切な代用薬かもしれないと結果は示唆した。(Sato訳)
■皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫の2頭の犬のイソトレチノインとインターフェロンαに対する臨床反応:ケースリポート
Clinical response to isotretinoin and interferon-α of two dogs with cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma: a case report.
BMC Vet Res. 2018 Dec 4;14(1):382. doi: 10.1186/s12917-018-1710-y.
Lee GW, Song SB, Kang MH, Park HM.
背景:皮膚上皮向性T細胞性リンパ腫(cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma:CETL)に対する特定の治療はない。犬のCETLに対するレチノイドとインターフェロン-α(IFN-α)の投与の組み合わせは報告されていない。
症例提示:2頭の犬(シーズーとミニチュアピンシャー)は、多発性結節性皮膚病変を呈した。病理組織検査で表皮と真皮にリンパ球のびまん性浸潤とCD3陽性免疫表現型プロフィールを認めた。臨床および病理組織検査をもとに、CETLを診断した。2頭ともイソトレチノインとINF-αで治療し、完全あるいは部分奏功の臨床的改善を示した。それらの犬の疾患は、治療開始から更なる臨床症状もなく、生存期間中央値264日以上にわたってうまくコントロールできた。2頭の犬で、27か月と10か月の追跡調査を行い、再発あるいは転移の所見はなかった。
結論:著者らはCETLの2頭の犬で、イソトレチノインとINF-α併用の臨床効果を述べる。イソトレチノインとINF-αの組み合わせによる長期管理は、それら症例のCETLの治療において有効であった。(Sato訳)
■犬のB細胞性リンパ腫に対する第一治療としてドキソルビシンとプレドニゾンの回顧的分析
Retrospective analysis of doxorubicin and prednisone as first-line therapy for canine B-cell lymphoma.
BMC Vet Res. 2018 Nov 20;14(1):356. doi: 10.1186/s12917-018-1688-5.
Al-Nadaf S, Rebhun RB, Curran KM, Venable RO, Skorupski KA, Willcox JL, Burton JH.
背景:犬の高グレードB細胞性リンパ腫に対し、ドキソルビシン(DOX)ベース化学療法プロトコール、CHOPは最も効果的な治療である;しかし、このプロトコールにかかるコストと時間は、多くのオーナーに実行可能なものではない。1つの代替治療オプションは最も効果的な薬剤のDOXとプレドニゾンの組み合わせである。DOX単剤治療の過去の研究は、既知の負の予後因子、T細胞性リンパ腫の犬を含み、B細胞性リンパ腫の犬を別々に分析するよりも、報告された生存期間がより短いかもしれないということがあった。この研究の目的は、DOXとプレドニゾン±L-アスパラギナーゼ(L-ASP)で治療した時、ハイグレードB細胞性リンパ腫の犬の結果を評価することだった。予後因子の確認は2つ目の目的だった。
結果:33頭の犬を研究した;31頭は反応が評価可能で、全体の反応率は84%だった。無増悪期間(PFS)と全体の生存期間(OS)の中央値は147日と182日だった。1年生存率は23%だった。PFSあるいはOSに対し、プロトコール完了以外のサブステージ、血小板減少、体重など従来の予後因子を含む変数で有意なものは見つからなかった。
結論:DOXとプレドニゾン±L-ASPで治療した高グレードB細胞性リンパ腫の犬は、リンパ腫免疫表現型で区別しなかった過去の研究の反応率、PFS、OSと同様である。このプロトコールはCHOPの代わりにはならないが、プレドニゾン単独よりも大きな治療効果が得られ、時間とコストが問題となる場合の代替法である。(Sato訳)
■舌に発生したイヌT-zoneリンパ腫の臨床病理学的特徴
Clinicopathologic features of lingual canine T-zone lymphoma
Vet Comp Oncol. 2018;16:131?139.
L. J. Harris, E. D. Rout, K. L. Hughes, J. D. Labadie, B. Boostrom, J. A. Yoshimoto, C. M. Cannon, P. R. Avery, E.J. Ehrhart, A. C. Avery
イヌTゾーンリンパ腫(TZL)はユニークな組織学的パターン、細胞形態でCD45が喪失、無症候性のT細胞リンパ腫のサブタイプである。イヌTZLは一つ以上のリンパ節腫大、リンパ球増加症を程することが多い。我々はTZLの新たな節外型である舌に発生したものについて報告する。フローサイトメトリー、細胞診、病理、免疫染色、抗原受容体再構成(PARR)アッセイのためのPCRによる免疫表現系の様々な組み合わせを元に舌に発生したTZLを12頭の犬で診断した。
11頭ではリンパ球増加症やリンパ節の腫大が認められた。3頭では当初病理検査のみで形質細胞腫瘍と診断されており、診断は難しい可能性がある。様々な治療で7頭は寛解が得られ、4頭は安定しており、リンパ節と末梢血においては無症候性のままであった。1頭では進行し治療に反応せず、組織学的に高悪性度であった。この論文ではTZLのユニークな特徴に焦点を当て、舌腫瘍の新しい鑑別診断を述べる。また舌TZLの12頭の犬の臨床特徴、診断、結果について特徴付けた。(Dr.Maru訳)
■多中心型リンパ腫の超高齢犬に対する化学療法の有用性
Usefulness of chemotherapy for the treatment of very elderly dogs with multicentric lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. April 2018;252(7):852-859.
DOI: 10.2460/javma.252.7.852
Antony S Moore, Angela E Frimberger
目的:ステージIIIからVの多中心型リンパ腫の14歳以上の犬において、初回寛解期間と生存期間に関係する要因を評価する
計画:回顧的コホート研究
動物:より若い犬に使用する用量の化学療法(n=22)、あるいはプレドニゾロン単独(7)で治療した多中心型リンパ腫の14歳以上の犬29頭
方法:医療記録から治療反応や関連する有害事象を含む様々なデータを集めた。最初の寛解の持続期間および生存期間(化学療法開始から)を生存分析で判定し、それらの結果を種々のグループで比較した。
結果:プレドニゾロン単独で治療した7頭(24%)は、生存期間中央値が27日で、その後の分析から除外した。残りの22頭のうち、21頭(95%)は臨床的完全寛解に達した;1頭(5%)は部分寛解に達した。最初の寛解の持続期間の中央値は181日だった。貧血の犬(中央値110日)は、そうでない犬(中央値228日)よりも短い寛解期間だった。全22頭の生存期間中央値は202日で、1年および2年生存率はそれぞれ31%と5%だった。6頭(27%)はグレード3、あるいはそれより悪く分類される化学療法の有害事象を起こした。
結論と臨床関連:プレドニゾロン単独に対し、化学療法で治療した犬は生存期間が大幅に長くなった。リンパ腫に対し評価した化学療法プロトコールは、年齢を理由に化学療法の中止や投与量の調節の必要もなく、より若い犬のように超老齢犬に有益で許容することが示唆された。(Sato訳)
■CCNUは犬の皮膚上皮向性リンパ腫の治療として有効か?:批判的吟味のトピック
Is CCNU (lomustine) valuable for treatment of cutaneous epitheliotropic lymphoma in dogs? A critically appraised topic.
BMC Vet Res. 2017 Feb 21;13(1):61. doi: 10.1186/s12917-017-0978-7.
Laprais A, Olivry T.
背景:皮膚(上皮向性)T細胞性リンパ腫(cutaneous T-cell lymphoma:CTCL)と診断された犬の治療について、CCNUと他の治療プロトコールが一般的にオーナーに提供される。化学療法プロトコールは不定な利益を提供する;それらは異なる副作用を持ち、一般的にオーナーにとって無視できないコストで薬物毒性を検出するためのモニタリングを必要とする。
この時点で、CCNUはCTCLの犬の治療で最もよく推奨されているが、この薬剤の利点に対する明らかなコンセンサスはない。最も高い確率で完全寛解や長期生存期間が得られる化学療法プロトコールを知っておくことは、入手できる一番のエビデンスを基に獣医師やオーナーが治療オプションを選択するのに役立つだろう。
我々の目的は、CCNUベースのプロトコールと他の処置の間で、完全寛解率と生存期間を比較する文献を再検討した。CTCLの少なくとも5頭の犬で治療結果を報告している文献において含まれているデータを批判的に調査した。1頭の症例報告および5頭以下のケースシリーズは、低クオリティの不確かなエビデンスを避けるため再検討しなかった。
結果:2017年2月8日の時点で得られる最良のエビデンスの検索および再検討、分析で、CCNUとペグ化リポソーマルドキソルビシンが、CTCLの約三分の一の犬において最も高い完全寛解率が得られると思われることが示唆された。他の治療プロトコールは、寛解率に対して使用できる情報を報告していなかった。治療しない場合、CTCLの犬の生存期間の平均/中央値は3-5ヶ月と変動した。CCNUプロトコールで生存期間中央値は6か月、レチノイド(イソトレチノインおよび/あるいはエトレチナート)、PEG L-アスパラギナーゼ、あるいはプレドニゾロン単独療法はそれぞれ11.9ヶ月と4か月だった;しかし、全てそれらの期間は少数の犬から得られたものだった。
結論:CCNUは皮膚T細胞性リンパ腫の約三分の一の犬の症状を完全寛解に導くが、それら寛解は短期間である。CCNU後の生存期間中央値は、治療しなかったときよりも長く思えるが、他の薬剤がより良い長期予後を提供すると思われる。CCNUの効果、単独あるいは多剤、寛解率、生存期間、QOLへの影響について調査する追加研究が必要である。(Sato訳)
■高グレード原発性縦隔リンパ腫の犬の患者特性、予後因子、転帰
Patient characteristics, prognostic factors and outcome of dogs with high-grade primary mediastinal lymphoma.
Language: English
Vet Comp Oncol. March 2018;16(1):E45-E51.
DOI: 10.1111/vco.12331
E L Moore , W Vernau , R B Rebhun , K A Skorupski , J H Burton
この回顧的研究の目的は、高グレード原発性縦隔リンパ腫の犬の患者特性を調べることと、転帰および関連する予後因子を判定することだった。
合計42頭の犬を確認し、そのうち36頭は治療を受け、経過情報が入手できた。
最も一般的な臨床症状は、元気消失、食欲不振、多尿/多飲だった。高カルシウム血症と胸水は診断時の一般的な所見だった。表現型は、ほとんどが排他的にT細胞性で、WHOリンパ腫分類シェーマに定義されたリンパ芽球性細胞形態に関連していることが多かった。
全体の無増悪生存期間(PFS)と総生存期間(OS)は133日と183日だった。CHOP(シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)プロトコールによる治療は、他の薬剤治療を受けた犬と比べてPFS(144日)とOS(194日)を改善した(それぞれP=0.005とP=0.002);診断時に胸水がないことは、OSを増加させたが、PFSはそうではなかった。
それらの結果は、縦隔リンパ腫の犬の予後は悪いが、CHOPベースのプロトコールで治療した場合に生存期間を改善するかもしれないと示唆する。(Sato訳)
■治療を受けていない犬の多中心性リンパ腫に対するビンブラスチン単剤の反応率
Response rate to a single dose of vinblastine administered to dogs with treatment-naive multicentric lymphoma
Vet Comp Oncol. 2018 Aug 16. doi: 10.1111/vco.12433.
Harding K, Bergman N, Smith A, Lindley S, Szivek A, Milner R, Brawner W, Lejeune A.
ビンクリスチンは、犬の高悪性度リンパ腫に対するゴールドスタンダードな治療である、ビンクリスチン・シクロホスファミド・ドキソルビシン・プレドニゾロン(CHOP)化学療法プロトコルに組み入れられている。ビンクリスチンは比較的高い頻度で、胃腸障害が認められることあるが、ビンブラスチンは一般的に忍容性が高く、加えてあまり使用されておらず、毒性が最小限であるため、ビンクリスチンの代用薬となる可能性がある。
この研究の目的は、治療を受けていない中-大細胞性の多中心性リンパ腫を有する犬に、投与されたビンブラスチンの単回投与による奏効率と毒性を決定することである。
20頭のご家族がいる犬が、ご家族の同意を得て組み入れられた。ビンブラスチンを2mg/m2で投与した効果に続いて、ビンブラスチンを2.5mg/m2投与するパイロットスタディを、サイモンのミニマム、フェーズⅡ、2段階試験を行った。
同時にステロイドまたは他の化学療法を投与された犬はいなかった。2mg/m2でビンブラスチンを投与された、14例の犬のうち1例で部分奏功が認められた。
5例のうち3例が2.5mg/m2のビンブラスチンに対して部分奏功が認められた。胃腸毒性は両群とも稀で、低グレードであった。
2.5mg/m2を投与した群の犬の大半(80%)は、投与1週間後に好中球減少が認められた。
ビンブラスチンは治療を受けていない、多中心性リンパ腫を有する犬で、2mg/m2の用量で、良好な忍容性を示したが、有効性は最小限であった。反応率が乏しいためこの用量での治療は推奨されない。2.5
mg/m2を投与された犬の少ないサブセットの群では、有意な改善率(P = 0.04)を示し、これらの予備的所見を確認するためのさらなる研究が必要であるが、高用量で有効性が改善される可能性があることを示唆している。(Dr.Masa訳)
 評価方法
評価方法
7日目で治療・毒性評価を終了しその他の治療へ移行している為、この臨床試験の一時点・短期間での評価を、長期間の寛解や予後予測に一般化してはいけないと思います。また、論者が指摘するように、この論文のポピュレーション(中?大型犬中心)でのビンブラスチンの用量は、2.0mg/m2では恐らく不十分である可能性は高いように思います。
■ロムスチン・ビンクリスチン・プロカルバジン・プレドニゾロン併用化学療法で治療された、犬のT細胞性リンパ腫の35例
Canine T cell lymphoma treated with lomustine, vincristine, procarbazine, and prednisolone chemotherapy in 35 dogs
Vet Comp Oncol. 2018 Aug 16. doi: 10.1111/vco.12430.
Morgan E, O'Connell K, Thomson M, Griffin A.
犬のT細胞性リンパ腫はB細胞性リンパ腫と比較し、過去に予後が悪いと報告されている。犬のリンパ腫に対して、シクロホスファミド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・プレドニゾロンプロトコルは広く第一選択として用いられている。T細胞性リンパ腫に他の治療法がいくつかの研究で試みられている。
この研究では、T細胞リンパ腫を有する35例の犬の第一選択治療として、変更型ロムスチン・ビンクリスチン・プロカルバジン・プレドニゾロンプロトコルの使用を調査した。
全35例の犬の無進行生存(PFS)期間中央値は431日で、6ヶ月、1年、2年および3年のPFSはそれぞれ69%、54%、29%および12%であった。中央生存期間(MST)は507日であった。
29例の犬で完全寛解が認められ、PFS中央値は509日間だった。 30例の犬でプロトコルの間に有害事象が認められ、そのうち73%がグレード1または2であった。このプロトコルは、以前の研究と比較して、PFSの中央値およびMSTの延長が認められ、犬のT細胞リンパ腫に対する第一選択の化学療法プロトコルとしての使用が示唆される。(Dr.Masa訳)
 近年時々報告されるT細胞性リンパ腫用のプロトコルをこの論文でも検討しています。ただ、突っ込み所がちょっと多い論文です。最も気になる点は、似たプロトコルのBrown
PM et al.,VCO, 2017とは違い、「臨床上進行が早い」と曖昧な組み入れ基準でLow-grade/indolentリンパ腫(特にT-zone
リンパ腫)が除外されていない可能性があることです(上皮向性皮膚型リンパ腫は除外されています)。またエントリーしている犬種は中・大型が多く、このプロトコルのまま本邦で用いるのは、有害事象の面から厳しいと感じます。
近年時々報告されるT細胞性リンパ腫用のプロトコルをこの論文でも検討しています。ただ、突っ込み所がちょっと多い論文です。最も気になる点は、似たプロトコルのBrown
PM et al.,VCO, 2017とは違い、「臨床上進行が早い」と曖昧な組み入れ基準でLow-grade/indolentリンパ腫(特にT-zone
リンパ腫)が除外されていない可能性があることです(上皮向性皮膚型リンパ腫は除外されています)。またエントリーしている犬種は中・大型が多く、このプロトコルのまま本邦で用いるのは、有害事象の面から厳しいと感じます。
■犬の再発性B細胞性リンパ腫に対するラバクフォサディン:異なった2つの用量での効果と有害事象
Rabacfosadine for relapsed canine B-cell lymphoma: Efficacy and adverse event profiles of 2 different doses
Vet Comp Oncol. 2018 Mar;16(1):E76-E82. doi: 10.1111/vco.12337. Epub 2017 Sep 11.
Saba CF, Vickery KR, Clifford CA, Burgess KE, Phillips B, Vail DM, Wright ZM, Morges MA, Fan TM, Thamm DH.
非環式ホスホリン酸ヌクレオチドPMEGの新規2重プロドラッグであるラバクフォサディン(RAB)は、標的外毒性を減らし、選択的に腫瘍性リンパ球を標的とする。21日毎の薬用量で副作用は許容でき、効果が認められると、過去の研究で示唆されている。
この研究の目的は、再発性B細胞性リンパ腫の犬に21日毎に2つの異なる用量で投与した時のRABの安全性と効果を評価することである。
この前向き研究には、1回ドキソルビシンをベースとした化学療法プロトコルがうまく行かなかった症例が組み入れられた。登録された際に、RAB投与を5回まで、21日毎に、0.82mg/kgか、もしくは1mg/kgの30分かけて静脈投与で行うかどうか、ランダムに振り分けられた。反応性評価と、有害事象(AEs)の評価はVCOGクライテリアに基づき、21日毎に評価された。
50例の犬が組み入れられ、16例が0.82mg/kgで、34例が1.0mg/kgで治療を受けた。全反応率は74%で、45%の症例で完全寛解(CR)が認められた。無病進行期間中央値(PFIs)は、全ての犬、反応が認められた犬、CRの犬で、それぞれ108日、172日、203日だった。反応率とPFIsは両群で同様だった。AEsの発生、投与延期、投与量の減量や休薬に2つの群で有意な差は認められなかった。血液学的、胃腸、皮膚や肺のAEsは(同薬剤の)過去の報告と同様だった。1症例でGrade 5の肺線維症が認められたが、一方でAEsは支持療法で改善された。
ラバクフォサディンは通常忍容性が高く、再発性B細胞性リンパ腫の犬の化学療法プロトコルオプションとして効果的であった。(Dr.Masa訳)
 過去の研究結果(Vail DM et al., Clin Cancer Res, 2009)から多中心性B-細胞性リンパ腫を組み入れています。ラバクフォサディンをCHOPに組み込んで治療していく方がよいのか、レスキュー治療に回した方が良いのか、今後の研究結果が待たれる所ですが、少なくても、現時点では心強いレスキュー治療になる可能性が高い治療だという印象を受けました。
過去の研究結果(Vail DM et al., Clin Cancer Res, 2009)から多中心性B-細胞性リンパ腫を組み入れています。ラバクフォサディンをCHOPに組み込んで治療していく方がよいのか、レスキュー治療に回した方が良いのか、今後の研究結果が待たれる所ですが、少なくても、現時点では心強いレスキュー治療になる可能性が高い治療だという印象を受けました。
■消化器型小細胞性リンパ腫として過去に治療されたあと、大細胞性リンパ腫が認められた猫:発生率、臨床徴候、臨床病理学的データ、二次性悪性腫瘍の治療、反応と生存について
Feline large-cell lymphoma following previous treatment for small-cell gastrointestinal lymphoma:incidence, clinical signs, clinicopathologic data, treatment of a secondary malignancy, response and survival
J Feline Med Surg. 2018 Jun 1:1098612X18779870. doi: 10.1177/1098612X18779870
Wright KZ, Hohenhaus AE, Verrilli AM, Vaughan-Wasser S1.
【アブストラクト】
【目的】 リンパ腫は猫の悪性腫瘍において一般的で臨床的に重要な悪性腫瘍である。消化器型(GI)小細胞性リンパ腫を罹患した猫の2次性がんを発症する確率は7-14%と報告されている。この研究の目的は小細胞性GIリンパ腫の治療を行ったあとに大細胞性リンパ腫と診断された猫における予後、治療への反応性、臨床病理学的データ、臨床徴候と発生率を評価することである。
【方法】 単一の専門病院の医療記録において、2008-2017年の間にリンパ腫と診断された全ての猫をレビューした。小細胞GIリンパ腫と診断した後の、大細胞リンパ腫の診断および完全な予後データがある症例が、さらなる検討のために選択された。
【結果】 740例の猫がリンパ腫と診断されていた。12例の猫(12/121)が小細胞性GIリンパ腫の治療を受けたあと、大細胞性リンパ腫の全ての解剖学的型が発生したと診断をうけていた。9例の猫がこの研究の組み入れ基準に該当し、分析に用いられた。小細胞性GIリンパ腫と診断されてから、大細胞性リンパ腫と診断されるまでの無病生存期間中央値は543日であり、生存期間中央値は615日だった。大細胞性リンパ腫と診断されてから、死亡までの無病生存期間中央値は55日で、生存期間中央値は24.5日だった。ヘマトクリット・アルブミンと総タンパク質は、小細胞性リンパ腫と診断された時の数値と比較し、大細胞性リンパ腫に進行したときでは、有意な減少が認められた。
【結論と関連性】 大細胞性リンパ腫は、消化器型小細胞性リンパ腫の治療を受けていた猫の9.9%(12/121)で発生した。猫の診療にあたる者は、消化器型小細胞性リンパ腫と診断されている猫の体重減少、貧血、低アルブミン血症や低蛋白血症が進行した場合、大細胞性リンパ腫を鑑別診断に加える必要がある。 (Dr.Masa訳)
■CHOPを行った犬リンパ腫における治療前の好中球数と毒性の関連
Impact of Pretreatment Neutrophil Count on Chemotherapy Administration and Toxicity in Dogs with Lymphoma Treated with CHOP Chemotherapy
Q. Fournier , J.-C. Serra, I. Handel, and J. Lawrence
J Vet Intern Med 2018;32:384?393
背景:化学療法前の好中球数のカットオフ値は任意であり施設ごと臨床家ごとに異なる。好中球低下の犬における予防的抗生物質投与も同様である。
目的:犬リンパ腫に対してCHOPを行うときの好中球数のカットオフ値について治療前とその後の毒性に関連があるか評価した。2つ目の目的として現在用いられている予防的抗生物質のカットオフ値について評価する。
動物:リンパ腫でCHOPを行った64頭
方法:615の好中球数について6つに分類した。3つの値1.5×10^3/μL, 2.0×10^3/μL,
2.5×10^3/μLについて評価した。好中球数のクラスと毒性の関連性を評価した。発熱のない好中球低下(1.5×10^3/μLを下回る)よりも高い数値での予防的抗生物質投与を行ったものも調査した。
結果:1.5×10^3/μLよりも少ないために化学療法を実施しなかったものは7%で存在した。2.0×10^3/μL, 2.5×10^3/μLでそれぞれ10%, 16%で実施されなかった。これら3つの低値群で毒性との間に関連は認められなかった。0.75-1.5×10^3/μLのものは治療しなくても自然に回復した。
結論と意義:1.5×10^3/μLをカットオフ値としたものでの投与延期は最小限に抑えられ、カットオフ値が1.5-1.99×10^3/μLでは毒性との関連はなかった。カットオフ値が0.75×10^3/μL付近における予防抗生物質の処方について調査する必要がある。(Dr.Maru訳)
■CTによる犬縦隔リンパ節の転移診断:横断的回顧的調査
Metastatic diagnosis of canine sternal lymph nodes using computed tomography characteristics: A retrospective cross- sectional study
R. Iwasaki, M. Murakami, M. Kawabe, K. Heishima, H. Sakai, T. Mori
Vet Comp Oncol. 2018;16:140?147.
胸骨リンパ節正確な評価は犬の胸部および腹部腫瘍のステージ分類で重要である。CTは非侵襲的であるが正確な診断ができるかどうかは明らかではない。本横断的回顧的検討ではCT測定の診断力を評価した。胸骨リンパ節に対してCTと細胞診を実施した57頭について回顧的に調査した。転移陰性(21頭)と陽性(36頭)の2群に分類した。ロジスティック回帰分析ではリンパ節の大きさ(胸骨リンパ節と第2胸骨比)とプレコントラスト減衰に有意差が認められた。これらのパラメータを組み合わせることで特異性および100%の陽性予測値(カットオフ値はそれぞれ1.0, 37.5HU)であった。このことからサイズ比とプレコントラスト減衰はCTによる胸骨リンパ節転移の鑑別に効果的である。(Dr.Maru訳)
■リンパ腫の形態と予後:体系的文献調査
Prognostic significance of morphotypes in canine lymphomas: A systematic review of literature
D. Sayag, C. Fournel-Fleury, F. Ponce
Vet Comp Oncol. 2018;16:12?19
犬リンパ腫では形態と予後に不一致しないところがあり臨床応用するには困惑するところがあった。本研究の目的は犬リンパ腫の形態の予後に関して体系的に述べることにある。システマティック・ レビューおよびメタアナリシスのための優先的報告項目(PRISMA)基準を用いた。後ろ向きおよび前向き研究が含まれていた。エビデンスレベルは研究ごとに判断した。ある研究は犬リンパ腫の形態が予後に影響を与えたと示唆されていたが、そのエビデンスは分類を正確に決定するには十分ではなかった。利用できる研究の数とエビデンスレベルから、アップデートされたKielとWHO分類が適切であった。無作為試験がないこと、前向き試験がないことが欠点であった。Current recommended classification of canine lymphoma is the systematic determination of morphotype in each new case. アップデートされたKielとWHO分類が最も価値のある分類である。大規模な前向き調査と各形態についての正確な定義についての国際的なコンセンサス、標準化されたステージ分類と治療が望まれる。(Dr.Maru訳)
■難治性猫リンパ腫に対するメクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾロンによるレスキュー化学療法プロトコール
Mechlorethamine, vincristine, melphalan and prednisolone rescue chemotherapy protocol for resistant feline lymphoma.
Language: English
J Feline Med Surg. October 2017;0(0):1098612X17735989.
Olya A Martin , Josh Price
目的:この回顧的研究の目的は、猫リンパ腫のレスキューに対しメクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾロン(MOMP)化学療法の使用を評価することと、プロトコールの毒性を述べ、無増悪生存期間に対する予後指標を判定する
方法:2007年から2017年の間にテネシー大学獣医メディカルセンターにおいてMOMP化学療法で治療した12頭の医療記録を評価した。評価したパラメーターは、リンパ腫細胞の大きさ、解剖学的部位、投与した過去のレスキュープロトコールの化学療法剤と数だった。化学療法関連毒性も記述した。
結果:12頭中7頭がレスキュープロトコールに反応した。持続期間中央値39日(範囲14-345日)の3頭は完全奏功を示し、4頭は部分奏功に至った。完全奏功の猫は、治療に反応しなかった猫よりも有意に長い無増悪生存期間だった。12頭中5頭は血液毒性(好中球減少)が発生し、1頭は消化管毒性が発生した。毒性はほとんどの症例で軽度だった;入院が必要な猫はいなかった。好中球減少は無増悪生存期間の増加に関係した。
結論と関連性:再燃性および難治性リンパ腫の猫に対し、MOMPは安全で効果的なレスキュー化学療法プロトコールである。(Sato訳)
■日本の柴犬の腸管T細胞性リンパ腫の病理学的特徴
Pathological features of intestinal T-cell lymphoma in Shiba dogs in Japan.
Vet Comp Oncol. 2018 Mar 25. doi: 10.1111/vco.12396. [Epub ahead of print]
Matsumoto I, Uchida K, Nakashima K, Goto-Koshino Y, Chambers JK, Tsujimoto H, Nakayama H.
腸管T細胞性リンパ腫は、獣医療で内視鏡やクローナリティ分析が広く利用されるようになって、犬で診断される頻度が多くなっている。しかし、腸管T細胞性リンパ腫に対する疫学的調査は過去に実施されておらず、腸管T細胞性リンパ腫の犬種、年齢、性別分布に関する情報は大部分が不明なままである。
この研究では、犬の腸管T細胞性リンパ腫に対する犬種素因をオッズ比と95%信頼区間を算出することで判定した。
確認した43犬種のうち、柴犬、ジャーマンシェパード、ケアンテリア、ボストンテリア、パピヨン、パグ、マルチーズの7犬種に腸管T細胞性リンパ腫の発生リスクの増加があると思われた。代表的な柴症例の免疫組織化学検査で大細胞および小細胞型リンパ腫両方に広範囲の細胞傷害性免疫表現型が見られた。
面白いことにCD20の同時発現が11%の症例に見られた。潜在的にCD20の異常な発現あるいはCD20陽性T細胞の正常な集団の腫瘍性転化の可能性があった。代表的犬種間の平均年齢の比較では、柴犬はミニチュアダックスフンドよりもわずかに若かった(P<0.05)が、2犬種の生存性に差はなかった。
柴犬は慢性腸症の素因があるため、この犬種ではその基礎にある炎症過程が腸管T細胞性リンパ腫の発生に寄与しているのかもしれない。我々の所見は、犬種特異な犬の腸管T細胞性リンパ腫の基礎にある病院への洞察を提供する。(Sato訳)
■猫の小腸リンパ腫において粘膜侵入および血管内細菌の識別
Identification of Mucosa-Invading and Intravascular Bacteria in Feline Small Intestinal Lymphoma.
Language: English
Vet Pathol. March 2017;54(2):234-241.
S N Hoehne , S P McDonough , M Rishniw , K W Simpson
消化管粘膜の持続的細菌感染は、ヒトや実験動物において胃癌や粘膜関連リンパ組織(mucosa-associated
lymphoid tissue:MALT)リンパ腫と因果関係がある。
著者らは猫の消化管型リンパ腫と粘膜関連細菌との関係を研究した。消化管型リンパ腫の猫50頭(小細胞性、n=33;大細胞性、n=17)とリンパ腫ではないコントロール猫38頭(病理組織検査において正常から最小の変化、n=18;リンパ球性プラズマ細胞性腸炎、n=20)の腸バイオプシーを評価した。細菌の数と空間分布(すなわち、腔内細胞デブリ、絨毛関連粘膜、上皮、粘膜侵入、血管内、漿膜への付着)をユーバクテリアプローブEUB-338による蛍光in situハイブリダイゼーションで判定した。
粘膜侵入最近は、小細胞性リンパ腫(18%)、病理組織で正常から最小の変化、およびリンパ球性プラズマ細胞性腸炎(3%)の猫よりも大細胞性リンパ腫(82%、P≦0.001)の猫でより多く観察された。血管内バクテリアは、もっぱら大細胞性リンパ腫(29%)で観察され、漿膜コロニー形成は小細胞性リンパ腫(11%、P≦0.01)、正常から最小の変化(8%、P≦0.01)、リンパ球性プラズマ細胞性腸炎(6%、P≦0.001)の猫よりも大細胞性リンパ腫((57%)の猫でより多かった。
大細胞性リンパ腫の猫の血管や漿膜内への高頻度の侵入細菌は、大細胞性リンパ腫に関係する敗血症関連性合併症を説明し、臨床管理に情報を与えるかもしれない。猫消化管型リンパ腫の原因病理において粘膜内細菌の役割を調査する追加研究が必要である。(Sato訳)
■多中心型B細胞性リンパ腫の犬におけるドキシサイクリンの第II相試験において検出された代謝異常
Metabolic Abnormalities Detected in Phase II Evaluation of Doxycycline in Dogs with Multicentric B-Cell Lymphoma.
Front Vet Sci. 2018 Feb 26;5:25. doi: 10.3389/fvets.2018.00025. eCollection 2018.
Hume KR, Sylvester SR, Borlle L, Balkman CE, McCleary-Wheeler AL, Pulvino M, Casulo C4, Zhao J.
ドキシサイクリンはヒトのリンパ腫細胞やマウスの異種移植片において増殖抑制効果を持つ。著者らは、ドキシサイクリンは犬のリンパ腫細胞生存性を低下させるだろうと仮説を立て、自発性、結節性、多中心性、サブステージa、B細胞性リンパ腫で過去に化学療法で治療していない飼育犬において、その臨床的耐容性を前向きに評価した。
投与期間は1-8週間の範囲だった(中央値および平均、3週間)。犬には10(n=6)あるいは7.5(n=7)mg/kg、1日2回で経口投与した。1頭は6週間安定疾患だった。完全あるいは部分奏功が見られた犬はいなかった。5頭の犬はビリルビン、ALT、ALP、±AST上昇で肝障害を示唆するグレード3および/あるいは4の代謝異常を発症した。
著者らの研究集団で、経口ドキシサイクリンの吸収を評価するため、10頭の投与犬の血清濃度を液体クロマトグラフィータンデム質量分析法で測定した。血清濃度は様々で3.6-16.6μg/ml(中央値、7.6μg/ml;平均、8.8μg/ml)の範囲だった。
インビトロにおける犬のリンパ腫細胞生存性に対するドキシサイクリンの効果を評価するため、犬のB細胞性リンパ腫細胞株(17-71およびCLBL)と、4頭の結節組織からの原発B細胞性リンパ腫細胞に対しトリパンブルー色素排除試験を実施した。6μg/mlのドキシサイクリン濃度は、犬のリンパ腫細胞生存性を、マッチした無処置のコントロール細胞と比較して80%抑制した(混合モデル解析、P<0.0001;Wilcoxon signed rank test、p=0.0313)。
ドキシサイクリンの短期経口投与は犬リンパ腫の奏功に関与しないが、追加研究でドキシサイクリンが犬のリンパ腫細胞の細胞生存経路を変える可能性があると判定されれば、併用療法をする価値があるかもしれない。代謝異常の可能性のため、担癌犬に対するこの薬剤の使用には密なモニタリングが勧められる。長期ドキシサイクリン治療の耐容性を評価する追加研究が必要である。(Sato訳)
■高グレードリンパ腫あるいは白血病の犬27頭におけるL-アスパラギナーゼ療法後の血漿アンモニア濃度
Plasma ammonia concentration after L-asparaginase therapy in 27 dogs with high-grade lymphoma or leukemia.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018 Feb 22. doi: 10.1111/vec.12695. [Epub ahead of print]
Speas AL, Lyles SE, Wirth KA, Fahey CE, Kow K, Lejeune AT, Milner RJ.
目的:高グレードリンパ腫あるいは白血病の犬において、L-アスパラギナーゼ(L-asp)投与後の血漿アンモニア濃度上昇の発生率を確認すること;L-asp投与後の高アンモニア血症の発生に対するリスク因子を確認すること;高アンモニア血症に関連する有害事象の発生を調べること
計画:2011年5月から2012年3月の間に連続して組み込んだ犬の前向き症例管理下試験
動物:高グレードリンパ腫あるいは白血病の犬27頭
処置:全ての犬にL-aspを投与量中央値400IU/kgで筋肉内投与した。
測定値と主要結果:基礎およびL-asp投与後16、48時間目に血漿アンモニア濃度を測定した。高アンモニア血症の発生に対するリスク因子を判定するため、臨床病理異常を評価した。L-asp投与後の有害事象を記録した。
基礎、16時間、48時間目の血漿アンモニア濃度中央値はそれぞれ、44μg/dL、166.9μg/dL、114μg/dLだった。投与後16および48時間目の血漿アンモニア濃度中央値は基礎値と比較して有意に上昇した。L-asp投与後に6頭に有害事象があった。明らかに高アンモニア血症によると思われる有意な臨床症状は見られなかった。高アンモニア血症発生に対するリスク因子は確認されなかったが、16時間と48時間目の高アンモニア血症発生に正の相関があった。
結論:L-asp投与後のリンパ腫あるいは白血病の犬において無症状の高アンモニア血症は一般的と思われる。L-asp投与後の高アンモニア血症の発生に対するリスク因子は確認されず、重度有害事象はまれだった。(Sato訳)
■再燃した犬の非ホジキン高グレードリンパ腫のロムスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LPP)多剤化学療法プロトコールによる治療の評価
Evaluation of a multi-agent chemotherapy protocol combining lomustine, procarbazine and prednisolone (LPP) for the treatment of relapsed canine non-Hodgkin high-grade lymphomas.
Vet Comp Oncol. 2018 Jan 30. doi: 10.1111/vco.12387. [Epub ahead of print]
Tanis JB, Mason SL, Maddox TW, Blackwood L, Killick DR, Amores-Fuster I, Harper A, Finotello R.
犬リンパ腫の標準治療は、プレドニゾロン、シクロフォスファミド、ビンクリスチン、ドキソルビシンのようなアントラサイクリン(CHOP)、あるいはエピルビシン(CEOP)による多剤化学療法である。ロムスチン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LOPP)はレスキューとして評価されており、励みになる結果を示しているが、CHOP/CEOPによる再発患者はビンクリスチンの耐性が起こっている可能性が高く、この薬剤は効果を改善することなくLOPP毒性を高めるかもしれない。
この研究の目的は、21日周期で投与するビンクリスチンを含まない修正LOPPに対する反応を評価する。
2012年から2017年の高グレード多中心型リンパ腫の犬の医療記録を再調査した。再燃したリンパ腫をレスキュープロトコールとしてLPPで治療された犬を登録した。LPPの反応、開始から中止までの期間(TTD)、毒性を評価した。41頭の犬を含めた。
25頭(61%)の犬がLPPに反応し、12頭は完全寛解(CR)、13頭は部分反応(PR)だった。反応のあった犬は反応がなかった犬と比べ、有意に長いTTD(P<0.001)で、CRは84日、PRは58日だった。好中球減少は20頭(57%)で認められた:12頭グレードIからII、8頭はグレードIIIからIV。血小板減少は頭数が少なかった(20%):5頭がグレードIからII、2頭がグレードIIIからIV。12頭は消化管毒性を起こした(30%):10頭はグレードIからII、2頭はグレードIII。19頭はALTが上昇した(59%):9頭がグレードIからII、10頭がグレードIIIからIV。8頭(19%)は毒性のために治療を中止した。
LPPプロトコールは容認できる効果と毒性プロフィールおよび院内処置が最少だと示す。(Sato訳)
■犬の小細胞T細胞性腸管リンパ腫の臨床的特徴と予後
Clinical characteristics and outcome in dogs with small cell T-cell intestinal lymphoma
Vet Comp Oncol. 2018 Jan 11. doi: 10.1111/vco.12384
Couto KM, Moore PF, Zwingenberger AL, Willcox JL, Skorupski KA.
腸管小細胞性リンパ腫は犬においてあまり良くわかっていない。
この研究の目的は犬の腸管小細胞性リンパ腫の臨床的特徴と予後を明らかにすることである。
腸管小細胞性リンパ腫の犬は、高グレード消化管(GI)リンパ腫と比較し、生存期間は長いと仮説した。小細胞性GIリンパ腫と病理組織学的に診断された犬の病理学的記録を検索した。17例の犬が小細胞性腸管リンパ腫と診断されており、回顧的に臨床的なデータと予後を集めた。病理組織診断は病理学認定医によってレビューされ、組織切片は免疫表現型と分子クロナリティ評価に用いられた。
全ての犬は、小細胞性、T細胞性、小腸の様々部分から診断されたリンパ腫で、1例で腹腔内リンパ節にも病変が認められた。全ての犬でGIの病気の影響による臨床徴候が認められた;下痢(13例)が最も一般的に認められた。超音波検査上の異常は、13例中8例で認められ、異常な層構造(7例)、高エコー性の線条所見(7例)が最も共通して認められた。
合計で14例の犬が何らかの治療を受けた。全ての犬の中央生存期間(MST)は279日であり、治療を受けた犬のMSTは628日だった。初診時に貧血と体重減少が認められた犬では、有意に生存期間が短く、ステロイドとアルキル化剤を併用した犬では、有意に長い生存期間が認められた。
小細胞性、T細胞性、腸管リンパ腫は犬で明らかに違った病気であり、これらの治療を行うことで、生存を延長できる可能性がある。
(Dr.Masa訳)
コメント:論文を読み進める前に、まず気になるのは、小細胞性(T細胞性)腸管リンパ腫という病気の診断基準をどう定義しているかですが、病理診断は
Peter F Moore先生1人がレビューを行い、小リンパ球の有意な浸潤(腸管絨毛粘膜固有層や上皮にリンパ球が浸潤するなど)が認められ、免疫組織化学染色でCD3陽性があり、PCRで評価をおこなっているようです。
■猫リンパ腫に対するレスキュー療法としてデキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシン-D、シタラビン化学療法プロトコール
A dexamethasone, melphalan, actinomycin-D and cytarabine chemotherapy protocol as a rescue treatment for feline lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2017 Oct 16. doi: 10.1111/vco.12360. [Epub ahead of print]
Elliott J, Finotello R.
再燃性高グレード/大型細胞性リンパ腫の猫19頭をデキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシン-D、シタラビン(DMAC)で治療した。全ての猫は第一線化学療法としてシクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン(COP)を投与されており、ほとんどの猫はレスキュー剤前に少なくとも2種投与されており、19頭中14頭はエピルビシンとロムスチンを投与されている。
5頭(26%)は化学療法に反応(腫瘍関連の臨床症状/腫瘍の大きさの改善あるいは解消、または完全/部分反応と定義)があったが、DMACの2サイクル以上投与された猫はいなかった。
ほとんどの猫はプロトコールをよく許容したが、3頭はVeterinary Cooperative
Oncology Group (VCOG)グレード4の好中球減少、1頭はグレード4の血小板減少を経験した。DMAC開始から無増悪期間と総生存期間の中央値はそれぞれ14日と17日だった。
再燃性リンパ腫の猫に対し、好結果のレスキュー化学療法プロトコールについてまだ課題があるが解決されない状態である。(Sato訳)
■リンパ腫の犬においてマッチした対照と比較したインスリン様成長因子、インスリン、乳酸およびβ-ヒドロキシ酪酸の血中濃度の予備調査
Preliminary investigation of blood concentrations of insulin-like growth factor, insulin, lactate and β-hydroxybutyrate in dogs with lymphoma as compared with matched controls.
Vet Comp Oncol. 2017 Dec 4. doi: 10.1111/vco.12376. [Epub ahead of print]
McQuown B, Burgess KE, Heinze CR.
正常細胞と比較して腫瘍細胞の代謝に違いがあることは良く確認されている。これはコントロール犬よりも血中インスリンおよび乳酸濃度がより高いと報告されている癌の犬のエネルギー代謝については特に確かである。さらにいくつかのヒトおよび動物の研究は、インスリン様成長因子1(insulin-like
growth factor 1:IGF-1)シグナル経路は、腫瘍形成および腫瘍進行に役割を果たしているのかもしれない。現在、IGF-1は多中心型リンパ腫の犬で評価されていない。
この前向き横断研究において、IGF-1とエネルギー代謝-インスリン、グルコース、乳酸、β-ヒドロキシ酪酸-の他のマーカーの血中濃度を組織学的あるいは細胞学的に確認した治療を行っていないリンパ腫の犬16頭を測定した。それらの結果を16頭の年齢、体重が同じの健康なコントロール犬16頭と比較した。食餌の履歴を収集し、蛋白、脂肪、炭水化物摂取を群間で比較した。
結果は、IGF-1、インスリン、グルコース、インスリン:グルコース比に群間の違いがないことが証明された。しかし、リンパ腫の犬の乳酸、β-ヒドロキシ酪酸はコントロール犬よりも高かった(それぞれ1.74±0.83mmol/L vs 1.08±0.27mmol/Lと2.59±0.59mmol/L vs 0.77±0.38mmol/L)。食餌中蛋白、脂肪、炭水化物の中央値に群間の違いはなかった。
この予備研究は、リンパ腫の犬でコントロールに比べ、インスリンとIGF-1濃度がより高いことは一貫性のある所見ではないかもしれないと示唆する。リンパ腫の犬のβ-ヒドロキシ酪酸の増加の意義は今後の大規模前向き研究の調査で求められる。(Sato訳)
■犬の再燃性リンパ腫の経口メルファランによる治療
Oral melphalan for the treatment of relapsed canine lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2017 Sep 21. doi: 10.1111/vco.12356. [Epub ahead of print]
Mastromauro ML, Suter SE, Hauck ML, Hess PR.
犬のリンパ腫に対する多剤レスキュープロトコールに経口メルファランが含まれているが、この目的に対する単剤としてその活性は確立されていない。安価なコスト、投与のしやすさ、許容性から、犬リンパ腫の単剤レスキュー療法で経口メルファランは魅力的な候補となっている。
経口メルファランで治療した再燃性犬リンパ腫の19症例の回顧的評価を実施した。メルファランは主に投与量中央値19.4mg/m2の高用量プロトコールで投与した(n=16)。15頭(78.9%)は同時にコルチコステロイドも投与した。算出した全体の臨床的利点は、(部分反応PR+安定疾患SD)31.6%(PR3/19;SD3/19)で、全ての犬の反応評価はpossibleだった。メルファラン投与後の進行までの期間は、部分反応の3頭で14、24、34日、安定疾患の3頭で20、28、103日だった。毒性を評価可能な17頭中12頭は有害事象を経験し、3頭だけがグレードIII異常の有害事象だった。血液毒性が一般的(11/17)で、消化管毒性は珍しかった(1/17)。治療は限られた臨床的利点で長続きする反応ではなかったが、経口メルファランの許容性は良く、他に有効な薬剤が少ない場合、合理的なレスキューオプションかもしれない。(Sato訳)
■原発性結節性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の犬のCHOP化学療法後の臨床結果に影響する要因の回顧的分析
Retrospective analysis of factors affecting clinical outcome following CHOP-based chemotherapy in dogs with primary nodal diffuse large B-cell lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2017 Nov 20. doi: 10.1111/vco.12364.
Childress MO, Ramos-Vara JA, Ruple A.
化学療法で治療したリンパ腫の犬の予後に多くの要因が影響することが知られている。しかし、リンパ腫の特定サブタイプの犬に対して明確に定義されている予後的要因は少ない。
この研究の目的は、原発性結節性びまん性大型細胞性B細胞リンパ腫(diffuse
large B-cell lymphoma:DLBCL)に対し、CHOP化学療法を行った犬の予後的要因を確認することだった。
2006年から2016年にPurdue 獣医教育病院(PUVTH)で、DLBCLに対して治療を行った犬の医療記録を再調査した。予後に潜在的に関連している要因を、多変量の統計学的方法で分析した。
98頭の犬を研究に組み入れた。化学療法の一番良い総反応は、80頭(81.6%)の完全寛解で、18頭(18.4%)の部分寛解だった。全集団の無増悪生存期間(PFS)中央値は252日(範囲19-1068日)だった。CHOP後に部分寛解(完全寛解よりも)に達することに有意に関係する要因は、診断時の血小板減少の存在(OR6.88;95%CI
1.98-23.93;P=0.002)、基礎血清グロブリン濃度(OR2.63;95%CI 1.03-6.75;P=0.044)、診断時の年齢(OR1.36;95%CI
1.08-1.71;P=0.009)だった。最も低い四分位値(93日以下)でPFSに有意に関係する要因は、診断時の血小板減少の存在(OR8.72;95%CI
1.54-49.33;P=0.014)、診断時の年齢(OR1.47;95%CI 1.12-1.94;P=0.005)、基礎好中球数(OR1.18;95%CI
1.02-1.37;P=0.025)だった。
好中球減少の存在、より高齢、より多い好中球数、より高い血清グロブリン濃度は、DLBCLに対しCHOP化学療法を行った犬において、特に予後不良に関係するかもしれない。(Sato訳)
■犬のリンパ腫の形態型の予後的意義:文献の系統的レビュー
Prognostic significance of morphotypes in canine lymphomas: A systematic review of literature.
Language: English
Vet Comp Oncol. May 2017;0(0):.
D Sayag , C Fournel-Fleury , F Ponce
犬リンパ腫の形態型と予後の関係は文献で相反する結果を呈し、臨床診療で応用に対しジレンマを引き起こす。
この研究の目的は、犬のリンパ腫の形態型の予後的意義に対する文献の系統的レビューを示すことだった。
Standardized Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA)基準を適用した。回顧的および前向き研究を含めた。エビデンスのレベルは各研究に対して判定した。
いくらかの容認できるエビデンスは、犬のリンパ腫の形態型の有意な予後的影響を示唆した。しかしそのエビデンスは、最も適切な分類シェーマを正確に判定するには十分強いものではない。アップデートしたKiel and World Health Organization (WHO)分類は、入手可能な研究とそれらのエビデンスのレベルだけに関して最も適切な分類システムを維持していると思われる。入手可能な前向き研究の想定的欠如と無作為コントロール試験の欠如という限界がある。
現在推奨される犬のリンパ腫の分類は、各新しい症例の形態型の系統的判定である。アップデートしたKielとWHO分類は両方とも犬に適合させ、最も価値のある関心とシェーマに残存する。大規模集団の前向き研究、正確な各形態型を定義する国際的コンセンサスが標準的なステージング法と治療の応用で求められる。(Sato訳)
■リンパ系腫瘍:形態とフローサイトメトリーの関連
Lymphoid Neoplasia: Correlations Between Morphology and Flow Cytometry.
Language: English
Vet Clin North Am Small Anim Pract. January 2017;47(1):53-70.
Emily D Rout , Paul R Avery
細胞診はリンパ腫や白血病の診断に一般的に使用される。度々、リンパ球増殖性疾患の診断は細胞診で得られるが、犬のリンパ腫と白血病の一般的なサブタイプのいくつかは、特徴的な細胞特性を持ち得る。
リンパ腫と白血病の診断と更なる特徴を得るにはフローサイトメトリーが重要なツールである。細胞のサイズあるいは確実な細胞表面たんぱく質の発現のような免疫表現型の特徴は、重要な予後の情報を得られる。
この概説は6つのメジャーなタイプの犬のリンパ腫および白血病に対し、細胞学的特徴、フローサイトメトリーの免疫表現型、免疫表現型の予後情報を述べる。(Sato訳)
■犬多中心型リンパ腫の37症例におけるレスキュー剤としてテモゾロミド単独あるいはドキソルビシンとの併用
Temozolomide alone or in combination with doxorubicin as a rescue agent in 37 cases of canine multicentric lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2017 Aug 2. doi: 10.1111/vco.12335. [Epub ahead of print]
Treggiari E, Elliott JW, Baines SJ, Blackwood L.
テモゾロミド(temozolomide:TMZ)は、再燃性リンパ腫の犬の治療に過去にドキソルビシン(doxorubicin:DOX)との組み合わせで使用されたアルキル化剤である。しかし、単剤で使用された時のこの薬剤のデータは非常に限られている。
この回顧的研究の目的は、多剤併用化学療法で不成功に終わった多中心型リンパ腫再燃の犬において、TMZの有効性と毒性を評価し、TMZとDOXを併用した時の犬のグループの結果を比較することである。
26頭をTMZ群に含め、11頭をTMZ/DOX群に含めた。反応は医療記録の回顧的再検討で評価した。
両群の総生存期間中央値(MST)は40日(範囲1-527日)だった。
TMZ群において、無増悪期間(TTP)中央値は15日(範囲1-202日)で、MSTは40日(範囲1-527日)、総反応率(ORR)は32%、46%に毒性が記録された。
TMZ/DOX群において、TTP中央値は19日(範囲2-87日)、MSTは24日(範囲3-91日)、ORRは60%、63%に毒性が記録された。
しかし、血液学的毒性の比率は関連する臨床症状がないために察知されていないかもしれない。2群間のMSTとTTPの違いは統計学的に有意ではなかった。同様に負の予後因子は確認されなかった。
反応は一般に短期の生存だが、この研究からTMZがTMZ/DOXと同様の効果が得られ、記録された毒性の頻度が少ないかもしれないと示唆される。(Sato訳)
■T細胞性リンパ腫の犬の第一線治療としてLOPP化学療法
LOPP chemotherapy as a first-line treatment for dogs with T-cell lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2017 May 16. doi: 10.1111/vco.12318. [Epub ahead of print]
Brown PM, Tzannes S, Nguyen S, White J, Langova V.
背景:この研究の目的は、無治療のT細胞性リンパ腫の犬に対する化学療法で、ロムスチン(CCNU)、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LOPP)プロトコールの使用を述べ、過去のCHOP化学療法と比較した反応率、毒性、無病期間を述べる。
素材と方法:ロムスチン(CCNU)、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾロン(LOPP)プロトコールで治療した、まだ治療をしていないT細胞性リンパ腫の犬31頭の犬の回顧的症例研究
結果:T細胞性リンパ腫の犬31頭を治療した。全体の反応率は97%だった。LOPP化学療法に反応のあった30頭の犬で、無病期間中央値は176日(範囲0-1745日)だった。この研究群の全体の生存期間中央値は、323日(範囲51-1758日)だった。この研究において全ての死亡は、リンパ腫に起因した。
結論:T細胞性リンパ腫に対するLOPP化学療法は、低い毒性と良好な相反応率を示し、許容性も良かった。このプロトコールは最小限の毒性で、CHOPで治療した犬の高グレードT細胞性リンパ腫に対する無病期間と生存期間に匹敵することを示した。(Sato訳)
■リンパ系腫瘍:形態とフローサイトメトリーの関連
Lymphoid Neoplasia: Correlations Between Morphology and Flow Cytometry.
Language: English
Vet Clin North Am Small Anim Pract. January 2017;47(1):53-70.
Emily D Rout , Paul R Avery
細胞診はリンパ腫や白血病の診断に良く使用される。度々リンパ球増殖性疾患の診断が細胞診で得ることができ、犬のリンパ球と白血病の一般的なサブタイプのいくつかが特有の細胞学的特徴を持ち得る。
フローサイトメトリーはリンパ球と白血病の診断や更なる特徴を得るのに重要なツールである。ある細胞表面蛋白の発現や細胞の大きさなど免疫表現型の特徴は、重要な予後の情報を提供する可能性がある。
このレビューは、犬のリンパ腫と白血病の6つのメジャーなタイプの細胞学的特徴、フローサイトメトリー免疫表現型、免疫表現型による予後の情報を述べる。(Sato訳)
■犬の多剤耐性リンパ腫に対するリン酸トセラニブ(パラディア)単剤療法の効果
Effects of toceranib phosphate (palladia) monotherapy on multidrug resistant lymphoma in dogs.
J Vet Med Sci. 2017 Jun 6. doi: 10.1292/jvms.16-0457. [Epub ahead of print]
Yamazaki H, Miura N, Lai YC, Takahashi M, Goto-Koshino Y, Yasuyuki M, Nakaichi M, Tsujimoto H, Setoguchi A, Endo Y.
著者らは多剤耐性(multidrug resistant:MDR)の犬リンパ腫は、血小板由来成長因子レセプターα(PDGFRα)、血管内皮細胞増殖因子レセプター2(VEGFR2)、c-kitに対する遺伝子発現を増加させるかどうか、リン酸トセラニブ(TOC)がMDR犬リンパ腫に対する治療としての可能性を持つかどうかを調べた。
MDRのT細胞性リンパ腫の犬のPDGFRα発現は、無処置のT細胞性リンパ腫よりも高く、T細胞性リンパ腫の犬のc-kit発現は、B細胞性リンパ腫のそれらより大きいことを臨床データは示した。
TOC単独療法は、重大な副作用もなく、良好な許容を示し、投与した5頭中2頭は部分反応を示した。
ここで示されたデータは、MDRの犬やT細胞性リンパ腫の犬に対するTOCベースの治療の評価に貢献できる。(Sato訳)
■猫の大顆粒性リンパ球性リンパ腫
Feline large granular lymphocyte lymphoma: An Italian Society of Veterinary Oncology (SIONCOV) retrospective study.
Vet Comp Oncol. 2017 May 29. doi: 10.1111/vco.12325. [Epub ahead of print]
Finotello R, Vasconi ME, Sabattini S, Agnoli C, Giacoboni C, Annoni M, Dentini A, Bettini G, Guazzi P, Stefanello D, Bottero E, Mesto P, Marinelli R, De Feo C, Marconato L.
猫の大顆粒性リンパ球(large granular lymphocyte:LGL)リンパ腫は、深刻な予後と化学療法に対する反応不足を特徴とするリンパ腫のあまり見かけないサブタイプである。臨床病理および予後因子に対する報告は限られている。新しくLGLと診断され、初期に悪性度判定(血液検査、生化学検査、胸部エックス線検査、腹部超音波検査)を行い、追跡調査ができた109頭の猫を回顧的に評価した。
91.7%の症例において消化管内±腸管外の関与に発生し、8.3%は消化管外の場所にあった。症状は頻繁に見られた。貧血(31.2%)、好中球増多(26.6%)は一般に観察され、14頭(12.8%)は末梢血に腫瘍細胞が見られた。よく見られた生化学的異常は、ALT上昇(39.4%)、低アルブミン血症(28.4%)だった。37頭中20頭(54.1%)は血清LDHが上昇していた。
猫により治療は様々で、手術(11%)、化学療法(23%)、コルチコステロイド(38.5%)、無治療(27.5%)が行われていた。進行までの期間中央値(median
time to progression:MTTP)は5日で、生存期間中央値(median survival time:MST)は21日だった。サブステージb、循環腫瘍細胞、化学療法投与なし、治療反応なしの症例は有意にMSTが短かった。
小さい部分集団の猫(7.3%)は6か月以上生存し、LGLリンパ腫の中にはより良い臨床経過をたどる猫を見つけることができると示唆された。(Sato訳)
■犬の慢性腸炎と腸管リンパ腫の診断に対する内視鏡細胞診
Endoscopic Cytology for the Diagnosis of Chronic Enteritis and Intestinal Lymphoma in Dogs.
Vet Pathol. 2017 Jan 1:300985817705175. doi: 10.1177/0300985817705175. [Epub ahead of print]
Maeda S, Tsuboi M, Sakai K, Ohno K, Fukushima K, Kanemoto H, Hiyoshi-Kanemoto S, Goto-Koshino Y, Chambers JK, Yonezawa T, Uchida K, Matsuki N.
犬の細胞診は迅速な診断方法であるが、慢性腸炎や腸管リンパ腫に対する内視鏡バイオプシーの細胞学的基準は良く定義されていない。細胞診を用いた即座の診断は、迅速に治療が開始できることで、患者にメリットがある。
この研究の目的は、内視鏡細胞診と病理組織検査結果の相関を調査することだった。
この研究で、慢性消化管疾患の臨床症状がある167頭の犬を研究した。病理結果を基に、以下の診断が判定された:リンパ球プラズマ細胞性腸炎93頭、好酸球性腸炎5頭、小細胞性腸管リンパ腫45頭、大細胞性腸管リンパ腫24頭。2人の臨床病理医が内視鏡細胞診の圧迫スメア標本を回顧的に評価した。炎症、小細胞性リンパ腫、大細胞性リンパ腫の細胞診断は、リンパ球浸潤の程度、浸潤したリンパ球の大きさ、好酸球/肥満細胞浸潤をもとにした。
細胞診で評価したリンパ球浸潤の程度に沿って、臨床的重症度スコアも有意に増加した。167症例中136症例(81.4%)において細胞診と病理診断が完全に一致した。腸炎とリンパ腫の鑑別に対し、内視鏡細胞診の感受性は98.6%、特異性は73.5%、陽性適中率は72.3%、陰性適中率は98.6%だった。ログランク検定、コックス回帰分析は、細胞診の結果は予後を予測すると示した。
それらの結果から、犬における内視鏡細胞診は腸の炎症とリンパ腫の診断に役立つ有効な方法であると示唆される。(Sato訳)
■犬のリンパ腫における脾臓と肝臓の超音波検査と細胞診:病期移行と予後の評価に対する所見の影響
Splenic and hepatic ultrasound and cytology in canine lymphoma: effects of findings on stage migration and assessment of prognosis.
Language: English
Vet Comp Oncol. August 2016;14 Suppl 1(0):82-94.
V Nerschbach , N Eberle , A E Joetzke , R Hoeinghaus , S Hungerbuehler , R Mischke , I Nolte , D Betz
より感受性の高い診断方法の使用の結果として、ヒトや犬で病期移行(stage migration)が述べられる。
多中心型リンパ腫の186頭の犬で、従来のステージングの結果に加え、利用可能な肝臓と脾臓の超音波検査と細胞診検査結果を登録した。
脾臓と肝臓のそれぞれの超音波および細胞診所見の追加で、肝臓および脾臓に関与として分類された犬は、わずかにより少ない頭数という結果になった。多中心型リンパ腫の犬において、細胞診の追加はステージIVからステージIIIの犬の有意なシフトを導いた。肝臓と脾臓の超音波および細胞診所見は、併用化学療法の犬の完全寛解や生存期間に有意に影響しなかった。
犬のリンパ腫のステージング方法論は再定義すべきで、脾臓と肝臓の超音波および細胞診の予後的意義の更なる調査が求められる。(Sato訳)
■ラバクフォサディン/ドキソルビシンの併用:未治療の犬の多中心性リンパ腫における効果と忍容性
Alternating Rabacfosadine/Doxorubicin: Efficacy and Tolerability in Naive Canine Multicentric Lymphoma
J Vet Intern Med. 2017 Apr 3. doi: 10.1111/jvim.14700. [Epub ahead of print]
Thamm DH, Vail DM, Post GS, Fan TM, Phillips BS, Axiak-Bechtel S, Elmslie RS, Klein MK, Ruslander DA.
【背景】 犬の多中心性リンパ腫の標準的な治療はドキソルビシン(DOX)をベースとした多剤併用療法であるが、完遂するのに典型的には12-16回の来院が必要なプロトコルに、財源や来院回数で躊躇するご家族も少なくない。ヌクレオチドアナログ 9-(2-phosphonylmethoxyethyl) guanineのダブルプロドラッグである、ラバクフォサディン(RAB)は単剤でも犬のリンパ腫で効果を示す可能性があり、ドキソルビシンとは違った作用メカニズムを持つ
【仮説/目的】 未治療の多中心性リンパ腫に対し、RABとDOXを交互に投与したときの効果と副作用(AE)を評価することを目的とする。
【動物】 治療を過去に受けていない54例の犬
【方法】 オープンラベルの多施設間臨床試験。RAB(1.0mg/kg IV 第0、6、12週)とDOX(30mg/㎡ IV 第3、9、15週)を交互に投与した。完全寛解が認められた症例で、月ごとの評価を続けた。臨床病理的評価と寛解評価とAEsは21日毎に評価された。
【結果】 全体の反応率は84%(CR;68%、PR:16%)だった。全体の無病進行期間中央値は194日(CR:216、PR:63日)だった。殆どのAEsは軽度で自己限定的なものだった:胃腸障害と血液学的なAEsが最も一般的だった。13例の犬に皮膚障害が認められ、2例の犬にグレード5の肺線維症が認められた。
【結論と臨床意義】 RAB/DOXの治療は一般的には忍容性が高く、より少ない来院頻度でDOXベースの標準的な多剤併用療法と匹敵するPFIsだった。殆どの副作用が軽度もしくは中程度のものであり、自己限定的だった。他の化学療法剤とRABとの併用や、長期的な予後を調査する上で、より研究が必要である。(Dr.Masa訳)
コメント:2016年のACVIMで発表されていましたが、遂に論文になったようです。研究デザインを含め、色々含む所はありますが、選択肢が増える可能性はありそうです。また致死性の肺線維症はRABを使用した過去の報告でも認められており、注意が必要です。
■結腸直腸原発と考えられるリンパ腫に罹患した31例の犬の臨床症状、治療と予後(2001-2013)
Clinical presentation, treatment and outcome in 31 dogs with presumed primary colorectal lymphoma (2001 ? 2013)
Vet Comp Oncol. 2016 Mar 29.
I Desmas , J H Burton , G Post , O Kristal , M Gauthier , J F Borrego , A Di Bella , A Lara-Garcia
【アブストラクト】
この多施設間の回顧的研究の目的は、結腸直腸原発と考えられるリンパ腫(presumed primary colorectal lymphoma:PCRL)の犬の臨床症状・治療・予後を明らかにし、予後因子を特定することである。
合計で31例の犬が組み入れられた。PCRLの主な特徴は、高グレード(n=18)であり、免疫表現型がB細胞性であった(n=24)。殆どの犬がサブステージb(n=25)で最も認められたのは血便(n=20)であった。1例は外科治療のみが行われた。30例の犬で化学療法がおこなわれた;それらの中で13頭は外科もしくは放射線治療が併用された。
PFSは1318日で、疾患に関連したMSTは1845日だった。14例の犬が研究終了時まで生存しており、フォローアップ期間の中央値は684日(3-4678日)だった。より若い犬で長いPFS(P=0.031)と疾患に関連したMST(P=0.01)が認められた。血便の有無はより長いPFSに関係していた(P=0.02)。化学療法に局所治療を加えることは予後を明らかに改善はしなかった(P=0.584)。犬のPCRLは他のタイプのnon-Hodgkin’sリンパ腫よりもPFSとMSTがかなり長かった。(Dr.Masa訳)
■治療をうけていない32例の猫の中-大細胞性の消化管型リンパ腫におけるロムスチン(CeeNu)の回顧的評価
A retrospective evaluation of lomustine (CeeNU) in 32 treatment naive cats with intermediate to large cell gastrointestinal lymphoma (2006?2013)
Vet Comp Oncol. 2016 Jun 9. doi: 10.1111/vco.12243.
Rau SE, Burgess KE.
【アブストラクト】
猫のリンパ腫における多剤併用化学療法プロトコルは様々な効果と認容性が報告されている。フェーズ1試験において、ロムスチンは猫のリンパ腫において効果を示していたが、治療を受けていない猫の中-大細胞性の消化管型(GI)リンパ腫における効果は未だに分かっていない。
この研究は猫のGIリンパ腫の治療におけるロムスチンの効果と認容性を評価するものである。病理学的もしくは細胞学的に中-大細胞性GIリンパ腫と診断された32例の猫を回顧的に確認した。臨床徴候、血液・生化学的性状と導入時のL-アスパラギナーゼの使用を因子として評価した。反応率は50%(16/32)で、反応期間中央値は302日(範囲:64-1450日)だった。無病生存期間中央値は132日(範囲:31-1450日)で、全生存期間中央値は108日(範囲:4-1488日)だった。食欲低下のヒストリー、貧血、ロムスチンの用量が有意に無病生存期間と関連していた。総合的には、ロムスチンによる治療は猫のGIリンパ腫治療において認容性が高く、効果的な治療だった。 (Dr.Masa訳)
■犬の多中心リンパ腫の2度目のレスキューとしてのビンブラスチン:39症例(2005-2014)
Vinblastine as a second rescue for the treatment of canine multicentric
lymphoma in 39 cases (2005 to 2014).
Language: English
J Small Anim Pract. August 2016;57(8):429-34.
J A Lenz , C S Robat , T J Stein
目的:この研究の目的は、2度目のレスキューとして多中心リンパ腫の犬をビンブラスチン単剤で治療した時の反応と結果を回顧的に評価することだった。
方法:2005年から2014年の間にビンブラスチンレスキュー療法を受けた39頭(UW-マジソンとCCNU/Lアスパラギナーゼプロトコール時あるいは完了後に再燃)の飼育犬の医療記録から、臨床症状、診断検査、薬用量、治療の回数、副作用、反応と結果に関する情報を再調査した。
結果:ビンブラスチンの開始投与量の中央値は2.6mg/m(2)(1.7-2.8mg/m(2))、疾患進行まで毎週投与した。胃治療した39頭のうち、3頭(7.7%)は完全寛解に達し、7頭(17.9%)は部分反応に達し、18頭(46.2%)は安定疾患を維持、11頭(28.2%)は進行疾患だった。10頭(25.6%)はグレードIIIあるいはIVの好中球減少を発症し、4頭(10.3%)はグレードIIIあるいはIVの血小板減少を発症した(1頭は両カテゴリー)。ビンブラスチン開始後、無増悪生存期間中央値は29.5日(0-77日)で、総生存期間中央値は46日(4-250日)だった。最初の寛解の持続期間が結果の正の指標と確認された。
臨床意義:再発あるいは難治性リンパ腫の犬において、単剤のビンブラスチンの許容性は良い。反応は不十分で短期持続だった。(Sato訳)
■リンパ腫の犬の化学療法耐性と治療結果の予測に対するMDR1遺伝子発現の判定
Determination of MDR1 gene expression for prediction of chemotherapy tolerance and treatment outcome in dogs with lymphoma.
Vet Comp Oncol. December 2015;13(4):363-72.
I Gramer; M Kessler; J Geyer
多剤耐性遺伝子1(MDR1)発現レベルを、標準化学療法を受けている悪性リンパ腫の種々のタイプの27頭の犬で分析した。
MDR1リアルタイムPCR発現解析に血液サンプルを使用した。治療耐性と結果を臨床検査及びアンケートで定期的に評価した。
治療下で重度副作用を発症した犬は、薬剤をよく許容した犬と比べて、基礎MDR1遺伝子発現レベルが有意に低かった。治療中の長期MDR1遺伝子発現解析において、4頭は基準の発現と比べ2倍以上のMDR1上方制御を示した。他には見られないが、それらの犬4頭全てが疾患の進行示した。
結論として、犬のリンパ腫に対し基準および経過観察中のMDR1遺伝子発現レベルは重度有害薬剤反応の発生および/あるいは化学療法中のMDRの進展の予測値となりえた。(Sato訳)
■犬の多中心型リンパ腫に対するCHOP-LAspベースの治療法の維持療法ありとなしの比較
Comparison of a CHOP-LAsp-based protocol with and without maintenance for canine multicentric lymphoma.
Vet Rec. 2017 Jan 18. pii: vetrec-2016-104077. doi: 10.1136/vr.104077. [Epub ahead of print]
Lautscham EM, Kessler M, Ernst T, Willimzig L, Neiger R.
犬のリンパ腫の治療に維持療法をしないことが推奨されるのは、少数の症例かつ大部分は過去のコントロールを用いたものに基づく。
本研究は、維持療法をしない場合と維持療法ありの同じプロトコールで、最初の寛解期間(DFR)および全生存期間(ST)を比較した。
408頭の犬を28週間のCHOP-LAspの導入療法で治療した。75頭 (cohort 1)においては、その後、ビンクリスチン、クロラムブシルおよびアクチノマイシンDの維持療法を全部で2年間おこなった。残りの333頭の犬は、治療は導入療法後中止した(cohort 2)。
Cohort1におけるDFRとSTの中央値は、216日と375日であり、cohort2では、184日と304日であった。Cohort 1の6ヶ月、1年、2年生存率は、73、50, 24%であったのに対し、Cohort2では、67, 39, 21%であった。2つの治療法の間に有意差はなかった(STについてはP=0.291でありDFRについてはP=0.071であった)。多重解析では、コルチコステロイドを前もって使用していたこと(P=0.005)、診断時の血小板減少症(P=0.019)、ステージ(P=0.009)、再発時のサブステージb(P<0.001)、年齢(P=0.002)、強化療法を必要とする不完全または状態のよくない寛解(P=0.004)が、両グループにおいて生存期間と負の相関を示した。本研究によって、犬の多中心型リンパ腫の治療を維持療法なしで使用することが支持された。(Dr.Taku訳)
■注射部位の皮膚リンパ腫:17頭の猫の病理、免疫表現型、分子特性
Cutaneous Lymphoma at Injection Sites: Pathological, Immunophenotypical, and Molecular Characterization in 17 Cats.
Vet Pathol. July 2016;53(4):823-32.
P Roccabianca , G Avallone , A Rodriguez , L Crippa , E Lepri , C Giudice , M Caniatti , P F Moore , V K Affolter
猫の原発性皮膚型リンパ腫(FPCLs)は猫の全てのリンパ腫の0.2%から3%を占め、皮膚非表皮行性小型T細胞性腫瘍の頻度が高い。FPCLの発生は、猫白血病ウイルス(FeLV)陽性や皮膚の炎症と関係ないと思われる。
腫瘍発生部位に過去にワクチン接種をしていた17頭の皮膚リンパ腫の猫を47頭のFPCLsの猫から選別した。臨床症状、病歴、免疫表現型、FeLV
p27およびgp70発現、クローナリティを評価した。
オス(12/17)と家猫短毛種(13/17)が多く、平均年齢は11.3歳だった。5頭において注射から発生までの期間は15日から約9年の範囲だった。診断時、17頭中11頭は内臓疾患の所見がなかった。リンパ腫は肩甲骨間(8/17)、胸部(8/17)、体幹(1/17)皮膚領域に発生していた;表皮行性の欠如;壊死(16/17)、血管中心性(13/17)、血管浸潤(9/17)、血管破壊(8/17)リンパ様凝集から構成される末梢炎症(14/17)を特徴とした。FeLV gp70および/あるいはp27蛋白は17個中10の腫瘍で発現した。WHO分類、免疫表現型、クローナリティにより、病変は大型B細胞性リンパ腫(11/17)、未分化大型T細胞性リンパ腫(3/17)、ナチュラルキラー細胞様リンパ腫(1/17)、末梢T細胞性リンパ腫(1/17)に分類された。1症例の系列は分からなかった。
注射部位の皮膚型リンパ腫(CLIS)は、猫注射部位肉腫、そしてヒトで報告された亜急性から慢性炎症において発生するリンパ腫のいくつかの臨床および病理学的特徴を共有していた。注射およびFeLV発現の再活性化により誘発される持続炎症がCLISの発生に寄与しているのかもしれない。(Sato訳)
■治療未経験の中間型から大型細胞性消化管リンパ腫の猫32頭におけるロムスチンの回顧的評価(2006-2013)
A retrospective evaluation of lomustine (CeeNU) in 32 treatment naive cats with intermediate to large cell gastrointestinal lymphoma (2006-2013).
Vet Comp Oncol. 2016 Jun 9. doi: 10.1111/vco.12243.
Rau SE, Burgess KE.
猫リンパ腫に対する多剤化学療法は、不定な効果と耐容性が示されている。第I相試験において、ロムスチンはリンパ腫の猫に対する効果が証明されているが、治療していない猫の中間型/大型細胞性消化管(GI)リンパ腫に対する使用は分かっていない。
この研究では、猫のGIリンパ腫の治療に対し、ロムスチンの効果と耐容性を評価した。
組織学的あるいは細胞学的に中間型/大型細胞性GIリンパ腫の猫32頭を回顧的に評価した。評価したファクターは、臨床症状、血液/生化学パラメーター、導入時のL-アスパラギナーゼの使用を含めた。
反応率は50%(16/32)、反応の持続期間中央値は302日(範囲64-1450日)だった。無憎悪期間中央値は132日(範囲31-1450日)、全体の生存期間中央値は108日(範囲4-1488日)だった。食欲不振の病歴、貧血の存在、ロムスチンの量は有意に無憎悪生存期間に関係した。
総体的に、猫の消化管型リンパ腫に対し、ロムスチンは耐容性はよく、効果的な治療である。
■犬のリンパ腫に対する血清バイオマーカーの臨床応用に関する現況
The Current State of Clinical Application of Serum Biomarkers for Canine Lymphoma.
Front Vet Sci. 2016 Sep 30;3:87. eCollection 2016.
Bryan JN.
犬リンパ腫の診断、予後、治療モニタリングに対する血清バイオマーカーは、ここ10年以上で臨床的に関心の高いものになっている。腫瘍の産物、生化学酵素、サイトカイン、メタボリックプロファイリング、漏出酵素や血清蛋白などがリンパ腫のバイオマーカーとして研究されている。複数のバイオマーカーの併用が最も高い感受性と特異性を示している。
C-反応性蛋白、チミジンキナーゼ1、ハプトグロビンは最も広く研究されており、TK Canine Cancer Panel およびCanine Lymphoma Blood Testなどの診断検査で商業化されている。それらの検査はそれぞれ疾患や健康犬の集団、あるいは疾患犬の前向き研究で、臨床方針決定に応用するため評価されている。それらの検査の応用に対するいくつかのエビデンスは存在するが、リンパ腫の広範囲の型における大規模研究は欠如している。
それらのバイオマーカーは、一般に診断時および再燃時に上昇する。バイオマーカー上昇により導かれた早期介入がリンパ腫の犬の生存期間、あるいはQOLを改善するかどうか調べる追加研究が必要である。(Sato訳)
■犬の非緩慢性T細胞性リンパ腫のVELCAP-TSCプロトコールによる治療:70頭の回顧的評価(2003-2013)
Treatment of canine non-indolent T cell lymphoma using the VELCAP-TSC protocol:
A retrospective evaluation of 70 dogs (2003-2013).
Vet J. May 2016;211(0):39-44.
Ingrid H Goodman , Antony S Moore , Angela E Frimberger
犬の非緩慢性リンパ腫の免疫表現型は予後的価値を有する;T細胞性リンパ腫はB細胞性リンパ腫の犬よりも反応率が悪く、生存期間が短い。
この研究は、アルキル化剤の豊富な併用化学療法で治療したT細胞性リンパ腫の犬70頭における完全寛解(CR)、無憎悪生存期間(PFS),総生存期間(OST)に対する予後因子を回顧的に評価した。
全体の寛解率は72.9%だった;45頭(64.3%)はCRに達し、6頭(8.6%)は部分寛解だった。診断時に好中球減少だった犬は、CRに達する確率が有意に高かった。
全体のPFSの中央値は175日だった;化学療法開始後1、2、3年PFSはそれぞれ26.8%、15.8%、12.6%だった。CRに達した犬のPFS中央値は有意に長かった。
全体のOSTは237日だった。化学療法開始後1、2、3年生存率はそれぞれ31%、20.2%、11.5%だった。OST中央値はCRに達した犬で有意に長く、ボクサーや診断時にサブステージbの犬は有意に短かった。
このプロトコールで治療した犬の30%以上が1年以上生存し、T細胞性リンパ腫の犬の集団に対し、好ましい結果と長期生存性が可能であると示唆している。(Sato訳)
■末梢性リンパ腫の犬に対する多剤併用化学療法からプレドニゾロンを除いた場合の影響についてのランダム化対照試験
A randomized controlled trial of the effect of prednisone omission from a multidrug chemotherapy protocol on treatment outcome in dogs with peripheral nodal lymphomas.
J Am Vet Med Assoc. 2016 Nov 1;249(9):1067-1078.
Childress MO, Ramos-Vara JA, Ruple A.
目的 末梢性リンパ腫の犬において、多剤併用化学療法からプレドニゾロンを除いた場合の転帰への影響について検討すること
デザイン 単施設、非盲検、ランダム化並行群間試験
動物 病理組織学的に末梢性リンパ腫であると確定診断し、治療後4週間以上の生存期間が望める40頭の飼い犬
方法 治療は、L-アスパラギナーゼ、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン(L-CHOP)または、プレドニゾロン除く以外は同等のプロトコール(L-CHO)で行った。主要転帰は無増悪生存期間であった。転帰に関与する獣医師と評価者は、治療の割り当てについて知らされていないわけではなかった。治療の割り当ては、組み入れ前にそれぞれの犬の飼い主にはわからないようにしてあったが、インフォームドコンセントの記入後には明らかにされた。
結果 試験は、組み入れに時間がかかったため早期に終了した。試験には、40頭の犬が組み入れられ、L-CHOP(18頭)またはL-CHO群(22頭)に割り当てられた。全40頭の結果は、主要転帰について解析した。無増悪生存期間の中央値は、L-CHO群では142.5日であり、L-CHOP群では292日であった(ハザード比 1.79、95%信頼区間, 0.85-3.75)。重篤な副反応はL-CHOを受けてた犬においてより一般的であった。しかしこの差について有意差はなかった。
結論と臨床的意義 L-CHOPからプレドニゾンを除くことは、末梢性リンパ腫の犬の無増悪生存期間を改善するようにはみえなかった。しかし、本試験は、両群における無増悪生存期間の臨床的に意味のある差を検出するにはパワー不足であるように思えた。(Dr.Taku訳)
■犬の多中心型リンパ腫とCHOPプロトコールの構成薬物の一時的関連の評価:シクロフォスファミドは最も弱い関連か?
Assessment of temporal association of relapse of canine multicentric lymphoma with components of the CHOP protocol: Is cyclophosphamide the weakest link?
Vet J. 2016 Jul;213:87-9. doi: 10.1016/j.tvjl.2016.04.013. Epub 2016 Apr 29.
Wang SL, Lee JJ, Liao AT.
シクロフォスファミド、ヒドロキシダウノルビシン、ビンクリスチンおよびプレドニゾロン(CHOP)を用いる多剤併用化学療法は犬のリンパ腫の治療で最もよく使用される。罹患犬の多くは化学療法の最初のステージ中に反応するが、ほとんど再燃する。
この研究目的は、マジソン-ウィスコンシン変法25週化学療法プロトコールを用い、特定化学療法剤の使用と臨床的再燃との関連を評価することだった。
多中心型リンパ腫に罹患した68頭中41頭が治療期間中に再燃した。ビンクリスチン(n=9)あるいはドキソルビシン(n=5)と比較して、シクロフォスファミド(n=24;P<0.01)の投与後に再燃がより多く発生した。
ゆえに、従来のCHOPベースの化学療法の治療結果は、シクロフォスファミドを他の細胞毒性薬に置き換えることで改善するかもしれない。(Sato訳)
■結腸直腸が原発であると推定されるリンパ腫の31頭の犬の臨床徴候、治療および転帰について(2001-2013年)
Clinical presentation, treatment and outcome in 31 dogs with presumed primary colorectal lymphoma (2001-2013).
Vet Comp Oncol. 2016 Mar 29. doi: 10.1111/vco.12194.
Desmas I, Burton JH, Post G, Kristal O, Gauthier M, Borrego JF, Di Bella A, Lara-Garcia A.
この多施設の回顧的研究の目的は、結腸直腸が原発であると推定されるリンパ腫(PCRL)の犬の臨床徴候、治療、転帰を明らかにし、予後因子を決定することである。
合計31頭の犬を含めた。PCRLの重要な特徴は、高悪性度(18頭)、免疫表現型はB細胞型(24頭)であった。大部分の犬は、サブステージbであり(25頭)、血便を伴っていることが多かった(20頭)。外科手術のみを受けた犬は1頭であった。30頭の犬は化学療法をうけ、そのなかで13頭が外科手術または放射線療法を受けた。無増悪生存期間(PFS)は1318日であり、本疾患に関連する生存期間の中央値 (MST)は、1845日であった。14頭の犬は研究の終了時に生存しており、追跡期間の中央値は684日(3-4678日)であった。
若い犬ほどより長いPFS (P?=?0.031)およびMST(P?=?0.01)を示した。血便があることはより長いPFSと一致していた(P?=?0.02)。化学療法に加えて局所治療をすることは、転帰を有意にかえることはなかった(P?=?0.584)。犬のPCRLは、他のタイプの非ホジキンリンパ腫よりかなり長いPFSとMSTを示す。(Dr.Taku訳)
■犬の再燃したリンパ腫のメクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾン(MOMP)による治療
Mechlorethamine, vincristine, melphalan and prednisone (MOMP) for the treatment of relapsed lymphoma in dogs.
Vet Comp Oncol. 2015 Dec;13(4):398-408. doi: 10.1111/vco.12055. Epub 2013 Aug 5.
Back AR, Schleis SE, Smrkovski OA, Lee J, Smith AN, Phillips JC.
再燃したリンパ腫の犬88頭を28日治療サイクルのMOMP(メクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾン)プロトコールで治療した。
MOMPプロトコールの総反応率(ORR)は51.1%で、期間は56日(範囲7-858日)の中央値だった。12%の犬は完全寛解となり、期間中央値は81日(42-274日)、38.6%の犬は部分反応を示し、期間中央値は49日(範囲7-858日)だった。
T細胞性リンパ腫の犬のORRは55%で、期間中央値は60日(範囲49-858日)、B細胞リンパ腫のORRは57%で、期間中央値は81日(範囲7-274日)(P=0.783)だった。全ての犬の総生存期間は183日(範囲17-974日)だった。
44%の犬は毒性を経験し、ほとんどはグレードIに分類された。MOMPプロトコールの許容性は良いようで、再燃したリンパ腫の犬の1つのオプションである。(Sato訳)
■多中心型リンパ腫の犬において高フェリチン血症は短い生存期間と関係する
Hyperferritinemia is associated with short survival time in dogs with multicentric
lymphoma.
J Vet Med Sci. August 2015;77(7):843-6.
Seishiro Chikazawa; Yasutomo Hori; Fumio Hoshi; Kazutaka Kanai; Naoyuki Ito
Department of Small Animal Internal Medicine, School of Veterinary Medicine, Kitasato University, 23-35-1 Higashi, Towada, Aomori 034-8628, Japan.
この研究で著者らは、多中心型リンパ腫の犬において治療前の血清フェリチン濃度と生存期間の関連を研究した。
多中心型リンパ腫の犬18頭で研究した。血清フェリチン濃度(3000ng/mlカットオフ)を基に、犬を高フェリチン群、低フェリチン群と分類した時、高濃度(3000ng/ml以上、n=11)の犬の生存期間中央値は40日で、低濃度(3000ng/ml未満、n=11)の犬のそれは360日だった。この差は統計学的に有意だった(P=0.001)。
この所見は、多中心型リンパ腫の犬において最初に高濃度の血清フェリチンは生存期間が短いことを示すと示唆する。この所見を確認する大規模研究が必要である。(Sato訳)
■高グレードB細胞性リンパ腫の犬のフローサイトメトリーによるKi67の予後的意義
Prognostic significance of Ki67 evaluated by flow cytometry in dogs with high-grade B-cell lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2016 Jan 21. doi: 10.1111/vco.12184. [Epub ahead of print]
Poggi A, Miniscalco B, Morello E, Gattino F, Delaude A, Ferrero Poschetto L, Aresu L, Gelain ME, Martini V, Comazzi S, Riondato F.
Ki67は高グレードと低グレード犬のリンパ腫を区別できるが、その腫瘍の特定のサブタイプにおいて予後的役割は分かっていない。
修正ウィスコンシン-マジソンプロトコール(UW-25)で治療した高グレードB細胞性リンパ腫の犬40頭で、フローサイトメトリーにより評価したKi67%(Ki67-陽性細胞の比率)の予後的意義を検討した。
リンパ腫特異生存性(LSS)と無再燃期間(RFI)との関連性に対し、以下の変数を調査した:Ki67%、犬種、性別、年齢、ステージ、サブステージ、完全寛解(CR)。
多変量解析により、Ki67%(P=0.009)とCRの達成(P=0.001)はLSSに対する独立した予後因子だった。中程度のKi67%(20.1-40%)の犬のLSSおよびRFI(それぞれ中央値866日と428日)は、低値の犬(中央値42日、P<0.001;中央値159日、P=0.014)や高値の犬(中央値173日、P=0.038;中央値100日、P=0.126)よりも長かった。Ki67の決定は、犬の高グレードB細胞性リンパ腫の犬において、フローサイトメトリーによる分析の臨床的有用性を改善する予後を示すツールである。(Sato訳)
■犬のT細胞性リンパ腫における動物依存のリスクファクター
The animal-dependent risk factors in canine T-cell lymphomas.
Vet Comp Oncol. 2015 Aug 24. doi: 10.1111/vco.12164. [Epub ahead of print]
Jankowska U, Jagielski D, Czopowicz M, Sapierzy?ski R.
悪性リンパ腫は犬に起こる最も一般的な悪性腫瘍の一つである;それらの中でT細胞性リンパ腫はあまり一般的に認められるわけではない。最近は多くの著者が、特に免疫細胞化学やフローサイトメトリーで支持される場合、犬のリンパ腫に対する十分な診断方法として細胞診を推奨している。
この研究の目的は、ポーランドで特異細胞学的サブタイプを含む犬のT細胞性リンパ腫(TCLs)における動物依存のリスクファクターの特徴を述べることだった。
腫瘍の種類とサブタイプの判定は、過去に発表された犬用の最新のKielの細胞学的分類を基に行った。
2犬種(ボルドー・マスチフ、ボクサー)がTCLの素因を持つ一方で、B細胞性リンパ腫に素因を持つエビデンスは示されなかった。低グレードリンパ腫の犬は、高グレードリンパ腫の犬よりも有意に老齢だった。(Sato訳)
■大顆粒リンパ腫の猫6頭
Large granular lymphoma in six cats.
Pol J Vet Sci. 2015;18(1):163-9.
Sapierzy?ski R, Jankowska U, Jagielski D, Kliczkowska-Klarowicz K.
大顆粒リンパ腫(LGLs)は分類シェーマにかかわらないリンパ腫の特定のグループからなる。LGLはより少ない、あるいはより成熟した形態の細胞から成るが、一般に腫瘍細胞は、細胞診で明瞭な細胞質内のアズール性顆粒を有する。
この研究の目的は、猫の大顆粒リンパ腫に対する臨床および細胞学的データを示すことと、症例の治療に対する反応を分析することだった。
2012年から2014年の間で6頭の猫が大顆粒リンパ腫に罹患していた。1頭の猫はLGL鼻型を認め、もう1頭は全身型で、4頭の猫は消化器型だった。細胞病理に対する細胞サンプルを1頭の鼻腔マスから、1頭の拡大した下顎リンパ節と胸腔から、4頭の腹部マスから超音波ガイドの細針バイオプシーにより採取した。
治療は6頭中5頭で導入した。2頭はグルココルチコイドの緩和療法を行い、2頭はCOPプロトコールの化学療法、1頭はマシチニブで治療した。抗ガン療法で治療した猫の生存期間の中央値は9か月で、グルココルチコイドで治療した猫の生存期間中央値は1.5ヶ月だった。
結論として、大顆粒リンパ腫(特に消化器型)は猫のリンパ腫で比較的一般的な型である。臨床検査、画像検査のような単純な診断方法は、多くの症例で十分である。攻撃的な挙動、一般的に予後不良にもかかわらず、従来の化学療法は解剖学的型や組織学的悪性度に関係なく使用して良い反応を示す猫もいる。(Sato訳)
■再燃あるいは難治性リンパ腫の犬に対するカルボプラチンとシタラビン化学療法の効果と毒性
Efficacy and toxicity of carboplatin and cytarabine chemotherapy for dogs with relapsed or refractory lymphoma (2000-2013).
Vet Comp Oncol. 2015 Oct 14. doi: 10.1111/vco.12176.
Gillem J, Giuffrida M, Krick E.
2000年から2013年の間に再燃あるいは難治性リンパ腫の治療で、カルボプラチン(n=8)あるいはカルボプラチンとシタラビン(n=14)による化学療法で治療した22頭の犬のカルテを回顧的に再検討した。
臨床反応率は18.2%(4/22)だった。進行までの期間の中央値は18日(反応した犬は56日、反応しなかった犬は12日、P=0.0006)だった。総生存期間の中央値は28日(反応した犬は109日、反応しなかった犬は21日、P=0.0007)だった。血小板減少と好中球減少はそれぞれ84.2%(16/19)と52.6%(10/19)の犬に発生した。グレードIVの血小板減少と好中球減少はそれぞれ56.3%(9/16)と60.0%(6/10)の犬に発生した。2つの薬剤を投与された犬は、カルボプラチン単独投与の犬よりも好中球減少(P=0.022)あるいは血小板減少(P=0.001)を起こす確率が高かった。反応があった全ての犬は、2つの薬剤を投与され、その併用で28.6%(4/14)の反応率だった。
その併用に反応した犬もいたが、毒性は高く、その反応は長く続かなかった。適切な支持療法を持って、このプロトコールはいくらかの犬に対して許容できるレスキューのオプションとなるかもしれない。(Sato訳)
■脾臓摘出によって治療した犬の脾臓リンパ腫の転帰と予後因子(1995年-2011年)
Outcome and Prognostic Factors for Canine Splenic Lymphoma Treated by Splenectomy (1995-2011).
Vet Surg. 2015 Oct 1. doi: 10.1111/vsu.12405. [Epub ahead of print]
van Stee LL, Boston SE, Singh A, Romanelli G, Rubio-Guzman A, Scase TJ.
目的 脾臓摘出によって治療した犬の脾臓のリンパ腫の転帰を評価し、他の部位に生じているかどうか、補助的な化学療法、WHOの犬のリンパ腫の病理組織学的分類の効果などを含めた予後因子についても評価した。
デザイン 多施設回顧的研究
動物 28頭の飼い犬
方法 脾臓のリンパ腫と組織学的に診断され、脾臓摘出によって治療された犬について、獣医腫瘍外科学会のメンバーによって提出された1995-2011年のカルテを調査した。補助的な化学療法を実施したものもしていないものも組み入れた。全生存期間、無病期間、死因について明らかにした。転帰について、犬の悪性リンパ腫の予後因子とWHOの組織学的な分類を評価した。
結果 脾臓摘出によって治療した脾臓のリンパ腫の犬の1年生存率は58.8%であったが、これ以降この疾患によって亡くなった犬はいなかった。B細胞型リンパ腫が、他のタイプの脾臓のリンパ腫よりもよりよい生存の予後を示した。MZリンパ腫とマントル細胞型リンパ腫が、本研究では最も多いB細胞型リンパ腫であった。血腹と脾臓リンパ腫に関連した臨床症状、すなわち腹部膨満、元気消失、食欲消失などが予後の悪い指標であり、脾臓に限局している場合は予後がよい指標であった。手術前後の補助的な化学療法は生存に対してプラスにはならなかった。
結論 我々の症例に基づくと、脾臓に限局している場合は、脾臓摘出のみの治療が効果的であった。化学療法は、脾臓に限局したリンパ腫の場合、生存を改善しないようである。(Dr.Taku訳)
■外科的切除とCHOPベースのアジュバント化学療法で治療した猫の孤立性の高悪性度消化管リンパ腫:20例の回顧的研究
Feline discrete high-grade gastrointestinal lymphoma treated with surgical resection and adjuvant CHOP-based chemotherapy: retrospective study of 20 cases.
Vet Comp Oncol. 2015 Sep 3. doi: 10.1111/vco.12166.
Gouldin ED, Mullin C, Morges M, Mehler SJ, de Lorimier LP, Oakley C, Risbon R, May L, Kahn SA, Clifford C.
この回顧的研究の目的は、孤立性の中-高悪性度消化管リンパ腫を外科的に切除し、そのあとCHOPベースの化学療法で治療した猫の予後を評価することである。
性別、品種、ヘマトクリット、白血球数、血清アルブミン濃度、臨床ステージ、消化管閉塞、腹膜炎などの、生存への影響について評価した。
20頭の猫が組み入れ基準を満たし、3頭の猫は、データの解析時点でまだ生存していた。全生存期間の中央値
(MST)は417日(範囲 12-2962日)であった。無病期間 (DFI)は357日(範囲 0-1585日)で、6頭の猫は、死亡する前まで寛解したままと考えられた。臨床ステージのみがMSTとDFIに有意な影響を示した。孤立性の中?高悪性度消化管リンパ腫の猫を外科的に切除し、そのあとCHOPベースの化学療法で治療した場合、全生存期間は許容できるものであった。(Dr.Taku訳)
■猫の中間から高グレードリンパ腫の修正ウィスコンシン-マジソン大学プロトコールによる治療:119症例(2004-2012)
Treatment of feline intermediate- to high-grade lymphoma with a modified university of Wisconsin-Madison protocol: 119 cases (2004-2012).
Vet Comp Oncol. 2015 Jun 25. doi: 10.1111/vco.12158.
Collette SA, Allstadt SD, Chon EM, Smith AN, Garrett LD, Choy K, Rebhun RB, Rodriguez CO Jr, Skorupski KA.
CHOPベース(シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンカアルカロイド、プレドニゾロン)化学療法プロトコールは、猫のリンパ腫の治療でよく推奨される。犬で維持療法不要のCHOPベースプロトコールが発表され、既に使用されている一方で、猫では同様の維持療法不要のプロトコールに関する文献は限られている。
この研究の目的は、修正25週ウィスコンシン-マジソン大学(UW-25)化学療法プロトコールを行った中間から高グレードリンパ腫の猫の結果を述べることである。2つ目の目的は潜在的予後因子を検査することだった。
5施設からUW-25ベースプロトコールで治療した119頭の猫を研究した。カプラン-マイヤーの無憎悪期間(PFI)および生存期間中央値(MST)は56日と97日(範囲2-2019)だった。治療に対し完全反応(CR)だと判断した猫は、部分反応あるいは反応なしの猫よりも有意にPFIおよびMSTが長かった(それぞれ、PFIが205日vs54日vs21日、P<0.001とMSTが318日vs85日vs27日、P<0.001)。(Sato訳)
■シクロフォスファミドの経口投与を行っているリンパ腫の犬における無菌性出血性膀胱炎発症のリスクファクター:症例-コントロール研究
Risk factors for development of sterile haemorrhagic cystitis in canine lymphoma patients receiving oral cyclophosphamide: a case-control study.
Vet Comp Oncol. December 2014;12(4):277-86.
R Gaeta; D Brown; R Cohen; K Sorenmo
無菌性出血性膀胱炎(SHC)はシクロフォスファミド治療で知られているリスクである;しかし多くの犬の報告はケースシリーズである。
この症例-コントロール研究で、シクロフォスファミドを経口投与しているリンパ腫の犬においてSHCのリスクファクターを調べた。
SHCの犬22頭と66頭のコントロール犬を確認した。一変量解析において、SHCのリスクファクターに年齢(P=0.041)、導入プロトコール(P=0.021)、累積シクロフォスファミド投与量(P=0.002)が含まれた。多変量解析において、累積シクロフォスファミド投与量の増加はSHCのリスク増加に関係し、「短期」導入プロトコール(プロトコール1)はリスク低下に関係した。年齢と導入プロトコールの考慮後、シクロフォスファミド投与量において750mg/m2増加につきSHCのオッズは2.21上昇した。
経口シクロフォスファミドによるSHCは、累積投与量増加により起きる主に遅延毒性である。(Sato訳)
■犬のリンパ腫における化学療法誘発性の好中球減少症は寛解期間と生存期間の延長に関連する
Chemotherapy-induced neutropenia is associated with prolonged remission duration and survival time in canine lymphoma.
Vet J. 2015 Apr 28. pii: S1090-0233(15)00174-4. doi: 10.1016/j.tvjl.2015.04.032.
Wang SL, Lee JJ2, Liao AT3.
骨髄抑制は、化学療法の最も一般的な副作用のうちの一つである。
この研究の目的は、化学療法誘発性の好中球減少症がリンパ腫の犬における寛解と生存期間についての正の予後因子となるかどうかを明らかにすることである。
多中心型リンパ腫の50頭の犬に対して通常の用量でのCHOP療法を実施した。治療後に好中球減少症が認められたかどうかについて、CBCを記録した。毒性、寛解、生存期間を記録し解析した。13頭の犬は化学療法誘発性の好中球減少症が認められ、37頭については研究期間において好中球減少症は認められなかった。体重を除いて(P=0.02)、シグナルメントや負の予後因子があるかについて有意差はなかった。好中球減少症のグループおよび好中球減少症がなかったグループにおける最初の寛解期間の中央値は、それぞれ812日と219日であった (P<0.01)。好中球減少症のグループおよび好中球減少症がなかったグループにおける生存期間の中央値はそれぞれ952日と282日であった(P<0.01)。
化学療法誘発性の好中球減少症が認められたリンパ腫の犬は、好中球減少症が認められなかった犬と比較して、寛解期間および生存期間が有意に長かった。より長い寛解期間と生存期間を得るために、重度な副作用をおこさずに好中球減少症を起こすように化学療法の用量をそれぞれ調節する方がいいのかもしれない。(Dr.Taku訳)
■犬と猫の眼球内および眼球周囲リンパ腫:21症例の回顧的レビュー(2001-2012)
Intraocular and periocular lymphoma in dogs and cats: a retrospective review
of 21 cases (2001-2012).
Vet Ophthalmol. November 2014;17(6):389-96.
Juri Ota-Kuroki; John M Ragsdale; Bhupinder Bawa; Nobuko Wakamatsu; Keiichi Kuroki
目的:犬と猫の眼内および眼周囲リンパ腫の免疫学的表現型と組織学的分類を行う
方法:4か所の獣医診断検査所のデータベースで、2001年から2012年の間に犬と猫の眼内あるいは眼周囲リンパ腫の症例を検索した。ヘマトキシリン-エオジン染色のスライドをリンパ腫の確認と分類のために再検討し、腫瘍性リンパ球の系列を判定するため、CD3(T-細胞マーカー)、CD79aおよび/あるいはCD20(B-細胞マーカー)に対する免疫組織化学検査を行った。
結果:眼のリンパ腫の犬6頭と猫15頭を確認した。犬の症例では、3つの眼内と3つの眼周囲リンパ腫で、2つの眼内と1つの眼周囲リンパ腫はB-細胞性で、眼内と眼周囲リンパ腫の各1つずつがT-細胞性、1つの眼周囲リンパ腫はCD3、CD79a、CD20に非反応性だった。
猫の症例では、6つの眼内と9つの眼周囲リンパ腫で、5つの眼内と6つの眼周囲リンパ腫はB-細胞性で、1つの眼内と3つの眼周囲リンパ腫はT-細胞性だった。
犬の1症例のみが同時に全身性リンパ節腫脹があり、犬の結膜リンパ腫の1症例のみが同時に皮膚リンパ腫があり、猫の1症例のみが診断時に両眼が侵されていた。
結論:犬と猫の眼内および眼周囲リンパ腫は、B-細胞性表現型の方が多い。通常リンパ腫は眼球内あるいは眼球に隣接して発生した時、原発腫瘍と考えられないが、それらの腫瘍は最初に眼球および/あるいは眼周囲部分で見つかることも多い。正確な早期診断アプローチは、B-細胞性リンパ腫はT-細胞性よりも一般に化学療法により敏感に反応するため、動物のQOLに対し非常に重要である。(Sato訳)
■犬のリンパ腫の様々なサブタイプにおけるP-糖蛋白の免疫組織化学的検出
Immunohistochemical detection of P-glycoprotein in various subtypes of canine lymphomas.
Pol J Vet Sci. 2015;18(1):123-30.
Soko?owska J, Urba?ska K, Gizi?ski S, Zabielska K, Lechowski R.
多剤化学療法はリンパ腫の犬に対して現在の治療のスタンダードである。多剤耐性は化学療法の効果に関係する最も重要な要因である。この現象に対して原因となる主要な蛋白はP-糖蛋白である。リンパ腫の特定のサブタイプにおけるP-糖蛋白発現についてあまり分かっていない。
この研究目的は、犬リンパ腫の様々なサブタイプにおけるP-糖蛋白発現の評価だった。
P-糖蛋白の陽性反応は、リンパ腫の様々な形態学的サブタイプの25症例中12症例で見つかった。しかし、11のリンパ腫のうち3つで、陽性に弱く染められた細胞の割合は10%未満で、それらの腫瘍も陰性と考えた。10%から50%のP-糖蛋白陽性細胞を持つ腫瘍は、中心芽細胞性および中心芽-中心細胞性腫瘍の1症例で見つかった。5つのリンパ腫においてP-糖蛋白の発現は腫瘍細胞の50%を超えた。それらの症例は、中心芽細胞性、中心芽-中心細胞性、リンパ芽球性およびバーキット様サブタイプで見つかった。陽性反応は主に細胞質内で観察されたが、顕著な核周辺のドット様染色パターンが見つかる症例もいた。2症例において限局性染色パターンは免疫標識の優性タイプだった。P-糖蛋白陽性細胞を含む全てのリンパ腫の中で、免疫標識の強度は、弱(6/25)、中(2/25)、強(3/25)と評価した。
我々の結果は、中心芽細胞性リンパ腫のような一般に発生するものも含む異なる形態学的サブタイプの犬の新規に診断されたリンパ腫のほぼ1/3で存在することを示す。ゆえに、診断時のP-糖蛋白発現の判定は、治療プロトコールの計画で貴重な情報となりえる。さらに我々の結果は、犬の腫瘍におけるP-糖蛋白発現はゴルジ帯に位置する可能性があることを示している。(Sato訳)
■犬のリンパ腫における脾臓と肝臓の超音波検査および細胞診:stage migrationと予後の評価に対する所見の影響
Splenic and hepatic ultrasound and cytology in canine lymphoma: effects of findings on stage migration and assessment of prognosis.
Vet Comp Oncol. 2014 Dec 3. doi: 10.1111/vco.12127.
Nerschbach V, Eberle N, Joetzke AE, Hoeinghaus R, Hungerbuehler S, Mischke R, Nolte I, Betz D.
stage migrationはより感受性の高い診断法の使用の結果として人と犬で述べられている。
多中心型リンパ腫の犬186頭を従来のステージングの結果、また利用できる肝臓と脾臓の超音波および細胞診検査結果と共に研究した。
脾臓と肝臓の超音波および細胞診所見の追加で、肝臓と脾臓の関与があると分類された犬の数はわずかに低くなった。多中心型リンパ腫の犬において細胞診の追加はステージIVからステージIIIへの有意にシフトさせることとなった。肝臓と脾臓の超音波および細胞診の所見は多剤化学療法の犬における完全寛解および生存期間に有意な影響を及ぼすことはなかった。
犬リンパ腫のステージング方法論を再定義するべきで、脾臓と肝臓の超音波および細胞診の予後に対する意義をさらに調べる正当性が考慮される。(Sato訳)
■犬のリンパ腫:分類タイプ、疾患ステージ、腫瘍のサブタイプ、分裂速度、治療と生存性との関係
Canine lymphomas: association of classification type, disease stage, tumor subtype, mitotic rate, and treatment with survival.
Vet Pathol. 2013 Sep;50(5):738-48. doi: 10.1177/0300985813478210. Epub 2013 Feb 26.
Valli VE, Kass PH, San Myint M, Scott F.
犬のリンパ腫は多くの場合、化学療法で治療される腫瘍であるが、治療の反応とその異なるサブタイプと関連させるデータは少ない。
この研究は臨床診断がリンパ腫の犬992頭からの生検標本を基にする。全ての症例はCD3とCD79アルファに対する免疫組織化学的検査で免疫表現型を決定した。組織球性の増殖を伴う症例はCD18に対して免疫組織化学的に評価した。クローナリティーは12症例でPCRにより確かめられた。生存性データと完全な生存情報(死亡原因あるいは追跡調査から外れた時期)は456頭で得ることができた。入手できた場合の追加共変動情報は大きさ、年齢、性別、表現型、ステージ、リンパ腫のグレード、有糸分裂指数、治療プロトコールだった。B-およびT細胞性リンパ腫のサブステージが多いため、症例を以下の7つの診断カテゴリーにグループ分けした:(1)良性過形成;(2)低グレードB細胞性;(3)高グレードBおよびT細胞性;(4)低グレードT細胞性;(5)全ての有糸分裂グレードの中心芽細胞性大型B細胞性(臨床ステージで細分化);(6)全ての有糸分裂グレードの免疫芽細胞性大型B細胞性;(7)高グレード末梢T細胞性。グループ分けは組織学的グレード(400倍1視野あたり有糸分裂速度、低グレード0-5、中間6-10、高グレード>10)と生存機能評価に対するステージで決定した。
犬のサイズ(犬種を基に)あるいは性別に生存性との関係は見つからなかった。緩慢性あるいは低グレードタイプの診断カテゴリー全ては有糸分裂速度が低いが、臨床的に高グレードのものは有糸分裂速度が高かった。ほとんどの症例の診断カテゴリーは中心芽細胞性大型B細胞性リンパ腫だった。リンパ腫のこの最も症例の多いグループと比較して、高グレードリンパ腫の犬は有意に高い死亡率で、低グレードT細胞性リンパ腫の犬は有意に死亡率が低かった。高、中間、低グレードリンパ腫の治療は4グループに分けられた:無治療、ドキソルビシンを使用あるいは使用しない化学療法、プレドニゾンのみ。低グレードT細胞性(T-zone)リンパ腫は最も生存期間中央値(622日)が長かったが、T細胞性高グレード(末梢T細胞)サブタイプの犬は最も生存期間中央値が短かった(162日)。中心芽細胞性大型B細胞性リンパ腫の犬の生存期間中央値は低いステージで127日、中間ステージで221日、進んだステージで215日だった。
T-zoneリンパ腫の犬は、進行に関するサインがないため、おそらく疾患のより遅いステージと診断される。ヒトのリンパ腫のように特定サブタイプの診断に対し、免疫表現型と組織学的診断が最低限必要とされる。(Sato訳)
■犬のリンパ腫および白血病細胞系におけるアポトーシス誘発に対する一般的な抗腫瘍剤の効果
The Effect of Common Antineoplastic Agents on Induction of Apoptosis in Canine Lymphoma and Leukemia Cell Lines.
In Vivo. 2014 09-10;28(5):843-850.
Pawlak A, Rapak A, Zbyryt I, Obmi?ska-Mrukowicz B.
背景/目的:犬の最も一般的な造血の癌であるリンパ腫は、有力な治療方法である化学療法に感受性を示す。この研究の目的は、GL-1、CL-1、CLBL-1、ジャーカット細胞系に対する抗腫瘍剤シクロフォスファミド(CYC)、クロラムブシル(CBL)、シトシンアラビノシド(ARA)、デキサメサゾン(DEX)、ドキソルビシン(DOX)、エトポシド(ETO)、ロムスチン(LOM)、プレドニゾン(PRED)、ビンクリスチン(VINK)の濃度依存性細胞毒性とアポトーシス誘発能力を評価することだった。
材料と方法:細胞の生存能力とアポトーシスのレベルを判定するため、3つの異なる検査を実施した:チアゾリルブルーテトラゾリウムブロミド(MTT)、アネキシンV/ヨウ化プロピジウム(An/PI)染色およびフローサイトメトリックDNAフラグメンテーション。
結果:全ての上記物質は、異なるレベルのアポトーシス誘発を有し、試験した細胞系の増殖に対し濃度依存性の抑制効果を示した。VINKとDOXは犬の細胞系の生存能力を強く低下させ、CYCでは最も高いレベルのアポトーシスを誘発した。
結論:犬のリンパ腫(CL-1、CLBL-1)および白血病(GL-1)細胞系は、犬の腫瘍に対し、新しいより効果的な治療法を開発するのに有効なツールである。(Sato訳)
■難治性リンパ腫の猫に対するレスキュー薬剤としてロムスチンの評価
Evaluation of lomustine as a rescue agent for cats with resistant lymphoma.
J Feline Med Surg. 2012 Oct;14(10):694-700. Epub 2012 May 10.
Dutelle AL, Bulman-Fleming JC, Lewis CA, Rosenberg MP.
この回顧的研究は難治性猫リンパ腫の39症例に対し、レスキュー薬剤としてロムスチンを評価した。評価したパラメーターは、リンパ球細胞の大きさ、過去に使用した化学療法薬剤の数、過去に実施された化学療法プロトコールの数、リンパ腫の診断からロムスチン投与の開始までの時間、体重とリンパ腫の解剖学的部位だった。
細胞の大きさ、過去に使用した化学療法薬剤の数、過去に実施された化学療法プロトコールの数、解剖学的部位は全て無増悪期間に対する有意な予後因子だった。
21頭(54%)はロムスチンを1回以上投与されていた。総無増悪期間中央値(MPFI)は39日(7-708日)だった。大型に対し、小型および中型細胞リンパ腫のMPFIはそれぞれ21日と169日だった。消化管に対し、消化管以外のリンパ腫に対するMPFIはそれぞれ180日と25.5日だった。
ロムスチンは猫のリンパ腫におけるレスキュー薬剤として、受け入れられる効果と安全性を有する。(Sato訳)
■多中心型大細胞リンパ腫の犬の骨髄病変の予測についての血液学的所見
Hematologic findings predictive of bone marrow disease in dogs with multicentric large-cell lymphoma.
Vet Clin Pathol. 2014 Aug 19. doi: 10.1111/vcp.12182.
Graff EC1, Spangler EA, Smith A, Denhere M, Brauss M.
背景 多中心型大細胞性リンパ腫の犬の完全なステージ分類には骨髄の評価が必要であるが、臨床の現場では実施されないことが多い。
目的 目的は、通常の末梢の血液所見、すなわち血液塗抹の鏡検によってリンパ腫の犬において骨髄浸潤があるかを予測できるか決定することである。
方法 新たに大細胞性リンパ腫と診断された107頭の犬から採取した血液塗抹と骨髄穿刺の評価を含めた血液学的なデータを回顧的に評価した。腫瘍性のリンパ球は、細胞の大きさ、核の大きさ、クロマチンのパターン、核小体があるかによって同定した。10%以上腫瘍性のリンパ球が存在した場合に陽性の検体と判断した。骨髄においてリンパ腫が存在するかしないかに基づいて、2つの群に分けた。様々な点(血液塗抹で陽性を示す、HCT、血小板数、全白血球数、白血球分画)について、単変量ロジスティックモデルと多変量ロジスティックモデルを用いて、骨髄浸潤を予測できるかについて評価した。
結果 血小板減少症と、血液塗抹で10%以上腫瘍性のリンパ球が認められることは、骨髄浸潤の存在を予測する有意な因子として同定された。別々に考えると、血液塗抹で陽性を示すこと、または血小板減少があることのどちらかは、感度は低かった(60%)が、特異性は中等度であった(それぞれ89%と87%)。これらの変数を一緒に評価すると感度は上昇した(80%)。
結論 多中心型の大細胞性リンパ腫の犬において、血小板減少症または循環血中に腫瘍性のリンパ球が存在することは、骨髄浸潤を示唆しているが、確定的ではなかった。正常な末梢血所見は、骨髄においてリンパ腫の可能性を除外するものではない。(Dr.Taku訳)
■犬の緩慢性リンパ腫の臨床、病理組織、免疫組織化学的特徴
Clinical, histopathological and immunohistochemical characterization of canine indolent lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2013 Dec;11(4):272-86. doi: 10.1111/j.1476-5829.2011.00317.x. Epub 2012 Feb 2.
Flood-Knapik KE, Durham AC, Gregor TP, Sanchez MD, Durney ME, Sorenmo KU.
緩慢性リンパ腫は全ての犬のリンパ腫の29%を占める;しかし、サブタイプや生物学的挙動に関する限られた情報しかない。
この回顧的研究は、緩慢性リンパ腫の犬75頭の臨床的特徴、病理組織学的および免疫組織化学的特性、治療、転帰、予後因子を述べる。
WHO病理組織学的分類およびCD79a、CD3、Ki67、P-糖蛋白(P-gp)に対する免疫組織化学(IHC)を実施した。
最も一般的な病理組織学的サブタイプはT-zoneで61.7%、(MST33.5ヶ月)、続いて辺縁帯、25%、(MST21.2ヶ月)、P=0.542だった。予備的病理組織学的分類に対するIHCの追加は、20.4%の症例で診断を考え直す結果となった。全身的治療の使用は生存性に影響しなかったP=0.065。CHOPベースの化学療法でのMST21.6ヶ月と比べ、クロラムブシルとプレドニゾンで治療した犬はMSTに到達しなかったP=0.057。
総MSTが4.4年ということが、実際この疾患が緩慢な疾患であると示している。しかし、全身的治療の効果を前向き試験により調査すべきである。(Sato訳)
■リンパ腫の犬においてドキソルビシン治療と関連した遅発性の嘔吐の頻度は絶食により軽減される
Fasting Reduces the Incidence of Delayed-Type Vomiting Associated with Doxorubicin Treatment in Dogs with Lymphoma.
Transl Oncol. 2014 May 12. pii: S1936-5233(14)00049-7. doi: 10.1016/j.tranon.2014.04.014.
Withers SS, Kass PH, Rodriguez CO Jr, Skorupski KA, O'Brien D, Guerrero TA, Sein KD, Rebhun RB.
絶食はG1期の遮断によって消化管の細胞の増殖率を低下させ、インスリン様成長因子 (IGF-1)のダウンレギュレーションを含む細胞シグナルの変化を通して癌細胞ではなく正常な細胞の保護を促進する。
そういうことで、この研究の目的は、ドキソルビシンを投与した犬において遅発型の化学療法誘発性の悪心と嘔吐に対する絶食の影響を検討することである。本研究は、前向きランダム化のクロスオーバー研究であり、ドキソルビシンを2回投与した。担癌犬をドキソルビシンの1回目または2回目の投与の前日の午後6時からスタートし24時間絶食させるようにランダムに割り当て、すべての治療は午後12時の1時間前か後の間に投与した。次の投与の前は通常通り給餌した。循環IGF-1濃度は、各ドキソルビシンによる治療の直前に得た血清サンプルで測定した。
組み入れた20頭の犬から35回の投与のデータを得た。給餌した犬と比較して、絶食していた犬は有意に低い嘔吐の発生率を示した(67%に対して10%、P=0.02)。さらに、クロスオーバーした用量を与えた15頭中、通常通り給餌した際にドキソルビシン誘発性の嘔吐を起こした5頭の犬のうち4頭において嘔吐はなかった(P=0.05)。他の消化管や健康上、骨髄の毒性、血清IGF1濃度に違いは認められなかった。(Dr.Taku訳)
■リンパ腫の犬におけるサイクロフォスファミドと併用したロムスチンの耐容性
Tolerability of lomustine in combination with cyclophosphamide in dogs with lymphoma.
J Am Anim Hosp Assoc. 2014 May-Jun;50(3):167-73. doi: 10.5326/JAAHA-MS-6020. Epub 2014 Mar 21.
Rassnick KM, Bailey DB, Malone EK, Flory AB, Kiselow MA, Intile JL.
この回顧的研究で、リンパ腫の犬におけるロムスチン(CCNU)とサイクロフォスファミド(CTX)の併用プロトコールに関する毒性を述べる。
0日目に60mg/m2の目標量でCCNUを経口投与し、目標量250mg/m2のCTXを0日目から4日目を通して分割経口投与し、全ての犬に予防的抗生物質を投与した。
この研究では57頭の犬に90回の処置を行った。好中球減少が主要な毒性で、CCNU/CTXの最初の処置の後、グレード4の好中球減少が起こる総体的頻度は30%(95%信頼区間、19-43%)だった。グレード4の好中球減少を起こした犬の平均体重(19.7kg±13.4kg)は、グレード4の好中球減少を起こさなかった犬の平均体重(31.7kg±12.4kg;P=0.005)よりも有意に少なかった。1頭の犬(3%)は肝毒性を示唆する血液学的変化を示した。腎毒性あるいは出血性膀胱炎の所見を示した犬はいなかった。消化管の副作用はあまりなかった。
ここで報告された知見を基に、担癌犬においてCCNU60mg/m2とCTX250mg/m2(5日で分割)の併用を4週間ごとに投与する方法は許容可能である。(Sato訳)
■リンパ腫の化学療法の一部としてフロセミドの併用をしない3日間の経口シクロフォスファミドを投与した犬における無菌性出血性膀胱炎の発生
Incidence of sterile hemorrhagic cystitis in dogs receiving cyclophosphamide orally for three days without concurrent furosemide as part of a chemotherapeutic treatment for lymphoma: 57 cases (2007-2012).
J Am Vet Med Assoc. 2013 Oct 1;243(7):1025-9. doi: 10.2460/javma.243.7.1025.
Best MP, Fry DR.
目的:フロセミドを併用せず、犬のリンパ腫の治療に対する多剤併用化学療法の一部としてシクロフォスファミドの最大耐量(MTD)を3日に分割して経口投与した後の無菌性出血性膀胱炎(SHC)と他の副作用の発生を調べる
デザイン:回顧的ケースシリーズ
動物:57頭の犬
方法:記述したシクロフォスファミド処置を行ったリンパ腫の犬を確認するために医療記録を再調査した。シグナルメント、リンパ腫のステージ、併発疾患、シクロフォスファミド投与量、副作用(SHCを含む)、寛解率、転帰に関する情報を入手した。SHCの発生は、フロセミド処置を行った、あるいは行わなかった単回1日投与量としてシクロフォスファミドのMTDを投与した過去の文献から抽出したコントロール群のそれと比較した。
結果:研究期間中に全57頭のうち、SHCを発症した犬はいなかった。57頭中47頭(82%)のリンパ腫は完全寛解した。他の副作用は珍しく、自然治癒性だった;骨髄抑制を起こした犬はおらず、5頭の犬だけが軽度の消化管障害を起こした。フロセミドを使用せず単回投与としてシクロフォスファミドを投与した過去のコントロール犬で報告されたSHCの発生(24/219頭)よりも有意に低く、フロセミドを使用した単回投与としてシクロフォスファミドを投与した過去のコントロール犬で報告されたSHCの発生(2/139頭)と有意差はなかった。
結論と臨床関連:この研究で、フロセミドを使用せず1日のMTDを分割して3日間経口投与した後でSHCを発症した犬はいなかった。このシクロフォスファミドの投与方法が現行の単回投与法と同等、あるいは優れているか確かめる研究がさらに必要である。(Sato訳)
■犬のT-zoneリンパ腫:免疫表現型、予後、特徴
Canine T-Zone Lymphoma: Unique Immunophenotypic Features, Outcome, and Population Characteristics.
J Vet Intern Med. 2014 Mar 21. doi: 10.1111/jvim.12343.
Seelig DM1, Avery P, Webb T, Yoshimoto J, Bromberek J, Ehrhart EJ, Avery AC.
背景 犬のT細胞型リンパ腫 (TCL)は、低悪性の経過をたどるT-zoneリンパ腫 (TZL)のようないくつかの型が含まれ、臨床的にも組織学的にも一つの疾患ではない。免疫表現型は人においてTCLの分類に重要な方法であり、犬でも同じように有用であるかもしれない。
仮説/目的 CD45の発現欠失がTZLの診断の特異的な特徴である。
動物 組織学的検査とフローサイトメトリーによる免疫表現型解析を同時に実施した20頭の犬を詳細に検討した。免疫表現型解析によって診断した追加の494頭の犬について、TZLの犬の集団を同定できるかの調査に使用した。
方法 TCLの35頭の犬のリンパ節生検サンプルを、2人の病理学者によってWHO分類に従い分類した。CD45-のTCLの犬は20頭、CD45+ のTCLは15頭いた。病理学者にはフローサイトメトリー所見は知らされていなかった。CD45-のリンパ腫の20頭の犬について結果の情報を調査し、さらなる494頭の犬の集団の特徴を調べた。
結果 CD45-の20頭全ての症例はTZLと分類された。CD45+の15例は、進行性のTCLであると分類され、添付の論文に記述されている。TZLの症例は生存期間の中央値が637日であった。免疫表現型の解析によってTZLと診断された追加の494頭の犬の検査では、40%の症例がゴールデンレトリバーで、中央値10歳齢で診断されており、多くの症例はリンパ節腫大とリンパ球増多症があった。
結論 TZLは診断に使用可能な独特の免疫表現型の特徴を持っている。(Dr.Taku訳)
■腹腔内抗腫瘍性薬物輸送:悪性リンパ腫の猫におけるシクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロンプロトコールでの経験
Intraperitoneal antineoplastic drug delivery: experience with a cyclophosphamide, vincristine and prednisolone protocol in cats with malignant lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2014 Mar;12(1):37-46. doi: 10.1111/j.1476-5829.2012.00329.x. Epub 2012 Apr 10.
Teske E, van Lankveld AJ, Rutteman GR.
この回顧的研究で、悪性リンパ腫の猫26頭での腹腔内化学療法プロトコール-シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン(IP-COP)の有効性と安全性を調べた。
IV投与に猛烈に抵抗する猫において、腹腔内ルートはより実践的な方法で、投与がより安全で猫のストレスも少ない。完全寛解(CR)率は76.9%(n=20)だった。最初の寛解の持続期間中央値は421日だった。1年-、2年-無病期間を計算すると67.1%と48.0%だった。生存期間中央値は388日で、全体の1年-、2年-生存率は54.7%と46.9%だった。
若い猫はより好ましい予後を示した。CRに達することが長期生存には必須だった。特異的な腹腔内投与に関係する有害事象(AE)は見られなかった。AEは一般的に軽度で、過度に多いということはなかった。
それらの結果は、COPプロトコール化学療法の投与で、腹腔内ルートは安全で有効な代替法であると示した。(Sato訳)
■26頭の猫における12週間の維持療法なしの多剤併用療法を用いた猫のリンパ腫の治療
Treatment of feline lymphoma using a 12-week, maintenance-free combination chemotherapy protocol in 26 cats.
Vet Comp Oncol. 2014 Feb 19. doi: 10.1111/vco.12082.
Limmer S, Eberle N, Nerschbach V, Nolte I, Betz D.
この前向きの臨床試験の目的は、猫のリンパ腫において短期間の維持療法なしの化学療法プロトコールの効果と毒性を調査することである。
高悪性度から中悪性度のリンパ腫と確定診断された26頭の猫を、L-アスパラギナーゼ、ビンクリスチン、シクロフォスファミド、ドキソルビリン、プレドニゾロンを順番に何度も投与する12週間のプロトコールで治療した。完全寛解
(CR)と部分寛解 (PR)の率は46%と27%であった。最初のCRの中央値は394日で、PRの中央値は41日であった。CRになるために影響する因子はとくになかった。全生存期間は、78日であった(範囲は9-2230日)。CRの猫の生存期間の中央値は454日であり、PRの猫の場合は82日であった。毒性の程度は基本的に低く、最も認められたのは食欲低下であった。CRに到達した猫では、長期間の寛解と生存を得るのに維持療法なしの化学療法で十分であるように見えた。CRになる可能性を決める補助因子、反応を強める方法、化学療法誘発性の食欲不振を解決する方法については将来的に同定する必要がある。(Dr.Taku訳)
■猫のリンパ腫の解剖学的および形態学的分類に関する予後解析
Prognostic Analyses on Anatomical and Morphological Classification of Feline Lymphoma.
J Vet Med Sci. 2014 Feb 10.
Sato H1, Fujino Y, Chino J, Takahashi M, Fukushima K, Goto-Koshino Y, Uchida K, Ohno K, Tsujimoto H.
本研究は、解剖学的部位および細胞形態学的に分類した163頭の猫のリンパ腫の予後を解析することである。
解剖学的に、消化管型リンパ腫が最も多いタイプで、縦隔型および鼻腔リンパ腫よりも有意に短い生存期間を示した。細胞形態学的には、猫のリンパ腫において多いサブタイプはなかった。免疫芽球型(18%)、胚中心芽球性(16%)、Globule leukocyte型(15%)、リンパ球性(12%)、リンパ芽球性(12%)、多形中-大細胞型(10%)、未分化大細胞型(7%)が比較的よくみとめられるサブタイプであった。Globule leukocyte型リンパ腫の猫の大部分は消化器型であった。この分類の中で生存期間の中央値を比較すると、globule leukocyte型リンパ腫の猫は、高悪性度のものおよび他の低悪性度のリンパ腫よりも有意に短い生存期間を示した。さらに、高悪性度のリンパ腫の猫は、他の低悪性度のリンパ腫の猫よりも有意に短い生存期間を示した。
この研究によって、猫のリンパ腫における解剖学的および細胞形態学的な評価の臨床的な意義が示唆された。(Dr.Taku訳)
■デキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシンD、シトシンアラビノシド(DMAC)化学療法の再発した犬のリンパ腫に対する効果と副作用
The efficacy and adverse event profile of dexamethasone, melphalan, actinomycin D, and cytosine arabinoside (DMAC) chemotherapy in relapsed canine lymphoma.
Can Vet J. 2014 Feb;55(2):175-80.
Parsons-Doherty M, Poirier VJ, Monteith G.
この回顧的研究では、デキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシンD、シトシンアラビノシド(DMAC)を用いた化学療法プロトコールを、CHOPに基づいたプロトコールで治療されていた86頭の犬に対して、最初のレスキュー療法として使用した場合の効果と副作用について評価した。
43頭の犬が寛解し(16%完全寛解、27%部分寛解)、57頭は反応しなかった。全無増悪生存期間 (PFS)の中央値は24日であった。41%の犬において血小板減少症、17%の犬において好中球減少症、13%の犬において消化器毒性が認められた。全体では、16%(79頭中13頭)の犬においてグレードIIIからIVの血小板減少症が認められ、8%(74頭中6頭)の犬においてグレードIIIからIVの好中球減少症、1%(79頭中1頭)の犬においてグレードIIIからIVの消化器毒性が認められた。
DMACプロトコールの効果は、再発したリンパ腫に対して用いられる他のレスキュープロトコールと同様であったが、PFSがより短かった。主な副作用は血小板減少症であり、これによって治療が制限されることもある。(Dr.Taku訳)
■節外皮下リンパ腫の猫97頭の特徴、病理組織所見、転帰(2007-2011)
Patient characteristics, histopathological findings and outcome in 97 cats with extranodal subcutaneous lymphoma (2007-2011).
Vet Comp Oncol. 2014 Jan 10. doi: 10.1111/vco.12081.
Meichner K, von Bomhard W.
猫の節外リンパ腫の珍しい型である皮下リンパ腫の猫97頭における疫学、臨床、マクロおよび顕微鏡による腫瘍特性と転帰を述べる。
中年(中央値11歳)、オス(60.8%)、家猫短毛種(89.7%)が一般に罹患した。多くの腫瘍は、痛みがなく、硬く、皮下結節あるいはマスで、胸部側面あるいは腹壁や肩甲骨間に出る傾向があった。表層あるいは底の組織に伸びる深い皮下浸潤、広い中心部分の壊死、周囲炎症が特徴的な病理組織所見だった。レトロウイルス感染の有病率は低かった。治療後の局所再発は一般的(43.5%)で、経過の後半には遠隔関与が32.2%に見られた。総生存期間中央値は148日だった。
猫の皮下リンパ腫は珍しいが、皮下のマスの重要な鑑別診断として考慮すべきである。腫瘍は攻撃的な生物学的挙動を示す。予後を含む治療オプションは追加研究で調査すべきである。(Sato訳)
■猫の縦隔型リンパ腫:シグナルメント、レトロウイルス感染、化学療法に対する反応性、予後因子についての後向き研究
Feline mediastinal lymphoma: a retrospective study of signalment, retroviral status, response to chemotherapy and prognostic indicators.
J Feline Med Surg. 2013 Dec 23. [Epub ahead of print]
Fabrizio F, Calam AE, Dobson JM, Middleton SA, Murphy S, Taylor SS, Schwartz A, Stell AJ.
歴史的に、猫の縦隔型リンパ腫は、若齢、猫白血病ウイルス (FeLV)陽性であること、シャム猫、生存期間が短い事と関連しているとされている。UKにおけるFeLVワクチンが普及した後の最近の研究はない。
本後向き多施設研究の目的は、ワクチンが普及したあとの状況で、猫の縦隔型リンパ腫におけるシグナルメント、レトロウイルス感染、化学療法に対する反応性、生存と予後因子について再評価することである。
縦隔の腫瘤に関連した症状があり細胞学的/病理組織学的にリンパ腫と確定した猫の記録を5つのUKの2次診療施設(1998-2010年)から情報を得た。治療反応、生存と予後因子は、追跡情報がある治療された猫において評価した。
55例を調査した。年齢の中央値は3歳齢であり(範囲、0.5-12歳齢)、12頭(21.8%)の猫は、シャム猫であり、雄と雌の比率は3.2 : 1.0であった。5頭がFeLV陽性であり、2頭がFIV陽性であった。化学療法に対する反応性と予後については、38頭において評価した。奏功率は94.7%であり、完全寛解(CR)および部分寛解 (PR)の率は、COP(シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾン)(n = 26, CR 61.5%, PR 34.0%)か、マジソン-ウィスコンシン(MW) (n = 12, CR 66.7%, PR 25.0%)かによって有意な差はなかった。生存期間の中央値は373日(範囲 20-2015日間)であり、COPは484日間(範囲20-980日間)およびMWは211日間(範囲24-2015日間)であった(P = 0.892)。CRに到達した猫は、生存期間がより長かった(980日で、PRの場合42日)(P = 0.032)。年齢、品種、性別、部位(縦隔型か縦隔型プラスそれ以外の部位)、レトロウイルスに感染しているか、前以てグルココルチコイドによる治療を受けたかについては、反応性や生存に影響はなかった。
猫の縦隔型リンパ腫症例は、化学療法によく反応し、とくにCRに到達した猫においては、生存期間が長い。FeLV抗原陽性猫の数は低く、雄と若いシャム猫がより多かった。(Dr.Taku訳)
■1頭のボクサーで行ったリンパ管肉腫の新しい治療アプローチ
A novel approach to treatment of lymphangiosarcoma in a boxer dog.
J Small Anim Pract. June 2013;54(6):334-7.
A Marcinowska; J Warland; M Brearley; J Dobson
5歳メスのボクサーの尾側乳腺部が腫脹していた。そのマスを外科的に切除し、病理組織検査で、境界不明瞭な病変が乳腺組織に伸び、付属リンパ節の洞に浸潤を認めた。診断はリンパ管肉腫だった。完全な血液検査、胸部エックス線検査、腹部および術部の超音波検査で、術部の炎症の可能性と鼠径リンパ節の反応/転移性変化を除いて顕著な異常は認めなかった。
ドキソルビシン投与により6か月再発がなかった。再燃時、クロラムブシルとメロキシカムのメトロノミック療法を行ったが適切なコントロールができなかった。リン酸トセラニブを導入し、皮膚プラークだけを残し、マスのほぼ完全な寛解をもたらした。
著者の知識では、犬のリンパ管肉腫の2つの新しい治療アプローチを行い、過去に発表された生存期間よりも良い結果を得たことを述べた最初の報告である。(Sato訳)
■16頭の化学療法で治療した猫の胃リンパ腫の回顧的研究
A Retrospective Study of Feline Gastric Lymphoma in 16 Chemotherapy-Treated Cats.
J Am Anim Hosp Assoc. 2013 Nov 11.
Gustafson TL, Villamil A, Taylor BE, Flory A.
この研究の目的は、シグナルメント、臨床症状、検査所見、付随する所見、治療に対する反応性、転帰に関して、猫の胃リンパ腫の症例について述べ、予後の変数を明らかにすることである。
化学療法で治療したステージIおよびIIの胃リンパ腫の16頭の猫を使用した。75%の猫が寛解した。全初期寛解期間は108日であった。他のタイプの猫のリンパ腫と同様に、治療に対する反応性は、予後に関連があった。完全寛解(CR)の猫は、部分寛解 (PR)の猫と比較してより生存期間が長かった。去勢雄が、避妊雌より長い生存期間を示したというように、性別も予後に関連があり、さらにレスキュー療法による治療も予後に関連があった。レスキュー療法を受けた猫は、受けていない猫より初期寛解期間が短かった。事前にステロイドによる治療を受けていた事とステージは、有意な予後の変量とはならなかった。
この研究は、猫において化学療法で治療した胃リンパ腫の特徴を表している。猫の胃リンパ腫に対する外科療法と化学療法の効果を比較し明らかにするためには、さらなる研究が必要である。(Dr.Taku訳)
■新規に診断された猫におけるリンパ腫の眼症状
Ocular manifestation of lymphoma in newly diagnosed cats.
Vet Comp Oncol. 2013 Sep 17. doi: 10.1111/vco.12061.
Nerschbach V, Eule JC, Eberle N, Hoinghaus R, Betz D.
リンパ腫の眼症状はヒトや犬で記述されているが猫では珍しい。この前向き研究において、リンパ腫と新規に診断され、治療を行っていない猫を臨床ステージ及び眼科所見に関して評価した。
26頭の猫を研究した。12頭(48%)において眼の変化が認められた。前ぶどう膜炎と後ぶどう膜炎が優勢な所見で、影響を受けた個体の58%で見られた。他の所見には、眼球突出、角膜表面病変と結膜水腫があった。
8頭の猫は化学療法を受け、そのうち2頭は眼病変があった。それら2頭の猫は前ぶどう膜炎の完全寛解、後ぶどう膜炎の部分的寛解に至った。
眼の関与の検出のため、ステージIVからステージVへのステージ変化が4頭で起きた。
それらの所見から、眼科的検査は罹患猫の追加検査と同様、猫のリンパ腫のステージングの重要な部分として考慮される。(Sato訳)
■毎週のシクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾンベースプロトコールで治療した猫のリンパ腫:114症例(1998-2008)
Lymphoma in cats treated with a weekly cyclophosphamide-, vincristine-, and prednisone-based protocol: 114 cases (1998-2008).
J Am Vet Med Assoc. 2013 Apr 15;242(8):1104-9. doi: 10.2460/javma.242.8.1104.
Waite AH, Jackson K, Gregor TP, Krick EL.
目的:リンパ腫の猫のシクロフォスファミド-、ビンクリスチン-、プレドニゾン(COP)-ベース化学療法プロトコールに関係する臨床的反応率、無進行生存期間、総生存期間、可能性のある予後因子を評価すること
構成:回顧的症例シリーズ
動物:リンパ腫の猫114頭
方法:1998年から2008年の間にペンシルバニア大学Matthew J. Ryan動物病院で毎週COPベースの化学療法プロトコールを受けた猫のカルテを、シグナルメント、関与した解剖学的部位、細胞の形態、治療、転帰に関して評価した。レトロウイルスの状況、基準の体重、サブステージ、解剖学的部位、投与遅延、投与縮小、治療に対する反応を予後の重要性に対して評価した。
結果:症例の多く(94頭(82.4%))はサブステージbで、最も一般的な解剖学的部位は消化管(57頭(50%))だった。最初の化学療法サイクル後の臨床反応率は47.4%だった。治療に対する反応は無進行生存期間と総生存期間に有意に関係し、サブステージは無進行生存期間に有意に関係した。無進行生存期間と総生存期間の中央値は65.5日と108日だった。反応しない猫と比べて、反応した猫の無進行生存期間(364日対31日)と総生存期間(591日対73日)の中央値は有意に長かった。
結論と臨床的関連:COP-ベースの化学療法1サイクル目後の臨床反応は、リンパ腫の猫の無進行生存期間と総生存期間に対して予測的だった。ゆえに化学療法1サイクル後の反応は、それ以上の治療についてのガイドとして役立つだろう。新しい予後因子は確認されなかった。(Sato訳)
■リンパ腫の犬における化学療法許容度および治療結果を予測するためのMDR1遺伝子発現の判定
Determination of MDR1 gene expression for prediction of chemotherapy tolerance and treatment outcome in dogs with lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2013 Jul 3. doi: 10.1111/vco.12051.
Gramer I, Kessler M, Geyer J.
多剤耐性遺伝子1(MDR1)発現レベルを、標準的化学療法プロトコールを受けている異なるタイプの悪性リンパ腫の犬27頭で分析した。血液サンプルを使用しMDR1リアルタイムPCR発現解析を行った。治療許容度と結果は、定期的な臨床検査とオーナーへの聞き取りで評価した。
治療下で重度副作用が起きた犬は、薬剤をよく許容した犬と比べ、有意に低い基礎MDR1遺伝子発現レベルを示した。治療中の長期MDR1遺伝子発現解析において、基線の発現と比べ4頭の犬は2倍以上のMFR1アップレギュレーションを示した。他はいないが、それら4頭の犬全てが疾患進行を示した。
結論として、基線および継続したMDR1遺伝子発現レベルは、リンパ腫の化学療法中の重度薬剤副作用の発生および/あるいは多剤耐性の発生に対する予測値ということができた。(Sato訳)
■犬の再燃性リンパ腫のメクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾン(MMOP)による治療
Mechlorethamine, vincristine, melphalan and prednisone (MOMP) for the treatment of relapsed lymphoma in dogs.
Vet Comp Oncol. 2013 Aug 5. doi: 10.1111/vco.12055.
Back AR, Schleis SE, Smrkovski OA, Lee J, Smith AN, Phillips JC.
再燃したリンパ腫の犬88頭を28日サイクルのMOMP(メクロレタミン、ビンクリスチン、メルファラン、プレドニゾン)プロトコールで治療した。
MOMPプロトコールの総反応率(ORR)は51.1%で、中央反応期間は56日(範囲7-858日)だった。12%の犬は中央値81日(範囲42-274日)の間完全寛解を呈し、38.6%の犬は中央値49日(範囲7-858日)の間部分寛解を呈した。T細胞型リンパ腫の犬は、ORRが55%で中央反応期間は60日(範囲49-858日)で、B細胞型リンパ腫の犬のORRは57%で反応中央期間は81日(範囲7-274日)(P=0.783)だった。
全頭の総生存期間は183日(範囲17-974日)だった。毒性を54%の犬が経験したが、大多数はグレードIに分類された。
再燃したリンパ腫の犬に対するMOMPプロトコールはよく耐えることができ、1つのオプションとなると思われる。(Sato訳)
■15頭の犬の消化管のリンパ腫の超音波検査所見
J Small Anim Pract. 2013 Jul 25. doi: 10.1111/jsap.12117. [Epub ahead of print]
Sonographic features of gastrointestinal lymphoma in 15 dogs.
Frances M, Lane AE, Lenard ZM.
目的 この研究の目的は、犬の消化管のリンパ腫の超音波検査上の特徴を明らかにすることである。
方法 後向き研究であり、病理組織(可能であれば免疫組織化学検査も)または細胞診および腹部超音波検査で消化管リンパ腫と診断された犬を用いた。
結果 リンパ腫と病理組織学的に確定診断した15頭のうち4頭 (26.7%)は超音波検査上の異常は認められなかった。超音波検査上の異常があった犬においても、腸管壁の肥厚、壁の構造が存在するか消失しているかといった特徴はかなり様々であった。消化管に関連した臨床症状は消化管のリンパ腫の信頼できるマーカーではなく、体重減少、嘔吐、下痢はあまりない症状であった。腸管閉塞もどの患者にも認められなかった。
臨床的意義 犬において消化管のリンパ腫を超音波検査上の見え方は非特異的なものであった。消化管のリンパ腫は、超音波検査上腸管が正常に見えたとしても鑑別診断にあげておかなければならない。(Dr.Taku訳)
■犬のリンパ腫に対する多剤併用療法にエピルビシンを用いた場合
Epirubicin as part of a multi-agent chemotherapy protocol for canine lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2012 Feb 28. doi: 10.1111/j.1476-5829.2011.00311.x.
Elliott JW, Cripps P, Marrington AM, Grant IA, Blackwood L.
この研究の目的は、アントラサイクリン系抗癌剤としてエピルビシンを含む多剤併用化学療法を受けたリンパ腫の97頭の犬の治療の結果を明らかにすることである。
75頭は、維持療法なしで25週のプロトコールを、22頭は維持療法ありでうけた。完全寛解率は96%であり、最初の再発までの期間および全生存期間はそれぞれ216日および342日であった。T細胞型リンパ腫の犬とWHOのサブステージbの犬は、全生存期間と最初の再発までの期間が有意に短かった。ドキソルビシンを含んだ治療と同様の毒性でそのプロトコールは耐容性があった。
多剤併用療法にエピルビシンを加えることは安全であり、犬の多中心型のリンパ腫の治療に対して効果がある。高い初期反応率と全生存期間の中央値は、ドキソルビシンを用いた他の報告されたプロトコールと同様であった。(Dr.Taku訳)
■犬の緩慢性/侵襲性リンパ腫:組織学的関連性を備えた臨床スペクトル
Canine indolent and aggressive lymphoma: clinical spectrum with histologic correlation.
Vet Comp Oncol. 2013 Jun 20. doi: 10.1111/vco.12048. [Epub ahead of print]
Aresu L, Martini V, Rossi F, Vignoli M, Sampaolo M, Arico A, Laganga P, Pierini A, Frayssinet P, Mantovani R, Marconato L.
新たにリンパ腫と診断した63頭の犬は、完全なステージングを行い、同じ化学療法を受けた。びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫は最も多い組織タイプ(44.4%)で、続いて末梢性T細胞性リンパ腫(20.6%)であった。緩慢性リンパ腫は症例の30.2%を数えた。侵襲性B細胞性リンパ腫に罹患した多くの犬はステージIVだった。緩慢性/侵襲性T細胞性リンパ腫の犬はよりステージVが見られ、症候性であった。肝臓と骨髄は優勢にそれぞれB細胞性、T細胞性によって影響を受けた。臨床ステージはサブステージ、性別と総LDH濃度に有意に関連した。侵襲性B細胞性リンパ腫はより寛解に達しやすかった。中央生存期間は侵襲性/緩慢性T細胞性リンパ腫で55日、緩慢性B細胞性リンパ腫で200日、侵襲性B細胞性リンパ腫で256日であった。進行した緩慢性リンパ腫の予後は、侵襲性リンパ腫のそれとはかなり異なるようには見えない。様々な組織タイプについて熟知することは、正確な診断および治療をするのに意味を持つ。(Dr.Kawano訳)
■多中心型リンパ腫の犬の連続した止血のモニタリング
Serial haemostatic monitoring of dogs with multicentric lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2013 May 25. doi: 10.1111/vco.12041.
Kol A, Marks SL, Skorupski KA, Kass PH, Guerrero T, Gosselin RC, Borjesson DL.
リンパ腫は犬の最も一般的な造血性悪性腫瘍で、凝固性亢進とその後の血栓塞栓症に関係している。
この研究の目的は、多中心型リンパ腫の犬で、止血状態の連続的特徴を述べることだった。トロンボエラストグラフィー、トロンビン-抗トロンビン複合体濃度、通常の血液および凝固パネルを測定した。
研究に27頭の犬を含め、15頭が寛解で研究を終了した。来院時、多中心型リンパ腫の犬の81%(22/27)は、凝固性亢進に一致する止血プロフィールに変化していた。凝固性亢進の検査所見は、治療中あるいは臨床寛解から1か月でも解消しなかった。化学療法プロトコール完了時の凝血形成の促進率は生存期間短縮と関係した。
多中心型リンパ腫の犬は、来院から化学療法完了後4週間まで凝固性亢進の頻度が高いと結論付けた。化学療法プロトコールがうまく終わっている犬において、Kの角度増加と短縮は生存期間短縮と関係するかもしれない。(Sato訳)
■リンパ腫の犬の蛋白尿
Proteinuria in canine patients with lymphoma.
J Small Anim Pract. January 2013;54(1):28-32.
A Di Bella; C Maurella; A Cauvin; J M Schmidt; B B Tapia; S M North
目的:健康な犬と比べてリンパ腫の犬の蛋白尿はより一般的に見られるか判定することと、リンパ腫の犬で蛋白尿の程度と頻度を評価すること
方法:リンパ腫の犬32頭の尿蛋白:クレアチニン比を測定し、健康な犬30頭と比較した。
結果:リンパ腫の犬は健康な犬に比べ蛋白尿になりやすそうである。リンパ腫の犬の蛋白尿は一般的だが、ほとんどの症例は重度ではない。蛋白尿の有無はリンパ腫のステージ、あるいはサブステージに関連しない。
臨床的意義:軽度蛋白尿はリンパ腫の犬の一般的な所見である。蛋白尿の臨床的影響はおそらく低い。(Sato訳)
■心臓リンパ腫に続発した完全房室ブロックの犬の1例
Complete atrioventricular block secondary to cardiac lymphoma in a dog.
J Vet Cardiol. December 2012;14(4):537-9.
Joshua A Stern; Jeremy R Tobias; Bruce W Keene
2次元経胸郭心エコー検査で、心室中隔基底部に約1x1x1cmのラフな球形のマスがある1頭の犬で第3度房室(AV)ブロックを認めた。その犬は嗜眠と時折おこる虚脱の短期的病歴があり、オーナーはマス病変が発見された後に安楽死を選択した。検死で心室中隔、心室自由壁、心房心筋内に複数のマスを認めた。最終診断は大細胞型(T細胞性)リンパ肉腫だった。(Sato訳)
■犬の大細胞型B細胞リンパ腫における末梢血異常と骨髄浸潤
Peripheral blood abnormalities and bone marrow infiltration in canine large B-cell lymphoma: is there a link?
Vet Comp Oncol. 2013 Feb 18. doi: 10.1111/vco.12024.
Martini V, Melzi E, Comazzi S, Gelain ME.
公式ガイドラインは、犬のリンパ腫のステージングにおいて血球減少が存在しない限り骨髄(BM)評価の必要性を考えていない。
この研究の目的は、犬の大細胞型B細胞リンパ腫において、血液異常が骨髄関与を予測できるかどうかを調べることだった。
フローサイトメトリーでBM浸潤を評価した。
血液学的異常がない犬と1つ以上異常がある犬の間に違いは見られなかった。しかし、血小板減少、白血球増加、リンパ球増加の犬において浸潤の程度は有意に高く、血小板数に負の相関があり、血液浸潤に正の相関があった。
我々の結果は、血小板減少、白血球増加あるいはリンパ球増加が高い浸潤を示唆できたとしても、血液異常が常に骨髄関与を予測するわけではないと示唆する。ゆえに、BM評価は浸潤したサンプルで間違わず、分類を改善するためにルーチンなステージングに含めるべきである。しかし、その臨床的関連性と予後予測の価値はいまだ明確ではなく、さらに研究が必要である。(Sato訳)
■直腸リンパ腫の犬11例:後ろ向き研究
Rectal lymphoma in 11 dogs: a retrospective study.
J Small Anim Pract. October 2012;53(10):586-91.
N Van Den Steen; D Berlato; G Polton; J Dobson; J Stewart; G Maglennon; A M Hayes; S Murphy
目的:犬の直腸のリンパ腫の臨床的挙動および免疫表現型を回顧的に評価する
方法:病理組織検査で直腸のリンパ腫と診断された11頭の犬を回顧的に再検討した。診断時、あるいは回顧的にCD3およびCD79a抗体の免疫組織化学検査を実施した。
結果:治療プロトコールは、6頭の犬が外科手術と補助的化学療法、2頭は切開性バイオプシーのみ行った後に化学療法、1頭は外科的切除のみ、1頭は対症療法、1頭は無治療と様々だった。化学療法は低用量COP(シクロフォスファミド-プレドニゾロン-ビンクリスチン)プロトコール(4頭)、あるいは6週間CHOPベース(シクロフォスファミド-ビンクリスチン-プレドニゾロン-アントラサイクリン)プロトコール(4頭)で治療されていた。化学療法を使用した犬は、化学療法を使用しなかった犬よりも有意に長く生存した(2352日対70日)。生存期間中央値は出せなかったが、総平均生存期間は1697日だった。11サンプルのうち10サンプルで免疫組織化学検査を実施し、全ての症例はB細胞リンパ腫だった。
臨床的意義:直腸の犬のリンパ腫は予後が好ましい。それら病変の免疫組織化学評価は、検査した全ての症例でB細胞リンパ腫と一致した。(Sato訳)
■腎臓リンパ腫の猫の1例:診断、治療、生存期間
[Renal lymphoma in a cat: diagnostics, therapy and survival time. A case
report].
Das renale Lymphom bei der Katze: Diagnostik, Therapieverlauf und Uberlebenszeit. Ein Fallbericht.
Language: German
Tierarztl Prax Ausg K Klientiere Heimtiere. August 2012;40(4):271-7.
S Schmidt; V Nerschbach; N Eberle; R Mischke; I Nolte; D Betz
この症例報告で腎臓リンパ腫の7歳去勢済みオスのヨーロッパショートヘアーの猫についての診断、治療、反応、結果を詳述する。多剤併用化学療法を使用し、導入後8日目に部分寛解、72日目に完全寛解に達した。化学療法中に猫の状態は良好だった。副反応は、嘔吐と短期間のわずかな意気消沈の2つの事象しか見られなかった。化学療法終了後629日目、1449日の寛解が続いたのち、腎臓リンパ腫の再発が診断された。
2度目の化学療法中、CNSへのリンパ腫の拡大が明らかになり、1509日(4歳)の生存期間後に安楽死となった。適切な多剤併用化学療法による猫の腎臓リンパ腫の治療は、良好な生活を維持しながら長期生存を達成できることをこの症例は示す。(Sato訳)
■大腸菌L-アスパラギナーゼで治療したリンパ系腫瘍の犬の循環抗アスパラギナーゼ抗体を検出するためのELISAの開発
Development of an ELISA to detect circulating anti-asparaginase antibodies in dogs with lymphoid neoplasia treated with Escherichia coli l-asparaginase(*)
Vet Comp Oncol. 2012 Dec 18. doi: 10.1111/vco.12014.
Kidd JA, Ross P, Buntzman AS, Hess PR.
犬のリンパ腫における大腸菌L-アスパラギナーゼに対する抵抗性は、頻繁に繰り返して投与することで起こり、実証はないがその現象は中和する抗体の誘導によることが多い。
投与犬はその薬剤に対する抗体を作り出すという仮説を検証するため、著者らは血漿抗アスパラギナーゼ免疫グロブリンG応答を測定するELISAを作成した。
複数の回数投与されている犬のサンプルを用い、L-アスパラギナーゼに対する特定の反応性を証明したが、未処置の犬のサンプルは陰性だった。最適化されたELISAは感受性があると思われ、陽性コントロール犬でエンドポイント価は>1600000だった。測定法内および測定法間の変動係数は3.6および14.5%だった。その測定は、ELISA陽性血漿がアスパラギナーゼ活性を免疫沈降できたという知見により支持された。
臨床的患者を評価した時、10頭中3頭は1回の投与後に力価が発生した;反復投与で7頭中4頭が陽性だった。L-アスパラギナーゼ抗体はPEG化製剤の結合低下を示した。ELISAは抵抗性を持つ抗体反応の潜在的関連を調べるのに有効である。(Sato訳)
■猫の腎リンパ腫:診断、治療そして生存期間、症例報告
[Renal lymphoma in a cat: diagnostics, therapy and survival time. A case report].
Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 2012;40(4):271-7.
Schmidt S, Nerschbach V, Eberle N, Mischke R, Nolte I, Betz D.
腎リンパ腫にり患した7歳の去勢雄のヨーロピアンショートヘアにおける診断、治療そして反応と結果について症例報告する。併用化学療法の使用によって、導入後8日で部分寛解に、72日後に完全寛解へ達した。化学療法中、猫は良好な生活の質を維持できた。副作用は、嘔吐と1度の短時間のわずかな虚脱という2つのエピソードに限られた。化学療法終了後629日、寛解中の1449日目に、腎リンパ腫の再発が診断された。2回目の化学療法の中で、中枢神経系へリンパ腫が拡大し、猫は全生存率1509日(4年間)後に安楽死した。適切な併用化学療法によって腎リンパ腫の治療が、よい生活の質を維持しながら長い生存期間に達することができるとこの症例は示している。(Dr.Kawano訳)
■猫の消化管リンパ腫:粘膜構造、免疫表現型、分子クローン性
Feline gastrointestinal lymphoma: mucosal architecture, immunophenotype,
and molecular clonality.
Vet Pathol. July 2012;49(4):658-68.
P F Moore; A Rodriguez-Bertos; P H Kass
1995年から2006年の間に120頭の猫で消化管リンパ腫を確認した。WHOのシェーマに従いリンパ腫を分類した。
粘膜T細胞リンパ腫の猫(n=84)が多く、生存期間中央値は29か月だった。粘膜T細胞リンパ腫はWHOの腸症型T細胞リンパ腫(EATCL)タイプIIに一致した。T細胞浸潤は62%の猫に見られ、絨毛および/あるいは陰窩上皮において小型から中型T細胞のクラスターあるいはびまん性浸潤を起こした。同様のリンパ球は特徴的なパターンで固有層に浸潤した。
経壁性T細胞リンパ腫の猫(n=19)は生存期間中央値が1.5ヶ月だった。経壁性T細胞リンパ腫はWHOのEATCLタイプIに一致した。上皮向性T細胞浸潤は58%の猫に見られた。大リンパ球(n=11)、ほとんど細胞質顆粒(LGL-グランザイムB+)(n=9)が多かった。病変の特徴は固有筋層を通過する経壁の拡がりだった。
粘膜および経壁T細胞リンパ腫共に大部分は小腸に限られ、分子クローン性分析で90%の猫にT細胞レセプターγのクローン性あるいは少クローン性再構築を認めた。
B細胞リンパ腫の猫(n=19)の生存期間中央値は3.5ヶ月だった。B細胞リンパ腫は胃、空腸、空腸-盲腸-大腸移行部の経壁病変として発生していた。多くはびまん性の中心芽細胞型大B細胞リンパ腫だった。
結論として猫の消化管において、特有の粘膜構造、CD3発現、クローン増殖を特徴としたT細胞リンパ腫が優勢を占めた。(Sato訳)
■胆嚢を巻き込んだ消化管小細胞型リンパ腫の猫の1例
Gastrointestinal small-cell lymphoma with gall bladder involvement in a
cat.
J Feline Med Surg. April 2012;14(4):267-71.
Katie J Baxter; Richard C Hill; Shannon L Parfitt; Clifford R Berry; Travis W Heskett; Barbara J Sheppard
13歳メスの避妊済み家猫短毛種が、血清肝酵素濃度上昇と食欲低下を主訴に来院した。腹部超音波検査で胆嚢の管腔面に沿って複数の固着性高エコー構造と、高エコーの結節のある軽度に拡大した肝臓を認めた。開腹して胆嚢摘出を実施し、バイオプシーを行った。
免疫組織化学と病理組織検査で胆嚢、肝臓、小腸内のTリンパ球小細胞型リンパ腫と診断された。クローナリティー検査で診断を確認した。その猫はプレドニゾロン、クロラムブシル、ウルソデオキシコール酸の治療で23か月臨床的安定を維持している。これは1頭の猫に見られた胆嚢の小細胞型リンパ腫の最初の報告である。(Sato訳)
■猫の低悪性度消化器型リンパ腫:どの程度一般的なのか?
Feline low-grade alimentary lymphoma: how common is it?
J Feline Med Surg. 2012 Jul 18.
Russell KJ, Beatty JA, Dhand N, Gunew M, Lingard AE, Baral RM, Barrs VR.
中悪性度(IGAL)および高悪性度(HGAL)の消化器型リンパ腫(AL)は、消化管または腸間膜リンパ節の吸引の細胞診によって診断できるのに対して、低悪性度の消化器型リンパ腫(LGAL)の診断には、生検による病理組織学的な評価が必要である。細胞診で診断されたIGALやHGALの症例に生検を行なわないため、組織学のみを用いてALのサブタイプの相対頻度を評価すると、LGALの頻度は多いということになるかもしれない。
5年間にわたってオーストラリアで最初に来院した症例において、病理組織学および細胞診によって診断されたALのサブタイプの相対的な頻度について検討した。
LGALの臨床病理学的な特徴を、IGAL/HGALのそれらと比較した。53例のALのうち、30例(15LGAL、13HGAL、2IGAL)は組織学的に診断され、23例のIGAL/HGALは細胞診によって診断された。LGALの症例は、組織学的な診断の50%からなっていたが、全ALの28%にしかならなかった。触診可能な腹腔の腫瘤は、LGAL (7%)よりもIGAL/HGAL (43%)においてより一般的であった(オッズ比 7.6、P=0.01)。貧血は、LGAL (7%)と比較して、IGAL/HGAL (41%)においてより一般的であった(オッズ比 9.6, P=0.02)。腹部の超音波検査において、IGAL/HGALの41%において消化器の壁在性腫瘤が認められたのに対し、LGALにおいては全く認められなかった(P=0.01)。詳細な消化器の超音波検査所見の情報が得られたものでは、胃腸壁の肥厚が最も一般的な異常であった(82%)。LGALの猫(20%)よりも、IGAL/HGALの猫(71%)において、腸の肥厚が認められた猫において、正常な層構造の消失がより一般的であった(P=0.02)。
本研究集団において、組織学的診断を行なった症例に加えて、細胞診によって診断された症例を含めたときには、LGALの頻度はより少なかった。最初の報告以来、LGALと診断される相対頻度は増加している。LGAGLとIGAL/HGALを鑑別するのに、多くの有意な臨床病理学的な所見が有用である。(Dr.Taku訳)
■犬の多中心型リンパ腫の治療に対する15週間のCHOP療法の評価
Evaluation of a 15-week CHOP protocol for the treatment of canine multicentric lymphoma.
Vet Comp Oncol. 2012 May 2.
Burton JH, Garrett-Mayer E, Thamm DH.
用量強化CHOP療法は、非ホジキンリンパ腫の人の予後を改善することが示されているが、犬のリンパ腫に対する用量強化CHOP療法の評価は現在のところ限られている。
この後向き研究においては、15週間の用量強化CHOP療法は、他のドキソルビシンを含んだ多剤併用療法と同様の効果でより短い治療となりうる、という仮説をたてた。
多中心型リンパ腫の31頭の飼い犬を15週間のCHOP療法で治療したところ、全奏功率は、100%であり、無病期間(PFI)の中央値は140日であった(95%信頼区間は91-335日)。2回以上治療を送らせた犬は、多変量解析によると有意に長いPFIと全生存率を示した。
用量強化は、予後とは関連しなかった。副作用がない犬は用量が足りていないのかもしれない一方、副作用のために複数回遅延した犬は、それぞれの最大の投与量を受けられたのかもしれない。個々の患者の用量の最適化に焦点を絞った研究を将来的に行う必要がある。(Dr.Taku訳)
■猫の皮膚上皮向性T-細胞リンパ腫:文献と新しい5症例のレビュー
Cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma in the cat: a review of the literature
and five new cases.
Vet Dermatol. October 2011;22(5):454-61.
Jacques Fontaine; Marianne Heimann; Michael J Day
皮膚上皮向性T細胞リンパ腫(CETL)は、表皮と付属上皮に特別な向性を持つ腫瘍性Tリンパ球の皮膚浸潤を特徴とする。
猫でこの疾患の報告は非常に珍しい。Vetdermlistを通し獣医皮膚専門医の非公式の議論から臨床的データを収集した。同時にヨーロッパ診断的病理組織検査所2か所(Institut de Pathologie et Genetique/Bio.be Gosselies, Belgium and the School of Veterinary Sciences, University of Bristol, UK)の症例アーカイブを再調査した。良好な臨床的記述のある15症例を選択し、皮膚バイオプシー5セットを再調査のため入手した。
皮膚上皮向性T細胞リンパ腫は一般的に老猫にみられ、性別あるいは品種の偏りは明白ではない。孤立あるいは複数病変は特定位置に出るという傾向はないと報告された。病変は、紅斑性プラークあるいはパッチ、鱗屑脱毛性パッチおよび治癒しない潰瘍あるいは結節で、時々、好酸球性プラークに似る。痒みはまれで、口腔粘膜の病変は観察されなかった。犬よりも猫のCETLの臨床診断はより難しい。最終診断は皮膚バイオプシーサンプルの病理組織検査を基にするべきである。
猫CETLの特徴的病変は犬で報告されるものと同様であるが、付属腺の関与はこのシリーズで観察されなかった(n=5)。腫瘍性T細胞は一般的に小型から中型だった。CETLの猫の生存期間は、犬よりもより不定だと思われる。治療に関して明確な推奨方法を示すには、評価する症例が少なすぎる。(Sato訳)
■サブステージ-aハイグレード多中心型リンパ腫の犬に対する診断的評価と推奨される治療:獣医師の調査結果
Diagnostic evaluation and treatment recommendations for dogs with substage-a
high-grade multicentric lymphoma: results of a survey of veterinarians
Veterinary and Comparative Oncology, Article first published online: 2 MAR 2012
R. C. Regan, M. S. W. Kaplan, D. B. Bailey
この研究の目的は、サブステージ-a ハイグレード多中心型リンパ腫の犬に対し、現行の最初に推奨される診断および治療に関して獣医師に調査することだった。
調査は2009年Veterinary Cancer Society conferenceで行われ、犬のリンパ腫に対して提供するデモグラフィック情報、最初のステージング診断方法、勧める治療を訪ねた。
最も一般的な推奨されるステージング診断方法は、CBC(100%)、生化学検査(100%)、尿検査(85%)、リンパ節細胞診(88%)、胸部エックス線検査(84%)、免疫表現型の検査(76%)、腹部超音波検査(75%)だった。よく使用される第一線のB-細胞プロトコールは、L-アスパラギナーゼ、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンの組み合わせだった(L-CHOP、51%)。CHOP(30%)および他のCHOPベースのプロトコール(12%)も使用されていた。回答者の31%はB-とT-細胞リンパ腫を違う方法で治療していた。プロトコールの期間は16週以下から2年以上と幅があった。
リンパ腫で現行のステージングおよび勧められる治療はさまざまである。推奨方法を標準化できるように考慮すべきである。(Sato訳)
■猫リンパ腫の治療中に見られる体重変化の予後的意義
Prognostic significance of weight changes during treatment of feline lymphoma.
J Feline Med Surg. December 2011;13(12):976-83.
Erika L Krick; Renee H Moore; Rachel B Cohen; Karin U Sorenmo
この研究の目的は猫のリンパ腫治療中の体重変化の予後的意義を検討することだった。2つ目の目的は、基準となる体重、細胞の種類、部位に従って体重変化を比較することだった。
1995年から2007年の間に化学療法でリンパ腫を治療した209頭の記録を評価した。シグナルメント、細胞の種類、リンパ腫の部位、基準の体重、治療中の体重、転帰の情報を収集した。リンパ腫特異的生存率(LSS)を基準の体重と治療中の体重変化に従い比較した。長期体重変化を細胞の種類(小型、大型)、部位(消化管、非消化管)および基準の体重に従い比較した。
1か月で体重が5%以上落ちた大型細胞リンパ腫の猫は、体重増加あるいは体重が安定している猫よりも有意にLSSが短かった(P=0.004)。長期の体重変化の比率は基準となる体重群により有意な違いが見られた。それらの所見は、猫の大型細胞リンパ腫における体重減少の予後的重要性を示している。(Sato訳)
■犬の緩慢性リンパ腫の臨床的、組織病理学的、免疫組織化学的特徴
Clinical, histopathological and immunohistochemical characterization of canine indolent lymphoma
Veterinary and Comparative Oncology, Article first published online: 2 FEB 2012
K. E. Flood-Knapik, A. C. Durham, T. P. Gregor, M. D. Sanchez, M. E. Durney, K. U. Sorenmo
緩慢性リンパ腫は全ての犬のリンパ腫の29%からなる。しかし、そのサブタイプや生物学的挙動に関して限られた情報しかない。
この回顧的研究は、緩慢性リンパ腫の犬7 5頭の臨床的特質、組織病理学および免疫組織化学的特徴、治療、結果、予後因子について述べる。WHO組織病理学的分類およびCD79a、CD3、Ki67、P-糖蛋白(P-gp)に対する免疫組織化学(IHC)検査を実施した。最も一般的な組織病理学的サブタイプは、T領域、61.7%(MST33.5ヶ月)で、続いて辺縁帯、25%(MST21.2ヶ月)、P=0.542だった。予備的組織病理学的分類に対するIHCの追加で症例の20.4%は診断が見直された。全身療法は生存性に影響しなかった、P=0.065。CHOPベースの化学療法によるMST21.6ヶ月と比べ、クロラムブシルとプレドニゾンで治療した犬はMSTに届かなかった、P=0.057。総MST4.4年はこれが緩慢性疾患だと実際に確認させる。しかし全身療法の影響は、前向き試験を通して判定すべきである。(Sato訳)
■局所に生じた口腔の粘膜皮膚型リンパ腫の犬の治療に用いた放射線療法:14症例
Radiotherapy in the management of localized mucocutaneous oral lymphoma in dogs: 14 cases.
Vet Comp Oncol. 2011 Apr 21.
Berlato D, Schrempp D, Van Den Steen N, Murphy S.
口腔の粘膜皮膚型リンパ腫は犬において稀である。通常は、長期的なコントロールは外科手術でも化学療法でもうまくできない。
この研究の目的は、局所に生じた口腔の粘膜皮膚型リンパ腫の犬を放射線療法で治療した場合の生存を後向きに評価するものである。口腔のリンパ腫と診断され放射線療法を行なった犬を3つの施設の症例データベースで検索した。全身性の疾患があった犬は除外した。生存は、Kaplan-Meier法で計算し、予後変数は、ログランク検定で解析した。
14頭の犬を用いた。生存期間の平均は、1129日(95%信頼区間、711-1546日)で、中央値は770日であった。放射線療法に対する全体の反応率は67%であった(5頭は完全寛解で3頭は部分寛解であった)。リンパ節転移が認められなかった犬(P = 0.002)と放射線療法に完全寛解した犬(P = 0.013)では、延命効果が認められた。放射線療法は耐性が高く、局所的な犬の口腔リンパ腫の効果的な治療であった。(Dr.Taku訳)
■犬リンパ腫のチミジンキナーゼ分析
Thymidine kinase assay in canine lymphoma
Veterinary and Comparative Oncology, Article first published online: 8 DEC 2011
J. W. Elliott, P. Cripps, L. Blackwood
この研究の目的は、リンパ腫の犬における最初の寛解期間(DFR)あるいは生存性にチミジンキナーゼ(TK)が相関するかどうか、および初期TKレベルがステージ、サブステージと相関するかどうかを評価すること、加えて診断時のTKレベルが免疫表現型と相関するかどうかも分析することだった。単純なリンパ腫を治療している73頭の犬でTKを分析し、その後再び治療後に分析した;47%の犬は初期TKが参照範囲よりも高かった。B-細胞リンパ腫の犬の初期TK活性はT-細胞リンパ腫の犬よりも高かった。TKレベルはより高いステージの疾患の犬でより高いというわけではなく、治療前のTK活性はDFRあるいは生存性に関係しなかった。診断時にTKは上昇していても、寛解中に参照範囲に降下した。診断時に53%の犬のTKは正常で、過去の報告よりも高い数字だった。リンパ腫の犬でTKの有用性を調査する追加研究が必要である。(Sato訳)
■T-細胞リンパ腫の1頭の猫に見られた呼吸困難と肺の硬化
Dyspnoea and pulmonary consolidation in a cat with T-cell lymphoma.
J Feline Med Surg. October 2011;13(10):772-5.
Alexa L Brown; Julia A Beatty; Robert G Nicoll; Tina Knight; Mark B Krockenberger; Vanessa R Barrs
13歳の去勢済みオスの家猫短毛種が急性の呼吸困難を呈した。胸部エックス線写真で顕著な両側尾側肺葉の硬化を認めた。病理組織検査で肺、腎臓、消化管関与の解剖学的に混合T-細胞リンパ腫の診断が確認された。
猫リンパ腫の症例で肺の関与は珍しく、肺リンパ腫のエックス線所見は非常に不定である。猫の原発性肺腫瘍で肺葉効果は延べられているが、過去に肺のリンパ腫の関与はなかった。この珍しい症状は、猫の重度気管支肺疾患の原因としてリンパ腫の可能性があることを臨床医に警告するものである。(Sato訳)
■ハイグレード多中心型リンパ腫の犬における長期生存の予測因子
Predictors of long-term survival in dogs with high-grade multicentric lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. 2011 Feb 15;238(4):480-5.
Marconato L, Stefanello D, Valenti P, Bonfanti U, Comazzi S, Roccabianca P, Caniatti M, Romanelli G, Massari F, Zini E.
目的:ハイグレード多中心型リンパ腫の犬の生存を予測する因子を決定する
研究手法:後向きコホート研究
動物:2000年から2009年の間に4つの動物病院で評価された127頭のハイグレード多中心型リンパ腫の犬
方法:化学療法で治療しており、完全に病期分類可能であったハイグレード多中心型リンパ腫の犬を同定するために、カルテを調査した。収集したデータは、シグナルメント、病歴、血液学的所見、腫瘍の特徴、治療、転帰だった。診断後2年以上生存した場合を長期生存と定義した。2年以上生きた犬との関連について変数を解析した。
結果:用いた127頭の犬の中で、13頭 (10%) が2年以上生存し、生存期間の中央値は914日であった(範囲は740-2058日)。3年、4年、5年生存率は、4%、3%、1%であった。長期生存した13頭の犬の中で11頭が、診断時に、体重10kg以上、PCV35%以上、イオン化カルシウムが高値ではない、胚中心芽細胞性リンパ腫であり、免疫表現型がB細胞型
、骨髄への浸潤がない、リンパ腫のステージがIからIV、あらかじめコルチコイドで治療されていない、という条件を示した。2年以上生きられなかった114頭の犬のうち26頭(23%)において同じ条件の組み合わせが認められ、長期生存の陰性的中率は97.8%であった。長期生存犬の6頭のうち4頭は研究期間中に他の癌でなくなり、そのうちの3頭は骨肉腫であった。
結果と臨床的な関連:診断時に前述した変数の組み合わせがないということは、リンパ腫の犬が2年以上生存できないことを予測するのに役に立つであろう。他の種類の腫瘍、とくに骨肉腫は、長期的に生存したイヌにおいて生じることがある。(Dr.Taku訳)
■犬における高グレード多中心型リンパ腫のステージングと治療:最近の発達と未来の見込み
The staging and treatment of multicentric high-grade lymphoma in dogs: a review of recent developments and future prospects.
Vet J. April 2011;188(1):34-8.
Laura Marconato
近年、犬のリンパ腫の生物学の理解でかなりの進歩があり、結果的に個別に考えられた治療や分類シェーマの質が増強されている。しかし、多剤併用化学療法で完全緩解にいたるが、この腫瘍の死亡率は高いままである。このレビューは、犬の高グレード多中心型リンパ腫のステージング、従来のおよび新しい治療戦略(化学療法、骨髄移植、放射線療法、分子標的物質など)、再発あるいは難治性症例の管理に焦点を当てている。(Sato訳)
■犬の再燃性リンパ腫の治療でフロリダ大学ロムスチン、ビンクリスチン、プロカルバジンおよびプレドニゾン化学療法プロトコールの評価
Evaluation of the University of Florida lomustine, vincristine, procarbazine, and prednisone chemotherapy protocol for the treatment of relapsed lymphoma in dogs: 33 cases (2003-2009).
J Am Vet Med Assoc. July 2011;239(2):209-15.
Christine E Fahey; Rowan J Milner; Karri Barabas; David Lurie; Kelvin Kow; Shannon Parfitt; Sarah Lyles; Monica Clemente
目的:犬の難治性リンパ腫のレスキュープロトコールとして、過去に評価されたロムスチン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン(LOPP)のコンビネーションの修正法の毒性および効果を評価すること
構成:回顧的症例シリーズ
動物:細胞学的あるいは組織学的にリンパ腫と診断され、導入化学療法プロトコールに耐性を示した犬33頭
方法:ロムスチンはプロトコールの0日目に投与した。ビンクリスチンは0日目と14日目に投与した。プロカルバジンとプレドニゾンは0-13日目を通して投与した。このサイクルを28日毎に繰り返した。
結果:フロリダ大学LOPPプロトコールの開始から中止までの期間中央値は84日(範囲10-308日)だった。総生存期間中央値は290日(範囲51-762日)だった。このプロトコールの全体の反応率は61%(20/33)で、36%(12)は完全反応、24%(8)は部分反応だった。中毒率は過去に発表されたLOPPプロトコールよりも低かった。
結論と臨床関連:フロリダ大学LOPPプロトコールは、リンパ腫の犬のレスキュープロトコールとして、メクロレタミン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾンプロトコールに代わって使用できると思われる。(Sato訳)
■犬と猫の消化管リンパ腫
Alimentary lymphoma in cats and dogs.
Vet Clin North Am Small Anim Pract. March 2011;41(2):419-32.
Tracy Gieger
消化管(GI)に関係する病気の急性症状あるいは長期病歴を持つ動物において、消化管リンパ腫を疑うべきである。併発疾患を確認するのに全身の病期検査(CBC/化学/尿/チロキシン濃度/胸部エックス線写真)を用いる。腹部超音波検査は腸壁の肥厚、マス病変、併発臓器関与、リンパ節腫脹、腹部リンパ節腫脹を実証するのに有効である。超音波所見は、診断組織学的標本を得ることを目的とする開腹、腹腔鏡、あるいは内視鏡などの次の検査をすべきか決定するのに使用できる。組織病理学的に、リンパ腫はリンパ芽球あるいはリンパ球性と思われる。ステロイドおよび栄養サポートを含む化学療法は、消化管リンパ腫の管理で必須である。(Sato訳)
■多中心型T-細胞リンパ腫のCHOP化学療法による治療
CHOP chemotherapy for the treatment of canine multicentric T-cell lymphoma.
Vet Comp Oncol. March 2011;9(1):38-44.
R B Rebhun; M S Kent; S A E B Borrofka; S Frazier; K Skorupski; C O Rodriguez
多中心型T-細胞リンパ腫の犬は、シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンのCHOP化学療法プロトコールで一般的に治療される。
この研究の目的は、多中心型T-細胞リンパ腫の犬に対するCHOP化学療法の使用を評価することだった。この特定の部分集合の犬における予後因子の確認は第2の関心事だった。24頭中23頭はSHOP化学療法に反応し、それらの犬は中央値146日の間プロトコールを継続した。ステージ、サブステージ、高カルシウム血症あるいは縦隔頭側マスのエックス線所見を含む無進行生存性(PFS)に関係する変数はなかった。全ての犬の総生存期間(OST)中央値は235日だった。来院時に血小板減少症だった犬は、有意に長いOSTを示した(323日v.s.212日、P=0.01)。(Sato訳)
■犬の第三眼瞼結膜の粘膜関連リンパ組織リンパ腫の1例
Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the third eyelid conjunctiva in a dog.
Vet Ophthalmol. January 2011;14(1):61-5.
Il-Hwa Hong; Sun-Hee Bae; Sang-Gwan Lee; Jin-Kyu Park; Ae-Ri Ji; Mi-Ran Ki; Seon-Young Han; Eun-Mi Lee; Ah-Young Kim; Sang-Young You; Tae-Hwan Kim; Kyu-Shik Jeong
4歳の避妊済みメスのコッカースパニエルが、左第三眼瞼の突出で来院した。両眼の第三眼瞼を反転すると、球表面に小葉に別れたマスが存在した。左第三眼瞼はより大きく突出していた。眼球あるいは全身性関与と明らかな関連はなかった。左第三眼瞼の腫瘍を切除し、組織検査を行った。組織学的に辺縁帯を形成するリンパ系細胞に囲まれたリンパ濾胞の過形成があった。それらのリンパ系細胞は所々で結膜上皮内に浸潤していた。濃縮および崩壊性の核を伴ういくつかのアポトーシス体がリンパ濾胞の胚中心に観察された。有糸分裂像はまれに見られた。免疫組織化学的に、腫瘍細胞はCD79aを発現したが、CD3はなかった。第三眼瞼の粘膜関連リンパ組織(MALT)の結節外辺縁帯B細胞リンパ腫の診断が、組織学および免疫表現型的特徴をもとになされた。
1年の経過観察で、左第三眼瞼の切除部分にマスの再発所見は見られず、右第三眼瞼の残存腫瘍の大きさに変化はなかった。その犬にはそれらの腫瘍をのぞき明らかな所見はなく、全身性関与の所見もなかった。著者の知るところでは、これが1頭の犬に見られた第三眼瞼のMALTリンパ腫の最初の報告である。(Sato訳)
■犬のリンパ腫に対するL-CHOPとCCNUおよびMOPPを組み込んだL-CHOPプロトコール(L-CHOP-CCNU-MOPP)の比較
Comparison between L-CHOP and an L-CHOP protocol with interposed treatments of CCNU and MOPP (L-CHOP-CCNU-MOPP) for lymphoma in dogs.
Vet Comp Oncol. December 2010;8(4):243-53.
K M Rassnick; D B Bailey; E K Malone; J L Intile; M A Kiselow; A B Flory; L L Barlow; C E Balkman; S M Barnard; A H Waite
CCNUとMOPPを組み込んだL-CHOPプロトコール(L-CHOP-CCNU-MOPP)をステージIII-Vリンパ腫の犬66頭で評価した。結果は過去のL-CHOPプロトコールで治療した71頭のグループと比較した。完全寛解(CR)率(それぞれ85および80%)は、プロトコール間で有意差がなかった(P=0.48)。L-CHOP-CCNU-MOPPで治療した犬の最初のCR持続期間は有意に長かった:中央値317日;2-年CR率35% v.s. 中央値298日;2-年CR率13%、P=0.05)。L-CHOP-CCNU-MOPPプロトコールで、サブステージ-bの犬は、サブステージ-aの犬よりも再燃する危険が4.3倍高かった(P=0.002)。化学療法の副作用に関係する消化管への影響の頻度は、プロトコール間で違いはなかった(P=0.77)。L-CHOP-CCNU-MOPPで治療した犬において好中球減少症(主としてCCNU後)がより頻繁に発生した(P<0.001)。
つまり、L-CHOPプロトコールと比較すると、L-CHOP-CCNU-MOPPプロトコールのほうが最初のCR持続期間の延長を示したが、この所見の妥当性は、臨床判断を条件としているかもしれない。(Sato訳)
■1頭のミニチュアダックスフントに見られた原発性骨格筋リンパ腫の長期生存性
Long term survival of primary skeletal muscle lymphoma in a miniature dachshund.
J Vet Med Sci. May 2010;72(5):673-7.
Yoshinori Takeuchi; Yasuhito Fujino; Yuko Goto-Koshino; Koichi Ohno; Kazuyuki Uchida; Hiroyuki Nakayama; Hajime Tsujimoto
8歳のミニチュアダックスフントが、右の大腿部筋肉のマスと食欲不振を呈した。マスの細胞診で、多形の濃い核と狭い薄青の細胞質を持つ多数の小型リンパ系細胞を認めた。組織病理検査で腫瘍性リンパ系細胞が骨格筋で増殖し、筋肉構造と置き換わっていることが分かった。免疫組織化学および遺伝子検査で、多形小細胞型T-細胞lowグレードと分類される原発性骨格筋リンパ腫の確定診断がなされた。多剤化学療法で少なくとも3回の再燃が見られたが、初診から713日生存した。(Sato訳)
■犬リンパ腫における用量増強、メンテナンスフリーCHOPベース化学療法プロトコールに関係する結果と毒性
Outcome and toxicity associated with a dose-intensified, maintenance-free CHOP-based chemotherapy protocol in canine lymphoma: 130 cases
Veterinary and Comparative Oncology, Volume 8, Issue 3, pages 196-208,
September 2010
K. Sorenmo, B. Overley , E. Krick, T. Ferrara, A. LaBlanc, F. Shofer
ペンシルバニア大学動物病院で犬リンパ腫に対する用量増強/用量高濃度化学療法プロトコールを計画し、実行した。この研究で、我々はこのプロトコールで治療した130頭の犬の臨床特性、予後因子、効果、毒性を述べる。大半の犬はステージ疾患(63.1%ステージV)、サブステージb(58.5%)が進行していた。進行までの時間中央値(TTP)およびリンパ腫特異生存期間はそれぞれ219日と323日だった。それらの結果は、過去のより少ない用量増強プロトコールと同様である。サブステージは生存に対する有意な負の予後因子だった。毒性の発生率は高く、53.9%の犬が減量を必要とし、45%の犬が治療を延期した。減量および延期を必要とした犬は、有意に長いTTPおよびリンパ腫特異生存期間を示した。それらの結果は、用量増強は重要だが最適な結果に対し個々の患者の毒性に従い調整する必要があることを示唆する。(Sato訳)
■犬リンパ腫のドキソルビシンおよびシクロフォスファミドによる治療:無作為プラセボ対照試験
Doxorubicin and cyclophosphamide for the treatment of canine lymphoma: a randomized, placebo-controlled study
Veterinary and Comparative Oncology Volume 8, Issue 3, pages 188-195, September
2010
J. C. Lori, T. J. Stein, D. H. Thamm
ドキソルビシンで治療した犬リンパ腫の生存期間(STs)中央値は5.7-9ヶ月である。多剤プロトコールで治療した犬はより長いSTsを示すため、我々はリンパ腫の犬でシクロフォスファミドの追加が容認できる毒性で維持しながら、結果を改善させるかどうかを評価した。
ステージIII-Vの多中心型リンパ腫の犬32頭を3週間毎の5回のドキソルビシン投与と最初の4週間のプレゾニゾン漸減投与で治療した。同時に無作為にシクロフォスファミドあるいはプラセボを投与した。17頭の犬にドキソルビシンとプラセボ、15頭の犬にドキソルビシンとシクロフォスファミドを投与した。反応、毒性、進行フリー期間(PFI)およびSTを評価した。
ドキソルビシンとシクロフォスファミドの組み合わせはよく許容し、ドキソルビシン単独以上に副作用を起こすことはなかった。シクロフォスファミド投与犬で結果に数的改善が見られたにもかかわらず、シクロフォスファミドの追加は反応率、PFI、STに統計学的改善を示さなかった。(Sato訳)
■リンパ腫の犬において再発を予測する乳酸脱水素酵素活性の連続測定の臨床関連
Clinical relevance of serial determinations of lactate dehydrogenase activity used to predict recurrence in dogs with lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. May 2010;236(9):969-74.
Laura Marconato, Giampaolo Crispino, Riccardo Finotello, Silvia Mazzotti, Eric Zini
目的:リンパ腫の犬における血清乳酸脱水素酵素(LDH)活性の連続測定が、転帰を予測および疾患進行の早期認識を補助するのに使用できるかどうかを評価する
構成:前向きコホート研究
動物:リンパ腫の犬50頭
方法:新規にリンパ腫と診断された犬、あるいは治療されていないリンパ腫の犬のLDH活性を測定した。LDH活性は初回診断時、化学療法完了時、化学療法から1、3、6ヶ月後に測定した。治療反応と再発を記録した。化学療法の終了時、および各タイムポイントで、LDH活性上昇を伴う完全寛解の犬の比率を連続45日あるいは90日以内に再発した犬と再発しなかった犬で比較した。無病期間および生存期間を予測するため入院時のLDH活性の使用を評価した。
結果:化学療法完了時、化学療法から1ヵ月後、連続45日の間に再発したLDH活性上昇を伴う完全寛解の犬の比率(それぞれ3/9、7/9)は、再発がない犬の比率(それぞれ0/32、1/26)よりも有意に高かった。3あるいは6ヶ月時、45日以内に再発しなかった1頭だけ、LDH活性が上昇していた。診断時のLDH活性上昇は無病期間および生存期間に関与しなかった。
結論と臨床関連:LDH活性の測定は、リンパ腫の犬の再発を確認するのに役立つと思われる。再発の予測はレスキュー療法開始の適切な理由となる。(Sato訳)
■犬の皮膚上皮親和性T-細胞リンパ腫:30症例の概説
Canine cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma: a review of 30 cases
Jacques Fontaine, Marianne Heimann and Michael J. Day
この回顧的研究では、犬皮膚上皮親和性T-細胞リンパ腫(CETL)のヨーロッパでの30症例に見られた臨床的、組織学的そして免疫組織化学的兆候を概説した。臨床症状はかなり様々で、亜型との関連性はなかった。鱗屑(60%)を伴うび慢性紅斑(86.6%)と局所的な色素脱失(50%)が最も一般的な病変であった。皮膚は一律に影響をうけていたが、皮膚粘膜接合部あるいは粘膜が症例の50%で影響を受けていた。診断した時点での年齢中央値は10歳
(標準偏差 2.79, 範囲 4?15)で、発現と最終診断の期間中央値は5ヶ月(標準偏差
3.79, 範囲 0-12)だった。5症例はビションフリーゼだった。どの症例においても慢性皮膚炎の既往歴はなかった。
組織学的に、症例の86.7%で濾胞上皮は影響を受けていた。主に濾胞性疾患を伴った1例は向濾胞性菌状息肉腫(MF)と考えられたが、濾胞性ムチン沈着症は観察されなかった。表皮性ポトリエ微小膿瘍は一般的ではなかった(23.3%)。汗腺は症例の70%で浸潤していた。免疫組織化学的検査では、すべての症例でT細胞腫瘍が確定できた。腫瘍基部ではB細胞が各細胞として浸潤したか、あるいは直線的なバンドを形成したか、異所性濾胞を形成した。Ki67 標識は、増殖の指標の範囲を明らかにしたが、重症度とは関連がなかった。標準的な菌状息肉腫(MF)の確定診断は犬の40%、MF d'embleは36.7%、全身性パジェット様細網症が20%、局所性パジェット様細網症が1症例(ウォランジェ・コロップ・パジェット様細網症)でなされた。診断後の生存期間中央値は6ヵ月で、これは治療(ロムスチンあるいはプレドニゾロン)であまり変化しなかった。(Dr.Kawano訳)
■リンパ腫の犬における低コバラミン血症の有病率と予後とのかかわり
Prevalence and prognostic impact of hypocobalaminemia in dogs with lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. December 2009;235(12):1437-41.
Audrey K Cook, Zachary M Wright, Jan S Suchodolski, M Raquel Brown, Jorg M Steiner
目的:多中心型リンパ腫の犬における低コバラミン血症の有病率を判定し、血清コバラミン濃度と疾患の転帰の関連性を調査すること
構成:コホート研究
動物:多中心型リンパ腫の犬58頭
方法:多中心型リンパ腫の犬58頭の血清コバラミン濃度を測定した。低コバラミン血症の犬の臨床症状、ステージ、免疫表現型を、血清コバラミン濃度が基準値下限以上の犬のそれらと比較した。同様に周期的他剤併用化学療法プロトコールを実施した犬(n=53)の生存期間も比較した。60日前に死亡あるいは安楽死された治療犬の血清コバラミン濃度は、60日目に生存している犬のそれらと比較した。
結果:血清コバラミン濃度の範囲は<150-1813ng/lで、濃度の中央値は401ng/lだった。58頭中9頭(16%)が低コバラミン血症だった(血清コバラミン濃度<252ng/l)。低コバラミン血症の犬9頭中3頭は、少なくとも60日間生存し、比較として低コバラミン血症ではない(血清コバラミン濃度252ng/l以上)犬44頭中40頭(91%)は60日間生存した。周期的他剤併用化学療法プロトコールを実施した10頭の犬(10/53[19%])は60日までに死亡し、それらの犬の血清コバラミン濃度中央値(232ng/l)は、研究終了時まで生存した犬の濃度(556ng/l)よりも有意に低かった。
結論と臨床関連:この多中心型リンパ腫の犬の集団で低コバラミン血症は比較的少なかったが、予後不良に関係した。血清コバラミン濃度は多中心型リンパ腫の犬の予後に関する情報を提供するものかもしれない。(Sato訳)
■大豆由来イソフラボンが犬のリンパ球系細胞の成長を抑制する。
Soy-derived isoflavones inhibit the growth of canine lymphoid cell lines.
Clin Cancer Res. 2009 Feb 15;15(4):1269-76.
Jamadar-Shroff V, Papich MG, Suter SE.
目的:この研究は2つの犬のB細胞性リンパ球に対して、純粋なゲニステインと市販で利用可能なポリサッカライド含有ゲニステイン(GCP)と呼ばれるゲニステインの両方で、試験管内でのゲニステインの効果を評価し、正常犬に与えたときのGCPの経口生物学的利用率を決定することだった。
実験設計:ゲニステインとGCPの試験管内での効果は、細胞増殖分析とアポトーシス分析を使って評価した。両方の物質のIC50は、3-(4,5-ジメチル-2-チアゾリル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド (MTT)細胞増殖分析とヨウ化プロピジウム染色を使って決定した。アポトーシスはアネキシンV 染色、カスパーゼ3染色とカスパーゼ9染色そしてDNA ladderingを使って評価した。細胞周期解析とBcl-2/Bax比も検査した。段階的に増加させる薬物動態学的研究の初期投与量は、健常犬においてGCPの経口投与量でゲニステインが治療的血清濃度に達するかどうかを決定するために使用された。
結果:GL-1そして17-71細胞に対するゲニステインとGCPの72時間後の試験管内IC50はそれぞれ10
microg/mLと20 microg/mLだった。GCPは両方の細胞系をアポトーシスによって細胞死へと導き、処置した細胞は増加したBax:Bcl-2比を抑制した。増加させたGCP経口投与量を与えた健常犬におけるゲニステインの血清濃度は、用量段階的増大研究において72時間に試験管内IC50に達しなかった。
結論:これらの研究結果は、化学予防的にGCPの有用性を検討するため、犬のhigh-grade
B-細胞性リンパ腫が人の非ホジキンリンパ腫の大きな動物モデルと関連があることを意味するかもしれないという概念そして/あるいは犬のhigh-grade
B-細胞性リンパ腫が人の臨床的なリンパ腫試験への先導として役立つかもしれない治療戦略を支持します。(Dr.Kawano訳)
■猫の結節外リンパ腫:110頭の猫の化学療法に対する反応と生存性
Feline extranodal lymphoma: response to chemotherapy and survival in 110 cats.
J Small Anim Pract. November 2009;50(11):584-92.
S S Taylor, M R Goodfellow, W J Browne, B Walding , S Murphy, S Tzannes, M Gerou-Ferriani, A Schwartz, J M Dobson
目的:イギリスの猫結節外リンパ腫の治療に対する反応、生存性、予後因子を決定する
方法:7箇所の紹介センターで結節外のリンパ腫を診断した猫の記録を再調査し、徴候、腫瘍部位、以前の治療と化学療法プロトコールの情報を記録した。治療に対する反応と生存性に影響する因子を評価した。
結果:149症例が含有基準に合致した。69頭は鼻部リンパ腫、35頭は腎臓、15頭は中枢神経系、11頭は喉頭、19頭は種々の部位だった。66頭の猫はシクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロンの投与を受け、25頭はウィスコンシン-マジソン加ドキソルビシン他剤併用プロトコール、10頭はプレドニゾロン単独、9頭は他の組み合わせだった。治療した110頭の猫の反応率は85.5%だった。シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロンで治療した猫の72.7%は完全寛解に達し、生存期間中央値は239日だった。ウィスコンシン-マジソンプロトコールで治療した猫の64%は完全寛解に達し、生存期間中央値は563日だった。完全寛解に到った鼻部リンパ腫の猫は生存期間が最も長く(749日)、中枢神経系リンパ腫の猫は最も短かった(70日)。完全寛解が達成された場合、治療開始前のコルチコステロイド投与が有意に生存期間を短くした。
臨床意義:結節外リンパ腫の猫は化学療法に反応し、他の部位に匹敵する生存期間を達成する。治療前のコルチコステロイド投与は、完全緩解を達成した猫の生存期間を短縮した。(Sato訳)
■低グレード消化管型リンパ腫:17症例における臨床病理所見および治療に対する反応
Low-grade alimentary lymphoma: clinicopathological findings and response to treatment in 17 cases.
J Feline Med Surg. August 2009;11(8):692-700.
Amy E Lingard, Katherine Briscoe, Julia A Beatty, Antony S Moore, Ann M Crowley, Mark Krockenberger, Richard K Churcher, Paul J Canfield , Vanessa R Barrs
試験開腹中に採取した17頭の猫の胃腸管の複数部位の全層バイオプシーの組織および免疫組織化学的評価から、低グレード消化管型リンパ腫(LGAL)と診断した。
よく見られた臨床症状は、体重減少(n=17)、嘔吐および/または下痢(n=15)だった。11頭の臨床症状は慢性的だった。12頭の腹部触診は異常で、瀰漫性の腸管肥厚(n=8)、腸間膜リンパ節腫脹による異常なマス(n=5)、局所壁在腸管マス(n=1)などが認められた。よく見られた超音波所見は、正常あるいは層構造を保持したまま腸管壁厚の増加だった。腸間膜リンパ節の超音波ガイド下針吸引生検(n=9)は、バイオプシーの組織学的診断がリンパ腫の8頭の猫で良性リンパ過形成と誤診した。
16/17頭の猫において胃腸管の1つ以上の解剖学的部位に腫瘍浸潤があった。空腸(15/15頭)、回腸(13/14頭)、続いて十二指腸(10/12頭)が好発部位だった。12頭の猫は経口プレドニゾロンおよび高用量クロラムブシルパルス療法で治療し、2頭はマジソン-ウィスコンシン多剤プロトコール変法、3頭は両方のプロトコールを組み合わせて治療した。17頭中13頭(76%)は臨床的完全寛解に達し、寛解期間中央値は18.9ヶ月だった。完全寛解に達した猫(19.3ヶ月)は、完全寛解に達しなかった猫(n=4)(4.1ヶ月;P=0.019)よりも有意に生存期間中央値が長かった。経口プレドニゾロンと高用量クロラムブシルパルス療法の併用で治療したLGALの猫の予後は良好から優良である。(Sato訳)
■連続低線量率半身照射と化学療法による犬多中心性リンパ腫の治療
Sequential low-dose rate half-body irradiation and chemotherapy for the treatment of canine multicentric lymphoma.
J Vet Intern Med. 2009 Sep-Oct;23(5):1064-70.
D M Lurie, I K Gordon, A P Theon, C O Rodriguez, S E Suter, M S Kent
背景:連続半身照射(HBI)と化学療法の組み合わせが犬のリンパ腫の治療で可能であるが、照射感覚の延長は有効性に影響を及ぼすかもしれない。6Gy線量レベルで低線量率照射(LDRI)プロトコールを行う多くの犬は、2週間の照射間隔が可能である。
仮説:シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン(CHOP)ベースの化学療法プロトコールへのLDRIの組み込みは、犬のリンパ腫の治療に効果的である。
動物:多中心性リンパ腫と診断された28頭の飼育犬
方法:連続HBIと化学療法で犬リンパ腫を治療し、その効果と予後因子を評価する遡及研究。
結果:初回寛解の中央値は410日(95%信頼区間[CI]241-803日)だった。1-、2-、3年初回寛解率は54、42、31%だった。総生存期間中央値は684日( 95%CI 334-1223日)だった。1-、2-、3年生存率は66、47、44%だった。
結論と臨床関連:この研究の結果は、リンパ腫の犬の治療で2週間間隔の放射線照射と照射間化学療法の併用による治療強化が有効である事を示唆する。(Sato訳)
■形態および免疫学的に確認された犬白血病の臨床病理および疫学的評価
Clinical pathological and epidemiological assessment of morphologically and immunologically confirmed canine leukaemia
Vet Comp Oncol. September 2009;7(3):181-195. 57 Refs
F. Adam, E. Villiers, S. Watson, K. Coyne, L. Blackwood
従来、犬の白血病の分類は形態学的検査および細胞化学染色パターンに依存しているが、異常な細胞形態および染料取り込みは正確な分類を切り詰め、この分類をもとにした背景データは信頼できないだろう。
現在、免疫表現型決定は白血病分類のゴールドスタンダードである。この前向き研究の目的は、形態学および免疫学的に白血病と確認された犬の集団の臨床病理および疫学的特徴を評価し、カテゴリー(急性および慢性リンパ性白血病(ALL、CLL)、急性および慢性骨髄性白血病(AML、CML))内でそれらを比較することだった。形態学的および免疫学的に64症例の白血病を確認した:25症例はALL、17症例はCLL、22症例はAML。ALLおよびCLL症例におけるBおよびT免疫表現型の有病率に有意差はなかった。来院時、AML症例はALL症例よりも有意に年齢が若かった(P=0.04)。
その研究集団の中では、コントロール集団と比較してゴールデンレトリバーが多く見られた(6/25ALL症例、8/64白血病症例)。性差は見られなかった。ALLの犬は、CLLの犬よりも重度好中球減少(P
= 0.001)および血小板減少(P = 0.002)を示し、有意により血球減少を示した。ALLとAMLで見られた細胞減少の重症度と数に有意差は見られなかった。白血病症例の21頭は1種の血球減少を示し、15頭は2種の血球減少、21頭は汎血球減少を示した。貧血は別に見られた一般的な血球減少だった(17/21)。貧血および/あるいは血小板減少がない好中球減少の犬はいなかった。グループ間の総白血球数に違いはなかった。末梢血の異型細胞数はAMLよりALLで有意に多く見られた;両方独立し、総白血球数の比率として(P
= 0.03)。この研究は、急性白血病が慢性白血病よりもより顕著な血球減少を起こし、より多くの細胞形に影響するという仮説を強化するものである。(Sato訳)
■犬の再発性リンパ腫に対する単剤治療としてのダカルバジン
Dacarbazine as Single-Agent Therapy for Relapsed Lymphoma in Dogs.
J Vet Intern Med. 2009 Aug 26.
Griessmayr PC, Payne SE, Winter JE, Barber LG, Shofer FS.
背景:多中心型リンパ腫の犬において、治療がうまくいかないケースの原因は多剤耐性が最も一般的である。5-(3,3-ジメチル-1-トリアゼノ)-イミダゾール-4-カルボキシアミド(DTIC)は人のホジキンリンパ腫の標準的な治療として使われている非定型的なアルキル化剤であり、犬の抵抗性リンパ腫の多剤治療においても効果的である。しかし、犬の再発性リンパ腫の治療で、単剤療法としてのDTICの使用に対して入手できるデータはない。
仮説:単剤療法としてのDTICは、再発症例やこれまでに行った化学療法に反応しない症例に効果的且つ安全である。
動物:飼い主が所有している40頭の再発性リンパ腫の犬
方法:組織学的あるいは細胞学的にリンパ腫と確定診断し、再発した犬を遡及研究した。犬にDTIC
(2-3週毎に4-5時間の持続点滴により800-1000 mg/m(2))を投与し、反応率と反応期間を評価した。血液学的異常と胃腸管毒性を評価した。
結果:DTICで治療した犬の全反応率は35%(14頭の犬)で、無進行期間中央値は43日だった。13頭の犬は部分寛解で、1頭の犬は完全寛解だった。3頭は病勢安定となった。軽度の胃腸管毒性が3頭の犬の治療後に報告された。治療後7-14日で観察された主な毒性は血小板減少症であった。血小板減少症のため治療が遅れた。
結論:DTICを単独で使うと再発性リンパ腫の治療において効果的である。(Dr.Kawano訳)
■犬リンパ腫患者のプロテオーム識別とプロファイリング
Proteomic identification and profiling of canine lymphoma patients
Vet Comp Oncol. June 2009;7(2):92-105. 24 Refs
L. Ratcliffe, S. Mian, K. Slater, H. King, M. Napolitano, D. Aucoin, A. Mobasheri
この研究は、犬リンパ腫患者における血清生物マーカーを確認するために、プロテオームおよび生物情報科学的アプローチを利用した。非リンパ腫(n=92)およびリンパ腫(n=87)の患犬から採取した冷蔵血清サンプルをファーストオピニオンの獣医診療所から輸送し、イオン交換クロマトグラフィーに供し、表面エンハンス型レーザー脱イオン化質量分析法により分析した。19の血清蛋白のピークが、それらの正常化したイオン強度をもとに2群間に有意差(P<0.05)があるとして確認された。2つの生物マーカーがリンパ腫および非リンパ腫患犬の鑑別能力があると確認された。そのテストデータの分析の陽性適中率(PPV)は82%だった。臨床的追跡調査研究はリンパ腫が疑われた96頭の患犬で実施された。このデータの評価で特異値は91%、感受性は75%、PPVは80%、陰性適中率は88%だった。結論として、2つの血清生物マーカーの発現パターンは、血清サンプルでリンパ腫あるいは非リンパ腫カテゴリーにクラス分けすることが可能である。(Sato訳)
■犬の再発性リンパ腫における持続的L-アスパラギナーゼ、ロムスチンそしてプレドニゾンの多剤併用化学療法
Combination Chemotherapy with Continuous l-Asparaginase, Lomustine, and Prednisone for Relapsed Canine Lymphoma.
J Vet Intern Med. 2009 Aug 11.
Saba CF, Hafeman SD, Vail DM, Thamm DH.
背景:ロムスチン、L-アスパラギナーゼそしてプレドニゾン(LAP)のコンビネーションは犬のリンパ腫(LSA)における効果的なレスキュー療法である。これまでの研究において、我々はL-アスパラギナーゼを中止すると典型的に寛解が得られなくなると報告した。
仮説:ロムスチンと共にL-アスパラギナーゼを使うと犬のリンパ腫に対してよく通用し、レスキュー療法として効果的である。
動物:シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチンそしてプレドニゾンを基本とした化学療法プロトコールで治療し、その後再発した細胞学的に多中心型リンパ腫と診断されている48頭の飼い主所有の犬。
方法:合計5回の投与あるいは病気が進行するまで、L-アスパラギナーゼの皮下あるいは筋肉注射と同時に3週間毎にロムスチンを経口投与した。プレドニゾンはプロトコールの期間中漸減して投与した。
結果:このプロトコールで治療した犬の奏功率(ORR)は77%で、完全寛解(CR)は65%だった。進行するまでの中央時間(TTP)は70日だった。ゆるい比較に基づくと、これらの所見は我々が以前に報告した所見と有意差はなかった。実際に投与したロムスチン投与量は反応率あるいは寛解期間に影響を与えなかった。
結論/臨床重要性:これらの所見は、LAPプロトコールはリンパ腫の犬における実行可能なレスキュー療法オプションであることを結論付ける過去のデータを支持する。しかし、この研究結果はロムスチン治療と一緒に連続的にL-アスパラギナーゼを使用することは寛解期間を明らかに延長させず、より毒性が強いように思われると示唆される。(Dr.Kawano訳)
■リンパ腫の犬において貧血は生存期間短縮に関連する
Anemia is associated with decreased survival time in dogs with lymphoma.
J Vet Intern Med. 2009 Jan-Feb;23(1):116-22.
A G Miller, P S Morley, S Rao, A C Avery, S E Lana, C S Olver
背景:腫瘍を持つ人の患者で貧血は一般的な合併症で、生存期間短縮およびクオリティオブライフの低下に関連している。
仮説:リンパ腫の犬における診断時の貧血の存在は、生存および寛解期間に負に関連するが、骨肉腫の犬ではそうではない。
動物:コロラド州立大学動物がんセンターに治療に来院したリンパ腫の犬84頭と骨肉腫の犬91頭
方法:遡及症例-コントロール研究。初回診察時の貧血の有無(PCV<40)を判定するため医療記録を再調査した。生存および寛解期間の中央値はKaplan-Meier product limit methodで判定し、貧血と生存性の関連はmultivariable Cox proportional hazard regression analysisで判定した。
結果:コントロール犬あるいは骨肉腫の犬よりも、癌関連貧血はリンパ腫の犬でより頻度が高かった。リンパ腫および貧血の犬は、貧血のない犬と比べ、生存期間が有意に短縮した。リンパ腫の犬の寛解期間に対する貧血の影響はなかった。骨肉腫の貧血した犬は、貧血していない骨肉腫の犬と比べ、生存あるいは寛解期間を短縮していなかった。
結論と臨床関連:初回診察時のリンパ腫と貧血の犬における生存期間の短縮は、重要な予後の意義を持つ。犬における癌関連貧血の理解は、それら患者におけるクオリティオブライフおよび生存期間を改善する新しい機会を提供するかもしれない。(Sato訳)
■低グレードリンパ球性リンパ腫の猫の予後:41症例(1995-2005)
Outcome of cats with low-grade lymphocytic lymphoma: 41 cases (1995-2005).
J Am Vet Med Assoc. 2008 Feb 1;232(3):405-10.
Kiselow MA, Rassnick KM, McDonough SP, Goldstein RE, Simpson KW, Weinkle TK, Erb HN.
目的:種々の器官を侵した低グレードリンパ球性リンパ腫の猫の治療に対する反応、寛解期間そして生存期間に関連した要因を評価すること。
計画:回顧的症例シリーズ
サンプル母集団:組織学的に低グレードリンパ球性リンパ腫と確定診断した41頭の猫
方法:組織学的に様々な器官系の低グレードリンパ球性リンパ腫と診断し、1995年から2005年の間にプレドニゾンとクロラムブシルで治療した猫の診療記録と生検材料を再調査した。寛解期間と生存期間を測定するためにカプラン・マイヤー法を使った。予後と関連する可能性のある要因を比較した。
結果:一般的な臨床症状は体重減少(83%)、嘔吐(73%)、食欲不振(66%)そして下痢(58%)だった。検査した78%の猫は血清コバラミン濃度が低かった。リンパ腫は猫の68%で胃腸管に限局した。56%の猫が治療によって完全寛解に達し、39%が部分寛解に達した。5%の猫は反応しなかった。いかなる危険因子(解剖学的位置など)と治療に対する反応の間に関連が見られなかった。部分寛解は完全寛解と比べてより短い寛解期間だった。;中央寛解期間は完全寛解に達した猫の897日に比べ、部分寛解に達した猫で428日だった。他に寛解期間と関連する要因はなかった。全生存期間中央値は704日だった。生存期間と関連する有意な要因はなかった。
結論と臨床関連:リンパ球性リンパ腫のほとんどの猫はプレドニゾンとクロラムブシルによる治療に反応し、評価したすべての因子は予後とは関連がなかった。(Dr.Kawano訳)
■犬の抵抗性リンパ腫の治療におけるメクロレタミン、プロカルバジンおよびプレドニゾン
Mechlorethamine, procarbazine and prednisone for the treatment of resistant lymphoma in dogs
Vet Comp Oncol. March 2009;7(1):38-44. 14 Refs
N. C. Northrup, T. L. Gieger, C. E. Kosarek, C. F. Saba, B. E. LeRoy, T. M. Wall, K. R. Hume, M. O. Childress, D. A. Keys
抵抗性リンパ腫の犬41頭を修正MOPP(メクロレタミン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン)プロトコール(MPP[メクロレタミン、プロカルバジン、プレドニゾン]21日サイクルで投与、28日MOPPサイクルをから短縮)で治療した。MPPの総反応率は34%で、中央値は56日(95%信頼区間30-238)だった。17%の犬は完全寛解で持続期間中央値は238日、17%は部分寛解で中央値56日、32%は安定状態で中央値24日だった。細胞診における組織学的グレードあるいは細胞形態は反応に関係した。MPPプロトコールで最小限の毒性は見られ、更なる投与量増強あるいは他の化学療法剤の追加が可能と示唆される。(Sato訳)
■犬の皮膚上皮親和性T-細胞リンパ腫:概説
Canine cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma: a review
Vet Comp Oncol. March 2009;7(1):1-14. 67 Refs
J. Fontaine, C. Bovens, S. Bettenay, R. S. Mueller
犬の皮膚上皮親和性T-細胞リンパ腫は、病因の不明なまれな腫瘍性の状況である。皮膚炎の特徴は、皮膚および付属器構造に特定の向性を持つ腫瘍性Tリンパ球の浸潤を持つ。異なる臨床および組織形態(菌状息肉腫、パジェット様細網症、セザリー症候群)を概説する。犬のこの疾患はヒトの症候群に似ているが、犬症例の80%で腫瘍細胞がCD4-/CD8+なのに対し、ヒト患者の90%がCD4+/CD8-である。予後は悪く、生存期間は数ヶ月から2年である。治療は効果が低いことが多い。ロムスチンを使用した新しいプロトコールはこの疾患の予後不良を改善するかもしれない。(Sato訳)
■犬における膀胱の原発性悪性リンパ腫:放射線および化学療法の治療後長期寛解
Primary malignant lymphoma of the urinary bladder in a dog: longterm remission following treatment with radiation and chemotherapy
Schweiz Arch Tierheilkd. November 2008;150(11):565-9.
M Kessler, B Kandel-Tschiederer , S Pfleghaar, M Tassani-Prell
排他的に膀胱に限られる原発性(結節外)悪性リンパ腫は、ヒトや動物で非常に珍しい疾患であり、全身性(多中心性)リンパ腫が膀胱に広がっている悪性リンパ腫症例とは区別されるべきである。肉眼的に血尿と排尿困難を呈し、他の部位は関与しない膀胱のみの原発性B-cellハイグレードリンパ腫と診断された3歳避妊済みメスの雑種犬の症例を報告する。小分割体外照射療法と細胞障害性化学療法を組み合わせた治療後、腫瘍の急速な完全寛解をもたらせた。現在その犬は生存し、52ヶ月間寛解している。(Sato訳)
■リンパ腫の犬における抗酸化状態と酸化ストレスの生物マーカー
Antioxidant status and biomarkers of oxidative stress in dogs with lymphoma.
J Vet Intern Med. 2009 Mar-Apr;23(2):311-6. Epub 2009 Feb 4.
Winter JL, Barber LG, Freeman L, Griessmayr PC, Milbury PE, Blumberg JB.
背景:酸化ストレスは、獣医領域における癌患者の罹患率と死亡率に強い影響を与えるのと同じように発癌に影響を与えるかもしれない。この研究の目的は健常犬と比較して、治療前に新たにリンパ腫と診断した犬や寛解時の犬において、抗酸化物質濃度と酸化ストレスの生物マーカーを評価することだった。
仮説:リンパ腫の犬は、健常なコントロールの犬と比較して酸化体が増加し、抗酸化物質濃度が減少しており、これらの異常は寛解に達した時に正常化される。
動物:リンパ腫に罹患した17頭の犬と10頭の健常コントロール
方法:前向き、観察研究。健常コントロールの犬と比較し、リンパ腫と新たに診断して治療する前の犬において酸化ストレス[マロンジアルデヒドと総イソプロスタン(isoP)
]と抗酸化物質[α-トコフェロール、γ-トコフェロール、活性酵素吸収能力(ORAC)、グルタチオン・ペルオキシダーゼ(GSHPx)]を測定した。全ての犬が寛解に達した時、化学療法プロトコールの7週におけるリンパ腫の犬において同じパラメーターを測定した。
結果:基線において、リンパ腫の犬は健常コントロールの犬と比較して、α-トコフェロール(P
<.001)とγ-トコフェロール(P= .003)が有意に低かったが、グルタチオン・ペルオキシダーゼ(GSHPx)
(P=0.05)と活性酵素吸収能力(ORAC) (P=0.001)そしてイソプロスタン(isoP) (P
< .001)がより高い値を示した。リンパ腫の犬において、治療後のα-トコフェロール濃度はより高く(P=0.005)、アスコルビン酸はより低かった(P=0.04)。
結論と臨床重要性:リンパ腫の犬では、酸化物質濃度と抗酸化物質濃度は変化しており、これらの生物マーカーのいくつかの状態は寛解後に正常化することが結果から示唆される。犬のリンパ腫治療においてそれらを補正する抗酸化治療介入が有益かどうかを判断するためのさらなる研究が期待される。(Dr.Kawano訳)
■リンパ腫の犬における低線量率放射線半身照射と化学療法の毒性研究
A toxicity study of low-dose rate half-body irradiation and chemotherapy in dogs with lymphoma
Vet Comp Oncol. December 2008;6(4):257-267. 33 Refs
D. M. Lurie, M. S. Kent , M. M. Fry, A. P. Theon
まだ治療をしていない多中心型リンパ腫の犬13頭で、低線量率放射線全身照射(TBI)と化学療法の効果を調査する前向き研究を行った。2週にわけ半身に6あるいは8Gyの照射を行った。毒性は軽度から中程度の血液および胃腸(GI)症状だった。1頭は治療の合併症で死亡した。食欲不振は照射量に関係なく見られた。血液毒性は一般的に見られ、8Gy照射後はより重度だった。胃腸毒性は下半身の8Gy照射後に起きやすかった。白毛症以外に放射線照射の晩発作用は認められなかった。
結果は血液および非血液毒性は照射量に依存したことを示した。しかし6Gyを照射した全ての犬は、そのプロトコールをよく許容し、照射間隔2週間で治療強化は可能であった。それらの犬の予備的生存データは、非常に励みになるもので、犬のリンパ腫における低線量率放射線照射(LDRI)の効果を分析する強い理論的根拠を提供する。(Sato訳)
■血清アミロイドAは犬における多中心型リンパ腫の再燃のマーカーではない
Serum amyloid A is not a marker for relapse of multicentric lymphoma in
dogs
Vet Clin Pathol. March 2008;37(1):79-85.
Alexandre Merlo, Barbara Cristina Gagliano Rezende, Maria Luisa Franchini, Paula Rumy Goncalves Monteiro, Silvia Regina Ricci Lucas
背景:血清アミロイドA(SAA)は動物やヒトにおける炎症、感染、腫瘍の状態で濃度が上昇する急性期蛋白である。犬の多中心型リンパ腫は一般的な癌で、化学療法により長期生存が可能と示されている。しかし、頻繁な再燃で化学療法プロトコールの変更を余儀なくさせる。
目的:この研究の目的は、犬の多中心型リンパ腫の再燃に対するマーカーとして血清アミロイドAを評価することと、化学療法による治療中の血清アミロイドA濃度に変化が起きるかどうかを判定することだった。
方法:ELISAにより健康なコントロール犬(n=20)、化学療法を投与している健康犬(n=8)、リンパ腫の犬(n=20)の血清アミロイドAを測定した。化学療法を投与している全ての犬を無作為に2治療群に振り分け、シクロフォスファマイド、ビンクリスチン、プレドニゾン(CVP)とビンクリスチン、シクロフォスファマイド、メトトレキサート、L-アスパラギナーゼ(VCMA)プロトコールを行う群とした。血清アミロイドA濃度測定は、リンパ腫の犬および化学療法を受けている健康犬で1-4週目の化学療法前、その後は健康犬で4ヶ月間3週間毎、リンパ腫の犬で再燃時および再燃前のサンプルで行った。健康なコントロール犬は1回のみ血清アミロイドAを測定した。結果は頻回測定ANOVAで分析し、その後治療の週および群を比較するのにTukey多重比較法を使用した。
結果:平均血清アミロイドA濃度は健康犬、化学療法コントロール犬と比較し、化学療法前のリンパ腫の犬で有意に高かった。再燃時、血清アミロイドAの増加は見られなかった。化学療法プロトコールの種類で血清アミロイドA濃度の違いは見られなかった。
結論:血清アミロイドAは多中心型リンパ腫の犬の再燃のマーカーではなく、また行った化学療法もその濃度に影響しない。(Sato訳)
■血清チミジンキナーゼ1活性による犬の悪性リンパ腫と白血病のモニタリング治療-新しく完全自動化された非放射計分析の評価
Monitoring therapy in canine malignant lymphoma and leukemia with serum thymidine kinase 1 activity - evaluation of a new, fully automated non-radiometric assay.
Int J Oncol. 2009 Feb;34(2):505-10.
Von Euler HP, Rivera P, Aronsson AC, Bengtsson C, Hansson LO, Eriksson SK.
DNA前駆体の合成に影響するチミジンキナーゼ1(TK)はS-G2細胞周期にのみ発現する。血清TK濃度は腫瘍疾患の増殖性の活性に関連する。今までのTK濃度の測定は、ラジオ酵素分析(REA)および実験的なELISA方法に依存しており、バイオマーカーとしての臨床的使用には制限があったが、悪性リンパ腫(ML)に罹患した犬による最近の研究で、その広い可能性が実証された。特異的抗3'-アジド一燐酸デオキシチミジン(AZTMP)抗体を用いた競合免疫測定法に基づいた非放射測定法は、完全自動Liaisonチミジンキナーゼ測定器(DiaSorin社)へさらに進化している。
健康な犬(n=30)、白血病(LEUK)(n=35)、悪性リンパ腫(n=84)、非血液学的腫瘍(n=50)そして炎症性疾患(n=14)の犬からの血清を両方の方法で検査した。リンパ腫と白血病サンプルは抗癌剤使用前と使用中のものを利用できた。この研究でのLiaisonチミジンキナーゼ測定の変動係数はそれぞれ6.3%と3.4%(low/high TK)で、チミジンキナーゼのラジオ酵素分析(REA)(X軸)とLiaisonチミジンキナーゼ測定(Y軸)の関連はy=0.9203x + 1.3854 (R(2)=0.9501)だった。化学療法中に測定したチミジンキナーゼ1濃度は、完全寛解した犬と寛解していなかった犬の間に非常に明確な違いがあった。Tukey-Kramer法ですべての白血病と寛解できていない悪性リンパ腫は他のグループと有意に異なったことを示した。
Liaisonチミジンキナーゼ測定に高い精度、高い感受性とチミジンキナーゼのラジオ酵素分析(REA)に対する優れた相関性が認められた。Liaisonチミジンキナーゼ測定は犬の白血病と悪性リンパ腫の治療と管理における有用な臨床情報を提供し、人における試験でさらに検証する可能性をもつ。(Dr.Kawano訳)
■骨髄関与を伴う犬リンパ腫のVCAAベースプロトコールにシトシンアラビノシドを追加した治療:違いはあるのか?
Cytosine arabinoside in addition to VCAA-based protocols for the treatment of canine lymphoma with bone marrow involvement: does it make the difference?
Vet Comp Oncol. June 2008;6(2):80-89. 36 Refs
L. Marconato, U. Bonfanti, D. Stefanello, M. R. Lorenzo, G. Romanelli, S. Comazzi, E. Zini
シトシンアラビノシド(ara-C)は、ヒトの急性白血病および非ホジキンリンパ腫の治療で多くのプロトコールに組み込まれるものである。この研究の目的は、骨髄関与を伴う犬リンパ腫の集団におけるmyeloablative regimenでara-Cの効果を前向き評価した。17頭の犬を研究した。8頭はVCAAベースプロトコールで治療し(1群)、9頭はその方法にara-Cを加えて治療した(2群)。ara-Cはスケジュール5日目に、1日に150mg/m2のIV持続点滴を5日連続で行った。
治療中に1群の2頭および2群の8頭が完全寛解(CR)に達した。CR率は2群の方が有意に高かった(P<0.01)。生存期間中央値は、1群で72.5日(範囲6-174日)、2群で243日(範囲73-635日)だった。生存期間は有意に2群が長かった(P<0.001)。両プロトコールに犬は良く耐え、副作用の発生率も低かった。VCAAベースプロトコールにara-Cを加えることは、ステージVリンパ腫の犬に安全で効果があると思われる。ヌクレオシド類似体の取り込みは、今後の犬の治療戦略の発展に非常に重要かもしれない。(Sato訳)
■アクチノマイシンDを用いた再発あるいは抵抗性リンパ腫の犬におけるレスキュー療法の評価:49症例
Actinomycin D as rescue therapy in dogs with relapsed or resistant lymphoma: 49 cases (1999-2006).
Bannink EO, Sauerbrey ML, Mullins MN, Hauptman JG, Obradovich JE.
J Am Vet Med Assoc. 2008 Aug 1;233(3):446-51
目的:再発あるいは抵抗性を示す犬のリンパ腫に対して、アクチノマイシD用いて治療を行ったときの反応率と犬の無腫瘍期間を評価し、血液学的毒性と治療反応に関連した予後因子を特定すること。
統計:回顧的症例検討。
動物:再発あるいは抵抗性リンパ腫の犬49頭。
方法:医療記録から、シグナルメント、臨床徴候、身体検査所見、診断結果、サブステージ、以前までの化学療法、これまでにプレドニゾロンを併用していたか、アクチノマイシンDの投与用量、投与回数、反応、無腫瘍期間、そして治療後に行われたCBCの結果について評価した。
結果:アクチノマイシンDが3週間毎に5回、もしくは腫瘍が進行するまで1回平均投与量が0.68 mg/m2(範囲は0.42~0.72 mg/m2)で静脈投与された。26症例(53%)でプレドニゾロンが同時に投与された。20症例(41%)で完全寛解がみられ、中央無腫瘍期間は129日であった。血小板減少症が最も多くみられた血液学的毒性であった(n=22[45%])。プレドニゾロンの投与を行っていた症例、初回寛解期間が短い症例、そして以前の化学療法の使用薬剤数が多い症例では、アクチノマイシンDの治療に反応する可能性がより低いということと有意に関連していた。プレドニゾロンの投与を行っていた症例と以前の化学療法の使用薬剤が多い症例では無腫瘍期間が短いことと有意に関連していた。
結論と臨床関連:単剤としてのアクチノマイシンD投与は、多くの例で軽度の血小板減少症がみられたが、犬の再発および抵抗性リンパ腫のレスキュー化学療法として効果的であり、治療に良く耐えることができた。(Dr.UGA訳)
■鼻部および鼻咽頭リンパ腫の猫:50症例(1989-2005)
Nasal and nasopharyngeal lymphoma in cats: 50 cases (1989-2005)
Vet Pathol. November 2007;44(6):885-92.
L Little, R Patel, M Goldschmidt
猫の鼻腔腫瘍でリンパ腫は最も一般的であるが、この腫瘍の解剖学的、免疫組織学的、細胞学的特徴を特に扱った報告はほとんどない。50頭の猫を検死時にバイオプシーあるいは細胞診単独でリンパ腫と診断した。10頭の猫に複数臓器関与を認め、それらのうち2頭はそれぞれ小脳および前頭皮質に限局していた。腫瘍は、50頭中41頭(82%)は鼻部リンパ腫、5頭(10%)は鼻咽頭リンパ腫に分類され、4頭(8%)はその両方の組織が関与していた。組織学的に全て瀰漫性リンパ球様腫瘍と考えられ、濾胞リンパ腫の特徴を示した猫はいなかった。
病理学者によるスライド審査を得られた44例中40例(91%)は免疫芽細胞リンパ腫、2例(5%)は瀰漫性大細胞、1例は瀰漫性混合と分類され、1例は分類できなかった。免疫組織化学染色を行った45頭中32頭はCD79aに均一に陽性、7頭はCD3に均一に陽性、6頭はCD79aとCD3細胞の混合だった。上皮向性は評価に十分な上皮の提示があった5頭中4頭(80%)で見られた。それら4頭中3頭はB細胞、1頭は顆粒T細胞リンパ腫だった。21頭で鼻部細胞診を行い、15頭はリンパ腫と細胞学的に診断された。残りの5頭の診断は、炎症(n=4)、正常なリンパ組織(n=1)、あるいは診断されなかった(n=1)。一般的な生化学の異常は、26/46(57%)の猫で汎高蛋白血症、11/46(24%)の猫で低コレステロール血症だった。(Sato訳)
■犬上皮向性皮膚型リンパ腫に対するロムスチン(CCNU)の反応:46症例の回顧的研究(1999年~2004年)
Response of canine cutaneous epitheliotropic lymphoma to lomustine (CCNU): a retrospective study of 46 cases (1999-2004).
J Vet Intern Med. 2006;20(6):1389-97.
Risbon RE, de Lorimier LP, Skorupski K, Burgess KE, Bergman PJ, Carreras J, Hahn K, Leblanc A, Turek M, Impellizeri J, Fred R 3rd, Wojcieszyn JW, Drobatz K, Clifford CA.
背景:上皮向性リンパ腫(ELSA)は犬において珍しい皮膚の悪性T細胞性リンパ腫である。スタンダードな治療法に関してコンセンサスは得られておらず、犬の多中心型リンパ腫に対して伝統的に用いられている化学療法剤によりELSAの治療評価が行なわれている。
仮説:この多施設の回顧的研究の目的は、ELSAの治療における1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-l-nitrosourea (CCNU)の効果を評価することである。
動物:十分な追跡調査をし、治療反応の情報がある46例の犬。
方法:全ての症例で、組織病理学的に診断された。免疫組織化学(CD3, CD79a)は46例中42例のサンプルで行われた。
結果:全身の鱗屑を含む皮膚病変(25/46)、プラークまたは小結節(22/46)、粘膜皮膚病変(14/ 46)、角膜への浸潤(1/46)がみられた。リンパ節浸潤は7例で、セザリー症候群は2例で証明された。CCNU療法の回数の中央値は4回(範囲は1~11回)、初期用量中央値は60 mg/m2(範囲は30~95)であった。46例中、15例はCR、23例はPR、5例はSD、3例はPDであり、全体的な反応率は83%であった。反応がみられる治療回数の中央値は1回(範囲は1~6回)であった。全体的な中央反応期間は94日(範囲は22~282回)であった。好中球減少症(10/46)、血小板減少症(1/46)、貧血(1/46)、肝酵素の上昇(3/46)、詳細不明の理由(1/46)のため、16例が用量を減らす必要があった。
結論と臨床的重要性:高い反応率でよく耐えるプロトコルであり、ELSAの治療におけるCCNU単独又は多剤併用プロトコルの有用性を調査するために前向き研究が必要である。(Dr.HAGI訳)
■犬の再燃性あるいは難治性リンパ腫に対するL-アスパラギナーゼ、ロムスチンそしてプレドニゾンによるコンビネーション化学療法
Combination chemotherapy with L-asparaginase, lomustine, and prednisone for relapsed or refractory canine lymphoma.
J Vet Intern Med. 2007 Jan-Feb;21(1):127-32.
Saba CF, Thamm DH, Vail DM.
背景:犬のリンパ腫(LSA)は初期治療に反応するが、初期のプロトコールの薬剤に対して抵抗性を示すようになる。新しいレスキュープロトコールが必要である。
仮説: L-アスパラギナーゼ、ロムスチンそしてプレドニゾンのコンビネーションはよく耐えることが出来、犬のLSAのレスキュー療法として効果的である。
動物:難治性あるいはCHOP (シクロフォスファミド/ドキソルビシン/ビンクリスチン/プレドニゾン)に基づいた化学療法プロトコール後に再燃した多中心型LSAと細胞学的に確定診断した飼い主が所有する31頭の犬
方法:前向き臨床試験。ロムスチン(標的投与量. 70 mg/m2)を3週間間隔で合計5回あるいは病気が進行するまで経口的に投与した。はじめの2回のロムスチン治療と同時にL-アスパラギナーゼ(400 U/kg)を皮下注射した。プレドニゾンはプロトコールの期間中漸減して投与した。
結果:このプロトコールで治療した犬のすべての反応率は87%(27/31)で、完全寛解に達した犬が52%(16/31)だった。反応に対する中央期間は21日だった。腫瘍の進展に対する中央期間は63日(完全寛解に達した犬で111日、部分寛解に達した犬で42日)だった。
このレスキュープロトコールを始める前にL-アスパラギナーゼを受けた犬とそうでない犬の間には、反応率と進展する時間に明らかな違いはなかった。副作用は軽度で、31症例中29症例で自然治癒した。
結論と臨床関連:これはよく耐えられる犬の再燃性LSAのレスキュー療法である。反応率と寛解期間は他の有効なレスキュープロトコールと匹敵した。従ってこのプロトコールは実行可能なレスキューオプションである。(Dr.Kawano訳)
■二次性白血病をともなった猫の大顆粒リンパ球(LGL)リンパ腫:CD3/CD8 alphaalpha優位の腸原発型
Feline large granular lymphocyte (LGL) lymphoma with secondary leukemia: primary intestinal origin with predominance of a CD3/CD8(alpha)(alpha) phenotype.
Vet Pathol. 2006 Jan;43(1):15-28.
Roccabianca P, Vernau W, Caniatti M, Moore PF.
21例の猫の大顆粒リンパ球リンパ腫の臨床病理学的、免疫表現的特徴について検査を行った。全ての猫は在来種で、19例は短毛種、2例は長毛腫で、診断時の平均年齢は9.3歳であった。末梢血のLGLの数の増加は18/21の猫でみられた。好中球増加(12/21)と血清肝酵素の上昇(7/12)、総ビリルビンおよび直接ビリルビンの上昇(7/13)、BUNの上昇(5/14)、クレアチニンの上昇(2/14)がみられた。猫はたいてい病気が進行した状態で連れて来られ、診断後84日以上生存した症例はいなかった(平均18.8日)。LGLの細胞は形態学的に成熟した細胞(6/21)、未成熟な細胞(13/21)、両者の混合(2/21)がみられた。
剖検により、空腸、回腸、そして、頻度は低いものの十二指腸にも腫瘍の浸潤を認めた。小腸病変としては、潰瘍(9/13)、腫瘍細胞の上皮向性(9/13)が一般的であった。剖検により、腸間膜リンパ節(13/13)、肝臓(12/13)、脾臓(8/13)、腎臓(5/7)、骨髄(5/7)に腫瘍浸潤がみられた。19/21の症例でT細胞型(CD3epsilon
+)がLGLの腫瘍細胞を特徴とした。CD8alphaalpha+の細胞障害性/抑制遺伝子型は12/19のT細胞腫瘍でみられ、2例はCD4+CD8alphaalpha型、3例はCD4-CD8-型、2例はCD4+helper
T 細胞であった。CD8beta鎖発現はどの例でもみられなかった。2例ではB細胞起源かT細胞起源かが確証できなかった。CD103は19例中11%(58%)で発現した。猫における腫瘍性大顆粒リンパ球とネコ腸上皮内リンパ球(IELs)によって共有されたこの免疫表現的特徴から猫のLGLリンパ腫が小腸のIEL起源ということを立証する。(Dr.HAGI訳)
■長期間多剤併用プロトコールと短期間単剤プロトコールを用いた犬のリンパ腫の治療における効果の比較
Efficacy of a continuous, multiagent chemotherapeutic protocol versus a
short-term single-agent protocol in dogs with lymphoma.
J Am Vet Med Assoc. 2008 Mar 15;232(6):879-85.
目的:犬リンパ腫に対して、ドキソルビシンを基盤とした長期間にわたる多剤併用療法と、短期間だけドキソルビシンを用いた単剤のプロトコールによる反応率と寛解率、そして生存期間の比較をすること。
統計:無作為抽出臨床試験。
動物:114頭のリンパ腫の犬。
方法:犬はL-アスパラキナーゼ、ビンクリスチン、サイクロフォスファマイド、ドキソルビシン、メトトレキサート、そしてプレドニゾロンで治療したもの(n=87)、もしくはドキソルビシン単剤で治療したもの(n=27)であった。
結果:多剤併用のプロトコールを用いて治療した86例中(1例で反応不明)63例の犬(73%)と単剤のプロトコールを用いて治療した27頭中14頭(52%)において完全寛解が得られた。サブステージ</=と初診時に高BUN値であった犬は有意に完全寛解率が低くなっていた。両治療群間における反応率と生存期間では有意な差はみられなかった。血液学的、消化器毒性の発生は、嘔吐が多剤併用のプロトコールで治療した犬でより一般的にみられたことを除けば、両治療群間で違いはみられなかった。
結論と臨床関連:今回の犬の母集団では、長期間で多剤併用の化学療法と、短期間ドキソルビシン単剤のプロトコールによる反応率と生存期間に有意差は確認できなかった。(Dr.UGA訳)
■犬の薬剤耐性リンパ腫の治療のためのCCNUとDTIC化学療法の組み合わせ
Combination of CCNU and DTIC Chemotherapy for Treatment of Resistant Lymphoma
in Dogs.
J Vet Intern Med. 2008; 22(1) 164-171.
A.B. Flory, K.M. Rassnick, R. Al-Sarraf, D.B. Bailey, C.E. Balkman, M.A.
Kiselow, K. Autio
背景:P糖タンパク耐性はリンパ腫の犬で再燃をおこさせる一般的な原因である。CCNUとDTICは各々P糖タンパクによって影響されないアルキル化剤で、各々交叉耐性がない。この併用プロトコールにより総投与量の増加と相乗効果の改善をもたらすであろう。
仮説:CCNUとDTICの組み合わせは薬剤耐性リンパ腫又は以前投与された化学療法に反応しなくなったリンパ腫の犬の治療に用いることができる。
動物:基本的な化学療法(l-CHOP; L-アスパラギナーゼ, サイクロフォスファミド,ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン)に耐性があるリンパ腫の犬57例
方法:第1相、第2相の前向き研究が行われた。DTICを静脈内投与する5時間前にCCNUを速やかに経口投与した。共通の制吐薬と予防薬の抗生剤が用いられた。治療は4週間毎に行われた。
結果:8例の第1相試験の結果を基に、CCNU40mg/m2の経口投与とDTIC600mg/m2静脈内投与が、薬剤耐性リンパ腫57例の治療に用いられた。13例(23%)はCRになり、中央寛解期83日間、7例(12%)はPRで中央寛解期間25日間であった。l-CHOPにおけるCRの中央寛解期間において、CCNU-DTICに反応がない犬は、CCNU-DTICで寛解した犬よりも有意に長かった(225日(l-CHOP)対92日(CCNU-DTIC)(P=0.02))。主な副作用は好中球減少で、治療後7日目の好中球の数の中央値は1,275cells/μLで、ALT活性の上昇はもしかすると肝毒性に関連しているかもしれず、7例で検出された。
結論と臨床学的重要性:CCNUとDTICの組み合わせは薬剤耐性リンパ腫の犬のレスキューとして効果的な治療になり得る。(Dr.HAGI訳)
■猫リンパ腫の治療におけるVELCAP-Cの効果と副作用
Efficacy and Toxicosis of VELCAP-C Treatment of Lymphoma in Cats.
Hadden AG, Cotter SM, Rand W, Moore AS, Davis RM, Morrissey P.
J Vet Intern Med. 2008 Jan-Feb;22(1):153-7.
背景:リンパ腫は猫において最も一般的にみられる悪性腫瘍である。犬のリンパ腫では、ビンクリスチン、L-アスパラキナーゼ、サイクロフォスファマイド、ドキソルビシン、そしてプレドニゾン(VELCAP-S)によるプロトコールは効果的であり、よく耐えることができている。今回のプロトコール(VELCAP-C)の24週における使用法は猫の治療の為に考案された。
仮説:VELCAP-Cのプロトコールがリンパ腫の猫の治療において、より少ない化学療法のプロトコールで治療を行ったときと同様の生存期間を得られる。
動物:61頭のリンパ腫の猫。
方法:回顧的検討。VELCAP-Cに対する反応、副作用、そして生存期間を評価した。シグナルメント、臨床ステージ、CBC,そして生化学における影響および投与量について調査を行った。
結果:プロトコールを完全に終了した6頭の猫(10%)の中央生存期間は1189日であった。全体のうち43%(
61頭中23頭)の猫で完全寛解が得られ、中央生存期間は62日であった。導入時に投与量の減量が必要であった猫は、完全寛解を得られる傾向が認められた。診断時における体重減少、肝腫大は治療への反応が悪いという負の関連性がみられた。初回治療時における血清LDHの増加は生存期間と反比例していた。
結論と臨床重要性:今回の多剤併用プロトコールでは、より少ない薬剤で行う治療のデータを超える程の生存期間の延長が得られなかった。血清LDHの値はリンパ腫の猫において有益な予後因子であるかもしれない。(Dr.UGA訳)
■リンパ腫の犬におけるレスキュー化学療法としてテモゾロマイドまたはダカルバジンとアントラサイクリン系の併用の効果
Efficacy of temozolomide or dacarbazine in combination with an anthracycline for rescue chemotherapy in dogs with lymphoma
J Am Vet Med Assoc. August 2007;231(4):563-9.
Nikolaos G Dervisis, Pedro A Dominguez, Luminita Sarbu, Rebecca G Newman, Casey D Cadile, Christine N Swanson, Barbara E Kitchell
目的:再発または難治性リンパ腫の犬におけるアントラサイクリン系抗がん剤との組み合わせで、テモゾロマイドまたはダカルバジンの治療結果を比較する
構成:非無作為コントロール臨床試験
動物:再発性、または難治性リンパ腫の犬63頭
方法:21日サイクルで化学療法を行った。テモゾロマイドとアントラサイクリン系(ドキソルビシンまたはダクチノマイシン)の組み合わせを21頭に投与し、ダカルバジンとアントラサイクリン系を42頭の犬に投与した。効果と毒性を評価した。
結果:テモゾロマイド-アンテラサイクリン系併用で治療した18頭中13頭(72%)とダカルバジン-アンテラサイクリン系併用で治療した35頭中25頭(71%)は、完全または部分寛解した。レスキュー化学療法に対する反応の持続中央値は、テモゾロマイド群で40日(範囲、0-217日)、ダカルバジン群で50日(範囲、0-587日)だった。テモゾロマイド群よりもダカルバジン群の犬のほうが高グレードの血液毒性の発生が有意に高かったが、消化管毒性の発生は両群に有意差が見られなかった。完全または部分反応、レスキュー化学療法に対する反応の持続期間、レスキュー後の生存期間、または総生存期間の犬の割合に関して群間の有意差はなかった。
結論と臨床関連:2つの組み合わせは、再発または難治性リンパ腫の犬の治療に有望であるが、ダカルバジンの投与よりもテモゾロマイドのほうが使いやすく、血液毒性も少ない。(Sato訳)
■低グレードのリンパ球性リンパ腫の猫の転帰:41症例
Outcome of cats with low-grade lymphocytic lymphoma: 41 cases (1995-2005).
J Am Vet Med Assoc. 2008 Feb 1;232(3):405-10.
Kiselow MA, Rassnick KM, McDonough SP, Goldstein RE, Simpson KW,
Weinkle TK, Erb HN.
目的:様々な臓器に発生した低グレードのリンパ腫の猫の治療反応、寛解期間、
生存期間に関連する因子を評価すること。
様式:回顧的症例検討。
動物:低グレードのリンパ球性リンパ腫と組織学的に確定された41例の猫。
方法:1995年~2005年に低グレードのリンパ球性リンパ腫と組織学的に確定(様々な臓器に発生)し、プレドニゾンとクロラムブシルで治療した猫のカルテと生検標本の再調査を行った。寛解期間と生存期間を評価するためにカプランマイヤー法を使用した。因子については可能な限り予後について比較を行った。
結果:一般的な臨床徴候として、体重減少(83%)、嘔吐(73%)、食欲不振(66%)、下痢(58%)が認められた。78%においては血清コバラミン濃度が低値を示した。リンパ腫の68%は消化管型であった。56%で完全寛解、39%で部分寛解が得られた。5%では反応が認められなかった。解剖学的部位を含めどの危険因子も治療反応と関連がみられなかった。部分寛解は完全寛解と比べ寛解期間がより短く、中央寛解期間は部分寛解の猫で428日、完全寛解の猫で897日であった。寛解期間は他のどの因子においても関連性はなかった。全体的な中央生存期間は704日であった。生存期間と有意に関連のある因子はなかった。
結論と臨床関連:リンパ球性リンパ腫のほとんどの猫はプレドニゾンとクロラムブシルに反応し、ほとんどの因子は転帰と関連が認められなかった。(Dr.HAGI訳)
■犬の抵抗性リンパ腫の治療におけるCCNUとDTICの併用について
Combination of CCNU and DTIC Chemotherapy for Treatment of Resistant Lymphoma in Dogs.
J Vet Intern Med. 2008 Jan-Feb;22(1):164-71
Flory AB, Rassnick KM, Al-Sarraf R, Bailey DB, Balkman CE, Kiselow MA, Autio K.
背景:P糖蛋白による薬剤耐性は犬のリンパ腫再燃の一般的な原因である。CCNUとDTICはP糖蛋白に影響されないアルキル化剤であり、それぞれの交差耐性を欠く。これらを併用することで総投与量の増加と相乗効果という点において有益である。
仮説:CCNUとDTICの併用に耐えることができるとともに、抵抗性に進行したものや以前までの化学療法に反応しなくなった犬のリンパ腫の治療において治療することができる。
動物:標準的な化学療法(l-CHOP;L-アスパラキナーゼ、サイクロホスファマイド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン)の治療に抵抗性を示した57頭のリンパ腫の犬。
方法:予側I相試験とII相試験が行われた。DTICを静脈投与する5時間前にCCNUが経口投与された。制吐剤と予防的抗生剤が同時に使用された。治療は4週間毎に行われた。
結果:I相試験で行われた8頭の犬の結果から、CCNU 40mg/m2 POとDTIC 600 mg/m2
IVの組み合わせで57頭の難治性リンパ腫の犬を治療した。13頭(23%)の犬で完全寛解が得られ、寛解期間中央値が83日であり、7頭(12%)で部分寛解が得られ、寛解期間中央値25日であった。CCNU-DTICに反応しなかった犬のl-CHOPの完全寛解期間中央値は、CCNU-DTICによって寛解が得られた犬のものより有意に長かった(225日対92日,P=.02)。主な副作用は好中球減少であり、治療後7日目の平均好中球数は1,275/muLであった。ALTの増加もみられ、肝毒性との関連の可能性も7頭でみられた。
結論と臨床重要性:CCNUとDTICの併用は犬の難治性リンパ腫におけるレスキュー薬の効果的な選択肢の一つであることが示された。(Dr.UGA訳)
■犬のリンパ腫の化学療法への反応と生存期間における独立した予後因子としての貧血の評価:96症例(1993~2006)
Assessment of anemia as an independent predictor of response to chemotherapy
and survival in dogs with lymphoma: 96 cases (1993-2006)
J Am Vet Med Assoc. December 2007;231(12):1836-42.
Andrew H Abbo, Michael D Lucroy
目的:貧血(Hct 37%以下)がリンパ腫の診断時に認められるか否かによって、化学療法を行っている犬の治療反応や生存期間における負の予後要因になるかを決定すること。
統計:回顧的症例検討。
動物:化学療法を行っていた96頭のリンパ腫の犬。
方法:シグナルメント、初回の血液検査データ、化学療法のプロトコール、臨床反応、そして死亡日が回顧的にリンパ腫の犬の医療記録から収集した。単変量、多変量、そして生存解析が初回の化学療法の反応と生存期間に対して貧血がもたらす影響を調べるために行われた。
結果:全体を通して、貧血でない犬(n = 56)は、貧血した犬(n =
40)に比べ化学療法を行った際の完全寛解率が4倍であった。貧血した犬の中央生存期間(139日)は、貧血でない犬の中央生存期間(315日)に比べると有意に短いものであった。犬の多中心型リンパ腫(臨床ステージと化学療法のプロトコールの一致が見られた)に関する部分分析において、貧血のある犬(n
= 24)の中央生存期間(101日)は貧血がみられない犬(24; 284日)と比較すると有意に短かった。他の変数は生存期間と関連しなかった。
結論と臨床関連:今回の調査より、化学療法を行っているリンパ腫の犬において貧血は負の予後因子の一つであることが示された。リンパ腫の犬の貧血の改善による臨床結果に与える影響については更なる調査が必要になるであろう。
■犬の消化器型リンパ腫30例(1997-2004)の臨床結果
Clinical outcomes of 30 cases (1997-2004) of canine gastrointestinal lymphoma
J Am Anim Hosp Assoc. 2007 Nov-Dec;43(6):313-21.
Joseph David Frank, S Brent Reimer, Philip H Kass, Matti Kiupel
30例の犬の消化器型リンパ腫について検討した。発生部位は、胃、小腸、大腸に孤立性もしくは2ヵ所以上の部位に認められた。治療法として、切除のみ(4例)、切除と化学療法(8例)、化学療法単独(15例)もしくは支持療法のみ(3例)であった。4例は死亡、24例は安楽死を行い、2例は現在も生存している。全体の生存期間中央値は13日であった。生存している2例は大腸に発生したものであった。犬の消化器型リンパ腫は重症疾患とされるものの一つであり予後は不良である。しかし、結腸直腸に発生するものはより長期の生存が可能かもしれない。(Tako訳)
■<犬の多中心型リンパ腫のCoapとUW19プロトコールの比較>
Comparison of Coap and UW-19 Protocols for Dogs with Multicentric Lymphoma
J Vet Intern Med. 2007 Sep-Oct;21(6): 1355 1363
Kenji Hosoya, William C. Kisseberth, Linda K. Lord, Francisco J.
Alvarez, Ana Lara-Garcia, Carrie E. Kosarek, Cheryl A. London, and C.
Guillermo Couto
背景:犬のリンパ腫の治療に対して様々な化学療法のプロトコールが報告されている。しかしながら、異なる研究からのプロトコールの比較、特に、生存期間と毒性を評価することは難しい。
仮説:リンパ腫の犬においてCOAP (C, サイクロフォスファミド; O, ビンクリスチン; A, シトシンアラビノシド; P,プレドニゾン)と修正されたウィスコンシン大学19週(UW19)導入プロトコールのどちらを選択しても特に生存期間に影響はない。
動物:101頭の多中心型リンパ腫の犬
方法:回顧的研究(2001~2006)。8週COP(C, サイクロフォスファミド; O, ビンクリスチン; P,プレドニゾン)で導入しCOAPで維持を行ったもの(COAP群)もしくは19週CHOP ((C, サイクロフォスファミド; H,ドキソルビシン; O, ビンクリスチン; P,プレドニゾン)を基本としたプロトコル(UW19群)を実施し、初回寛解期間、生存期間、毒性、費用に関して比較を行った。
結果:COAP群は71例、UW19群は30例で実施した。再燃後には様々なプロトコールが用いられた。COAPとUW19群の最初の中央寛解期間はそれぞれ94日(範囲:6~356日)と174日(範囲:28~438日)であった(P<0.01)。犬の中央生存期間はCOAP群とUW19群でそれぞれ309日(6~620日)、275日(70~1102+)であった(P=0.09)。交絡因子(WHO臨床ステージ、年齢、性別、再導入でのドキソルビシンの使用)を補正すると、COAP群の犬は死亡の危険率がUW19群(P=0.03)と比較して1.9倍(95%信頼区間1.1~3.4)であった。好中球減少症と胃腸障害毒性の重症度はCOAP群よりUW19群において有意に高かった。
結論と臨床的重要性:長期間ドキソルビシンを含む連続併用化学療法プロトコールはドキソルビシンを含まないプロトコールの一例と比べたところ再燃の危険性が少ないとともにと化学療法に関連した死亡の危険性が低かった。(Dr.HAGI訳)
■多中心性リンパ腫の犬の第一選択療法としてのロムスチンとプレドニゾン:17症例
Lomustine and prednisone as a first-line treatment for dogs with multicentric lymphoma: 17 cases (2004-2005).
J Am Vet Med Assoc. 2007 Jun 15;230(12):1866-9.
Sauerbrey ML, Mullins MN, Bannink EO, Van Dorp TE, Kaneene JB, Obradovich JE.
目的:多中心性リンパ腫の犬の第一選択療法としてのロムスチンとプレドニゾン併用投与に関連した反応率、中央反応期間、副作用そして予後因子を評価する。
設計:回顧的症例集積検討
動物:17頭の犬
手順:医療記録を評価した。シグナルメント、身体検査所見、診断検査結果、ステージとサブステージ、初期ロムスチンそしてプレドニゾン投与量、ロムスチン投与量の総量に関する情報を得た。
結果:5回投与、あるいは病気の進行が観察されるまで、ロムスチンを中央開始用量67
mg/m(2)で21日間隔の経口投与を行った。プレドニゾンは中央開始用量1.8 mg/kg/日
(0.82 mg/lb/日)、経口投与し、治療の初めの1ヶ月間から徐々に漸減した。6頭の犬は完全寛解し、3頭は部分寛解した。平均そして中央反応期間はそれぞれ48.8と39.5日であった。中央生存時間は111.2日だった。多重解析において、雌とより高用量のロムスチン投与量は、より長い無病期間と有意に関連した。好中球減少症は用量制限因子で、4頭の犬がロムスチン投与後1週間で、臨床的に重要な好中球減少症を呈した。
結論と臨床関連:ロムスチンとプレドニゾンの同時投与は多中心型リンパ腫の犬がよく耐えることができるが、罹患した犬の第一選択治療として、このコンビネーションの使用を支持しているわけではなかったということを結果が示している。(Dr.Kawano訳)
■犬リンパ肉腫に対するウィスコンシン大学2年プロトコールの再評価
Reevaluation of the University of Wisconsin 2-year protocol for treating canine lymphosarcoma
J Am Anim Hosp Assoc. 2007 Mar-Apr;43(2):85-92.
Claire Inderbinen Kaiser1, Janean L Fidel, Malgorzata Roos, Barbara Kaser-Hotz
この遡及研究で、新規に悪性リンパ肉腫と診断され、ウィスコンシン-マジソン(UW-M)化学療法プロトコールで通常治療した96頭の犬の集団を調査した。治療前の特徴は、予後因子判定に分析した。世界保健機関(WHO)ステージ(ステージIVを含む)のより高い犬、高カルシウム血症の犬は有意に再燃のリスクが高かった(それぞれP=0.018、P=0.016)。用量の減少、治療遅延、コルチコステロイドの前処置は臨床結果に関係しなかった。最初の寛解期間270日は、過去に報告されたデータと同様だった。全体の生存期間218日は、過去のデータよりもかなり短かった。(Sato訳)
■リンパ腫または骨肉腫の犬における化学療法中の予防的トリメトプリム-サルファジアジン:二重盲目プラセボ対照試験
Prophylactic trimethoprim-sulfadiazine during chemotherapy in dogs with lymphoma and osteosarcoma: a double-blind, placebo-controlled study
J Vet Intern Med. 2007 Jan-Feb;21(1):141-8.
J D Chretin, K M Rassnick, N A Shaw, K A Hahn, G K Ogilvie, O Kristal, N C Northrup, A S Moore
背景:化学療法の投与は病的状態発生リスクに関与する。獣医腫瘍学で化学療法関連病的状態の管理は第一に支持されている。
仮説:この研究の目的は、リンパ腫または骨肉腫の犬の化学療法関連病的状態に対し予防的抗菌剤使用の影響を評価することだった。
動物:研究資格は、骨肉腫またはリンパ腫と組織学的に確認された犬とした。
方法:最初にドキソルビシン化学療法投与後14日間、プラセボまたはトリメトプリム-サルファジアジンを投与する群に無作為に振り分けた。オーナーと臨床医は治療に関し盲目とした。7日目と14日目にCBC、身体検査とパフォーマンス、中毒グレードを評価した。調査した結果は入院、感染の疑い、胃腸毒性、好中球減少、非血液学的毒性、クオリティオブライフだった。
結果:骨肉腫34頭とリンパ腫39頭の73頭を研究した。トリメトプリム-サルファジアジンを投与した犬(n=36)は、入院率(P=.03)、非血液学的毒性(P=0.039)、グレード2-4の非血液学的毒性(P<.0001)、グレード2-4の胃腸毒性(P=.007)、変化したパフォーマンス(P=.015)を有意に低下させた。群で、抗菌剤を投与した骨肉腫の犬(n=34)は、非血液学的毒性の発生はほとんどなく(P=.02)と重度非血液学的毒性は少なかった(P=.038)。リンパ腫の犬(n=39)は入院(P=.035)、非血液学的毒性の程度(P=.036)、パフォーマンスの変化(P=.015)の発生は有意に低下した。
結論:骨肉腫またはリンパ腫の犬で、予防的トリメトプリム-サルファジアジンの使用は、最初のドキソルビシン投与から14日間、病的状態を減ずるのに有効である。(Sato訳)
■猫のIBDと 消化管リンパ腫の診断において内視鏡標本と全層生検標本の比較
Comparison of endoscopic and full-thickness biopsy specimens for diagnosis of inflammatory bowel disease and alimentary tract lymphoma in cats.
J Am Vet Med Assoc. 2006 Nov 1;229(9):1447-50.
J Am Vet Med Assoc. 2007 Feb 1;230(3):338; author reply 338.
Evans SE, Bonczynski JJ, Broussard JD, Han E, Baer KE.
目的: 猫の消化管リンパ肉腫の診断のために内視鏡生検(EB)標本の精度を評価すること。
デザイン: 前向き研究。
動物: 炎症性腸疾患(IBD)あるいは消化管リンパ肉腫の22頭の猫
手順: 開腹あるいは腹腔鏡下手術において全層生検(FTB)標本を得る直前に、胃と十二指腸の内視鏡検査において、内視鏡生検(EB)標本を得た。
組織病理診断の精度をEBとFTB標本の間で比較した。
結果: リンパ肉腫はFTB標本に基づいて10頭の猫で診断した。リンパ肉腫はすべての10頭の猫において空腸と回腸で検出され、9頭の猫で十二指腸、および4頭の猫で胃に検出された。同じ10頭の猫では、EB調査結果は3頭の猫においてリンパ肉腫と診断したが、3頭の猫では決定的ではなかった。胃のリンパ肉腫に罹患した猫4頭中3頭の胃のEB標本で正しく診断できたが、EB標本では小腸リンパ肉腫に罹患した4頭のIBDは正確に診断できなかった。
結論と臨床関連: EB標本は、胃のリンパ肉腫の診断の役に立つが、IBDと小腸のリンパ肉腫を区別するには、適切ではなかった。猫の消化管リンパ肉腫の最も一般的な部位が空腸と回腸であるので、正確な診断に得るためには、開腹か腹腔鏡検査でそれらの部位からのFTB標本を採取するべきです。腹腔鏡検査は、診断的な生検標本を得るために、内視鏡検査や開腹検査に比べて最少の侵略的な代替手段となるかもしれません。(Dr.Kawano訳)
■猫の骨髄におけるリンパ球増加の悪性、良性の鑑別
Differentiating Benign and Malignant Causes of Lymphocytosis in Feline Bone Marrow
J Vet Intern Med 19[6]:855-859 Nov-Dec'05 Retrospective Study 15 Refs
Douglas J. Weiss
血液または骨髄のリンパ球増加で、悪性および良性の原因の鑑別は不確定な可能性がある。この研究では、8年間かけて猫の骨髄検査結果報告から小リンパ球数増加を伴う猫を確認するため再調査した。再調査した203件のうち、12件(5.9%)が小リンパ球増加を示した。それら猫の診断は、慢性リンパ急性白血病(CLL;n=2)、赤芽球癆(PRCA;n=4)、免疫介在性溶血性貧血(IMHA;n=3)、胸腺腫(n=1)、胆管肝炎(n=1)、原因不明の発熱(n=1)だった。CLLから反応性リンパ球増加の鑑別に使用可能ないくつかの因子が確認された。
CLLの猫は老齢傾向にあり、リンパ球はわずかに大きく、核が裂け、または小葉に分かれていた。反応性リンパ球増加は、免疫介在性貧血、炎症性疾患に関与していた。反応性リンパ球増加で、増殖性リンパ球は、骨髄のリンパ様凝集に組織化して、B細胞優性だった。代わってCLLと胸腺腫で、増殖リンパ球は散在性に分布し、T細胞優性だった。ゆえに、リンパ球増加の原因の鑑別は、徴候、併発疾患の状況、リンパ球形態、骨髄のリンパ球分布、免疫表現型を評価に含めるべきである。猫の年齢、重度貧血の存在、炎症性疾患の所見も考慮すべきである。(Sato訳)
■リンパ腫再燃の犬に対するデキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシンD、シトシンアラビノシド(DMAC)プロトコール
Dexamethasone, melphalan, actinomycin D, cytosine arabinoside (DMAC) protocol for dogs with relapsed lymphoma
J Vet Intern Med. 2006 Sep-Oct;20(5):1178-83.
Francisco J Alvarez, William C Kisseberth, Stacey L Gallant, C Guillermo Couto
背景:一般に、再燃リンパ腫の治療は、反応の確率はより低く、寛解期間はより短い。この研究の目的は、再燃リンパ腫の犬の緩解再導入を目的としたDMAC(デキサメサゾン、メルファラン、アクチノマイシンD、シトシンアラビノシド)多剤化学療法プロトコールの効果を評価することだった。
仮説:DMACは再燃リンパ腫の犬の効果的な再導入プロトコールだろう。
動物:54頭の犬
結果:72%の犬が寛解(44%完全寛解[CR]、28%部分寛解[PR])に達し、11%は安定疾患(SD)、17%は進行疾患(PD)だった。寛解中央期間は61日(範囲2-467+日)だった。CR、PR、SDの寛解期間中央値はそれぞれ112、44、27日だった。反応率に影響する因子は、過去のドキソルビシンによる治療、過去のプロトコールで寛解に達する能力がないことだった。血小板減少症は56%の犬に発生し(3頭グレード1、6頭グレード2、7頭グレード3、7頭グレード4)、好中球減少症は17%の犬で起こった(1頭グレード2、2頭グレード3、4頭グレード4)。胃腸毒性は22%の犬で起こった(5頭グレード1、3頭グレード2、1頭グレード3)。
結論と臨床意義:再燃多中心型リンパ腫の犬に対し、DMACプロトコールは効果的なレスキュープロトコールである。血小板減少症は一般的な毒性症状であるが、一般にそのプロトコールにはよく許容した。(Sato訳)
■犬の多中心型リンパ腫の多剤併用化学療法プロトコールにおけるアスパラギナーゼの影響
J Am Anim Hosp Assoc. 2005 Jul-Aug;41(4):221-6.
Influence of asparaginase on a combination chemotherapy protocol for canine multicentric lymphoma.
Jeffreys AB, Knapp DW, Carlton WW, Thomas RM, Bonney PL, Degortari A, Lucroy MD.
多剤併用化学療法は犬のリンパ腫の治療において単剤化学療法より優れていますが、効果に対する夫々の薬剤の作用はよく理解されていない。改良したシクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾンによる化学療法プロトコール(COP)で治療した34頭、および同じプロトコールの導入期にアスパラギナーゼを投与した42頭の犬を比較することによって、化学療法プロトコールに対するアスパラギナーゼの作用を決定した。両方のグループは2週間と6週間の臨床反応と無進行期間に基づいて比較した。アスパラギナーゼは犬の研究において、明らかに臨床寛解の可能性の増加あるいは最初の無進行期間を延長させないかもしれません。(Dr.Kawano訳)
■猫の悪性リンパ腫におけるシクロフォスファミド、ビンクリスチン、そしてプレドニゾロン(COP)を使った化学療法:古いプロトコールでの新しい結果
Chemotherapy with cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (COP) in cats with malignant lymphoma: new results with an old protocol.
J Vet Intern Med.2002 Mar-Apr;16(2):179-86.
Teske E, van Straten G, van Noort R, Rutteman GR.
悪性リンパ腫の61頭を使った回顧的研究で、ネコ白血病ウイルス(FeLV)の発生率が低い国であるオランダにおいて確立された化学療法プロトコール(シクロフォスファミド、ビンクリスチン、そしてプレドニゾロン[COP])の効果を調べた。 22頭の猫(36.1%)が前縦隔リンパ腫、11頭(18.0%)は消化管リンパ腫、そして、7頭(11.5%)が末梢性リンパ腫、8頭(13.1%)が鼻リンパ腫そして13頭(21.3%)が種々のリンパ腫(腎リンパ腫2頭(3.3%)を含む)でした。 テストされた54頭の猫のウイルス検査をしたところ4頭(7.4%)だけがFeLV陽性でした。完全寛解(CR)した61頭中46頭(75.4%)において約1そして2年無病気期間(DFPs)は夫々51.4%と37.8%で、寛解中央期間は251日でした。
すべての猫の1年生存率は48.7%で、2年生存率は39.9%で、中央生存期間は266日でした。 前縦隔リンパ腫の中央生存期間、1年生存率は夫々262日と49.4%であった。シャム猫は、他の品種より生存と寛解の予後は良好でした。この研究における治療への反応は、重要な予後の指標となることを示しました。長期生存には完全寛解が必要です。完全寛解に達しなかった猫は1年以上長く生存する可能性が低くなります。この研究における若いシャム猫は、若齢で前縦隔リンパ腫により罹患しやすい傾向があり、全ての猫がFeLV陰性でした。異なる化学療法併用プロトコールを使った他の研究で報告されている結果と比較して、悪性リンパ腫に罹患した猫にとって最も高い寛解率と最も長い生存率であった。(Dr.Kawano訳)
■膀胱のリンパ腫:3頭の犬、1頭の猫
LYMPHOMA AFFECTING THE URINARY BLADDER IN THREE DOGS AND A CAT
LIVIA BENIGNI1, CHRISTOPHER R. LAMB1, NURIA CORZO-MENENDEZ2, ANDREW HOLLOWAY3, JANE M. EASTWOOD1
膀胱がリンパ腫に侵されている3頭の犬と1頭の猫を報告し、腹部エックス線と超音波所見を述べる。膀胱を侵しているリンパ腫の壁在病変は全ての動物の超音波検査で確認できた。膀胱リンパ腫の一般的な合併症は、水腎症と水尿管だった。2頭の造影検査は腹膜、後腹膜腔への尿の漏洩を調査するのに必要だった。エックス線、超音波所見は、他の膀胱腫瘍で報告されるものと同じだった。ゆえに膀胱リンパ腫は、移行上皮癌のようにより一般的な膀胱腫瘍と鑑別不可能だった。犬猫の膀胱壁の肥厚や壁在massの鑑別診断にリンパ腫を含めることは重要である。(Sato訳)
■画像診断-若犬の前立腺リンパ腫による二次的尿閉
IMAGING DIAGNOSIS-URINARY OBSTRUCTION SECONDARY TO PROSTATIC LYMPHOMA IN A YOUNG DOG
MATTHEW D. WINTER1, JENNIFER E. LOCKE2, DOMINIQUE G. PENNINCK3
3歳オスのドーベルマンピンシャーの2週間にわたる有痛性排尿困難、排便困難、体重減少を、タフツ大学フォスター小動物病院で検査した。超音波検査により両側水腎症、右側水尿管、肝脾腫大、対称性軽度前立腺肥大、膀胱拡大を認めた。前立腺の針生検、バイオプシーによりリンパ腫と診断した。犬の前立腺肥大の原因でリンパ腫はほとんどない。超音波所見は非特異的で、針生検またはバイオプシーが確定診断に必要である。(Sato訳)
■B-細胞結膜リンパ腫の猫1例
B-cell conjunctival lymphoma in a cat
Veterinary Ophthalmology
Volume 7 Issue 6 Page 413 - November 2004
CASE REPORT
Zaher A. Radi, Debra L. Miller and Murray E. Hines II
抄録
13歳の家猫短毛種メス猫から両側結膜腫瘍を外科的に切除し、組織学的に検査した。腫瘍は浸潤性の非被包性で、高密度に充填した大きなシート列状の円形から多角形の細胞のからなるものだった。腫瘍細胞はさまざまな大きさで、少量から中程度の細胞質を有し、卵形から円形の核を持っていた。腫瘍細胞の免疫組織化学染色で、BLA.36抗体で陽性、CD-3抗体で陰性に染まった。組織病理、免疫組織化学所見をもとに、結膜B-細胞リンパ腫の診断を下した。これは猫の結膜リンパ腫の免疫組織化学特性を持つ最初の症例である。(Sato訳)
■高カルシウム血症の鑑別:犬46頭の遡及研究
[Differential diagnosis of hypercalcemia--a retrospective study of 46 dogs]
Schweiz Arch Tierheilkd. 1998;140(5):188-97.
Uehlinger P, Glaus T, Hauser B, Reusch C.
高カルシウム血症の46頭の犬の症例を回顧的に研究した。高カルシウム血症の最も一般的な原因は悪性疾患で、大多数はリンパ肉腫(LSA,n=23)に罹患していた。
興味の深いことに15頭しか触知可能なリンパ節腫脹がなかった。
他の腫瘍は肛門嚢のアポクリン腺癌(n = 4)、乳癌(n = 2)、未分化癌 (n = 1)、そして悪性組織球症(n = 1)であった。 高カルシウム血症における非腫瘍性の原因は副腎皮質機能低下症(n = 5)、急性腎不全(n = 2)、慢性腎不全(n = 2)、高ビタミンD血症(n = 1)、そして原発性上皮小体機能亢進症(n = 1)であった。4症例については確定診断に至らなかった。
中等度から著しい高リン酸血症と高窒素血症は原発性腎疾患のすべての犬において、そして副腎皮質機能低下症の犬5頭中4頭で見られた。
対照的に腫瘍の犬31頭中たった4頭が(軽度の)高リン酸血症と20頭が軽度から中等度の高窒素血症が見られた。上昇したPTH濃度は原発性慢性腎疾患と原発性上皮小体機能亢進症の犬で見られたが、腫瘍の犬で1頭しか見られなかった。低いPTH濃度は高ビタミンD血症の犬および腫瘍の8症例で見られた。さらに腫瘍の3症例は正常範囲内であった。
結論
1. 高カルシウム血症の最も一般的な原因はLSAである。触知できるリンパ節腫脹がなくてもLSAを除外せず、さらなる診断ステップが必要かもしれない。
2. 中等度から著しい高リン酸血症の併発は原発性腎疾患あるいは副腎皮質機能低下症を示唆する。
3. PTH濃度の上昇は原発性上皮小体機能亢進症に一致するが、他の高カルシウム血症の原因を除外できない。(Dr.Kawano訳)
■猫の骨髄においてリンパ球増多を引き起こす疾患の良性と悪性の鑑別
Differentiating benign and malignant causes of lymphocytosis in feline bone marrow.
J Vet Intern Med. 2005 Nov-Dec;19(6):855-9.
血液あるいは骨髄でリンパ球増多を引き起こす疾患の良性と悪性は問題となることがあります。今回の研究では、8年間、猫の骨髄検査結果から小リンパ球増加を伴う猫を再検討した。203症例の中で12症例(5.9%)は小リンパ球増加を示した。これらの猫の診断は慢性リンパ球性白血病(CLL:2症例)、赤芽球癆(PRCA:4症例)、免疫介在性溶血性貧血(IMHA:3症例)、胸腺腫(1症例)、胆管肝炎(1症例)、および不明熱(1症例)が含まれた。CLLと反応性リンパ球増多を区別するのに役立つかもしれないいくつかの要因が特定された。
CLLの猫は、より高齢である傾向があり、リンパ球はわずかに大きく分葉そして分裂した核を持っていた。反応性リンパ球増多は免疫介在性貧血と炎症性疾患に関連していた。反応性リンパ球増多では、増殖したリンパ球は、骨髄においてリンパ性が集合して分布され、主にB細胞だった。一方、CLLと胸腺腫では、増殖したリンパ球は、び慢性に広がり、主にT細胞だった。従って、リンパ球増多の原因の鑑別はシグナルメント、同時発生の病気の状態、リンパ球の形態学、骨髄でのリンパ球の分布、および免疫形質の評価を含めるべきである。猫の年齢、重度の貧血そして炎症性疾患に関する証拠の存在も考慮すべきである。(Dr.Kawano訳)
■犬の心臓リンパ腫と心嚢水:12例(1994-2004)
Cardiac Lymphoma and Pericardial Effusion in Dogs: 12 Cases (1994-2004)
J Am Vet Med Assoc 227[9]:1449-1453 Nov 1'05 Retrospective Study 41 Refs
John M. MacGregor, DVM; Maria L. E. Faria, DVM, PhD; Antony S. Moore, MVSc, DACVIM; Anthony H. Tobias, BVSc, PhD, DACVIM; Donald J. Brown, VMD, PhD, DACVIM; Helio S. A. de Morais, DVM, PhD, DACVIM
目的:心臓リンパ腫による心嚢水が貯留した犬で、心嚢水分析結果を含む臨床特性と臨床病理所見、およびそれに関する転帰を判定する
構成:回顧的症例シリーズ
動物:12頭の犬
方法:罹患犬の医療記録から、心エコー検査所見、エックス線所見、心嚢水分析結果、臨床病理所見、治療プロトコール、予後を再検討した。
結果:全ての犬で心エコー検査により心嚢水が認められ、心嚢水の細胞診(11/12頭)、または心膜の組織検査(3/12)によりリンパ腫を認めた。大型犬種が多く見られ、体重の中央値は40.5kgだった。多くの血液学的、生化学変化は軽度で非特異的だった。多剤化学療法剤による治療を行った犬の生存期間は157日で、化学療法を行わなかった犬は22日だった。この差に有意性はないが、長期生存した犬も見られた。
結論と臨床関連:心嚢水の原因として心臓リンパ腫はまれで、結果から心臓リンパ腫は他のステージVサブステージbリンパ腫の予後不良を常に保証するわけではないと思われる。(Sato訳)
■リンパ腫の犬に対する標準的CHOPプロトコールにL-アスパラギナーゼを加えた時、効果と毒性に影響するか?
Does L-Asparaginase Influence Efficacy or Toxicity When Added to a Standard CHOP Protocol for Dogs with Lymphoma?
J Vet Intern Med 19[5]:732-736 Sep-Oct'05 Retrospective Study Refs
Valerie S. MacDonald, Douglas H. Thamm, Ilene D. Kurzman, Michelle M. Turek,
and David M. Vail
過去にリンパ腫を治療したことがない犬に、L-アスパラギナーゼ(L-ASP)を追加した、または追加しなかった同じCHOPベースの化学療法を施し、寛解率、初回寛解期間(FRD)および毒性を評価した。リンパ腫の犬115頭にL-ASPを加えたCHOPベース化学療法を計画したが、製薬会社が無作為を希望したため、31頭には予定していたL-ASPを投与しなかった。
2つの治療群の犬の徴候、それまでの陰性予後因子の有無は統計的に同じだった。L-ASPを投与した、投与しなかった犬のFRD中央値に違いは見られなかった(206日vs.217日;P=.67)。また全体の生存期間中央値にも差は見られなかった(L-ASP投与:310日vs.非投与:308日;P=.84)。投与、非投与群間に総寛解率に関する統計差は見られなかった(89.3%vs.87.1%;P=.75)。また群間寛解率にも違いはなかった(投与:83.3%、非投与:77.4%;P=.59)。毒性出現(好中球減少、下痢、嘔吐)と治療遅延(P=.80)も違いはなかった。
結果から、この多剤プロトコールにおいてL-ASPを省いても結果に重大な影響は及ぼさないと思われる。ゆえに導入が失敗しているリンパ腫の犬の再燃の治療にL-ASPを使用するため、使用を控えておくのが上策と思われる。(Sato訳)
■ウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコールで治療したリンパ腫の猫における反応率と生存時間:38症例(1996-2003)
Response rates and survival times for cats with lymphoma treated with the University of Wisconsin-Madison chemotherapy protocol: 38 cases (1996-2003).
J Am Vet Med Assoc. 2005 Oct 1;227(7):1118-22.
Milner RJ, Peyton J, Cooke K, Fox LE, Gallagher A, Gordon P, Hester J.
目的: ウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコールで治療したリンパ腫の猫における反応率と生存時間を決定すること
計画: 回顧的研究
動物: リンパ腫の猫38頭
手順: 診療記録を再検討し、年齢、性、品種、FeLVそしてFIV感染状態、解剖学的フォーム、臨床病期および生存時間の情報を得た。 免疫形質は判定しなかった。
結果:猫の年齢の平均±標準偏差 は10.9±4.4歳だった。総合的な中間生存時間は210日間(四分位範囲、90~657日間)で総合的な初期寛解期間は156日間(四分位範囲、87~316日間)だった。
年齢、性、解剖学的フォームおよび臨床病期は初期寛解期間あるいは生存時間との有意な関連性はなかった。
38頭中18頭(47%)の猫は完全寛解し、14頭(37%)が部分寛解し、6頭(16%)は反応がなかった。初期寛解期間は部分寛解の猫(114 日間)に比べ完全寛解の猫(654日間)で有意に長かった。完全寛解の猫の中央生存時間(654日間)は部分寛解の猫(122日間)そして反応がなかった猫(11日間)に比べ有意に長かった。
結論と臨床関連: リンパ腫の猫はウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコ-ルでの治療に高い確率で反応することが結果から示された。年齢、性、解剖学的フォーム、および臨床病期は初期反応の期間あるいは生存時間に有意な関連性はないが、初期の治療に対する反応は関連づけられた。(Dr.Kawano訳)
■猫の胃腸管リンパ腫
Gastrointestinal Lymphoma in Cats
Compend Contin Educ Pract Vet 27[10]:741-751 Oct'05 Review Article 30 Refs
Sandra Grover, DVM
リンパ腫は猫でよく診断される腫瘍で、現在胃腸管(GI)リンパ腫が一番よく見られる型である。GIリンパ腫の猫の多くはFeLV陰性で、年齢の中央値は9-13歳である。よく見られる臨床症状は食欲低下、嘔吐、下痢に続く体重減少である。腹部超音波検査は強力な診断ツールであるが、確定診断には組織サンプルが必要である。組織細胞型(小、大細胞型リンパ腫)は治療反応、生存期間を強く予測するものである。(Sato訳)
■結節外リンパ腫の猫における心内膜液滲出と心タンポナーデ
Pericardial effusion and cardiac tamponade in a cat with extranodal lymphoma.
J Small Anim Pract 45[9]:467-71 2004 Sep
Zoia A, Hughes D, Connolly DJ
5歳家ネコ長毛猫の段々悪化する呼吸困難を評価した。猫白血病ウイルス抗原の血清検査は陽性だった。胸部X線写真で胸水を認め、超音波検査で心内膜液滲出と心タンポナーデが明らかとなった。胸水と心内膜滲出液の細胞診で、播種性リンパ腫を示すリンパ芽球細胞を認めた。胸膜穿刺および心膜穿刺後、Wisconsin-Madison化学療法プロトコールでリンパ腫を治療した。3日後に猫は退院し、この時点(初回来院後6ヶ月)でまだ症状は出ていない。著者の知るところでは、心嚢液で腫瘍細胞の細胞学的確認を得た結節外リンパ腫が直接原因となるような猫の心内膜液滲出および心タンポナーデを確認する最初の報告である。(Sato訳)
■ウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコールで治療したリンパ腫の猫の反応率と生存時間:38症例
(1996--2003)
Response rates and survival times for cats with lymphoma treated with the University of Wisconsin-Madison chemotherapy protocol: 38 cases (1996-2003)
Journal of the American Veterinary Medical Association October 1, 2005 (Vol. 227, No. 7)
Rowan J. Milner, BVSc, MMedVet; Jamie Peyton, DVM; Kirsten Cooke, DVM, DACVIM; Leslie E. Fox, DVM, MS, DACVIM; Alexander Gallagher, DVM; Patti Gordon, DVM; Juli Hester
目的-ウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコールで治療したリンパ腫の猫の反応率と生存時間を判定する
計画-回顧的研究
動物-リンパ腫の猫38頭
方法-診療記録を再検討し、年齢、性、品種、FeLV、FIV感染状態、解剖学的フォーム、臨床ステージ、そして生存時間に関する情報を得た。免疫形質は実行しなかった。
結果-猫の年齢の平均±標準偏差は10.9±4.4歳だった。 総合的な中央生存時間は210日間(四分位範囲、90~657日間)で、総合的な初期寛解は156日
(四分位範囲、87~316日間)だった。 年齢、性、解剖学的フォームそして臨床ステージは初期寛解期間あるいは生存時間に有意に関連づけられなかった。38頭の猫のうち18頭(47%)は完全寛解となり、14頭(37%)には、部分寛解となり、6頭(16%)は反応がなかった。初期寛解期間は部分寛解(114
日)より完全寛解(654 日)の猫のほうが明らかに長かった。完全寛解の猫の中央生存時間(654
日)は部分寛解の猫(122 日)あるいは全く反応がなかった猫(11日)と比べて明らかに長かった。
結論と臨床関連-リンパ腫の猫は高い確率でウィスコンシン-マディソン大学の化学療法プロトコールによる治療に反応するだろうということが結果で示された。年齢、性、解剖学的フォーム、そして臨床ステージは初期反応あるいは生存時間の期間に明らかな関連性はなかったが、治療に対する初期反応には関連性があった。(Dr.Kawano訳)
■イギリスで初診診療獣医師による犬リンパ腫の治療
Treatment of canine lymphoma by veterinarians in first opinion practice in England.
J Small Anim Pract 43[5]:198-202 2002 May
Mellanby RJ, Herrtage ME, Dobson JM
初診診療で獣医師による犬リンパ腫治療方法を、イギリスの小動物動物病院1000件をランダムに選びアンケートにより調査した。382人の獣医師により完全な返答が得られた。回答者の95%は過去1年以内に犬リンパ腫を診断していた。回答者の87%は、彼らが診断したイヌリンパ腫症例の50%以上を治療していた。最もよく使用されていた治療プロトコールは、ビンクリスチン、シクロフォスファミド、プレドニゾロンの多剤組み合わせ(COP)だった。回答者の2%がドキソルビシンベースの治療プロトコールで、犬リンパ腫を最初に治療していた。この調査で、ドキソルビシンベースのプロトコールが生存期間を改善するいくつかの報告があるにもかかわらず、イギリスのほとんどの初診獣医師は犬のリンパ腫をCOPで治療すると示唆する。(Sato訳)
■犬のリンパ腫の臨床医による評価、リンパ節針吸引細胞診、フローサイトメトリーによる寛解状態の判定結果の比較
Comparison of Results of Clinicians' Assessments, Cytologic Examination of Fine-Needle Lymph Node Aspirates, and Flow Cytometry for Determination of Remission Status of Lymphoma in Dogs
J Am Vet Med Assoc 226[4]:562-566 Feb 15'05 Prospective Study 31 Refs
Laurel E. Williams, DVM, DACVIM; Maia Tcheng Broussard, DVM; Jeffrey L. Johnson, MS; Jennifer Neel, DVM, DACVP
目的:犬のリンパ腫の寛解を評価するときの臨床医間の一致性、寛解を判定するリンパ節触診、針吸引リンパ節の細胞診、フローサイトメトリーの結果の関連を判定する
構成:前向き研究
動物:治療していないリンパ腫の犬23頭
方法:2人の臨床医が個別にリンパ節を測定し、下顎、または膝窩リンパ節の細胞の細胞診、フローサイトメトリーを治療開始前1週間に実施した。臨床医の寛解評価と細胞診検査、そしてリンパ節測定を2、3、5週目に繰り返し、フローサイトメトリーは5週目に再度実施した。
結果:臨床医の寛解評価の間に有意な相関が確認された。5週目のリンパ節触診と細胞診検査の間に有意な相関が認められたが、2、3週目に認められなかった。フローサイトメトリーを使用することで、初回評価時にリンパ腫を23頭中16頭(70%)で診断したが、その後の評価は使用が少なく、5週目に細胞診で診断した1頭を含むどの犬にもリンパ腫の診断となる結果はなかった。
結論と臨床関連:以上結果から、身体検査、リンパ節容積の測定は、寛解の正確な判定に十分ではなく、フローサイトメトリーのみの検査は診断方法として信頼すべきでないかもしれない。そして針吸引リンパ節細胞診は治療の修正を考慮するとき寛解状態を判定する最も正確な方法と考えるべきだと思われる。(Sato訳)
■猫における非向表皮型皮膚リンパ腫の治療でロムスチンの使用
Use of Lomustine to Treat Cutaneous Non epitheliotropic Lymphoma in a Cat
J Am Vet Med Assoc 226[2]:237-239 Jan 15'05 Case Report 13 Refs
Shinobu Komori, DVM, PhD; Shinichiro Nakamura, DVM, PhD; Kimimasa Takahashi,
DVM, PhD; Masahiro Tagawa, DVM, PhD
17歳の避妊済み家猫短毛種の猫が、潰瘍、結節形成、紅斑、脱毛などの重度皮膚病変で紹介されてきた。非向表皮型皮膚リンパ腫を組織学的に診断した。内蔵の関与所見はなかったが、腎機能が低下していた。猫をロムスチン(45.5mg/㎡、PO、3週間)で治療し、3回目の投与後皮膚病変は改善した。重度毒性は確認されなかった。この結果は、猫の非向表皮型皮膚リンパ腫の治療にロムスチンが有効だと示唆するが、最適投与量、効果、起こりえる副作用について調査すべきである。(Sato訳)
■悪性リンパ腫の犬の血清チミジンキナーゼ活性:疾患のモニタリングと進行に対する有効なマーカー
Serum Thymidine Kinase Activity in Dogs with Malignant Lymphoma: A Potent Marker for Prognosis and Monitoring the Disease
J Vet Intern Med 18[5]:696-702 Sep-Oct'04 Prospective Study 37 Refs
Henrik von Euler, Roland Einarsson, Ulf Olsson, Anne-Sofie Lagerstedt, and Staffan Eriksson
犬悪性リンパ腫(ML)に対する腫瘍マーカーとして血清チミジンキナーゼ(sTK)活性を評価した。目的は、ヒトのようにsTKがMLの犬の生存期間に対する予後マーカーとして使用できるかどうか、そして治療犬の疾患の進行の早期症状を確認できるかどうか調査することだった。ML52頭の犬の血清サンプルで、初回TK活性を検査した。正常犬21頭と非血液系腫瘍の犬25頭のサンプルと比較した。MLの44頭を治療した。治療犬の血清TK活性を各治療前、その後再燃まで4週ごとに測定した。
平均±2標準偏差をもとに、正常犬(TK<7U/L)よりも2-180倍MLの犬(TK5-900U/L)のTK活性は高かった。他の腫瘍群で、2頭だけがコントロールよりも中程度の増加を示した(6.4と7.5U/L)。完全寛解(CR)となったMLの犬の平均sTK活性と健康なコントロール犬の活性に有意差はなかった(P=.68)。再燃までの最低3週間前、そして再燃時の平均sTKは、CR時に測定した活性よりも有意に高かった(P<.0001)。当初sTK>30U/LだったML犬は有意に生存期間が短かった(P<.0001)。さらに、sTK活性はMLの臨床病期分類を反映していた。化学療法を行っているMLの犬のsTK測定は、臨床的に検出できる疾患の再発前に、予後および再燃を予測する強力な客観的腫瘍マーカーとして使用できる。(Sato訳)
■犬リンパ腫の化学療法に続き半身放射線療法
Chemotherapy Followed by Half-Body Radiation Therapy for Canine Lymphoma
J Vet Intern Med 18[5]:703-709 Sep-Oct'04 Prospective Study 36 Refs
Laurel E. Williams, Jeffrey L. Johnson, Marlene L. Hauck, David M. Ruslander, G. Sylvester Price, and Donald E. Thrall
リンパ腫の治療で94頭の犬に、導入化学療法後、半身放射線療法を使用した。73頭(78%)は完全寛解を達成した。サブステージ(P=.011)と表現型(P=.015)を完全寛解率の指標として認めた。うち52頭に半身照射を行った。上半身と下半身に合計8.0Gy、3週間隔でコバルト-60光子連続4.0Gyの2分画照射を行った。それらの犬の最初の寛解の中央値は311日だった。最初の寛解の長さに対する唯一認められた指標は貧血だった(P=.024)。一般に半身照射後の中毒症は、骨髄抑制と胃腸症状で、めったに見られず軽度だった。31頭は再燃し、20頭は導入後、維持化学療法による治療を再開した。70頭(85%)のイヌは2回目の完全緩解を達成した。全52頭の総寛解中央値は486日だった。
この結果は、導入化学療法後の半身放射線照射が良く許容し、従来の化学療法のみのプロトコールに比べ緩解期間が延長するかもしれないと示唆するが、この延長は、臨床関連またはここに述べた方法の応用を正当化するに十分長いとはいえないかもしれない。(Sato訳)
■ボクサーのT-細胞由来悪性リンパ腫
T-Cell-Derived Malignant Lymphoma in the Boxer Breed
Vet Comp Oncol 2[3]:171-175 Sep'04 Brief Communication 39 Refs
D. M. Lurie, M. D. Lucroy, S. M. Griffey, E. Simonson and B. R. Madewell *
ボクサーはリンパ腫など、種々の腫瘍リスクが高い犬種である。この観察研究で、リンパ腫のボクサーから採取した組織切片を、T、Bリンパ球鑑別のため免疫染色し、一時的に選ばれたゴールデンレトリバーとロットワイラー集団のリンパ腫組織に行った同様の研究と比較した。ロットワイラーやゴールデンレトリバーよりも、ボクサーのT-細胞リンパ腫の頻度が有意に高かった(全対象P<0.001)。我々は、犬リンパ腫の免疫タイプと犬種の関連を報告した研究を知らない。他の短頭種がT-細胞リンパ腫の同様の優勢を持つかどうかさらなる研究が待たれる。(Sato訳)
■心膜滲出液と関連した心膜リンパ腫
Pericardial lymphosarcoma associated with pericardial effusion
DVM Newsmagazine、 Apr 1, 2004
By: Ronald Lyman, DVM, Dipl. ACVIM
患者が虚弱、虚脱、心拍微弱そして鈍い心音を呈したら、心膜滲出液が鑑別診断リストに挙がる。臨床医は球状の心陰影を明らかにするためのレントゲン検査の実施を選択し、続いて心膜腔内の液体を確定するための超音波心臓検査を遂行すると思われる。
一般的な診断
この時点で、出血を伴う血管肉腫、特発性そして感染性心膜炎などの一般的な診断のいくつかが直ぐに頭に浮かぶ。しかしタフツとウィスコンシン-マディソン大学による最近の研究で、心膜滲出液の原因がリンパ肉腫だったという犬の一連の症例が報告された(MacGregor et al in the Proceedings of the 21st ACVIM Forum,2003,pg 952)。もちろん確定したリンパ腫の長期の治療は、より一般的に考えられている心膜滲出液の原因と比較し明らかに異なる。これらの9症例すべてが心膜疾患と関連づいた症状を呈した。それらは虚脱が発現し、ほとんどが腹水となった。血液検査は診断に達する際、役に立たなかった。レントゲン検査や超音波心臓検査による更なる画像、心膜穿刺と細胞学的分析で腫瘍性リンパ球の存在を明らかにした。患者のうち3頭はドキソルビシンを含む複合化学療法による治療が行われ、それぞれ157日、328日以上、659日以上の生存した。心臓の問題がうまく管理できれば、生存日数は多中心型リンパ腫に匹敵した。
知識
従って、臨床医は心膜滲出液が心臓もしくは心膜リンパ肉腫の唯一の発現徴候であるかもしれないことを知るべきであろう。
人医領域では細胞診が確定診断にならなければ、時に心臓もしくは心膜の生検が必要となるかもしれないことが注目されている (Gowda et al in Angiology 599-604 Sept.-Oct. 2003)。我々の獣医領域の患者において原因が断定できない難治性心膜滲出液でこのオプションを考慮すべきである。
心血管系血行力学の改善に必要であれば、開胸術によって心膜開窓されるかもしれない
(Stepian et al J Small Animal Practice 2000, pgs 342-347) 。代りに、生検が行われ、ビデオ胸腔鏡下手術の遂行により心膜開窓されるかもしれない(Kovak
et al, JAVMA 2002, Volume 221, No. 7)。(Dr.Kawano訳)
■イヌリンパ肉腫のカルムスチン、ビンクリスチン、プレドニゾンによる治療
Carmustine, vincristine, and prednisone in the treatment of canine lymphosarcoma.
J Am Anim Hosp Assoc 40[4]:292-9 2004 Jul-Aug
Ricci Lucas SR, Pereira Coelho BM, Marquezi ML, Franchini ML, Miyashiro SI, De Benedetto Pozzi DH
ビンクリスチン、プレドニゾンにカルムスチンを併用した化学療法プロトコールで、多中心性悪性リンパ肉腫を治療した。治療した7頭中、6頭(85.7%)は完全寛解に達した。1頭は部分反応だった。生存期間中央値は、224日(平均386日)で、寛解期間中央値は、183日(平均323日)だった。カルムスチン投与後、顕著な好中球減少が観察された。治療中血小板や赤血球数に有意な変化は見られず、血清生化学検査結果にも化学療法による異常は認められなかった。この研究結果は、カルムスチンがイヌリンパ肉腫に有効な代替選択治療であると示した。(Sato訳)
■ネコリンパ腫の治療原則
Principles of treatment for feline lymphoma.
Clin Tech Small Anim Pract 18[2]:98-102 2003 May 26 Refs
Ettinger SN
リンパ腫はネコでよく診断される腫瘍である。ネコ白血病ウイルス抗原血症はここ15年で減少し、北アメリカのネコリンパ腫の存在、ネコの特徴、部位の頻度はかなり変化している。解剖学的分類系も変化したが、ほとんどの研究は、4分類:消化器、縦隔、多中心、結節外にリンパ腫を振り分けている。各型の臨床症状と一般的な鑑別診断を述べる。ステージングは疾患の程度を評価できる。イヌのように、ネコでもリンパ腫は全身性疾患で、化学療法がほとんどの型で選択される治療である。イヌのリンパ腫と対照的に、ネコリンパ腫は治療で一般により難しく、いらいらするようなこともある。反応率は低く、寛解期間はより短い。幸い、イヌよりもネコの化学療法の毒性は低い傾向がある。陽性予後因子は、ネコ白血病ウイルス陰性で、臨床上診断時に健康で、治療に対して反応することである。完全寛解の達成は、生存に対し予後徴候である。残念なことに反応は治療前に予測できない。(Sato訳)
■リンパ腫と白血病の犬における、血漿チミジンキナーゼ活性
Plasma thymidine kinase activity in dogs with lymphoma and leukemia.
J Vet Med Sci 59[10]:957-60 1997 Oct
Nakamura N ; Momoi Y ; Watari T ; Yoshino T ; Tsujimoto H ; Hasegawa A
犬のリンパ腫と白血病に関する血漿マーカーとして、血漿チミジンキナーゼ(TK)活性を評価しました。仮の切捨て値は、13頭の臨床的に健康な犬における血漿TK活性の平均+2SDをもとに、血漿TKの上限値として、6.0U/Lと設定しました。リンパ腫と白血病を持った20頭の犬すべてにおいて、血漿TK活性の値は、切捨て値より、高値を示しましたが、リンパ腫を持った犬における値は、化学療法後の腫瘍病変寬解と平行して減少しました。これらの所見は、血漿TK活性の定量が、犬におけるリンパ腫と白血病に関する血漿マーカーとして用いることができるということを示唆しております。(Dr.K訳)
■上皮小体ホルモン関連タンパクとイヌリンパ腫
Parathyroid Hormone-Related Protein and Canine Lymphoma
Sm Anim Clin Endocrinol 13[2]:19 May'03 Review Article 0 Refs
C. B. Chastain, DVM, MS, Dip ACVIM (Internal Medicine) & Dave Panciera, DVM, MS, Dip ACVIM (Internal Medicine)
Kubota A, Kano R, Mizuno T, et al. J Vet Med Sci 2002;64:835-837.
イントロダクション
背景:イヌの悪性腫瘍の高カルシウム血症に良く見られる原因はリンパ肉腫である。その介在物質は通常上皮小体ホルモン関連タンパク(PTHrP)である。リンパ肉腫の40%に至るイヌが、悪性腫瘍の高カルシウム血症を起こす。これがリンパ肉腫や高カルシウム血症のイヌの罹病率や死亡率の主な原因となりえる。
目的:この報告の目的は、高カルシウム血症のイヌのリンパ腫細胞により産生されるPTHrPを評価し、高カルシウム血症ではないイヌのリンパ腫細胞により産生されるPTHrPと比較することである。
サマリー
症例報告:7歳オスのシェットランドシープドックが、食欲不振、多飲、尿失禁の評価で来院した。身体検査で、全身のリンパ腫大と脾腫が明らかとなった。検査所見は、血漿カルシウム濃度13.7mg/dlなどだった。拡大したリンパ節の針吸引生検で、悪性リンパ球が認められた。化学療法を試みたが、3日後イヌは死亡した。腫瘍細胞のフローサイトメトリーで、T-細胞起源と一致した。高カルシウム血症のイヌの血漿PTHrP濃度は6.1pmol/lで、4頭のカルシウムが正常なリンパ腫のイヌと5頭の正常なイヌの濃度は検出不能(1.1pmol/l以下)だった。高カルシウム血症のイヌの細胞培養上澄み液のPTHrP濃度は1.3pmol/lだった。高カルシウム血症ではない他のリンパ腫のイヌの上澄みで、PTHrPは検出されなかった。
PCR法をPTHrPに関し開発した。高カルシウム血症と、高カルシウム血症ではないイヌのリンパ腫細胞は陽性だった。
結論:PTHrPは、高カルシウム血症やそうでないイヌのリンパ腫細胞により産生される。
臨床への影響
リンパ腫で検査した全てのイヌのPTHrPに対するPCR陽性結果は、リンパ腫産生PTHrPが高カルシウム血症を発症しないかどうかを示唆する。その方法は定量的ではなかった。そうだったとして、PCRにより判定したPTHrP産生量は、おそらく高カルシウム血症のイヌの血漿や細胞上澄み濃度でもより大きな値をとるだろう。使用したPCRは、正常犬の循環単核細胞を含む検査した全ての細胞が陽性だったので、特異性にかけていることが分かった。イヌのリンパ腫細胞がPTHrPを産生するかどうかは不明であるが、ありそうもないとはいえない。(Sato訳)
■環境のタバコの煙とペット猫における悪性リンパ腫のリスク
Environmental tobacco smoke and risk of malignant lymphoma in pet cats.
Am J Epidemiol 156[3]:268-73 2002 Aug 1
Bertone ER, Snyder LA, Moore AS
猫の悪性リンパ腫は一般的に家庭猫に発症し、ヒトにおける非ホジキンリンパ腫のモデルとして役立つかもしれない。いくつかの研究は、喫煙が非ホジキンリンパ腫のリスクを増加させると示唆している。家庭環境でタバコの煙に曝露されること(ETS)が猫の悪性リンパ腫のリスクを増加させるのかどうかを評価するために、マサチューセッツ獣医科教育病院において1993年から2000年に受診した、悪性リンパ腫の80頭の猫と114頭の腎疾患を持つコントロール猫において、この関係のケースコントロールスタディーを行った。
すべての被験者の飼い主は診断2年前までの家庭での喫煙レベルについての問うアンケートが郵送された。年齢やその他の要因を調整した後に、家庭でのETS曝露を受けているすべての猫の悪性リンパ腫の相対的なリスクは2.4であった(95%信頼区間:1.2,4.5)。曝露の期間と量両方で比例的にリスクは増加した。ETS曝露を受けた5歳以上の猫は非喫煙家庭の猫と比較して、相対的に3.2のリスクであった(95%信頼区間:1.5,6.9,p=0.003)。これらの所見は受動喫煙が猫の悪性リンパ腫のリスクを増大させるかもしれない事と、ヒトにおけるこの関係のさらなる研究が正当化される事を示唆している。(Dr.Massa訳)
■4頭のネコの原発性気管内リンパ肉腫
Primary Intratracheal Lymphosarcoma in Four Cats
J Am Anim Hosp Assoc 39[5]:468-472 Sep-Oct'03 Case Report 29 Refs
M. Raquel Brown, DVM, DACVIM; Kenita S. Rogers, DVM, MS, DACVIM; K. Joanne Mansell, DVM, MS, DACVP; Claudia Barton, DVM, DACVIM
4頭のネコ(家ネコ短毛種n=3、家ネコ長毛種n=1;年齢範囲4-13歳)を、呼吸困難、吸息喘鳴音、喘鳴音、開口呼吸の発作など上部気道疾患の症状のため検査した。4頭の胸部、頚部エックス線検査で、気管にmassの疑いがあり、気管支鏡で確認し、気管支鏡検査時に採取したバイオプシーまたはブラシ細胞病理検査、またはその両方をもとにリンパ肉腫(LSA)と確認した。4頭中3頭のネコはレトロウイルスの検査を行い陰性結果だった。症例no.1はグルココルチコイド単独で治療し、臨床症状の無い期間は35日で再発時すぐに安楽死を行った。症例no.2はグルココルチコイドとビンクリスチンで治療した。しかし、好中球減少となり更なるビンクリスチンの投与は行わなかった。その後放射線療法を開始し、12分画合計3,991Gyを照射した。
合併症は観察されず、17ヵ月後もネコは臨床的に正常を維持し、胸部エックス線写真でも疾患が無い状態だった。症例no.3は、ビンクリスチン、プレドニゾン、シクロフォスファミド、ドキソルビシンを用いた併用化学療法で治療した。来院後19ヶ月、ネコは無症候性で、継続化学療法を投与しなかった。症例no.4もno.3と同様の化学療法プロトコールで治療したが、骨髄抑制と食欲不振のため、プレドニゾンを除き全ての化学療法を中止した。その後、12分画合計4,800Gyの放射線照射を行った。来院3ヵ月後呼吸器症状は無い状態だったが、前ぶどう膜炎を伴う虹彩のmass、複数の皮膚のmassが発症した。皮膚の結節は細胞病理学的にリンパ肉腫に適合した。
原発性気管内リンパ肉腫はネコでまれである。8つの文献で報告されている症例の総数のうち、この報告で4症例が述べられている。
著者は、併用化学療法(すなわち、プレドニゾン、シクロフォスファミド、ビンクリスチン、ドキソルビシン)が、現在最小推奨療法で、放射線療法もネコ気管リンパ肉腫の治療に効果的であると締めくくる。(Sato訳)
■イヌのリンパ肉腫:診断と治療
Canine Lymphosarcoma: Diagnosis and Treatment
Compend Contin Educ Pract Vet 25[8]:584-600 Aug'03 Review Article 107 Refs
Ravinder S. Dhaliwal, DVM, MS, DACVIM (Oncology), DABVP; * Barbara E. Kitchell,
DVM, PhD, DACVIM
この文献は、イヌのリンパ肉腫(LSA)に対する診断と治療について述べている。臨床、病理学でイヌLSAの広範囲な主要研究によりいくつかの結論が出されえる。現在認識されているものに、この疾患は臨床と組織学的多様性を持ち、ほとんどのケースで、生存性は多剤化学療法により改善でき、再燃疾患の治療で、薬剤抵抗性が主要な問題となることである。異なる化学療法をそれらの生存率に沿って論じる。臨床試験を行っている新しい薬剤、最終的に失敗に終わる薬剤抵抗性のメカニズムも論じている。ほとんどのオーナーは、より長く生存し良好に生活でき、副作用も比較的軽度なため、ペットに対する化学療法に非常に満足する。(Sato訳)
■リンパ腫の猫におけるクロラムブチル誘発性の間代性筋痙攣
Chlorambucil-Induced Myoclonus in a Cat With Lymphoma
J Am Anim Hosp Assoc 39[3]:283-287 May-Jun'03 Case Report 42 Refs
Noemi Benitah, DVM; Louis-Philippe de Lorimier, DVM; Michele Gaspar, DVM; Barbara E. Kitchell, DVM, PhD *
9.5歳の去勢した雄のペルシャ猫が、内視鏡検査で採材された生検標本の病理組織検査に基づいて、小腸の進行性、瀰漫性、低グレードの上皮向性リンパ腫と診断された。猫は酢酸プレドニゾロン(2.5 mg/kg,筋肉内注射、24時間ごと)とクロラムブチル(15 mg/m2 [総量4 mg], 4日間24時間ごとに経口投与, 21日ごとに繰り返し)を含む化学療法のプロトコールで治療された。 投薬の間違いによって最初の2回のクロラムブチルが12時間あけて投与され、2回目投薬の数時間後から神経病的臨床症状(攣縮と興奮からなる)が始まった。
神経症状は、頭部と肢体の筋肉痙攣を伴い、顔面の攣縮と筋硬直が猛烈に進行し、これらはしばしば異音、動作、身体の拘束により発現した。少なくとも強直間代性の発作に一致する2つの短い症状発現も観察された。極度の興奮と知覚過敏が猫に表れ、完全な神経学的検査を行うことが出来なかった。CBC、血清生化学検査、レトロウイルス試験による最小限の情報からはストレス誘導性白血球像と高血糖を除いては本質的には気づかれなかった。
クロラムブチル誘発性神経毒性の試験的診断に基づいて、猫にはジアゼパムが投与され、補助的に静脈点滴と鼻腔食道フィーディングチューブによる経腸栄養補給を施した。48から72時間経過して神経症状が減少し、経口的にプレドニゾロンとシプロペプタジンを開始した。4日後(96時間後)、神経症状は解決し、継続栄養補給のために経皮胃フィステルチューブが設置された。その後にモディファイCOP(サイクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン)プロトコールが紹介した獣医師によって行われた。
クロラムブチルは様々な調子を整えるため、そして免疫介在性皮膚病、血液病、腎臓病で免疫抑制剤として処方されている。高用量は最も一般的と解釈されている副作用である骨髄抑制と胃腸毒性の可能性の増加と関連づけることが出来る。
この報告に基づいて、間代性筋痙攣または強直間代性発作として現れる神経毒性は獣医患者におけるクロラムブチル療法の副作用の可能性としてよく検討されなければならない。症状は薬の中止と支持的なケアーで解決する。(Dr.Massa訳)
■イヌの中枢、末梢神経系を巻き込んだ血管内リンパ腫
Intravascular Lymphoma Involving the Central and Peripheral Nervous Systems in a Dog
J Am Anim Hosp Assoc 39[1]:90-96 Jan-Feb'03 Case Report 16 Refs
* William W. Bush, VMD, DACVIM; Juliene L. Throop, VMD; Patricia M. McManus, VMD, PhD, DACVP; Amy S. Kapatkin, DVM, DACVS; Charles H. Vite, DVM, DACVIM; Tom J. Van Winkle, VMD, DACVP
5歳去勢済みの雑種犬が、5ヶ月にわたる不全対麻痺、運動失調、知覚過敏、血小板減少と、ここ2週間に起きた再発性の発作で来院した。全身身体検査で、呼吸数の軽度増加と努力性が認められた。神経学的評価で、多病巣性神経疾患が疑われ、首から尾までの脊椎筋肉組織の触診で重度の知覚過敏があった。全血検査で、慢性疾患の貧血、過去にコルチコステロイド投与を示す血清生化学プロフィールを示した。リケッチア、球虫、真菌、ウイルス血清学検査は異常なかった。胸部エックス線写真で、無気肺または肺炎と一致する軽度間質性パターンを示し、血液ガス評価で、低い正常酸素と二酸化炭素濃度、肺胞-動脈酸素勾配の上昇を示した。
入院して次の日、脳脊髄液(CSF)サンプルを採取し、分析結果は、CSFの出血と炎症の可能性を示した。好気性培養は陰性だった。プレドニゾン、抗生物質、鎮痛薬の投与にもかかわらず、患者の神経学的状態に目に見える改善は起こらなかった。入院3日目、脳と頚部のMRI検査を実施した。脳幹、小脳、大脳半球、右側室、背髄、髄膜に病変が見られた。鑑別診断に、感染/炎症または円形細胞腫瘍が上げられた。その後、CTガイドのバイオプシーを、右側頭葉に行い、血管内リンパ腫の細胞病理学と組織病理学所見を得た。疾患はプレドニゾン、L-アスパラギナーゼ、ビンクリスチンの化学療法を行っても進行した。そのイヌは、心臓(不整脈、高血圧)、皮膚(角化亢進、鼻梁背側の苔癬化)、呼吸器(誤嚥性肺炎、肺の血栓塞栓症の疑い)の合併症を併発し、安楽死と検死を決断した。組織病理学検査で、血管内リンパ腫は複数の器官(例えば、肺、神経、眼科、胃腸、内分泌、心臓)に及んでいた。免疫組織化学検査で腫瘍はT-細胞リンパ腫と示唆された。皮膚の変化は脈管障害と一致し、骨髄は侵されていなかった。
血管内リンパ腫は、血管の壁や管腔内で腫瘍性のリンパ球の増殖である。腫瘍細胞の血管の進行性の閉塞により血栓症、出血、梗塞を導く。よく神経症状が目立つ多システム系の疾患である。著者の知識によれば、これはイヌの中枢神経系を巻き込んだ血管内リンパ腫の生前診断と治療を行った最初の記述である。(Sato訳)
■フロセミドの併用する、またはしないでサイクロフォスファミドを投与しているリンパ腫の犬における無菌性出血性膀胱炎の危険因子:216症例(1990-1996)
Risk Factors for Sterile Hemorrhagic Cystitis in Dogs with Lymphoma Receiving Cyclophosphamide With or Without Concurrent Administration of Furosemide: 216 Cases (1990-1996)
J Am Vet Med Assoc 222[10]:1388-1393 May 15'03 Retrospective Study 27 Refs
Sarah C. Charney, DVM; Philip J. Bergman, DVM, PhD, DACVIM; Ann E. Hohenhaus, DVM, DACVIM; Josephine A. McKnight, DVM, DACVIM
目的:サイクロフォスファミドで治療を受けているリンパ腫の犬における、無菌性出血性膀胱炎(SHC)の発生率を決定し、罹りやすくする因子を見極め、またサイクロフォスファミドと同時に利尿剤の静脈投与がSHCの発生率を減少させるかどうか評価すること
構成:回顧した研究
動物:リンパ腫の犬216頭
方法: フロセミドの静脈投与の併用をする、またはしない2つのプロトコールのうち1つに従って、サイクロフォスファミドで化学療法を受けているリンパ腫の犬216頭の医療記録が調査された。2グループのデータはサイクロフォスファミドに関連したSHCの発生率と素因(年齢、品種、性別、体重、以前のまたは既存の病気、以前のまたは既存の尿路感染症、好中球減少症、窒素血症、薬用量、サイクロフォスファミド治療の回数)を決定するために調査された。
結果:サイクロフォスファミドに関連したSHCは、サイクロフォスファミドの治療に、フロセミドの同時投与を受けていない133頭中12頭(9%)で発症した。フロセミドを投与している83頭のうち、1頭(1.2%)だけにSHCが発症した。同時にサイクロフォスファミドとフロセミドの治療を受けている犬はフロセミドの治療を受けていない犬よりもSHCの発症が有意に減少していた。過去、または既存の免疫介在疾患を持っている犬は、有意にサイクロフォスファミドに関連したSHCを発症しやすかった。
結論と臨床への関連性:結果の分析は、サイクロフォスファミドと同時のフロセミド静脈投与とサイクロフォスファミドに関連したSHCの発生率の低下には関係があることを示唆している。
サイクロフォスファミドに関連したSHCの発生率は、フロセミドを同時投与せず治療した犬と、サイクロフォスファミドを経口投与した他の報告とで類似している。
サイクロフォスファミドに関連したSHCは、フロセミドをサイクロフォスファミドと同時に投与されなかったときに化学療法クールの早期に発現する。(Dr.Massa訳)
■ネコ上皮向性腸管悪性リンパ腫:10症例(1997-2000)
Feline Epitheliotropic Intestinal Malignant Lymphoma: 10 Cases (1997-2000)
J Vet Intern Med 17[3]:326-331 May-Jun'03 Retrospective Study 26 Refs
Janet K. Carreras, Micheal Goldschmidt, Martin Lamb, Robert C. McLear, Kenneth J. Drobatz, Karin U. Sorenmo
上皮向性腸管悪性リンパ腫(EIL)のネコ10頭の臨床、組織病理学、免疫組織化学的特徴を述べる。腸管バイオプシーのサンプルをEILの診断確認のために3人の病理学者により再検討した。それらのサンプル(n=10)は、正常なネコの腸管バイオプシー(n=11)、炎症性腸疾患のネコ(IBD;n=7)、非EILのネコ(n=9)の上皮内リンパ球の定量と免疫表現化に対して比較した。免疫表現性の研究は、T-そしてB-細胞免疫反応性を評価するために、それぞれCD3そしてCD79抗体染色で行った。
EILバイオプシーの上皮内リンパ球は、正常な腸管(NRL)やIBDのネコのサンプルよりも顕著に多かった。しかし、非EILとEILのネコの上皮内リンパ球数は、顕著な差は見られなかった。組織学的診断に関係なく、すべてのネコの上皮内リンパ球は小-中サイズのT細胞だった。臨床所見と画像検査で、罹患ネコに最小限または非特異的所見が認められた。ネコの多くは、IBDまたは消化管悪性リンパ腫の典型的なプロフィールに合致した。EILの10頭のネコのうち9頭は、プレドニゾンと追加の化学療法を併用し、または併用しないで治療した。4頭は化学療法に抵抗し、3.5ヶ月以内に安楽死した。残りの5頭は、11ヶ月以上長期生存した。生存期間の中央値は11ヶ月だった。EILをよりよく特徴づけ、IBDのネコ、非EILとその関連、この疾患の最適な治療法の判定のため、更なる研究が必要だろう。(Sato訳)
■イヌの多中心型リンパ腫における発生率と病原ファクターの回顧的研究(1998-2000)
A retrospective study of the incidence and
prognostic factors of multicentric lymphoma
in dogs (1998-2000).
J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 49[8]:419-24
2002 Oct
Jagielski D, Lechowski R, Hoffmann-Jagielska
M, Winiarczyk S
多中心型リンパ腫の63頭の犬で、疾患のリスクに関し評価を行った。他の犬種に比べ、ロットワイラーのリスクが最大と考えられた(オッズ比6.01、他犬種は0.32-2.75)。化学療法を行った43頭のグループで、最初の寛解期間や生存期間に影響を及ぼすと定義したファクターを評価した。化学療法の結果の最重要ファクターは、治療への反応、診断時のWHOに従った疾患のステージ、サブステージだった。(Sato訳)
■リンパ腫の犬に対する維持療法を行わない6ヶ月化学療法プロトコールの評価
Evaluation of a 6-Month Chemotherapy Protocol
with No Maintenance Therapy for Dogs with
Lymphoma
J Vet Intern Med 16[6]:704-709 Nov-Dec'02
Clinical Study 36 Refs
Laura D. Garrett, Douglas H. Thamm, Ruthanne
Chun, Robert Dudley, David M. Vail
この研究の目的は、犬のリンパ腫の治療にCHOP(Hはドキソルビシン、Oはビンクリスチン)を基本とし、維持期を含まない化学療法プロトコールと、維持期を含む同様のプロトコールを比較する事だった。多中心型リンパ腫の犬53頭を、ウィスコンシン大学(UW)-マジソン化学療法プロトコール(UW-25)6ヶ月修正バージョンで治療した。疾病フリー期間(DFI)と生存期間を、過去に長期維持期を併用し、同じプロトコールで治療した55頭のコントロール群と比較した。研究犬の緩解率は94.2%(完全緩解92.3%、部分緩解1.9%)だった。研究犬の疾病フリー期間と生存期間の中央値は282日と397日で、コントロール犬のそれぞれ220日、303日と比較すると、その値に有意差はなかった(P=.2835とP=.3365)。
一変量解析で、生存期間を有意に短くする指標として、サブステージb(P=.0087)、ジャーマンシェパード種(P=.0199)、体重>18kg(P=.0016)が認められた。より長い生存期間は、血小板減少症と関連があった(P=.0436)。多変量解析で、サブステージ(P=.0388)と体重(P=.0125)は疾病フリー期間に有意性を持ち、サブステージ(P=.0093)と血小板減少症(P=.0150)そして体重(P=0.0050)が生存期間に有意性を持つことが明らかとなった。全体的に、そのプロトコールに対し犬は良く許容し、41.5%(22/53)の犬は治療の延長や投与量の修正を必要としたが、9.4%(5/53)の犬しか入院を必要としなかった。維持期を併用しないCHOPベースの6ヶ月化学療法プロトコールは、長期維持期を併用した同様のプロトコールと比較した時、同様の疾病フリー期間や生存期間を得ることができる。(Sato訳)
■犬の抵抗性リンパ腫のMOPP化学療法による治療:117症例(1989-2000)の回顧的研究
MOPP Chemotherapy for Treatment of Resistant
Lymphoma in Dogs: A Retrospective Study of
117 Cases (1989-2000)
J Vet Intern Med 16[5]:576-580 Sep-Oct'02
Retrospective Study 26 Refs
Kenneth M. Rassnick, Glenna E. Mauldin, Renee
Al-Sarraf, G. Neal Mauldin, Antony S. Moore,
Samantha C. Mooney
この回顧的研究の目的は、リンパ腫の犬のレスキュー処置としてMOPP化学療法プロトコール(メクロレタミン、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン)の効果と毒性を評価することだった。以前投与した化学療法に抵抗性を示した117頭の犬を評価した。MOPPの治療前に、全ての犬は中央値213日の間、中央値6種類の化学療法剤を投与されていた。MOPPで31%(117頭中36頭)は、中央値63日間の完全緩解(CR)、34%(117頭中40頭)は中央値47日間の部分寛解(PR)を得られた。16%(117頭中19頭)は中央値33日間の安定疾患(SD)が得られた。MOPPに対する反応の予測値はわからなかった。
胃腸毒性は28%の犬(117頭中33頭)で発生し、13%の犬(15頭)は入院が必要だった。5頭は敗血症を発症し、最終的に2頭死亡した。MOPPは抵抗性リンパ腫の効果的な治療で、罹患犬の大多数がその治療に良く耐えた。(Sato訳)
■ネコリンパ腫の最新情報
What Is New On Feline Lymphoma?
J Feline Med Surg 3[4]:171-176 Dec'01 Proceedings
0 Refs
C Guillermo Couto
リンパ腫の組織学的、病理組織学的診断が成されると、予後や使用可能な治療オプションについて通常オーナーと話し合う。ネコリンパ腫の寛解率は、種々の化学療法プロトコールで治療した場合、約65-75%です。リンパ腫の多くは、多剤化学療法プロトコール(±外科手術および/または放射線療法)を行ったとき6-9ヶ月生存すると予想され、約20%は1年以上生存する。FeLV陽性猫の予後は悪く、陰性猫の生存期間はより長い(すなわち、9-18ヶ月、構造形態に依存する)リンパ腫非治療猫の生存期間は約4-8週間である。犬のリンパ腫よりも猫のリンパ腫の生存期間が短い最大の理由は、腫瘍が再燃した時、寛解への再導入が難しいからだと思われる。
私の経験では、ネコがステージ1の結節外リンパ腫で来院した時でさえ、その病気の全身性播種が診断後数週から数ヶ月の間に通常起こる。それゆえ、ネコリンパ腫の治療の要は、リンパ腫は全身性の腫瘍(結局はそうなる)という観点から化学療法である。外科手術および・または放射線療法は、化学療法前、または化学療法中に局所リンパ腫の治療に用いられる。この項で、リンパ腫の管理に対する一般的なガイドラインを述べる。この章で推奨されるプロトコールは、我々の病院で使用しており、文献で発表されている他の治療に匹敵する成功率を持つ。(Sato訳)
■腸管T細胞リンパ肉腫の猫に見られた過好酸性腫瘍随伴症候群
Hypereosinophilic paraneoplastic syndrome
in a cat with intestinal T cell lymphosarcoma.
J Small Anim Pract 43[9]:401-5 2002 Sep
Barrs VR, Beatty JA, McCandlish IA, Kipar
A
10歳、避妊済みメスの家猫短毛種が、最近になって体重減少、多飲多尿、下痢、嘔吐で来院した。身体検査で、腸管の肥厚と腸間膜リンパ節の拡張が明らかになった。臨床検査で、末梢血の好酸球増加、好酸球が増えた腹水、好酸性腸間膜リンパ節炎が見られた。グルココルチコイドの治療に一時的に反応したが、症状は進行し、安楽死した。組織検査で、小腸と腸間膜の好酸球浸潤と繊維増殖が見られた。小腸と腸間膜リンパ節の細胞周囲腫瘍性の大きな集合体は、免疫組織化学検査でTリンパ球と判定された。腸管T細胞リンパ肉種の診断が下された。この症例は、過好酸球性腫瘍随伴症候群がリンパ肉腫の猫に発生するかもしれないと示している。好酸球の走化性は、腫瘍リンパ球のインターロイキン-5の産生に反応するのかもしれない。(Sato訳)
■間接喫煙とネコの悪性リンパ腫の危険性
Bertone ER, Snyder LA, Moore AS : Am J Epidemiol
156[3]:268-73 :Environmental tobacco smoke
and risk of malignant lymphoma in pet cats.
ネコの悪性リンパ腫は人の非ホジキンリンパ腫の疾病モデルにされており、いくつかの研究は喫煙が非ホジキンリンパ腫の危険性を高めるかもしれないと報告している。室内での間接喫煙がネコの悪性リンパ腫の危険性を高めるか評価するために、80頭の悪性リンパ腫のネコ、114頭の腎疾患と診断された例について検討を行った。
このすべてのオーナーに、病気の診断からさかのぼること2年、室内での喫煙の程度に関する質問表を送付した。年齢やその他の要因を調節したところ、室内で間接喫煙に曝されていたネコの悪性リンパ腫の罹患率は2.4倍(95%信頼区間は1.2、4.5)であった。危険性は、暴露期間と暴露量に直線的に比例しているようであった。5年以上暴露していたものでは危険率が3.2倍(95%信頼区間は1.5、6.9)であった。これらのことから受動喫煙はネコにおいても悪性リンパ腫の危険性を高めることから、人でも更なる検討が必要である。(Dr.Tako訳)
■猫の悪性リンパ腫に対する化学療法シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン(COP):古いプロトコールの最新結果
Erik Teske et al; J Vet Intern Med 16[2]:179-186
Mar-Apr'02 Retrospective Study 31 Refs; Chemotherapy
with Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone
(COP) in Cats with Malignant Lymphoma: New
Results with an Old Protocol
猫白血病ウイルス(FeLV)があまり蔓延していないオランダで、悪性リンパ腫の猫61頭に対し、確立した化学療法プロトコール(シクロフォスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン[COP])の効果を調査する回顧的研究を行いました。22頭(36.1%)は縦隔型リンパ腫で、11頭(18.0%)は消化器型リンパ腫、7頭(11.5%)は末梢リンパ腫、8頭(13.1%)は鼻部リンパ腫、13頭(21.3%)は種々のリンパ腫(腎型リンパ腫2頭:3.3%を含む)でした。検査した54頭のうち、FeLV陽性はたった4頭(7.4%)でした。完全寛解(CR)は61頭中46頭(75.4%)で達成しました。完全寛解した46頭の1年、2年-病気フリー期間はそれぞれ51.4%と37.8%でしたが、寛解期間の中央値は251日でした。全体の1年生存率は48.7%で、2年生存率は39.9%、生存期間中央値は266日でした。縦隔型リンパ腫の生存期間中央値と1年生存率は262日と49.4%でした。他の種類より生存や寛解に対するシャムネコの予後はより良いものでした。この研究で、治療に対する反応はかなり予後を示すものとなりました。完全寛解は長期生存に欠かせません。完全寛解に達しなかった猫は、1年以上生存する機会がほとんどなくなりました。この研究の若いシャムネコは、全頭FeLV陰性で若齢時に縦隔悪性リンパ腫をより強く発病する傾向にありました。異なる組み合わせの化学療法プロトコールを行った他の研究報告と比較すると、今回の結果は、悪性リンパ腫の猫で高い寛解率とより長期の生存率を示しています。(Sato訳)
■リンパ腫と骨肉腫の犬における亜鉛、クロム、鉄の血清濃度
Kathy J. Kazmierski et al; J Vet Intern Med
15[6]:585-588 Nov-Dec'01 Clinical Study 22
Refs ;Serum Zinc, Chromium, and Iron Concentrations
in Dogs with Lymphoma and Osteosarcoma
我々は癌の犬の亜鉛、クロム、鉄の血清濃度を正常犬と比較した。リンパ腫(n
= 50)と骨肉腫(n = 52)の犬を評価した。リンパ腫の犬は平均亜鉛濃度(平均±SD;
1.0±0.3 mg/L)が、正常犬(1.2±0.4 mg/L)と比較して有意に低値(P
= .0028)であった。骨肉腫の犬でも平均亜鉛濃度は低値(1.1±0.4
mg/L)であったが、この差違は有意ではなかった(P
= .075)。血清クロム濃度は正常犬(4.7±2.8
ug/L)と比較して、リンパ腫(2.6±2.6 ug/L,
P = .0007)と骨肉腫(2.4±3.1 ug/L, P = .0001)の犬で有意に低値であった。血清鉄濃度と総鉄結合容量は、正常犬(それぞれ175.1±56.7ug/dLと277.1±47.4
ug/dL)と比較して、リンパ腫(それぞれ110.8±56.7
ug/dL, P < .0001,と236.6± 45.6 ug/dL,
P < .0001)と骨肉腫(それぞれ99.6±49.3ug/dL,P<.0001,と245.0±43.8
ug/dL, P = .0011)の犬で有意に低値であった。フェリチン濃度の中央値は、正常犬(805.8±291.1
ug/L,P<.0001)と比較して、リンパ腫(1291.7±63.0
ug/L)と骨肉腫(826.5±309.2 ug/L, P <.0001)の犬で有意に高値であった。癌の犬における、これらのミネラル異常の臨床的意義を診査するためには、さらなる調査が必要である。(Dr.Massa訳)
コメント:リンパ腫と骨肉腫においては血清中の亜鉛、クロム、鉄濃度が低値になるという文献です。
腫瘍性疾患におけるミネラル定量検査は臨床の現場ではあまり一般的ではありません。今回の文献内容からすると腫瘍の代謝系への関与はありそうですので、これからの研究によって亜鉛、クロム、鉄などの血清ミネラル量が疾患の重症度や予後の判定に役立つようになるといいですね。